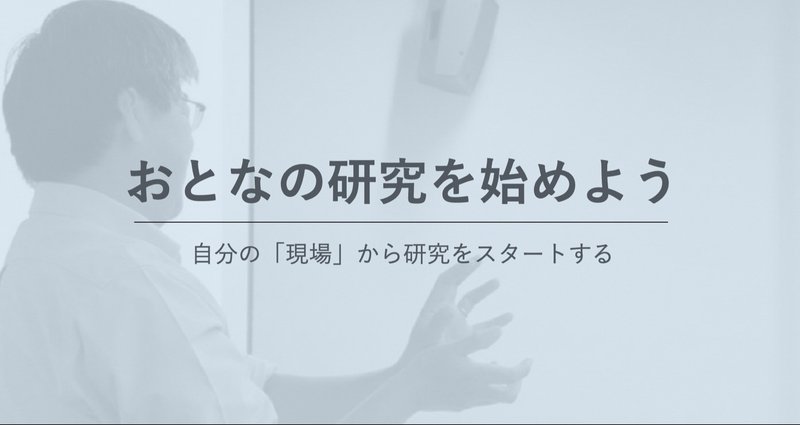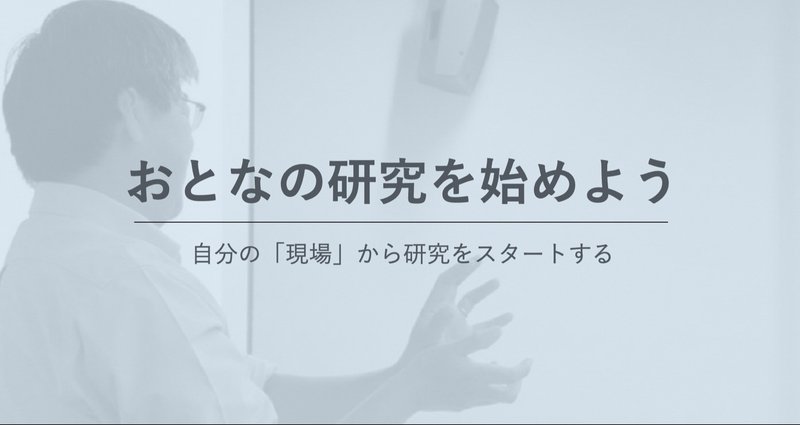6. 自分の現場の問題を社会に還元できる研究にする
前回は、自分の現場の中で、問題だと感じているこの問題は、一体どういう問題なのかということを考え、観察していくことによって「What型の研究」を始めることができるということを書きました。
さて、このように現場の中で問題だと感じたことに目をつけることで研究がスタートします。そうすると、「え? 自分の現場の問題を取り上げることで、それを "研究" と呼んでいいのですか?」と考える人がいるでしょう。つまり、自分の現場の問題は、そこそこ特殊なものであって、それを研究したとしても、それ