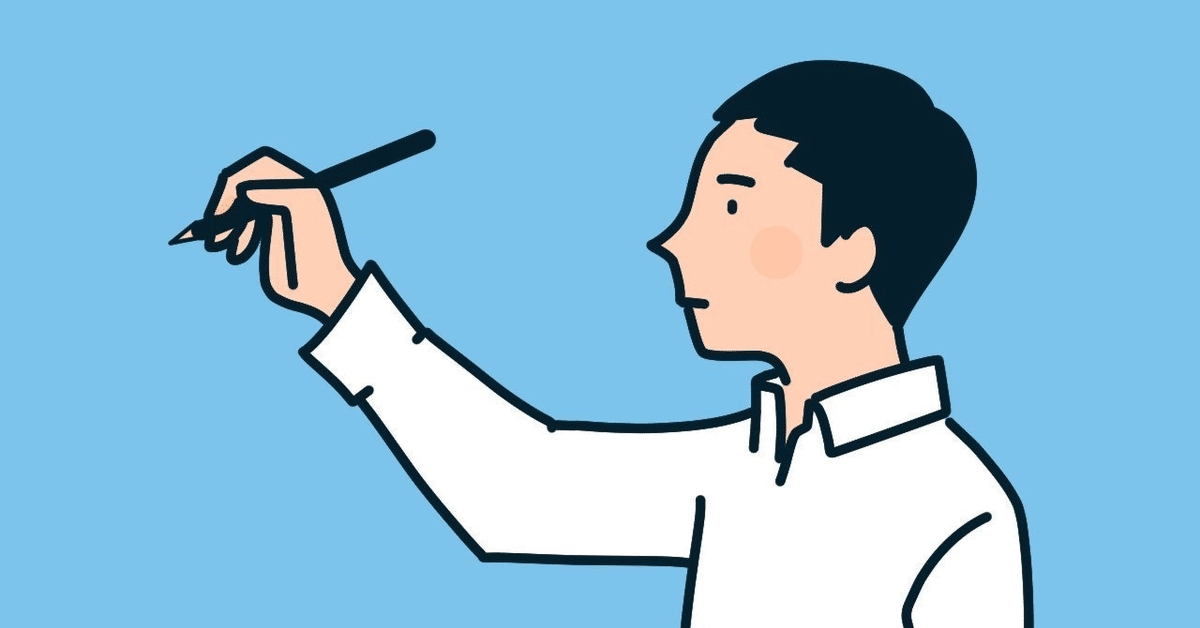
文章の自己帰属感について
漢字の密度がすごいことになってしまったけど、カミーノさんの記事を読んで思いついたのが、タイトルの言葉です。
記事の一文にTwitterでも多くの人が反応していました。
気合を入れて書いた文章はそれほどでもないのに、なぜコレが?!という文章のほうが多く読まれたりする。
なんなんでしょうか、この現象は。だれかこの現象に名前を!
構成や言葉選びに時間をかけ、推敲を重ねた投稿の反応が薄かったり。逆にサラサラっと書いた文章が多くの人に響いたり。文章って不思議だなぁ、と感じてる人ってやっぱり多いんですね。もちろん僕もです。
この現象が起きる理由を言葉にするならば、一般的には「狙った文章はウケない」に集約される気もします。逆をいえば自然体で書かれた文章はウケるとも言える。
でもまてよ、と。
エッセイはともかく、小説を狙って書かないひとはいません。でも、こころ打たれる作品はある。狙って書いた文章もウケるときがあるんです。それはプロが書いた作品だけでなく、noteで出会う小説にも多くの名作があることがそれを証明しています。
その違いはなんだろ?と思うわけです。そこで思いついたのが「文章の自己帰属感」。結論からいうと、「自分らしい文章」という平々凡々な言葉になるのですが、今回は敢えてUIデザインの文脈で使われる、自己帰属感という言葉で僕なりの考えを書いてみます。
-
自己帰属感とは、「融けるデザイン」を執筆された渡邊恵太さんが提唱された言葉です。
じこきぞく‐かん【自己帰属感】
主にコンピューターやスマートホンなどのユーザーインターフェースにおいて、利用者による操作と、画面上の対象物の動きが一致し、あたかも身体の延長のように感じる感覚。
一般的には馴染みがない言葉ですが、UI設計の世界では広く知られている概念です。ひらたく言えば、道具を使うときにその存在を忘れるくらい対象に集中できるかが重要で、まるで自分の手の延長であるかのごとく使えることが「使いやすい道具」の条件ということです。
たとえば、マウス。パーソナルコンピューターのUIで最大の発明といっていいマウス操作は、直感的で誰もがすぐに使いこなせます。上のYouTubeでもランダムに動くカーソルの中から、自分が操作しているカーソルを一瞬で認識できています。マウスが自意識からなくなり(=透明化)、あたかも自分の指先が画面の中に入り込み操作している感覚。これが、自己帰属感です。
自己帰属感を得られるか否か、そのポイントは道具を意識しなくなることです。反応速度が遅く、マウスの動きとカーソルの動きにタイムラグがあると、それが僅か0.1秒だとしても自己帰属感を得られません。その些細なズレが、マウスという道具を認識させ透明でなくしてしまう。それは、良いUIとは言えないのです。
文章の自己帰属感ってなに?
話を本題に戻します。どうしてぼくは、「読まれる文章」とは? という問に対して自己帰属感という概念を思い出したのか。それは、自分の指先がマウスカーソルとなって画面の中で一体化する感覚が、文章を書くときにもあると思ったからです。
自分でも驚くほど、サラサラと調子よく書けるときってありますよね。まるで頭の中に浮かんだ言葉が、そのまま画面に湧き上がるような感覚。そんなとき、キーボードの存在は限りなく透明になってないでしょうか?
手とキーボードが意識から消えて、思いつくままに文章が連なっていく状態。読まれるために書いていることさえ忘れる瞬間。頭の中と画面の中が直結する感覚。これが、僕が考える文章の自己帰属感です。
アスリートのゾーンに近い感覚なのかもしれません。ボールが止まって見えるとか、鳥の目になってフィールド全体が見えたとか、そういう感じに近いのかも。文章を書く場面に置き換えると、気がついたら千文字や二千文字も書いていた、という状態ですね。
だから、サラっと書いたものがウケるの不思議! という感覚が生まれやすいのかもしれません。書いた本人としては、スラスラ書いた文章でも、ゾーンに入った文書は読み手にとって濃ゆいんですよね。その人の根幹に触れた気になる。だから心に響くし、誰かにシェアしたくなる。
-
ただ、誰かに読まれる前提で書いた文章にしか、自己帰属感は宿らない気がするんです。誰にも見せない日記の読者は自分ひとり。日記を読み返し、「自分らしい文章だな」と思う人は少ないでしょう。日記は文章のリズムや文体を楽しむものじゃなくて、書くことそのものに意味があるし、記憶を書きとめておくものだと思うのです。
例えば、流れ着いた無人島で一生を終えたひとの手記が500年後に見つかったとします。それが『雨、暑い、魚二匹と小さなエビ』と記録の羅列が続いた日記なら。貴重な資料かもしれませんが、語り継がれる文章ではないですよね。
でも、いつか誰かが目にする事を想像しながら書かれた文章なら、心打つ力を持っているはずです。絶望の中に希望を見出そうとする苦しみや、美しい風景に感動した気持ち、孤独に震える夜の暗闇の描写。そこに綴られる言葉は、どれもリアルで時を経ても生々しい。そしてそれは、その人にしか書けない文章です。
-
ちょっと強引ですが、「多くのひとの心に届く文章には、自己帰属感がある」と仮定しましょう。その発生要因は、以下の二つだと僕は考えます。
読まれる前提で書き始めた文章であること
読み手のことを忘れ、文章と自分が繋がる瞬間があること
2は少し抽象的な表現ですね。現象としては、前述したキーボードの存在がなくなり頭の中と画面の文字が直結する状態のことです。恐らく、これを狙ってできる人はいないのではないでしょうか? もしくは、プロの小説家はそれができるのでしょうか……。
10年以上まえのことですが、直木賞作家の道尾秀介さんが出ていた『情熱大陸』で忘れられないシーンがあります。番組の終盤、じゃこれからちょっと書きますね、とカメラマンに向けて声をかけた道尾さん。10分、20分と時間は進み、30分が過ぎた頃に振り返りこう言ったのです。「あっ、撮られてるの忘れてました」 ── もの凄い集中力というか、プロだなぁと唸った覚えがあります。
プロには及ばないものの、時間を忘れるほど書くことに集中することってありますよね。その瞬間に紡ぎ出された文章は、人を惹きつける力があるのでは? と僕は思います。
狙っては外れ、脱力しすぎても届かない。
気張りすぎては途中で折れるけど、気を抜いたら続かない。
文章を書くという行為は、楽しくもあり辛くもあり、ときに苦しくて理不尽だけど。やめられない魅力がありますよね。
