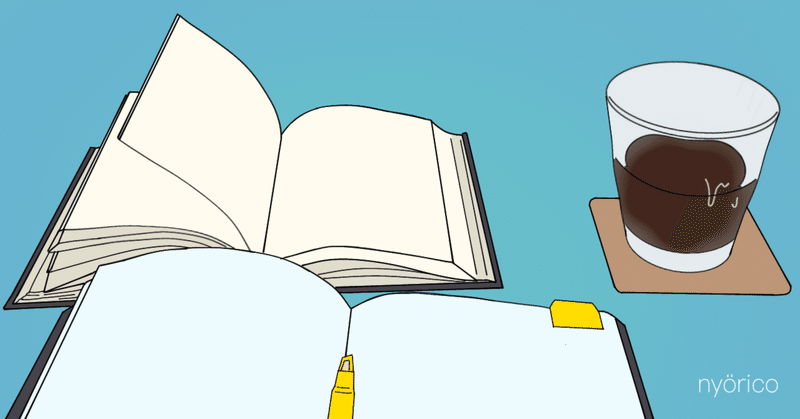
「氏の議論」研究
「氏」と言えば、・・・あまりホットにもならないで、せっかく法制審議会で決定までされたけれども、一向に実現はしないという妙な形になっている。それが「選択的夫婦別姓」というものである。・・・本格的に議論がされてからでも10年も経つのだろうか。法制審議会でもかなり丁寧な議論をして、まとまったのだが、議会には上程されないという妙な形になっている。・・・
と始まる、唄孝一先生の論文に出会う
唄先生は、あの、戦後の民法改正を振り返る座談会にも登場していた
「氏」をテーマにするとはいえ、あの改正議論(今となっては未完成に終わっていたという評価をせざるを得ない)に関連する記述があった
戦後の民法改正の「環」とされた「氏」
どういうことだろう?
・・・戦後の家族法改正のこと・・・ほぼ共通なのは、三つの流れがあったということだ。つまり、一番真ん中に当時のまだ「司法省」があり、そしてそこに我妻・中川という両大家が関わっておられ、法務省にも、優秀で、プライドの高い官僚法律家も何人かおられ、そういう方々が中心となって改正案の草稿を作っておられた。
その片側には当時の家制度を廃止するということに頑固に反対する人達がおられた。実は国会の議論は大方そうなのだが、調査会のような所でも、牧野英一という、刑法の大先生が、大いに論陣を張って起草委員の立場をやっつけて国会の議論と相呼応するような形になっていた。
それに対して、他の側に川島教授を大将として、野村平爾(早大)、当時数少ない女性法律家であった立石芳枝先生(明治大)、それから来栖三郎先生(東大)、そこにフランス法の野田良之先生(東大)なども入っておられた。
以上3つの立場が相争ったわけである。
何を争ったのだろうか?
当時の我妻先生は自らの立場をいくつかに整理されている。その1つは、「立法は妥協である。」ということ、つまり、「立法は高嶺の花を理想として追い求めるものではない。」、とよく言われた。それからもう1つは、「この改正は決して占領軍によって動かされているんじゃない。」ということで、むしろ、戦前の改正論との連続性を強調された。その他にもいくつかの主張があるが、その中身として大事なのは、法律上の家族制度と、それから道徳上の家族制度とを分ける、「道徳上の家族制度をどうこうしようなんてことは我々はちっとも言っていない、法律上の家族制度を問題にしているんだ」ということを我妻先生は書いたり話したりされている。当時私の耳には川島先生の説が一番もっともらしく聞こえ、我妻先生のその言い方を聞いて反発を感じた時もあった。先生自身も後から「あれは強い反対論をなだめるためのいわば戦術的意味も多分に含んだものであった。しかしそれにしても、家族関係を支配する道徳的理念は不変なものとして、教育の力で維持すべきだ、と文部大臣に要請していることは、いま、自分で読みかえしても、不満の念を禁じえない」・・・と言っておられる。
この辺のバトルが令和の今も引きずっているのだろうか?
映画化してわかりやすく表現してもらいたいものだ
議事録の公開待ち状態だし、戦後のあの頃の議論についてしっかり読んでいこうと思う
つづく
親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!
