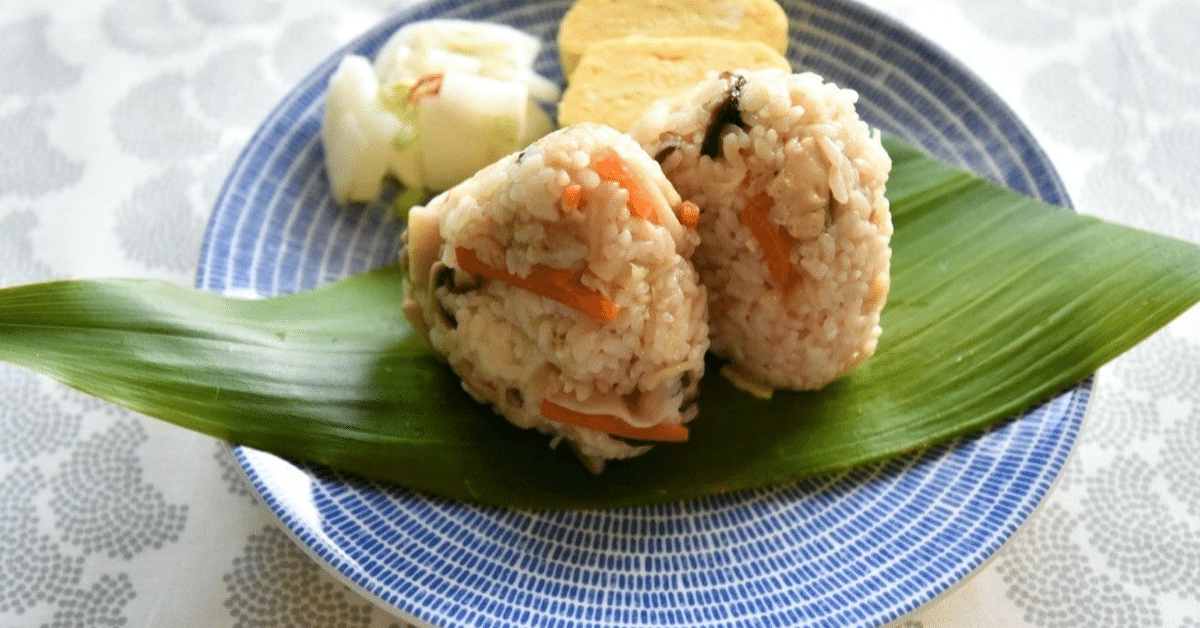
岩波書店『定本漱石全集』注解を校正する147 夏目漱石『道草』をどう読むか23 小説を読むということはこういうことだ
例えば種本から引用したとして、あるいは実際に起きたことを摘まんだとして、小説家が何かを書き、何かを書かないという細工のうちには、たとえそれが事実そのままだとあったとしても作為というものが生じるものだ。ここで私は小説家と書いたが、凡ての小説家の凡ての作品がそうであるわけはない。小説の背後に事実のあるなしはどうでもいいことだと考えた芥川龍之介、そして夏目漱石の小説は殆どそうした「書いてあることと、書かれていないこと」の組み合わせでできている。
靴下まで書いて靴を書かないのは芥川の作為である。この「書いてあることと、書かれていないこと」の組み合わせでできている小説のスタイルというものは必ずしも夏目漱石が原型というわけではないのだが、これまで見てきたように、夏目漱石作品にはそういうものがふんだんにあり、なかなか汲み尽くせない。
偽筆に時代を着けるのだ
彼は室の内をきょろきょろ見廻し始めた。殺風景を極めたその室の中には生憎額も掛物も掛っていなかった。
「李鴻章の書は好きですか」
彼は突然こんな問を発した。健三は好きとも嫌きらいともいい兼ねた。
「好きなら上げても好ござんす。あれでも価値にしたら今じゃよっぽどするでしょう」
昔し島田は藤田東湖の偽筆に時代を着けるのだといって、白髪蒼顔万死余云々と書いた半切の唐紙を、台所の竈の上に釣るしていた事があった。彼の健三にくれるという李鴻章も、どこの誰が書いたものか頗る怪しかった。島田から物を貰う気の絶対になかった健三は取り合わずにいた。島田は漸く帰った。
岩波はこの「時代をつける」に注解をつけて「偽物を本物のように見せかけるためにしていること」として健三の「子供らしい行為とは目的が異なる」とする。「偽物を本物のように見せかけるため」と「新しい独楽を使い込んだもののように見せかけるため」では確かに目的は異なるがやっていることの方向性は誤魔化す事であり同じである。
しかし問題はそこではなかろう。漱石はここで一つ「藤田東湖の偽筆」を持ち出し「どこの誰が書いたものか頗る怪し」い李鴻章の書を取り扱う島田が何十年もそういうことをやっている本質的に怪しい人物なのだと書いている。つまり人間の本質のようなもので、たまたま何かつい間違いを起こすのではなく、そういうことをする人間はずっとそういうことをしてきたし、これまでもするのだろうということだ。
あなた方の周りにもそうした人は必ずいる筈である。「ああ、この人はずっとこんなことを言ってきたんだろうな」という人。
作家で法政大学教授の島田雅彦氏がネット番組で、安倍晋三元首相暗殺事件を念頭に、「暗殺が成功して良かった」と発言し、炎上しています
— こちら夕刊フジ編集局 (@yukanfuji_hodo) April 19, 2023
夕刊フジの取材に対し、島田氏は「公的な発言として軽率であった」などと長文の回答を寄せました#島田雅彦#暗殺が成功してよかった#安倍晋三#長文回答 pic.twitter.com/7iD2tWOZVs
この発言がたまたま軽率なのではなく、
「マスクは1世帯2枚配る。手を上げた奴に一律10万円やる。ほかに何が欲しいかいってみろ」「あなたの首をいただけますか。税金はかかりません。むしろ節約になります」
— 島田雅彦 (@SdaMhiko) April 19, 2020
本質的にこういう人なのだ。ポンコツ上司は面白いくらいいつまでもポンコツだと思う。笑われていても気が付かない。まあ、それはそれとして、ここで漱石は健三を書画を持たない男として描いている。
①余裕がない
②趣味がない
いずれとも書かない。しかし「白髪蒼顔万死余云々」という唐紙が吊るされていたことを記憶している事を書き、董其昌の折手本を買って貰ったことを記憶していることを書いているので、ここは①余裕がない、ということなのだろう。
これは書かれていないけれども半分は書いてあるようなことだ。書いていないこととしては『門』のように屏風一つくらいの遺品も貰い受けていないのではないかということ、そしてどこかに偽書が紛れているかもしれないということだ。
世の中と調和する事の出来ない偏窟な学者
「何しに来たんでしょう、あの人は」
目的なしにただ来るはずがないという感じが細君には強くあった。健三も丁度同じ感じに多少支配されていた。
「解らないね、どうも。一体魚と獣ほど違うんだから」
「何が」
「ああいう人と己などとはさ」
細君は突然自分の家族と夫との関係を思い出した。両者の間には自然の造った溝があって、御互を離隔していた。片意地な夫は決してそれを飛び超えてくれなかった。溝を拵えたものの方で、それを埋めるのが当然じゃないかといった風の気分で何時までも押し通していた。里ではまた反対に、夫が自分の勝手でこの溝を掘り始めたのだから、彼の方で其所を平にしたら好かろうという考えを有っていた。細君の同情は無論自分の家族の方にあった。彼女はわが夫を世の中と調和する事の出来ない偏窟な学者だと解釈していた。同時に夫が里と調和しなくなった源因の中に、自分が主な要素として這入っている事も認めていた。
話は島田の訪問目的が解らないというところから、健三が「世の中と調和する事の出来ない偏窟な学者」だというところに移ってしまう。ここも敢て抽象的な表現で書き、健三と細君の里のトラブルを具体化しない。ただ溝があると説明している。健三は島田を変わり者扱いしたかったのに、健三が変わり者扱いされている。
それは何故か。
読者は健三が口にしていないこと「李鴻章の書」というものが偽者である可能性が高いという事実を知っているが、御住はそれを知らないので、「わざわざ偽者の書を与えて機嫌を取ろうとしている」とは聞こえていないわけだ。さらに比田や健三の姉の話と島田の話の食い違いも見えていないだろう。すると夫の困惑や疑惑が見えず、ただ言葉少なに島田を追い返した偏屈だけが見える。
それゆえのこうした話の流れなのだろう。
細君は笑いながら訊いた
細君は黙って話を切り上げようとした。しかし島田の方にばかり気を取られていた健三にはその意味が通じなかった。
「御前はそう思わないかね」
「そりゃあの人と貴夫となら魚と獣位違うでしょう」
「無論外の人と己と比較していやしない」
話はまた島田の方へ戻って来た。細君は笑いながら訊いた。
「李鴻章の掛物をどうとかいってたのね」
「己に遣ろうかっていうんだ」
「御止しなさいよ。そんな物を貰ってまた後からどんな無心を持ち懸けられるかも知れないわ。遣るっていうのは、大方口の先だけなんでしょう。本当は買ってくれっていう気なんですよ、きっと」
夫婦には李鴻章の掛物よりもまだ外に買いたいものが沢山あった。段々大きくなって来る女の子に、相当の着物を着せて表へ出す事の出来ないのも、細君からいえば、夫の気の付かない心配に違なかった。二円五十銭の月賦で、この間拵えた雨合羽の代を、月々洋服屋に払っている夫も、あまり長閑かな心持になれようはずがなかった。
「復籍の事は何にもいい出さなかったようですね」
「うん何にもいわない。まるで狐に抓まれたようなものだ」
始めからこっちの気を引くためにわざとそんな突飛な要求を持ち出したものか、または真面目な懸合として、それを比田へ持ち込んだ後、比田からきっぱり断られたので、始めて駄目だと覚ったものか、健三にはまるで見当が付かなかった。
細君が笑うのは健三にとっては島田が変わり者だと言っているのに、自分には島田よりも夫の方が別の意味で変わり者に思えるからである。その気が付かないところが笑われているのだ。
強慾な老人の一生
「宅の人はあんまり正直過ぎるんで」
御藤さんは昔健三に向って、自分の夫を評するときに、こんな言葉を使った。世の中をまだ知らない健三にもその真実でない事はよく解っていた。ただ自分の手前、嘘と承知しながら、夫の品性を取り繕うのだろうと善意に解釈した彼は、その時御藤さんに向って何にもいわなかった。しかし今考えて見ると、彼女の批評にはもう少し慥かな根底があるらしく思えた。
「必竟大きな損に気のつかない所が正直なんだろう」
健三はただ金銭上の慾を満たそうとして、その慾に伴なわない程度の幼稚な頭脳を精一杯に働らかせている老人をむしろ憐れに思った。そうして凹んだ眼を今擦り硝子の蓋の傍へ寄せて、研究でもする時のように、暗い灯を見詰めている彼を気の毒な人として眺めた。
「彼はこうして老いた」
島田の一生を煎じ詰めたような一句を眼の前に味わった健三は、自分は果してどうして老ゆるのだろうかと考えた。彼は神という言葉が嫌いであった。しかしその時の彼の心にはたしかに神という言葉が出た。そうして、もしその神が神の眼で自分の一生を通して見たならば、この強慾な老人の一生と大した変りはないかも知れないという気が強くした。
天下り、渡りを繰り返して七十迄老害をまき散らし続け、そして死んでいく「強慾な老人」というものを考える時、この『道草』の一節は作品の主題を離れて強烈なメッセージを投げかけて來る。そういう人が貴方の職場にもいるはずだ。
だらしない国会議員連中だ。写真は立憲軍団だが、他にも居眠り議員は大量にいる。眠るということはその分仕事をしていない。働かなかった分の税金はきっちり返させろ!pic.twitter.com/QQdErAYPre
— 世間はこいつらを忘れてはならない!この事件を風化させてはならない! bot版 (@bot_never4get7) April 12, 2023
この健三の自己批判は、もう一度「職業としての小説家になる直前の健三」という『道草』の設定を考えてみる時、「強慾な老人の一生」という誰でもが陥りがちな人生に対して「もう一つの別のやり方」が生まれるためのモラトリアムでもあるのだろう。ここで「はた」と目覚めることは無い。ここから苦しい逡巡が続く。しかし健三が島田という「強慾な老人の一生」を目の前に捉えた意味は大きい。
例えば「或る名僧は死ぬまで自分の寺の銭勘定をしていたそうである」と「強慾な老人の一生」を捉えたからには、お金以上の価値あるものを見出さなくてはならない。銭感情で人生を終えることを大きな損だと気が付かない人には、生涯夏目漱石作品を読むことができないだろう。
落付きを与えて遣りたくなる場合もあった
その晩の島田はこの前来た時と態度の上において何の異なる所もなかった。応対にはどこまでも健三を独立した人と認めるような言葉ばかり使った。
しかし彼はもう先達っての掛物についてはまるで忘れているかの如くに見えた。李鴻章の李の字も口にしなかった。復籍の事はなお更であった。噫にさえ出す様子を見せなかった。
彼はなるべくただの話をしようとした。しかし二人に共通した興味のある問題は、どこをどう探しても落ちているはずがなかった。彼のいう事の大部分は、健三に取って全くの無意味から余り遠く隔っているとも思えなかった。
健三は退屈した。しかしその退屈のうちには一種の注意が徹っていた。彼はこの老人が或日或物を持って、今より判明りした姿で、きっと自分の前に現れてくるに違ないという予覚に支配された。その或物がまた必ず自分に不愉快なもしくは不利益な形を具えているに違ないという推測にも支配された。
彼は退屈のうちに細いながらかなり鋭どい緊張を感じた。そのせいか、島田の自分を見る眼が、さっき擦硝子の蓋を通して油煙に燻った洋燈の灯を眺めていた時とは全く変っていた。
「隙があったら飛び込もう」
落ち込んだ彼の眼は鈍いくせに明らかにこの意味を物語っていた。自然健三はそれに抵抗して身構えなければならなくなった。しかし時によると、その身構えをさらりと投げ出して、飢えたような相手の眼に、落付きを与えて遣りたくなる場合もあった。
このおおらかさというか寛容さというか、島田に対する健三の態度の柔かさ、そして緊張を以て対峙しながら飽くまで相手に付き合う余裕は、癇癪持ちの漱石の塩原に対する態度とはまるで異なるものであろう。
そこが『道草』という作品の肝に関わる部分だろうとは気が付きながら、では実際にそのことがどういう意味を持つのかと考えてみると、これが案外何ともうまい答えの見つからないところだと気が付く。
勿論島田の出し方が随分工夫されていて、冒頭で出会っているのになかなか会いに来なかったり、四十九章になってまだ「金をくれ」と言わないので癇癪も起こせないのだが、例えそうだとしても「落付きを与えて遣りたくなる場合もあった」とは人が良すぎではなかろうか。
あるいはここは健三を「いい人」に見せたいところなのだろうか?
どこが悪いんです
その時突然奥の間で細君の唸るような声がした。健三の神経はこの声に対して普通の人以上の敏感を有っていた。彼はすぐ耳を峙てた。
「誰か病気ですか」と島田が訊きいた。
「ええ妻が少し」
「そうですか、それはいけませんね。どこが悪いんです」
島田はまだ細君の顔を見た事がなかった。何時どこから嫁に来た女かさえ知らないらしかった。従って彼の言葉にはただ挨拶があるだけであった。健三もこの人から自分の妻に対する同情を求めようとは思っていなかった。
「近頃は時候が悪いから、能く気を付けないといけませんね」
子供は疾うに寐付ついた後なので奥は寂としていた。下女は一番懸け離れた台所の傍の三畳にいるらしかった。こんな時に細君をたった一人で置くのが健三には何より苦しかった。彼は手を叩いて下女を呼んだ。
「ちょっと奥へ行って奥さんの傍に坐っててくれ」
「へええ」
下女は何のためだか解らないといった様子をして間の襖を締めた。健三はまた島田の方を向き直った。けれども彼の注意はむしろ老人を離れていた。腹の中で早く帰ってくれれば好いと思うので、その腹が言葉にも態度にもありありと現れた。
それでも島田は容易に立たなかった。話の接穂がなくなって、手持無沙汰で仕方なくなった時、始めて座蒲団から滑り落ちた。
「どうも御邪魔をしました。御忙がしいところを。いずれまたその内」
細君の病気については何事もいわなかった彼は、沓脱へ下りてからまた健三の方を振り向いた。
「夜分なら大抵御暇ですか」
健三は生返事をしたなり立っていた。
「実は少し御話ししたい事があるんですが」
健三は何の御用ですかとも聞き返さなかった。老人は健三の手に持った暗い灯影から、鈍い眼を光らしてまた彼を見上げた。その眼にはやっぱりどこかに隙があったら彼の懐に潜り込もうという人の悪い厭な色か動いていた。
「じゃ御免」
最後に格子を開けて外へ出た島田はこういってとうとう暗がりに消えた。健三の門には軒燈さえ点いていなかった。
この「どこが悪いんです」という問いに健三は返事をしていない。そのことを漱石は「彼の言葉にはただ挨拶があるだけであった」「健三もこの人から自分の妻に対する同情を求めようとは思っていなかった」と書いて誤魔化す。けして手拍子の会話をさせない。
それだけではなく実は読者にもまだ妻の病名は告げられていない。するっと読めば初見では妊娠の悪阻かと勘違いするところだ。後で考えると、ここは具体的には返答しづらい様子を書くことが正解だと思える。
そういう病気がここまで伏せられていた。
子供は疾うに寐付ついた後
ここでようやく島田の訪問は健三の帰宅を待ち受けた夜分のことだと解る。飯を出した気配もないので、島田は飯を済ませてきたのだろう。その点では島田にも晩飯時に合わせて訪問するのは失礼というぎりぎりの常識はあったようだ。
しかしこの時間は健三にとって明日の授業の準備に当てられるべき時間の筈だ。
健三は実際その日その日の仕事に追われていた。家へ帰ってからも気楽に使える時間は少しもなかった。その上彼は自分の読みたいものを読んだり、書きたい事を書いたり、考えたい問題を考えたりしたかった。それで彼の心は殆ど余裕というものを知らなかった。彼は始終机の前にこびり着いていた。
こう書かれていたのが三章。それから掛け持ちの仕事が増えた。
彼の仕事は前の日か前の晩を潰つぶして調べたり考えたりしなければ義務を果す事の出来ない性質のものであった。従って必要な時間を他に食い削られるのは、彼に取って甚しい苦痛になった。
三十三章ではこう書かれている。それなのに無意味な話をよく我慢したものだ。
夜分なら大抵御暇ですか
私ならさすがに反論するところだ。夜分閑な人間など碌なものではない。一日は二十四時間しかないのだ。世の中には本を読んでいると「暇なんだ」と思う人がいるようだ。恐らくその人は暇だから本を読むのだろう。だからそうではない読書があることを想像できないのだ。
しかし健三はあくまで聞き流す。努力していればしているだけ聞き流すことのできない失礼な言葉だと私は思うが、ここを健三は聞き流す。代わりに読者を憤慨させて、島田を悪く見せようという気が満々だ。
後生だから己の顔を見てくれ
細君の眼はもう天井を離れていた。しかし判然どこを見ているとも思えなかった。黒い大きな瞳子には生きた光があった。けれども生きた働きが欠けていた。彼女は魂と直接に繋っていないような眼を一杯に開けて、漫然と瞳孔の向いた見当を眺めていた。
「おい」
健三は細君の肩を揺った。細君は返事をせずにただ首だけをそろりと動かして心持健三の方に顔を向けた。けれども其所に夫の存在を認める何らの輝きもなかった。
「おい、己だよ。分るかい」
こういう場合に彼の何時でも用いる陳腐で簡略でしかもぞんざいなこの言葉のうちには、他に知れないで自分にばかり解っている憐憫と苦痛と悲哀があった。それから跪いて天に祷る時の誠と願もあった。
「どうぞ口を利いてくれ。後生だから己の顔を見てくれ」
彼は心のうちでこういって細君に頼むのである。しかしその痛切な頼みを決して口へ出していおうとはしなかった。感傷的な気分に支配されやすいくせに、彼は決して外表的になれない男であった。
細君の眼は突然平生の我に帰った。そうして夢から覚めた人のように健三を見た。
「貴夫?」
彼女の声は細くかつ長かった。彼女は微笑しかけた。しかしまだ緊張している健三の顔を認めた時、彼女はその笑を止めた。
「あの人はもう帰ったの」
「うん」
二人はしばらく黙っていた。細君はまた頸を曲げて、傍に寐ている子供の方を見た。
「能く寐ているのね」
子供は一つ床の中に小さな枕を並べてすやすや寐ていた。
健三は細君の額の上に自分の右の手を載せた。
「水で頭でも冷して遣ろうか」
「いいえ、もう好ござんす」
「大丈夫かい」
「ええ」
「本当に大丈夫かい」
「ええ。貴夫ももう御休みなさい」
「己はまだ寐る訳に行かないよ」
健三はもう一遍書斎へ入って静かな夜よを一人更かさなければならなかった。
なるほど細君に釣られてつい健三のことを「世の中と調和する事の出来ない偏窟な学者」だと思いこんでいた読者に対して、漱石はこんな形で健三の優しさを強調して揺さぶる。口には出さずともちゃんと女房を思いやるやさしさがあることを示して、だから妊娠するんだと安心させる。
己はまだ寐る訳に行かないよ
いや、飽くまでもセックスはしていないふりを装う。
この辺りの漱石は頑固だ。
[余談]
"なぜ〈僕〉という一人称は明治以降、急速に広がり、ほぼ男性だけに定着したのか。古代から現代までの〈僕〉の変遷を詳細に追う":友田健太郎『自称詞〈僕〉の歴史 日本語の一人称に宿る男の絆』https://t.co/un1NVlNpOS
— 悪漢と密偵 (@BaddieBeagle) April 19, 2023
あのちゃんも使う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
