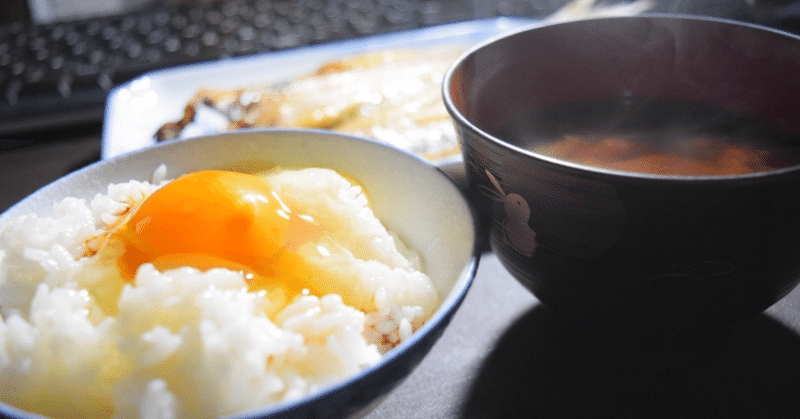
岩波書店『定本漱石全集』注解を校正する149 夏目漱石『道草』をどう読むか25 そんなことはどうでもいい
多くの老人たちが死ぬ前に後悔することは、やればできたかもしれないことをやらなかったことだそうだ。ただ、それはまだ死なない全ての人に当てはまることで、瞬間瞬間に失われていく人生の宿命みたいなものなのではなかろうか。
ブルシットジョブに絡めとられ、朝飯と晩飯を食べて死んでいく全ての人たちがそれ以外に何が出来るのかと言えば、実は限られている。自分自身の凡てが消耗品であると気が付いた時にはもう遅い。実際ランチ以外に人生の愉しみがない人たちの共感に支えられて『孤独のグルメ』はヒットした。
夏目漱石作品を読むこと、たった一冊でも読み切ること、それは美味しいランチより素晴らしい体験である筈である。ただまだ誰一人夏目漱石作品を読んだ人はいない。
ランチは翌日ウンチになる。
けれども面倒臭いにゃ違いないでしょう
これほど細君の病気に悩まされていた健三は、比較的島田のために祟られる恐れを抱いだかなかった。彼はこの老人を因業で強慾な男と思っていた。しかし一方ではまたそれらの性癖を充分発揮する能力がないものとしてむしろ見縊ってもいた。ただ要らぬ会談に惜い時間を潰されるのが、健三には或種類の人の受ける程度より以上の煩いになった。
「何をいって来る気かしら、この次は」
襲われる事を予期して、暗にそれを苦にするような健三の口振が、細君の言葉を促がした。
「どうせ分っているじゃありませんか。そんな事を気になさるより早く絶交した方がよっぽど得ですわ」
健三は心の裡で細君のいう事を肯った。しかし口ではかえって反対な返事をした。
「それほど気にしちゃいないさ、あんな者。もともと恐ろしい事なんかないんだから」
「恐ろしいって誰もいやしませんわ。けれども面倒臭いにゃ違いないでしょう、いくら貴夫だって」
「世の中にはただ面倒臭い位な単純な理由でやめる事の出来ないものがいくらでもあるさ」
健三は囚われている。「世の中にはただ面倒臭い位な単純な理由でやめる事の出来ないものがいくらでもある」からとして、心の中で賛成した「早く絶交した方がよっぽど得」という妻の考えを否定してしまう。どうしようもないものはどうしようもないとして、片付けられるものは少しでも片付けて面倒は少しでも減らした方がいいという方向には考えが進まない。
しかし人間関係のどうしようもないものは実際どうしようもないので、さっさと避難した方が得である。何とかする必要もない。喧嘩をする必要もない。こいつ駄目だなと思えば関わらないことだ。自分にはどうにもできないことで悩んでもしょうがない。
そこは健三も解っているのだ。この「やめる事の出来ないものがいくらでもあるさ」という勘定の中には「姉のこと」も入ってくる。夫もあり五十過ぎの姉に何故小遣いをやらねばならないのか、と根本の問題を健三は意識に上らせない。『道草』はそういうどうしようもない柵の中で生きる健三を描いた小説たからだ。
しかしここで「姉のほかには」と読者に考えさせないように性急に島田が現れる。
島田は変な顔をした
多少片意地の分子を含んでいるこんな会話を細君と取り換わせた健三は、その次島田の来た時、例よりは忙がしい頭を抱えているにもかかわらず、ついに面会を拒絶する訳に行かなかった。
島田のちと話したい事があるといったのは、細君の推察通りやっぱり金の問題であった。隙があったら飛び込もうとして、この間から覘いを付けていた彼は、何時まで待っても際限がないとでも思ったものか、機会のあるなしに頓着なく、ついに健三に肉薄し始めた。
「どうも少し困るので。外にどこといって頼みに行く所もない私なんだから、是非一つ」
老人の言葉のどこかには、義務として承知してもらわなくっちゃ困るといった風の横着さが潜んでいた。しかしそれは健三の神経を自尊心の一角において傷いため付けるほど強くも現われていなかった。
健三は立って書斎の机の上から自分の紙入を持って来た。一家の会計を司っていない彼の財嚢は無論軽かった。空のまま硯箱の傍に幾日も横たわっている事さえ珍らしくはなかった。彼はその中から手に触れるだけの紙幣を攫み出して島田の前に置いた。島田は変な顔をした。
「どうせ貴方の請求通り上げる訳には行かないんです。それでもありったけ悉皆上げたんですよ」
健三は紙入の中を開けて島田に見せた。そうして彼の帰ったあとで、空の財布を客間へ放り出したまままた書斎へ入った。細君には金を遣った事を一口もいわなかった。
この「島田は変な顔をした」が案外解らないところではなかろうか。「どうも少し困るので。外にどこといって頼みに行く所もない私なんだから、是非一つ」の前後の会話が不明なので、書かれている部分からはこの一言で健三は金を渡したように思える。「貴方の請求通り上げる訳には行かない」と健三が言うのは、先に島田からいくらほど欲しいという提示があったのかなかったのか、今回限りの金なのか、今月の小遣いなのかも不明だ。
この島田の変な顔には「問答もなく、是非一つで案外あっさり金を出すな、直ぐ出たな」という意外の感に打たれたところもありまた「逆に何の金だこれは」という戸惑いもあったのではなかろうか。
ここで島田が何と礼を言ったのか、帰り際にどんな挨拶をしたのかを書かない漱石も悪い。これではまるでATMだと読者の意識を悪い島田に向けさせて、先ほどの「やめる事の出来ないものがいくらでもあるさ」のところをぼかしてしまう。
それが女の義務なんだから仕方がない
その内細君の御腹が段々大きくなって来た。起居に重苦しそうな呼息をし始めた。気分も能く変化した。
「妾今度はことによると助からないかも知れませんよ」
彼女は時々何に感じてかこういって涙を流した。大抵は取り合わずにいる健三も、時として相手にさせられなければ済まなかった。
「何故なぜだい」
「何故だかそう思われて仕方がないんですもの」
質問も説明もこれ以上には上る事の出来なかった言葉のうちに、ぼんやりした或ものが常に潜んでいた。その或ものは単純な言葉を伝わって、言葉の届かない遠い所へ消えて行った。鈴の音が鼓膜の及ばない幽かな世界に潜り込むように。
彼女は悪阻で死んだ健三の兄の細君の事を思い出した。そうして自分が長女を生む時に同じ病で苦しんだ昔と照し合せて見たりした。もう二、三日食物が通らなければ滋養灌腸をするはずだった際どいところを、よく通り抜けたものだなどと考えると、生きている方がかえって偶然のような気がした。
「女は詰らないものね」
「それが女の義務なんだから仕方がない」
健三の返事は世間並であった。けれども彼自身の頭で批判すると、全くの出鱈目に過ぎなかった。彼は腹の中で苦笑した。
昨日芥川の『奉教人の死』に関して、奉教人たちも芥川自身も「ろおれんぞ」というトランスジェンダーを許容しているというような話を書いた。時流に合わせて調子のいい話が書きたかったわけではなくて、珍しく芥川の「そういうところ」が現れた作品だと読めたからだ。
夏目漱石作品では『こころ』で同性愛的な誤解が「だし」として使われているが、この『道草』は明確に男と女の世界である。そして女はほぼ「母」という役割に押し込められている。書かれている部分では健三の姉、御夏にはいかにも子がなさそうに感じられるものの、構想では確かに子がいた。

このように女を母、アカンボ製造機と見做すことは現代では甚だしい悪とされている。けれども『道草』は健三の実母が描かれない話だと見做した時、ここにはただ古い日本の男尊女卑の偏見があるわけではないと言えよう。それは勿論フェミニストお怒り小説第一位、芥川の『女』の畏怖とは全く異なるものだ。
この「女の義務」(五十三章)という理窟は後にかなり掘られる。後でやってもいいが、忘れそうなのでここでやってしまおう。
まず健三は確かに古い日本の男尊女卑の考えの中にいる。これは七十一章で露骨に説明されてしまう。現代ではもはや発禁レベルだ。
不思議にも学問をした健三の方はこの点においてかえって旧式であった。自分は自分のために生きて行かなければならないという主義を実現したがりながら、夫のためにのみ存在する妻を最初から仮定して憚らなかった。
「あらゆる意味から見て、妻は夫に従属すべきものだ」
二人が衝突する大根は此所ここにあった。
夫と独立した自己の存在を主張しようとする細君を見ると健三はすぐ不快を感じた。ややともすると、「女のくせに」という気になった。それが一段劇はげしくなると忽たちまち「何を生意気な」という言葉に変化した。細君の腹には「いくら女だって」という挨拶が何時でも貯えてあった。
「いくら女だって、そう踏み付にされて堪るものか」
健三は時として細君の顔に出るこれだけの表情を明かに読んだ。
「女だから馬鹿にするのではない。馬鹿だから馬鹿にするのだ、尊敬されたければ尊敬されるだけの人格を拵えるがいい」
健三の論理は何時の間にか、細君が彼に向って投げる論理と同じものになってしまった。
無論話者や漱石自身にはこの健三を「旧式」と呼ぶ程度のもう少し新しい時代の感覚はあったのだろう。従って健三の屁理屈がブーメランになる。健三は「尊敬されるだけの人格」を拵えていない。そういう健三の矛盾を突いて空威張りを牽制している。
そして御住に「いくら女だって、そう踏み付にされて堪るものか」と夫と独立した自己の存在を主張させたり、「双方とも手を出し始めた。打つ音、踏む音、叫ぶ音」として島田と御常を対等に喧嘩させたり(四十三章)、比田と御夏についても「二人の立ち廻りは今姉の自白するように受身のものばかりでは決してなかった」(五章)といった形で、けして女をただ弱きものとしては描いていない。
その一方でやはり女を「母」として捉えた時の考え方は窮屈なものである。
「芭蕉に実が結なると翌年からその幹は枯れてしまう。竹も同じ事である。動物のうちには子を生むために生きているのか、死ぬために子を生むのか解らないものがいくらでもある。人間も緩漫ながらそれに準じた法則にやッぱり支配されている。母は一旦自分の所有するあらゆるものを犠牲にして子供に生を与えた以上、また余りのあらゆるものを犠牲にして、その生を守護しなければなるまい。彼女が天からそういう命令を受けてこの世に出たとするならば、その報酬として子供を独占するのは当り前だ。故意というよりも自然の現象だ」
彼は母の立場をこう考え尽した後、父としての自分の立場をも考えた。そうしてそれが母の場合とどう違っているかに思い到いたった時、彼は心のうちでまた細君に向っていった。
「子供を有った御前は仕合せである。しかしその仕合を享ける前に御前は既に多大な犠牲を払っている。これから先も御前の気の付かない犠牲をどの位払うか分らない。御前は仕合せかも知れないが、実は気の毒なものだ」
この「母は一旦自分の所有するあらゆるものを犠牲にして子供に生を与えた以上、また余りのあらゆるものを犠牲にして、その生を守護しなければなるまい」とは、ぼんやりとした捨て子である健三の実母に対する恨み言でもあろうか。この狭量な「母の立場」の定義は確かに旧式なものではあろうが、不要な子として捨てられた者にしか分からない「渇望する理想の母」というものはまさにこうしたものなのであろう。健三の「女の義務」という言葉のうちには、「そうではなかった母」へのぼんやりとした恨みと共に、得られなかった理想が込められている。
ここをただ男尊女卑だから掘るのを止めようと逃げるのはまさに、
このロジックが見えていないから起こる誤読と云ってもよいだろう。
つまりしぶといのだ
健三の気分にも上り下りがあった。出任せにもせよ細君の心を休めるような事ばかりはいっていなかった。時によると、不快そうに寐ている彼女の体たらくが癪に障って堪らなくなった。枕元に突っ立ったまま、わざと樫貪に要らざる用を命じて見たりした。
細君も動かなかった。大きな腹を畳へ着けたなり打つとも蹴るとも勝手にしろという態度をとった。平生からあまり口数を利かない彼女は益沈黙を守って、それが夫の気を焦立たせるのを目の前に見ながら澄ましていた。
「つまりしぶといのだ」
健三の胸にはこんな言葉が細君の凡ての特色ででもあるかのように深く刻み付けられた。彼は外の事をまるで忘れてしまわなければならなかった。しぶといという観念だけがあらゆる注意の焦点になって来た。彼はよそを真闇にして置いて、出来るだけ強烈な憎悪の光をこの四字の上に投げ懸けた。細君はまた魚か蛇のように黙ってその憎悪を受取った。従って人目には、細君が何時でも品格のある女として映る代りに、夫はどうしても気違染いじみた癇癪持ちとして評価されなければならなかった。
とは言え、実際にはパワハラ、ドメスティクバイオレンス親爺であった漱石は、健三をまたそういう夫の一人として描いてしまう。現代の若い女性が読めば、読むに堪えない酷いことが書かれている。お腹が大きい奥さんを「しぶとい」などと憎むとは正しく異常である。
ここにある健三の感情は一体何なのだろうと考えてみて、これという旨い説明は思いつかない。「自分がすることをしておいて勝手だ」と笑えなくもないところを、どうもここは滑稽には書いていない。むしろ本当に芥川の『女』のほとんど「悪」それ自身のような母を描いているようでさえある。これは考えが旧式と言い訳ができることでもない。
こうした思いやりのなさは、やはり「尊敬されるだけの人格」のなさの具体的な表現で、これが後に子供の植木鉢を蹴飛ばすようなふるまいに繋がることは解る。それだけ鬱々としたもの、家族への親しみの無さを表わしているという形式は解る。
ただここに現れた健三という男がむしろ島田に対しては驚くほど寛容で癇癪を起さないのに、女房や子供には無暗に当たるという捻じれが何故のものなのかが解らない。ただの炬燵弁慶では面白くない。何か明確な意図がある筈なのだがなんなのだろうか。
明日解るかもしれないが今日は解らない。
[余談]
人間が読書できるのは「もともと別の機能があった脳の領域をリサイクルした」からと示す研究結果 - GIGAZINE
ふーん。
朗読が聞けるよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
