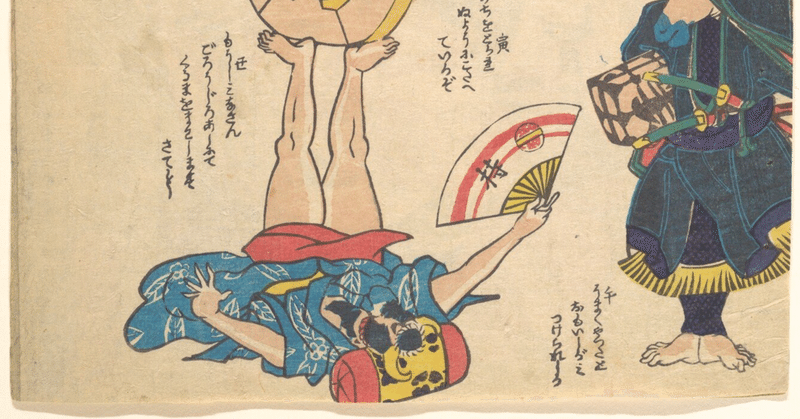
三島由紀夫の『花ざかりの森』をどう読むか④ 弟かもしれない
父は母屋にはふだんはいなかった。ひろい三棟の温室のわきへ、いおりのようなものをたててそこにいた。母屋とそのいおりとの間には、海原のようにお花ばたけだの菜園だの、葡萄や梨をうえた果樹園だのがひろがつていた。夏になると葡萄園のうえには蜂が雲のようにむらがっていた。ちかよってもある蜂はじつと葡萄のひろい葉にやすんでいた。わたしは庭のあちらにまばゆい夏の雲がたちあがり、そのために蜂の羽や毛がするどい黄金の針のように光るのを、それからやはり金いろをした巨きな目のなかに、かわいらしい夏雲が瀰ってゆくのをみた。……
二つ前の夢の中の景色は北国に雪の降り始める冬だったはずだ。しかしそんなことが問題ではない。母のことが書かれておらず母屋と父のいるいおりの位置関係の説明もいい加減なまま、果樹園の一部の葡萄園の話になり、蜂の話になり、夏雲の話に移った。『花ざかりの森』の文体は何かを物語るようでほとんど説明になっていない。決してそういう種類のユーモアではない。何かは語られ、ストーリは形作られない。なんなら何が起きているのかさえ定かではない。しかし古語や難読漢字が羅列されているわけでもない。少しは古言い回しもあるけれど、使われている言葉の殆どには少しの角ばったところのないもので、ある一行ごとの言葉の意味は明確でさえあるのだ。と私はすでに書いていた筈だ。その時あなたはどう思っていただろうか。
まさかね、そんなはずもあるまいにと。たしかにここは「夏雲が瀰(ひろが)って」しか難読な文字はないが、何が書かれているのは殆ど理解できなかったはずだ。流れからすればこれは繰り返し見る夢に出てくるたかい鉄門の内側の我が家の説明である筈なのだ。しかし「ひろい三棟の温室」はともかく、「海原のようにお花ばたけだの菜園だの、葡萄や梨をうえた果樹園だのがひろがつていた」などという景色が鉄門の奥にあるとすれば、それは殆ど新宿御苑のような長い壁に取り囲まれた領地をイメージしなくてはならないことになるのに対して、群がっていた筈の「ある蜂はじつと葡萄のひろい葉にやすんでいた」と画角は小さく転じ、なお「金いろをした巨きな目のなかに、かはいらしい夏雲が瀰ってゆくのをみた」で極小の画の中に拡大された夏雲が茫洋と氾るその撮影倍率の極端な変化に頭の中での絵の再構成が間に合わなかったはずである。
実際、
・鉄門の中の広大な敷地
・葡萄園のうえに雲のように群がる蜂
・葉の上で休む蜂
・蜂の目の中の夏雲
というカメラワークが私の説明で追いなおせた人も、「母」の問題と「父との距離」の問題、そして季節と、「温室では何が栽培されているのか」という問題、そして誰が果樹園の手入れをしているのか、米は作らないのかといった問題には気が回らなかったはずだ。昭和十六年十二月八日に太平洋戦争は始まる。まだ食糧難は始まっていないが、何とも暢気な景色過ぎるのである。
その景色はあくまでも夢のように暢気ながら、次にはこう書かれるのである。
母屋には祖母と母がすまっていた。私は幼な心も父と母の別居をいぶかったが、夜、祖母が痛みつかれてねいり、わたしもすっかり寝息をたてているとき、(ほんとうはちらちらと目をひらいては母の動静をさぐつているのだが)母が庭下駄をはいて、あかるい果樹園の月夜を、ずっとこちらまで長い影をひきずりながら、父のいおりへといそぐのを見た。そんなとき——これは悪い神経だろうか——わたしはむしろよろこばしいような愉しいような気持で、きづかない母のうしろ姿を眺めやったまみならず、しいておとなしくしようという殊勝な気持のほかには何も抱かなかった。
十六歳。
それは両親のセックスが一番恥ずかしくなる年齢ではなかろうか。
と、母が四つ這ひのやうな形でうつむいて、枕にこめかみをあてゝ、ちやうど縁側に立つてゐる私の方へ顔を向けてゐた。庭の明りのさす方へ向けてゐるわけなので、母の白い顔がよく見分けられた。その顔には苦痛の表情はなかつたけれども、私は母が癪か何かを起こしてゐて、父が上から背中を押してゐるのだと思つた。なぜなら母の顔の上に父の顔があつて、二つが上下に重なり合つてゐたからであつた。
谷崎潤一郎でさえ両親のセックスを冷静に捉えられるようなったのは年老いてからである。
それなのにまるで生活作文のようなほがらかさで、平岡公威少年は両親の逢引の様子を書いてしまう。そしてこれが夢の中の鉄の門の内側の母屋の話なのか、追憶の中の実際の景色なのか解らなくなる。
この部分だけ見れば追憶。しかし確かに夢の中の話だった筈なのだ。第一そんなに大きな屋敷など滅多にあるものではない。そして夢の話だと信じて読み進めようとすると忽ち話が見えなくなる。
祖母は神経痛をやみ、痙攣をしじゅうおこした。
これはもういくらなんでも夢のナラティブではない。実はこの前に改行はなく「何も抱かなかった。祖母」と切れ目はないのだ。ということはどこからどこまでが夢で、どこからが現実の追憶なのだろうか。
祖母の痙攣、うめき、うなり、病気の話はしばらく続く。
そのとき、わたしはありありと罎のなかに一匹の「病気」をみたのである。彼はごく矮さく、そろえた膝にあごをのせてねむっていた、自分の体を洗っている薬の海にはからきし気づかぬかのやうに。
そのさなかに「詩」が挟まれる。三島由紀夫作品を読むということはこうした「詩」に時々は付き合うという行為でもある。
これは具体的にはどういうことなのですかと問わない方がいい。これはすでに表層的な具体なのだ。寓意はなく詩だけがある。
母屋の果てのふるい部屋々々へ、わたしは兜やよろいや黒い毛ずねのような太刀なぞをみにいった。その帰り。婢はくりやへゆくほうの廊下でわたしと別れて、もうここからさきはおこわくはいらっしゃいますまい、と言いながらむこうへ行って了う。ほんとうはこれからがわたとにいちばんこわいのだ。しかしそれをいうのがわたしははずかしくて、哀訴ともなんともつかぬようなおもいをこめた目つきを投げるのがつねだった。それなのに婢は振り向いてくれない。三、四間さきの祖母のへやまでのあいだ。わたり廊下がひとつ。曲がりかどが三つ。——こはさにふるえながら、昼間のよく光った風がとおりすぎる暗い廊下を、ちょうどその風とおんなじにわたしが走ってゆく。と、角々で(ひとりは必ず)「病気」にであった。それもあたふたといそいでいる。わたしよりもずっと長身だ。顔のないのもあれば、顔のあるのもあった。顔のあるもののひとり、——それはつみもなくわらっていた。彼はまだ「死」と近しくない「病気」にちがいない。
天才。
そう簡単には書くことは出来ぬにしても、蓮田善明も一度はそう呟いてみぬことにはこのくだりを読み進めることはできなかったことだろう。

まさに教えて教えられるものでもなく、紅葉露伴、漱石鴎外をいくらお勉強したところで現れ得ない言葉の連なりがここにはある。
この追憶を三島由紀夫の最期の瞬間の証だと考えてみよう。女のように弱々しい、ちょっとしたものかげにもおびえるような幼い子供がいて、その傍らには疲れ切った生首がある。そして十六歳の天才少年は、「よく光った風がとおりすぎる暗い廊下」と書いてみる。風は光り、廊下は暗いのだ。「病気」は笑うこともできる。そんな追憶は生首の何も確かにしない。母は妹を拵えに行ったのだ、と三島由紀夫は書かなかった。その理由はまだ誰にも解らない。
何故ならばまだ書いていないからだ。
[余談]
氏は学習院の高等科時代に、母校の師であった清水文雄氏を通して雑誌『文芸文化』に近づき、それによって日本浪漫派につながった。氏の初期の作品に見られるおびただしい美辞麗句は、日本浪漫派の影響と言ってもよく、氏が十七歳のときに出版した短編集『花ざかりの森』は、読者に日本浪漫派の申し子のような印象を与えたのではないかと思う。
「思ってました」は「思ってませんでした」と同じ。が弊社の文化。本人的にはホントに「思っていた」としても、他人にそれはわからない。思いを表現や行動して、初めて周りに自分の考えを示すことができる。本人の思いが他人に認知され事実となる。「思ってました」は後からいくらでも言えるしね。
— 中山亮@マニュアル職人 (@rakayama) June 19, 2024
近代文学1.0は本当にこれ。
藤尾は自殺していない。
一郎は死んでいて、先生はホモではない。
かひやが下は蚊火屋の下ではなかろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

