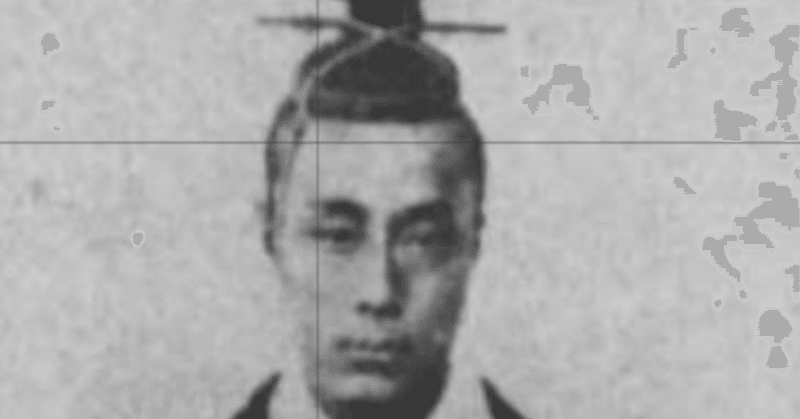
太宰を読め 平野啓一郎の『三島由紀夫論』を読む57
※その前に↑を読め
変革の思想
三島は、「『道義的革命』の論理」の中で、「国体思想そのものの裡にたえず変革を誘発する契機があって、むしろ国体思想イコール変革の思想」との考えを披露している。言うまでもなく、その「変革」の根源こそが、「永遠の現実否定」たる天皇であり、つまりこれが、国体における天皇の位置づけとなる。
この理屈は磯部浅一一等主計にちなんで言われたもののようだが、実は何度読み返しても良く解らない。一見天皇が変革のダイナモのような言われ方をしているように見えなくもない。しかし二・二六事件の首謀者の全体意見からはそうした天皇の位置づけは見えてこないからだ。
平野啓一郎も「三島由紀夫はこう書いている」という表層的な理解はしている気配はあるもののその意図を捉えきれていないようだ。
興味深いことに、三島は「国家と道義との結合は、つねに不安定な危険な看板」であるとし、「大東亜共栄圏と八紘一宇の思想」はその「擬制」の発展の帰結であり、現代の実例としては、アメリカの「自由と民主主義」が挙げられている。
この「擬制」は、より純粋な道義によって転覆される危険を常に帯びている。何故ならば、「道義の現実はつねにザインの状態へ低下」してしまうからである。これは、極めて今日的な指摘ともいえよう。
概ね間違っていないようだが「純粋な道義」といった時点で解っていないことが解る。道義は純粋でなくとも構わないのだ。ただ常に「本来の」とい言い張れば済むことなのだ。それに解っていないので書き方が小難しそうになっている。道義は理想である。理想の実現は難しいということをそんなにややこしく書くかね?
二・二六事件/蹶起趣意書
謹んで惟るに我が神洲たる所以は万世一系たる天皇陛下御統帥の下に挙国一体生成化育を遂げ遂に八紘一宇を完うするの国体に存す。
此の国体の尊厳秀絶は天祖肇国神武建国より明治維新を経て益々体制を整へ今や方に万邦に向つて開顕進展を遂ぐべきの秋(とき)なり。
然るに頃来(けいらい)遂に不逞凶悪の徒簇出して私心我慾を恣にし至尊絶対の尊厳を藐視(びょうし)し僭上之れ働き万民の生成化育を阻碍(そがい)して塗炭の痛苦を呻吟せしめ随つて外侮外患日を逐うて激化す、所謂元老、重臣、軍閥、財閥、官僚、政党等はこの国体破壊の元兇なり。
倫敦〔海軍〕軍縮条約、並に教育総監更迭に於ける統帥権干犯至尊兵馬大権の僭窃(せんせつ)を図りたる三月事件或は学匪(がくひ)共匪大逆教団等の利害相結んで陰謀至らざるなき等は最も著しき事例にしてその滔天(とうてん)の罪悪は流血憤怒真に譬へ難き所なり。中岡、佐(さ)郷屋(ごや)、血盟団の先駆捨身、五・一五事件の憤騰(ふんとう)、相沢中佐の閃発となる寔(まこと)に故なきに非ず、而も幾度か頸血を濺(そそ)ぎ来つて今尚些かも懺悔反省なく然も依然として私権自慾に居つて苟且偸(こうしょとう)安(あん)を事とせり。露、支、英、米との間一触即発して祖宗遺垂の此の神洲を一擲(いってき)破滅に堕せしむは火を睹るより明かなり。内外真に重大危急今にして国体破壊の不義不臣を誅戮(ちゅうりく)し稜(み)威(いつ)を遮り御維新を阻止し来れる奸賊(かんぞく)を芟除(さんじょ)するに非ずして宏謨(こうぼ)を一空せん。恰も第一師団出動の大命渙発せられ年来御維新翼賛を誓ひ殉死捨身の奉公を期し来りし帝都衛戍(えいじゅ)の我等同志は、将に万里征途に登らんとして而も省みて内の亡〔世〕状に憂心転々禁ずる能はず。君側の奸臣軍賊を斬除して彼の中枢を粉砕するは我等の任として能くなすべし。
臣子たり股肱たるの絶対道を今にして尽さずんば破滅沈淪(ちんりん)を飜すに由なし、茲に同憂同志機を一にして蹶起し奸賊を誅滅して大義を正し国体の擁護開顕に肝脳を竭(つく)し以つて神洲赤子の微衷を献ぜんとす。皇神皇宗の神霊冀(こいねがわ)くば照覧冥(めい)助(じょ)を垂れ給はんことを!
昭和拾壱年弐月弐拾六日
陸軍歩兵大尉 野中四郎
外同志一同
こうして二・二六事件の首謀者の代表意見を確認してみると「進展」とは言っているけれどここに「絶えざる変革」というニュアンスはない。
で問題は「万邦に向つて開顕進展を遂ぐべき」というのはいわば戦争の準備のために国家総動員できる体制を構築し、軍拡せよと言っているわけだという点にある。ナチスかぶれの軍閥が戦争を始めようとしたわけではなく、この青年将校らは八紘一宇を完うするの国体=皇道政府と強い軍隊を目指そうとしていたわけで、この点においては『英霊の声』の言い分とは少し違いが見られる。
そして少なくともここに「国体思想イコール変革の思想」という筋は見えない。今皇道政府と強い軍隊が必要だと言っている訳で、それは確かに変革ではあるけれど、国体とは本来そうあるべきところというニュアンスが強い。
国体を守るのは、軍隊であり、政体を守るのは警察である。政体を警察力を以て守り切れない段階に来て、はじめて軍隊の出動によって国体が明らかになり、軍は健軍の本義を回復するであろう。日本の軍隊の健軍の本義とは、「天皇を中心とする日本の歴史・文化・伝統を守る」ことにしか存在しないのである。国のねぢ曲った本体を正すという使命のため、われわれは少数乍ら訓練を受け、挺身しようとしていたのである。
ここでも国体を守る、と言っており、国体が変革の原動力という考えは見えない。しかし守ると言いながらも変革が求められている。この「守ると言いながらも変革が求められている」という担がれやすい性質が国体の正体なのであろうか。なんでもねじ曲がっている、本来はこうあるべきだと言っていれば変革の根拠になりうるというわけか。
【天皇】
天皇は国体である
天皇は神勅を奉じて祭祀を司る
皇位は世襲であって、その継承は男系子孫に限ることはない
天皇の国事に関するすべての行為は、顧問院が輔弼し、内閣がその責任を負う
顧問院は天皇に直属し、国体を護持する
顧問院は勅撰議員によって構成される
天皇は議会、内閣、裁判所を設置する
天皇は国軍の栄誉の源である
天皇は統帥権の運用および軍の最高指揮権を顧問院ならびに内閣に委ねる
天皇は衆議院の指名に基づき内閣総理大臣を任命する
天皇は内閣の輔弼により最高裁判所長官を任命する
天皇は顧問院の輔弼により検事総長、教育長官を任命する
天皇は国会(注・一院制)を召集し、衆議院を解散する
【国防】天皇に言及のある条文のみ抜粋
日本国軍隊は、天皇を中心とするわが国体、その歴史、文化を護持することを本義とし、国際社会の新倚と日本国民の信頼の上に健軍される
【非常事態法】
天皇は不測の事態により国の安寧秩序が脅かされる時は、公共の安全を保持し、またはその災厄を避けるため、戒厳令を宣告する
戒厳の要件および効力は法律で之を定める
担がれている。
ここでもはっきり天皇は国体であると言っているが、「護持」と言っており、変革のイメージがまるでない。イメージはまるでないけれど言われていることは確かに変革である。天皇をだしに、本来はこうあるべきだと、今の状況を変化させようとしている。無論決して過度な要求はない。天皇に祭司的な役割を負わせているだけだ。神話を否定した天皇が、現実的には古来のおまじないのような儀式を現に続けていることを鑑みれば、三島天皇論はむしろ現状肯定である。神話を否定したんなら全国のインチキな神社はすべて取り壊せと言わないところが大人である。
徳川幕府二百年の太平から、さまざまの文芸が生れたが、その発達と共に、遠い祖先の文芸思想にも触れる機会が多くなり、その研究が真剣に行われ始めたのと同時に、徳川幕府も、ようやくその政治力の困憊期にはいり、内にあっては百姓の窮乏を救うこと能わず、外にあっては諸外国の威嚇に抗し得ず、日本国をしてまさに崩壊の危機に到らしめた間一髪に於いて、遠い祖先の思想の研究家たちは、一斉に立って、救国の大道を示した。曰く、国体の自覚、天皇親政である。天祖はじめて基をひらき、神代を経て、神武天皇その統を伝え、万世一系の皇室が儼乎として日本を治め給う神国の真の姿の自覚こそ、明治維新の原動力になったのである。この天地の公道に拠らざれば救国の法また無しと観じて将軍慶喜公、まずすすんで恭順の意を表し、徳川幕府二百数十年、封建の諸大名も、先を争って己の領地を天皇に奉還した。ここに日本国の強さがある。如何に踏み迷っても、ひとたび国難到来すれば、雛の親鳥の周囲に馳せ集うが如く、一切を捨てて皇室に帰一し奉る。まさに、国体の精華である。御民の神聖な本能である。これの発露した時には、蘭学も何も、大暴風に遭った木の葉の如く、たわいなく吹き飛ばされてしまうのである。まことに、日本の国体の実力は、おそるべきものである、という周さんの述懐を聞いて、私の胸は高鳴り、なぜだか涙がだらしないくらいに出て、坐り直して私は周さんに尋ねた。
「それでは、あなたは日本には西洋科学以上のものがあると言うのですね?」
「もちろんです。日本人のあなたが、そんな事をおっしゃるのは情無い。日本が露西亜に勝ったではありませんか。露西亜は科学の先進国です。科学知識を最高度に応用した武器を、たくさん持っていたに違いない。旅順の要塞も、西洋科学の Essenz でもって築かれたものでしょう。それを日本軍は、ほとんど素手で攻め落しているじゃありませんか。外国人には、この不思議な事実が理解できかねるかも知れない。支那人にだって、わかるまい。とにかく僕は、もっともっと日本を研究してみたい。興味津々たるものがあります。」と爽かに微笑して言った。
表向きの三島国体論はほぼこの太宰治の『惜別』の範疇に収まるような素朴なものに感じられる。三島由紀夫を読むものは太宰治を読まないという妙な傾向があるので殆どこの指摘はされない。しかし三島由紀夫の国体論はたまたまか必然的にか、この本来帰るべき場所としての国体論をベースにしている。
そしてやはりこの国体論には変革のイメージではなく「皇室に帰一し奉る」という集合場所と言うか目印と言うか、それこそ天皇の馬前であったり、宮城といった位置のことではないかと思える。しかし結果として国体が御一新の原動力になっている。
例えば倒幕思想は、国体の護持の為の国家転覆思想の一つであったと考えてよかろう。ここでは国体思想が天皇を中心に変革の役割を果たした。天皇が永遠の現実否定して来たとも思えないけれども、少なくとも現実的にはただ一度は国体が国家を変革したのである。
大日本帝国は、万世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、我が万古不易の国体である。而してこの大義に基づき、一大家族国家として億兆一心聖旨を奉体して、克く忠孝の美徳を発揮する。これ、我が国体の精華とするところである。この国体は、我が国永遠不変の大本であり、国史を貫いて炳として輝いている。而してそれは、国家の発展と共に弥々鞏く、天壌と共に窮るところがない。我等は先づ我が肇国の事実の中に、この大本が如何に生き輝いているかを知らねばならぬ。
ただ基本国体とは不変であるべきものだ。あるべきものだがなかなかあるべき状態にならない。なぜならどのような状態になっても「違う違うそうじゃない」と文句を言うものがいるからだ。つまり国体とは本来あるべき天皇で、千五百年生きて、ぴかーっと光って、国民を誰一人飢えさせてはいけなくて、なんなら地震も起こさせてはいけないのだ。つまり本来の国体=ありうべき、あり得ない天皇なのだ。
(ヒロヒト 詔書 曰ク 国体はゴジされたぞ 朕はタラフク食ってるぞ ナンジ人民 飢えて死ね ギョメイギョジ」表面、「働いても 働いても 何故私達は飢えねばならぬか 天皇ヒロヒト答えて呉れ 日本共産党田中精機細胞」裏面)
国体は天皇だ。やはり冒頭に挙げた三島の国体論はその他さまざまな三島の国体観ともずれており、極端に異質で、誰とも折り合いがつけられない屁理屈に見える。「永遠の現実否定」たる天皇などというものは本来存在しなくて、国体=ありうべき、あり得ない天皇なのであり、「永遠の現実否定」たる天皇というのは三島由紀夫の言いがかりに過ぎない。何かまずいことがあると国体を護れと言って本来の国体でないことが指摘されうる。何が起きても文句を言われるのが天皇という理屈が三島の国体論である。それではあまりに天皇が気の毒だ。それこそ天皇が屁をこいても三島には叱られそうだ。
しかしこれはごくマイルドにしてみれば全然理解できない考えというわけでもない。天皇制とは『続日本紀』なんかを読めば確かに天皇と民草の関係において自然発生的にか制度としてか、現実的に続いてきた信頼関係のようなもので、「なゐふる」、つまり地震が起こると賑給たまはる(特別一時給付米がもらえる)、とか吉祥の白い蛇が見つかると天皇に献上されるとか、そういうお互いがお互いをいつくしみ・あがめる形で天皇はお上として機能してきたわけだ。
保育園落ちた、日本死ねというような純粋と言うか単なるあほな言説が「永遠の現実否定」である。冒頭の三島由紀夫の理屈では天皇はそこまで面倒を見なくてはならないことになってしまうが、三島天皇論はそこまであほではない。つまりいい感じに変革したらあとは現状維持でいいので、「永遠の現実否定」としての天皇ではなくなってしまう。そりゃ何でも文句つけようとしたらあるよ。犬猫の処分ゼロにしろとか、ベンチが少ないとか、そういうことまで含めての永遠の現実否定を天皇に押し付けるのかね? そりゃないよね。三島由紀夫だけは天皇が本当はただのヒトであり、永遠なんてものはないということを知っていたのだ。
しかし最初のところに戻って「国体思想そのものの裡にたえず変革を誘発する契機があって、むしろ国体思想イコール変革の思想」という考え方が、担がれるものが神輿で、神輿は担がれるものといいう理屈に収まるかどうかは怪しいところだ。
三島自身の最後の言葉でも「国体思想そのものの裡にたえず変革を誘発する契機があって」という発想に反して、変革が外因性であることを認めている。
僕がずっと考えてきたことはね、どうして日本には内発的な革命が起きないか、明治維新だって黒船が来なきゃ起こらなかったでしょ。それでまあ、今度の敗戦がなきゃ、都市改革は行われなかったでしょうね。そしてそれをやらなきゃならないってことを本当に解かっていながらできないんです、日本は。それはね、天皇制があるからだろうか、ということをまず考えたわけですね。
次にはこう考えたんです。
内発的な側面がないから天皇制が保たれてきたんだろうかと。逆の発想ですよね。私は次にこう考えた。天皇制がないから内発的な革命があるんだろうか。内発的な革命がないから天皇制があるんだろうか。ぼくはこの問題はそこに帰着するように思うんですね。最終的には。
国体思想が変革の契機だという理屈を通すとすれば、外圧に対する揺り戻しの根拠が国体である、とでも言ってみるしかないが、やはりここいらの定義はもう少しすっきりした形でまとめ直さないとどうにもならないように思える。何度も書いたが解ってはいけないことを解ってしまうのも駄目なことである。
[附記]
最後の言葉だけ読むと天皇あるいは国体というのは変革の契機ではなくてむしろ防御側、免振装置みたいなものに見えるんだよなあ。「変革を誘発する契機」を担がれやすさにしてしまうと、それは内部ではなくて外部なんだよな。
ところで、「蹶起趣意書」を実際に読むと難しい言葉がたくさん出てきてびっくりするでしょ。現実に危機は目の前に迫っていたわけで、彼らも馬鹿ではなく、真剣に日本のことを考えていた。「露、支、英、米との間一触即発して祖宗遺垂の此の神洲を一擲(いってき)破滅に堕せしむは火を睹るより明かなり」って実際そうなっちゃったしね。
そんな彼らが愛した日本のためにも平野啓一郎の『三島由紀夫論』は改められるべきなんだよなあ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
