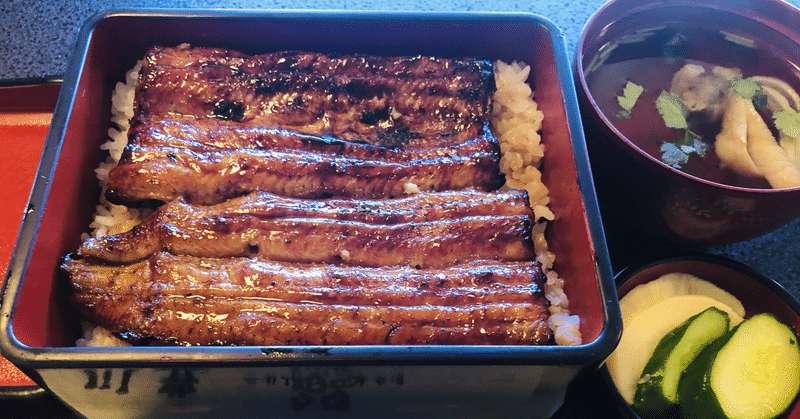
谷崎潤一郎の『金色の死』を読む 芸術は金では買えない
こゝに集めたる三篇は、一昨年の秋より昨年の秋にかけて作りたるものなり。その間に予は又別に「お艶殺し」を書き、「お才と己之介」を書きたり。後の二篇は旣に早く單行本として出版せられたるに前の三篇は「人氣少きが故に」今日まで其の機會を逸したるが如し。
人氣少きにも拘らず、予は彼の二篇より此の三篇を好むものなり。「お艶殺し」と「お才と己之介」とは、執筆中に知らず識らず人情本的興味に引き擦られ、予が濃厚なる主觀の色を自由に純粹に盛り上ぐる能はざりき。殊に「お才と己之介」に於いて、脫稿の後予は我ながら其の舊臭の堪へ難きか感じたりと記憶す。
「人氣を博するは容易の業なり。」とワイルドは云へり。然り、人氣を博するは容易なるが故に、又作家に取りて決して不愉快ならざるが故に、人氣は我等の恐るべきものなり。自ら警むること深からずば、或は我等は人氣の爲めに蠶毒せられん。
「お才と己之介」の世評喧しかりし時、予は寧ろ不當なる人氣に對して反感を抱きつゝありしかど、而も猶胸中の嬉しさを禁する能はざりき。予は予の淺ましさを後悔せるが故に斯く自白す。予は予の淺ましさを後悔せるが故に斯く自白す。後悔は改悛を伴ふものなり予は改悛せんとするなり。
大正五年五月 谷崎潤一郞
The three stories collected here were written between the fall of the year before last and the fall of last year. During that time, I also wrote "O-Yatsura" and "O-Sai to Konosuke" separately. While the latter two stories were published in book form earlier, the first three stories have not been published until now due to lack of popularity. Despite their scarcity, I prefer these three stories to his two. In the writing of "Oyamachi-killer" and "Osai to Konosuke," I was unknowingly drawn into the humanistic interest and could not freely and purely express the color of my rich subjective viewpoint. In particular, in "Osai to Minosuke", I remember that after reading the first draft, I felt the unbearable smell of the old days. It is an easy task to win people's hearts. Wilde said. But because it is so easy to gain publicity, and because it is never unpleasant for the writer, publicity is something we should be afraid of. If we are not careful, we will be poisoned by it. When the public was talking about "OSAI TO KINOSUKE," I was more against the wrong people, but I couldn't stop myself from being happy. I confess this because I regret my repentance. I confess this because I regret my repentance. I am penitent, and I will be penitent. May, 1916, Tanizaki Junichiro
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
ここに収めた3編は、一昨年の秋から昨年の秋にかけて書いたものです。この間、『お八つ』『お賽銭と幸之助』も別に書いています。後者2編は先に単行本化されましたが、前者3編は人気がなく、今まで出版されませんでした。その希少性にもかかわらず、私は彼の2編よりこの3編の方が好きである。「親町殺し」と「おさいと幸之助」の執筆では、知らず知らずのうちに人情味に引きずられ、自分の豊かな主観の色を自由に、純粋に表現することができなかったのである。特に「おさいとみのすけ」では、初稿を読んだ後、耐え難いほどの古臭さを感じたことを覚えている。人の心をつかむのは簡単なことである。とワイルドは言った。しかし、世評を得るのは簡単で、しかも作家にとって決して不愉快なことではないので、世評というのは恐れるべきものである。気をつけないと、それに毒されてしまう。世間で『おさいときのこすけ』が話題になったとき、私はどちらかというと悪い人たちに反発していたのですが、嬉しい気持ちは抑えきれませんでした。懺悔するのは、後悔しているからです。私は自分の懺悔を後悔しているので、このことを告白します。私は懺悔し、懺悔するつもりである。大正5年5月、谷崎潤一郎
www.DeepL.com/Translator(無料版)で翻訳しました。
こんな序とともに世間に問われた谷崎の『金色の死』は、『饒太郎』にいや増して「論文のような小説」であり、いくつもの奇妙な仕掛けを拵えている作品である。
その筋は、「私」の少年時代からの友人、岡村君が三井岩崎の半分ぐらいはあるという財産を使い果たして、仙石原から乙女峠へ通う山路を少し左へ外れた盆地二万坪を芸術の天国に作り上げ、全身に金箔を塗りたくって踊り狂った挙句死んでしまうというものだ。
岡村君は独特の価値観を有していた。
けれども僕の考へでは、滑稽な人物は何處迄も滑稽で、奇怪な死に樣をすればする程猶更面白い氣がするぢやないか。生きて居てさへ可笑しなテルシテスの顔が滅茶々々に叩き潰されて血だらけになつて蠢いて居る所を想像すると、實際滑稽に思はれるぢやないか。
(谷崎潤一郎『金色の死』)
これだけのことを言うために、谷崎はレッシングの『ラオコーン』の原文を二度も長尺で引用する。
Achilles ergrimmt, und ohne ein Wort zu versetzen, schlägt er ihn so unsanft zwischen Back' und Ohr, daß ihm Zähne, und Blut und Seele mit eins aus dem Halse stürzen. Zu grausam! Der jachzornige mörderische Achilles wird mir verhaßter, als der tückische knurrende Thersites; das Freudengeschrei, welches die Griechen über diese Tat erheben, beleidiget mich; ich trete auf die Seite des Diomedes, der schon das Schwert zucket, seinen Anverwandten an dem Mörder zu rächen: denn ich empfinde es, daß Thersites auch mein Anverwandter ist, ein Mensch.
アキレスは激怒し、言葉もなく頬と耳の間を無造作に殴り、歯と血と魂が一度に喉から落ちてしまいます。残酷すぎる! 復讐に燃え、殺人を犯すアキレスは、裏切り者で唸り声を上げるテルシテスよりも、私にとって憎い存在です。この行為にギリシャ人が上げる歓喜の声は、私を怒らせます。私は、近親者を殺人者に復讐しようとすでに剣を突き立てているディオメデスに味方します。テルシテスが、私の近親者で人間でもあると感じるからです。
だから、ラオコーンがため息をつくと、想像は彼の叫び声を聞くことができる。しかし、彼が叫ぶと、この想像から一歩も高くも低くも上がらず、より悲惨で、結果として面白みのない状態にある彼を見ることになるのだ。最初に泣き声を聞いたり、すでに死んでいるのを見たりする。
原文は例によってグーテンベルクで読むことが出来る。(余談のところにリンクを張っているので、ちらっと覗いてみてもらいたい。)この岡村の主張はやはり一貫もしていないし、ラオコン論争の域を半歩もはみ出していない。一貫していないのは例えばこういう点だ。
世の中に純粹の悲哀だの、滑稽だの、乃至歡喜だのと云ふものが存在する筈はないのだから。(谷崎潤一郎『金色の死』)
この主張は「滑稽な人物は何處迄も滑稽」という前言と明確に食い違う。かりそめの権威を笠に着る小役人の傲慢ごときの下劣な人間性はどこまでも下劣なものだとは思うが、滑稽とは情緒に支持される評価なので、滑ることもあるだろう。また、
「だから僕の最も理想的な藝術と云へば、眼で見た美しさを成る可く音樂的な方法で描寫する事にあるんだ。」
「そんなむづかしい事が出來るつもりなのかい。」
「出來ないまでも努力して見ようと思ふのさ。」(谷崎潤一郎『金色の死』)
こう言って置きながら岡村君が拵えたのは西洋芸術(彫刻中心)をあれもこれもかき集めたコスプレ・テーマパークであり、そもそも全く「音楽的」ではない。後の三島由紀夫のこじんまりとした邸宅のアポロ像のセンスのなさを思い出させる。縁あって、私は金持ち相手に美術品を売っていたことがある。金持ちの美術品の買い方は一言でいえば節操がない。あれこれの様式の、有名なものを欲しがる。美とは何なのか、全く解っていないのが美術品の購入者なのだ。岡村君のふるまいは、自分には美術の美とは何のことかさっぱりわかりません、むしろ美術に美など認めませんと言わんばかりだ。無論あれもこれもというか、あやれこれやの水準を認めうる審美眼というものはありうるだろう。ピカソもルーベンスもパンクロックもデスメタルも民謡も都都逸も侘茶もリリックも、低温調理も、e-Taxもセルフレジも、なんでも解るという人はいなくもないだろう。しかしおそらく美とは偏りである。そのことは谷崎も明記している。
「人間の肉體に於て、男性美は女性美に劣る。所謂男性美なるものゝ多くは女性美を模倣したるもの也。希獵の彫刻に現れたる中性の美と云ふもの、實は女性美を有する男性なるのみ。」
「藝術は性慾の發現也。藝術的快感とは生理的若しくは官能的快感の一種也。故に藝術は精神的のものにあらず、悉く實感的のもの也。繪書彫刻音樂は勿論、建築と雖も亦其の範圍を脫することなし。」(谷崎潤一郎『金色の死』)
こうしたところ「女性美を模倣」「實感的のもの」という要素も掘り下げられない。「多勢の美男美女を撰りすぐり、羅漢菩薩の姿をさせたり、悪鬼羅刹の装いをさせたり」という辺りには「女性美を模倣」の気配がない。「實感的のもの」というのも「自分は満身に金箔を塗抹して如来の尊容を現じ、其の儘酒を呷って躍り狂いました。」という辺りにあるのかも知れないが、折角金箔を塗っても自分では自分の踊りは見られまい。彫刻は眺めるもので実感的ではなかろう。
「あゝ西洋へ行きたい。西洋へ行きたい。立派な體格を持つた西洋人に生れなかつたのは僕の第一の不幸だ。」色の其の時分、彼の西洋崇拜熱は非常に旺盛になつて、一としきり「日本の物は何でも嫌ひだ。」などと云ひました。(谷崎潤一郎『金色の死』)
こうした西洋への憧れがあるのに、なぜ金に飽かしてわざわざ日本の箱根にコスプレ・テーマパークを作ったのか。何故西洋人を集めないのか。どうも中途半端で、むしろ中身そのものはチープではなかろうか。ところが「私」は小説家として成功しながら、別の芸術の可能性を考え、どこかで岡村君の芸術を恐れているようなところがある。
自分は生涯斯くの如き苦痛を犯して、生活の爲めに愚にも付かない「お話」を書き續けなければならないのか。さう考へると藝術家ぐらい非藝術的な、無意味な月日を送るものはないと云ふやうな心細さに襲はれました。心細いにつけても想ひ出すのは岡村君の事でした。(谷崎潤一郎『金色の死』)
この「生活の爲めに愚にも付かない「お話」を書き續けなければならないのか。」……という苦悩が、実際の谷崎の実感とはかけ離れたものであったことは疑いようはない。確かに『熱風に吹かれて』はやや引き延ばされた感じがある。姦通を餌に読者を釣っている要素もある。しかし肝心なことはまだ起きないで終わる。『捨てられる迄』もやや長い。幸吉が女言葉になるのは奇妙な具合だ。幸吉が死んだかどうか曖昧で、賺しになっている。しかし『饒太郎』はなかなかの野心作だ。長いのは長いが、中身がしっかり詰まっているし、面白い工夫がある。
谷﨑が『金色の死』を書いている時点では「序」に書かれたようないきさつ、つまり「人氣少きが故に」今日まで其の機會(単行本化)を逸したるが如し、という状況はまだ見えなかった筈である。だからこそ谷崎は『金色の死』という奇妙な作品を書くことができたのだ。
ラオコオン論争にふれながら、視覚芸術(空間芸術)と言語芸術(時間芸術)の区分に挑みながら、また、
先ず第一の定義からして僕には随分反対の点がある。成る程絵画は事物の共存状態を描くには違いない。けれども前後の経過を了解せしむるに足る含蓄ある瞬間を択ばなければならないと云う理屈が何処にあるだろう。絵画の興味は、画題に供せられた事件若しくは小説に存するのではない。たとえばロダンの作物の中に一人の人間が一人の人間の死骸を抱いて居る彫刻があって、其れに『サッフォの死』と云う題が付けられて居たとするね。ところで其の作品から美感を味わう為には、是非共サッフォの伝記を知らなければならないのだろうか。其瞬間の前後の経過を了解しなければならないのだろうか………。(谷崎潤一郎『金色の死』)
……こう岡村君に語らせながら、逆に『金色の死』にはこんな記述が溢れているのだ。
「此れはルウヴルにある希臘時代の『ピオムビノウのアポロ』だ。此れはナポリにある『ポムペイのアポロ』だ。ポリクレトの『ドリフォロス』だ。」
岡村君は歩きながら一々熱心に説明します。最も薄気味悪く感ぜられたのは、六角堂の屋根や廊下や石段に暴れ狂って居る一団の人影で、而もその排列が甚だ不規則に死体を投げ捨てた如く置かれて居るのです。それ等の多くはロダンの作品の中でも、一番刺戟的な姿勢や表情を持って居るもので、先ず甍の上には「鼻の欠けた人」や、「女の頭」や、「泣き顔」や、「苦痛」や、五つ六つの青銅の人の顔が、生首のようにごろごろと転がって居ました。「ウゴリノ伯」が餓に迫って我が子を喰い殺そうとして居る悽惨な形は、檻に入れられた虎の如く階段の上り口に這って居ます。「ヴィクトル、ユウゴオ」が欄干に肘を衝いて片手を伸ばして居るかと思えばその後に「サティイルとニムフ」が戯れ、「絶望」の男が足を抱えて倒れて居る傍には、「春」の男女が抱擁して接吻を交わして居ます。(谷崎潤一郎『金色の死』)
余談のところにできるだけリンクを張ったので確認してもらいたい。谷崎が並べ立てる彫刻類を思い浮かべることは余程の好事家でなくてはかなわないことだ。私は村上春樹作品に現れるクラシックやジャズの音楽をほぼ無視して、なんとなく音のない世界で作品を読んでいる。それでもザ・ビートルズの曲などはどうしてもイメージしてしまうことになる。ヤナーチェクの『シンフォニエッタ』も聞いてしまった。そのために少し『1Q84』のイメージが変わった。谷崎が並べ立てる彫刻類を思い浮かべるとやはり少しイメージが変わる。しかし、繰り返すが谷崎が並べ立てる彫刻類を思い浮かべることは余程の好事家でなくてはかなわないことなのだ。その事実を谷崎自身が証明している。「たとえばロダンの作物の中に一人の人間が一人の人間の死骸を抱いて居る彫刻があって、其れに『サッフォの死』と云う題が付けられて居たとするね。」と谷崎は岡村君に語らせる。
しかし『サッフォの死』はオーギュスト・ロダンの作ではなく、ギュスターブ・モローの作ではないのか?
「億兆の國民」から始まって、「お役人に聞かれると惡い」「足利尊氏は偉い」「紂王の寵妃、末喜」「やめておけ、やめておけ、今の政治に携わるのは危険なことだよ」「羽前國」「たとへ京都は、一旦右衛門の督や左馬頭の手に落ちても、昔から朝敵の栄えた例はございませぬ」「長く此の國の女王となった」「世間一帶がなんとなくお祭りのやうに景気附いて居た四十年の四月の半ば頃」「五段目の勘平」に続く、メッセージが繰り返されていまいか。
「ボクヲシンヨウシテハイケマセン」
谷崎潤一郎は繰り返しこう念押ししているのではなかろうか。これだけ衒学的にあちこちから色んな名前を持ってくれば、あるいはドイツ語を長尺で引用すれば、大抵の人は腰が引けてしまい、そんな相手なら簡単に誤魔化されると考えたのだろう。現に「億兆の國民」から「五段目の勘平」までのあからさまな錯誤というレトリックを指摘する者はこれまでこの宇宙でこの私唯一人だけしかいないだろう。「紂王の寵妃、末喜」に気が付いている人は何人かいるが、そこを掘ろうとした人は見つからない。
むしろ谷崎は視覚芸術の彫刻の名前を言語芸術の中に並べ立てて、いったい何が面白いのかね、と読者に対して挑発していないだろうか。これは島縮緬とか角帯とか、そうした風俗の言葉を現代人がイメージできないこととは次元の違う話だ。そもそも『熱風に吹かれて』はやや引き延ばされた感じがある。姦通を餌に読者を釣っている要素もある。…などと勝手な感想を述べる読者の何割が、レッシングの『ラオコーン』の原文を読んで理解できるものだろうか。谷崎はわざと原文を長々と引いている。全体はドイツ語、英語、ギリシャ古語が混交しているので、DeepLを駆使してもなかなか読むのは困難だ。谷崎はどこまでギリシャ語ができたのだろうか。どうして谷崎は斯くまでに尖らなくてはならなかったのか?
それはまさに「生活の爲めに愚にも付かない「お話」を書き續けなければならないのか。」という苦悩の真逆、そして「満身に金箔を塗抹して如来の尊容を現じ、其の儘酒を呷って躍り狂いました」とも真逆、どこを指すともベクトルの不確かながら、確かに作者をして「人氣少きにも拘らず、予は彼の二篇より此の三篇を好むものなり」と書かしめる谷崎潤一郎の意地の見栄であろう。
【余談①】『金色の死』言葉たち
企及 努力して、追いつくこと。肩を並べること。
擔とは、になう/かつぐ/肩にかつぐ/助ける
聘する 招聘する めとる/めす/礼をつくして招く/とう/たずねる/おとずれる
Sur L'eau モーパッサンの『水の上』という短編小説
鐵棒 かなぼう
後庭 こうてい 建物の裏側にある庭園。
石鐵砲 パチンコ?
轆轤 ろくろ
左袒 味方することや、賛成することのたとえ。「袒」は衣を脱いで肩をあらわにする意で、中国、前漢の功臣周勃 (しゅうぼつ) が呂氏 (りょし) の乱を鎮定しようとした際、呂氏に味方する者は右袒せよ、劉氏 (りゅうし) に味方する者は左袒せよ、と軍中に申し渡したところ全軍が左袒したという「史記」呂后本紀の故事から》味方すること。
貧乏揺ぎ びんぼうゆるぎ。すわっているとき、膝のあたりを絶えずこまかくゆり動かすこと。少し動くこと。
嘆聲 なげきの余り発する声。 嘆息。 感心してあげる声。 また、ある感情をこめた声。
唐桟
「唐桟」(とうざん)とは、江戸時代、東南アジアからもたらされた縞木綿のことです。 特色は、平織りで、極めて細い双糸を使うことで、木綿でありながら、絹そっくりの風合いを持っています。 江戸時代、遠い南の国からもたらされたエキゾチックな縦縞の「唐桟」は、粋で、人気を博しました。
結城
結城紬は、茨城県結城市を中心とした地域で作られている着物です。重要無形文化財として指定されている最高級の絹織物で、着物を着慣れた人ほどあこがれる着物でもあります。軽くて柔らかい肌触りで、着れば着るほどに風合いが増します。
https://ichiri-mall.jp/shop/c/cAB13/
因循 古いしきたりに従っているだけで改めようとしないこと。煮え切らない事。因循姑息。
伊達寛濶 気質、服装などのはでなさま。伊達模様廓寛濶 (だてもよう くるわのかんかつ)からか。
石持の綿入 石持(こくもち) ... 防寒を兼ねて綿入れ仕立てにする家庭でのくつろぎ着。
黄八丈
白博多の角帯
美顔術師
安本のレクラム
ラオコオン
レッシング
Achilles ergrimmt, und ohne ein Wort zu versetzen, schlägt er ihn so unsanft zwischen Back' und Ohr, daß ihm Zähne, und Blut und Seele mit eins aus dem Halse stürzen. Zu grausam! Der jachzornige mörderische Achilles wird mir verhaßter, als der tückische knurrende Thersites; das Freudengeschrei, welches die Griechen über diese Tat erheben, beleidiget mich; ich trete auf die Seite des Diomedes, der schon das Schwert zucket, seinen Anverwandten an dem Mörder zu rächen: denn ich empfinde es, daß Thersites auch mein Anverwandter ist, ein Mensch.
アキレスは激怒し、言葉もなく頬と耳の間を無造作に殴り、歯と血と魂が一度に喉から落ちてしまいます。残酷すぎる! 復讐に燃え、殺人を犯すアキレスは、裏切り者で唸り声を上げるテルシテスよりも、私にとって憎い存在です。この行為にギリシャ人が上げる歓喜の声は、私を怒らせます。私は、近親者を殺人者に復讐しようとすでに剣を突き立てているディオメデスに味方します。テルシテスが、私の近親者で人間でもあると感じるからです。
↓ これ読んでみて。飛ぶぞ。
テルシテス
ペエタアのルネッサンス
ペーター
ロダン? オーギュスト・ロダン?
『サツフオの死』 ギュスターブ・モロー?
Wenn Laokoon also seufzet
Wenn Laokoon also seufzet, so kann ihn die Einbildungskraft schreien hören; wenn er aber schreiet, so kann sie von dieser Vorstellung weder eine Stufe höher
だから、ラオクンがため息をつくと、想像は彼の叫び声を聞くことができる。しかし、彼が叫ぶと、この想像から一歩も高くも低くも上がらず、より悲惨で、結果として面白みのない状態にある彼を見ることになるのだ。最初に泣き声を聞いたり、すでに死んでいるのを見たりする。
豊国
ロオトレイク
チヤリネ サーカスの別称。
クイジイン cuisine
孤影悄然 孤影蕭然 ひとりでさみしげなさま。
翠緑 すいりょく みどりいろ。
龍頭鷁首 船首にそれぞれ竜の頭と鷁の首とを彫刻した二隻一対の船。 平安時代、貴族が池や泉水などに浮かべ、管弦の遊びなどをするのに用いた。 りゅうとうげきしゅ。 りょうとうげきす。
鷁 想像上の水鳥の名。 白色で、形は鵜(う)に似ていて、大空を飛び回り、また、巧みに水にもぐるという。 一説には、風鳥ともいう。 天子の船などの先端に、この鳥の首を刻むことが多かったので、転じて、その船をもいう。
奔湍 ほんたん 早瀬。急流。
嵯峨 さが 山などの高く険しいさま。
千態萬状 種々さまざまの状態。
遊仙窟
釣殿
寝殿造りで、東西の対(たい)の屋から出た廊の南端にある、池に臨んだ建物。 納涼・月見などのために用いられる。
藤原時代 日本史,とりわけ文化史,美術史上の時代区分の一つ。 いわゆる平安時代4世紀のうち最初の1世紀を弘仁・貞観時代というのに対して,寛平6 (894) 年の遣唐使廃止以後の3世紀を藤原時代と呼び,摂関藤原氏を中心として国風文化の進展した時代とする。
丹雘粉壁 たんわくふんぺき 平安神宮のような建築を、古い言葉で「丹楹粉壁(たんえいふんぺき)」と形容する。これは「赤い柱に、白い壁、蒼い瓦」を意味するもので、「黒檀の玉座」と合わせて風水の四神相応を体現している。宮殿や大社大寺の多くが、この思想で造られている。)
円楹甃瓦 えんえいしゅうが 丸く太い柱と平たい瓦。
蜀山兀として阿房出づ
外袍 トーガ
瑶珞ようらく 珠玉や貴金属を編んで、頭・首・胸にかける装身具。 仏菩薩などの身を飾るものとして用いられ、寺院内でも天蓋などの装飾に用いる。 もとインドの上流階級の人々が身につけたもの。
妍麗 けんれい あでやかで美しい事
ミケランジェロの「縛られた奴隷」
涓滴 けんてき 水のしずく。したたり。
嵬麗 がいれい かいれい 谷崎は『悪魔』『朱雀日記』『銀と金』でもこの語を使うが、他に使用例は一つしか見つからなかった。大きな山の雄大な樣と解するが、麗につらなるという意味があることから山々が連なる樣
とも思える。
Scheherazade
羅漢菩薩 羅漢は菩薩ではないので羅漢・菩薩の意味か?
曠世 こうせい 余にもまれなこと。
これもうコロナとか関係なしにダメなやつだろ pic.twitter.com/dSIUgc4Xrm
— Riko P @Ver.DAZU (@R_i_k_o_P) March 17, 2022
『あれ、この人態度が変だな?』と感じたら、その違和感は当たっています。もしかしたら『たまたま機嫌が悪かった?』と考えなくて大丈夫。その人は、あなたの優しさを利用し見下しているんです。そんな人の為に大切な時間を使う必要はないし離れられるなら離れた方が良い。
— 書楽遊人 しろ (@syorakuka) March 17, 2022
おはようございます(#^.^#) pic.twitter.com/8Yv2zdmwfF
昨日、新聞の折り込み広告に東北有志医師の会のチラシが入ってました✨🤗
— はちみつレモン (@7SrakQHGQf4zgGY) March 12, 2022
いままで「ワク打たないでね」と言うと変な目で見られてましたが、これで流れが変わりそう pic.twitter.com/lEEDlmVxI8
冗談抜きにこれなんだよなぁ… pic.twitter.com/NksELdCyV7
— ししまる (@SisiMARU_298) March 17, 2022
目も見えず、耳も聞こえないワンコ17歳。抱っこするたびに驚いた顔するので、たぶんこんな感じなんだと思います。#秘密結社老犬俱楽部 pic.twitter.com/DdSl9rjWrv
— ワンコ17歳 (@wanco15sai) March 18, 2022
お父さんが自分を見てくれなかったことで傷ついた。お母さんが自分を愛してくれなかったことで傷ついた。まりなちゃんにいじめられてたことで傷ついた。彼女が虚無だったのは、今まで誰も対面で「おはなし」してくれなかったから、心を打ち明ける機会すらななかっただけなんだね…… #タコピーの原罪 pic.twitter.com/QhezVyFoPS
— さいか (@yar_anaika) March 17, 2022
日本の海洋プラごみ調査では、4割が廃業した漁業事業者のもの。つまり、漁師さんがきちんと生活出来れば4割の海洋プラごみは削減できる。だがそこに金は入れない。
— hidekiminos (@hidekiminos) March 18, 2022
ウミガメの鼻にストローが刺さった映像。誰かが押し込まないと刺さりませんよ。世界を湾岸戦争に駆り立てた「ナイラ証言」と同じ構図。 pic.twitter.com/fjAT8mw2Jz
獲ったどー。 pic.twitter.com/65ENZsAMvS
— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) March 19, 2022
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
