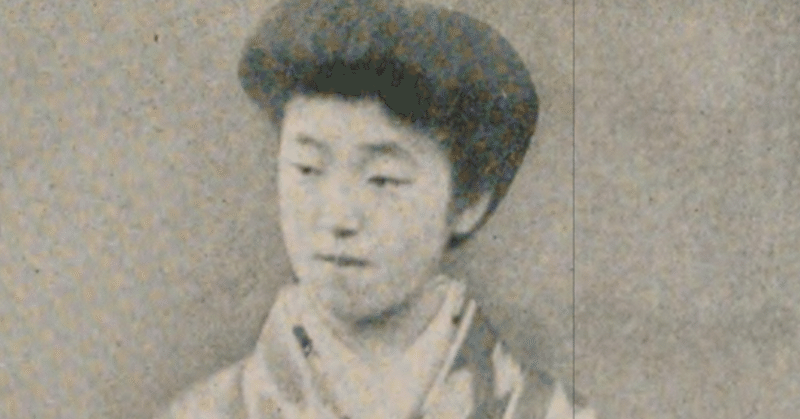
欠落していない 平野啓一郎の『三島由紀夫論』を読む51
清顕と勲の罪悪感
小説を読むということはちょっとした違いを読むということでありうる。しかし理解するということは同一性で括るということでもありうる。名前も聞いたことのなような外国の食べ物を紹介するとき、日本で言えばつくねです、少し辛いスパイスのきいた鳥の肉団子です、と言われれば何となくわかったような気になる。そうして同一性で括りすぎると、たまにおかしなことが起きてしまう。
更に大きく捉えるならば、そもそも三島文学には、「罪悪感」という主題が根本的に欠落しているという事実にも突き当たるであろう。
平野啓一郎は「三島文学には」、と書いているので三島由紀夫の死が一面においては生き残った者の罪悪感を過剰に受け止めすぎたためのものに見えなくもないことを反論として示すことはできない。
しかし『罪と罰』という小説を書いたことのない私もまた、「罪悪感」という主題が根本的に欠落していると批判されねばならないのかと考えてみた時、平野啓一郎の齟齬が見えてくる。平野は仮に「三島文学」と書いたのだがここでは直接的には『春の雪』と『奔馬』がまず射程に捉えられ、演繹的に、というか飛躍を怖れもせず急に持ち出されたのが「三島文学」という流れなので、まずは『春の雪』と『奔馬』の読みに関して、「罪悪感」という主題が根本的に欠落していると批判し得るかどうかという点を確認してみたい。
まず『春の雪』に関して平野が指摘している罪は「姦通」である。
清顕は時折大声で自分の罪を告白してまはりたい気持ちにかられることがあった。だが、さうしては聡子の折角の自己犠牲も無になるのだ。それを無にしても良心の重荷を取り払ふのが本当の勇気か、虜囚に等しい今の生活に黙つて耐へるのが正しい忍苦か、はつきり見分けをつけることは難しかつた。ただ、どれほどの苦悩を積んでも、何もせずにじつとしてゐることが、すなはち、父や一家の希望にも叶つてゐるといふ事態は耐え難かつた。
聡子の「病気」が公表された後、松枝清顕は聡子に対しては明らかに罪悪感を抱き苦悩しているように読める。
平野は「治典王に対する罪悪感も一切ない」と指摘したのではあるが、清顕に罪悪感が欠如している訳ではない。
彼らが苦悩し、自己否定に陥るのは、罪悪感に於いてではなく、恥辱に於いてであり、しかもその恥の意識は徹底して世俗的であって、社会的な他者との関係、通念的な規範からの逸脱を通じて齎らされるものである。
いや矢張り清顕の苦悩は聡子という一人の女性に関しての罪の意識から生じていて、世俗的な恥辱の概念の入り込む余地がないところで苦悩を導いている。
ここで彼ら、と言われているので、もう一人の主人公、飯沼勲の罪、あるいは罪悪感というものを確認せねばならないが、よくよく考えてみれば『奔馬』の飯沼勲は形式的には警察に捕まるほどの犯罪を犯していながら、そもそも罪を犯している感じさえしない。
「私の申し上げる罪とは、法律上の罪ではありません。聖明が蔽はれてゐるこのやうな世に生きてゐながら、何もせずに生き永らへてゐるといふことがまず第一の罪であります。その大罪を祓ふには、瀆神の罪を犯してまでも、何とか熱い握り飯を拵へて献上して、自らの忠心を行為にあらはして、即刻
腹を切ることです。死ねばすべては清められますが、生きてゐるかぎり、右すれば罪、左すれば罪、どのみち罪を犯してゐることに変はりはありません」
そして飯沼勲はそもそもこうして過剰な罪悪感の中で死を求めていた。恥辱で苦悩したりもしない。
恥辱、
卑しまれるのはいい。蔑まれるのはいい。それはまだしも耐へられる。どうしても耐へられないのは、槙子の証言からの当然の類推で、あの突然の逮捕はそもそも、勲が同志を売つたのではないかと疑はれることである。
ここに現れる恥辱の感覚も、十一人の同志たちと直接的に向かい合ったところに生じているもので、徹底して世俗的な恥辱の概念ではない。寧ろ勲は新聞に何と書き立てられるかなどということは眼中にない。世俗を乖離した狭い、死を誓い合った者たちだけに通じる恥辱である。
この批判を三島文学全体に広げると、膨大な量になりかねないのでこの二作に留める。
おそらく平野の「しかもその恥の意識は徹底して世俗的であって」という指摘は『天人五衰』における本多のスキャンダルを強く意識しすぎたところからの暴走であろう。総じて上手くまとめようという工夫がいくつもの齟齬を生じさせているように思える。
ところどころでは記憶の欠落というものがおそらく誰にもあるのだろうからそこはあまりきびしく責められない。思い込みというものもあるだろう。勘違いもある。それが人間というものだ。しかし反省すべきはこれが平野啓一郎一人の仕事ではないという点である。なぜもっと皆で仲良く協力しあい、注意深く点検できなかったのか。そこにはおごりというものが間違いなくあるだろう。自分は優秀だ、プロフェッショナルだ、今までたくさんの仕事をこなしてきた……そんな無駄な自信がおごりとなっていないだろうか。
では現実としてはどうだろう。
読み落としだらけだ。
それを決定版と呼んでみる。
洒落ならいい。
しかしこの内容では洒落にならない。
この本に関わったすべての人の責任である。
この本は何としても書き直されなくてはならない。
一応ここで『奔馬』に関しては一区切りとして、今後は(生きてゐれば)『暁の寺』に関する部分ももう少し細かく見ておきたい。
[余談]
私と一緒なら、出かけてもいいことになつてるんだから
この佐和の言い分からすれば、
①父親が最初から佐和に監視役として勲の作戦に参加させることを目論んでいたのではないか
という疑問が当然湧いてくる。なにしろ佐和も勲には蔵原を殺したいと言っていたわけだから、二人で誰かを殺しに行ってもおかしくはないのだから。
②佐和が出した千円という大金も元をたどると蔵原から出ていたものであると考えられる。本当に山林を売って得た金かどうかは怪しい。
とも考えられなくない。
本気で計画に前向きなら出せなくもない金であろうが、その割には残念がる様子もないし、謹慎もさせられていないのだから一人で蔵原を殺るチャンスはいくらでもあるのに行動しない。
これは怪しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

