
詩人になれなかった男 芥川龍之介の『戯作三昧』をどう読むか⑤ 兼芥川龍之介の俳句をどう読むか195
小説の読解にあれやこれやと外部から余計なものを持ち込むのは好きではない。
こういうのが最悪の文芸批評だと思う。『門』は『ツァラトゥストラかく語りき』を読まないと解らないとか、そういう人が一番駄目だと思う。自分が踏み込んだ一歩がもうぬかるんでいるのに、そのままずぶずぶと進んでいって泥の中に飲み込まれてしまうようなことになっている。一言でいえば思い込みが激しすぎる。
徒手空拳で考える、感覚で読むというのも違うと思う。
ある程度は調べることが必要だ。
例えば『戯作三昧』を読むためには最低限、曲亭馬琴がどんな人だと言われていたかという点はつかまなければならないだろうとは思う。しかし案外なことに、いやそれは当然と言えば当然のことながら、馬琴の俳諧に関する資料は極めて少ない。「八犬伝」は残った。しかし馬琴の俳諧は樋口一葉の和歌同様忘れられたものになってしまってはいないだろうか。
不思議なもので「萬葉集」は残った。万葉学者と呼ばれる奇特な人たち途切れない。ただ馬琴の俳諧はさしてありがたがられていない。
それでもやはり探してみると資料はあるもので、最初のユーモリスト、饗庭篁村が資料を残していてくれた。
それももちろん完全なものとは言えないし、『曲亭遺稿』に論が及んでいないことから少しは偏りがあるのかもしれないが、俳諧のスタートからの記録として貴重で、当時の俳諧の状況に触れた唯一の資料ともいえるので無理やり意訳してみた。
これがそれである。
自分で読み直してみて、改めてこれは面白いと思った点がある。
①芥川同様、馬琴もかなり早い時期に天才的な俳句を詠んでいること。
うぐひすの初音に眠る座頭かな 馬琴
これが七歳の発句だと言われて信じられるものであろうか。
うぐひすの初音というのはそもそも年齢を重ねていないと解らないものである。最初は上手く鳴けない。なんというか、音程もリズムも練習中で頼りなく、人によっては笑ってしまう、かわいらしいものだ。
それがまさに七歳の馬琴の初音、初めての発句とかかっている。しかしこちらは初音ながら達者である。
座頭は年寄りか。それこそ何度となくうぐひすの初音を聞いてきて、ああ春が来たなとうとうととしたのであろう。元々目開きではないのだから本当に寝ていたかどうかは解らない。
しかし幼鳥と座頭の取り合わせがなんとも言えず風雅なものである。まるで爺の発句である。
落葉焚いて葉守の神を見し夜かな 我鬼
これが尋常小学校四年、十歳の発句だと言われて信じられるものであろうか。その知的なところの説明はこの記事に書いた。
まあ二人とも早熟にもほどがある。
②二人とも故事にかこつけた知的な句を好む
馬琴の場合「白痴嚇かしのむつかしい句」などと饗庭篁村に冷やかされている。しかしこれは故事に通じた饗庭篁村だから言えることで、芥川の句の場合、故事にかこつけたことさえ見逃され続けてきたのだった。
蜃気楼見んとや手長人こぞる
この句は飯田蛇笏にさえ理解されなかった。
三四人だんびら磨ぐや梅雨入空
この句の由来もまた誰も知らないだろう。
芥川の場合はともかくとして、馬琴の場合、「文選」の素読をしろと言われて、「史記」に手を出したのが災い(幸い?)してか、「白痴嚇かしのむつかしい句」を読むようになった。芥川のルーツが貸本屋の講談本にあり、馬琴なども良く読んでいたことを考えると、これはそもそもたまたま似たということでもなさそうだ。
③二人とも詩人としては成功しなかった
芥川の俳句は今でもよく無言の鑑賞という地獄のような形でさらされているが、馬琴の句が引かれているのは自然に見ることはない。探せば見つかる。しかしいちいち探さなくても目に付くほかの俳人の句と比べれば、ほとんど忘れ去られてしまっていると言ってよいだろう。
しかし萩原朔太郎、室生犀星、佐藤春夫は芥川を詩人として認めていないのだから仕方ない。無言の鑑賞にさらされてもそれではしょうがない。
④「尤も、当節の歌よみや宗匠位には行くつもりだがね。」と言いたいような状況と馬琴の性質というものが確かにあった。
雪中庵蓼太の評価はさておくとして、「蓼太は評判はいいが學識が深くない」という饗庭篁村の指摘の通りであれば、その点において馬琴の言い分は通るであろう。梅翁派の素外、素丸については情報がない。情報がない、すなわち無価値というものでもなかろうが、人気があったのに情報がないという時点でやはり大したことはなかろう。
天保二年はそこから時代が移り、西暦であれば1831年、蕪村は1784年に没しているので、「芭蕉の次は蕪村、後は大したことはない」という考えの芥川にしてみれば、かなりあてずっぽうだったのかもしれないが、状況としてはまさにそう言いたいものがあり、なおかつ負けず嫌いな馬琴の性格からして、「尤も、当節の歌よみや宗匠位には行くつもりだがね。」という台詞は実に適切なのだ。
そしてその状況と性質において馬琴と芥川は実に似ていることが確認できた。
こういった点を踏まえて次にいこう。
しかし、銭湯を出た時の馬琴の気分は、沈んでゐた。眇の毒舌は、少くともこれだけの範囲で、確に予期した成功を収め得たのである。彼は秋晴れの江戸の町を歩きながら、風呂の中で聞いた悪評を、一々彼の批評眼にかけて、綿密に点検した。さうして、それが、如何なる点から考へて見ても、一顧の価のない愚論だと云ふ事実を、即座に証明する事が出来た。が、それにも関らず、一度乱された彼の気分は、容易に元通り、落着きさうもない。
彼は不快な眼を挙げて、両側の町家を眺めた。町家のものは、彼の気分とは没交渉に、皆その日の生計を励んでゐる。だから「諸国銘葉」の柿色の暖簾、「本黄楊」の黄いろい櫛形の招牌、「駕籠」の掛行燈、「卜筮」の算木の旗、――さう云ふものが、無意味な一列を作つて、唯雑然と彼の眼底を通りすぎた。
「どうして己は、己の軽蔑してゐる悪評に、かう煩はされるのだらう。」
一人の愚にもつかない悪評を聞いて人気作家が落ち込む。そういうこともないではなかろう。それが正しいかどうかではなく他人の悪意は簡単に人を傷つけることができる。七歳で、
うぐひすの初音に眠る座頭かな
と詠んだ天才。大流行作家の馬琴が、単なる見当違いの憎悪でしかないものに煩わされている。それは三島由紀夫が指摘していたように器械体操をすれば直るようなものでは無かろう。それは何故か。
実は何か自分でものを書いてみようという人は基本的に「よかれ」と思って書いているので、それに対して「あしかれ」と思って書いているように思われると楽しくないという理屈が働いてはいまいか。プロだから売れればいい、お金が稼げればいいというだけではなく、基本的に書くという行為が善意なのだ。善意というのは基本的に無防備で、隙だらけだ。
馬琴は又、考へつづけた。
「己を不快にするのは、第一にあの眇が己に悪意を持つてゐると云ふ事実だ。人に悪意を持たれると云ふ事は、その理由の如何に関らず、それ丈だけで己には不快なのだから、仕方がない。」
彼は、かう思つて、自分の気の弱いのを恥ぢた。実際彼の如く傍若無人な態度に出る人間が少かつたやうに、彼の如く他人の悪意に対して、敏感な人間も亦少かつたのである。さうして、この行為の上では全く反対に思はれる二つの結果が、実は同じ原因――同じ神経作用から来てゐると云ふ事実にも、勿論彼はとうから気がついてゐた。
こうして「気の弱い」「敏感な人」と言われてみて改めてこの画が気になる。

何故か馬琴は帯刀している。十返舎一九などが町人風に描かれるのに対して、馬琴はあくまでも武士なのだ。
なのになぜかしょんぼりしている。全然楽しそうではない。人の悪意が気になるから。いやそれは芥川の創作の中の馬琴だ。ではこの馬琴は何をそんなにしょんぼりしているのであろうか。饗庭篁村の資料の中にはそうしたものは見えなかった。『曲亭遺稿』にもそういうものは見えない。では芥川は何處からしょんぼりする馬琴というものを見つけ出してきたのであろうか。
「しかし、己を不快にするものは、まだ外にもある。それは己があの眇と、対抗するやうな位置に置かれたと云ふ事だ。己は昔からさう云ふ位置に身を置く事を好まない。勝負事をやらないのも、その為だ。」
ここまで分析して来た彼の頭は、更に一歩を進めると同時に、思ひもよらない変化を、気分の上に起させた。それは緊くむすんでゐた彼の唇が、この時急に弛んだのを見ても、知れる事であらう。
「最後に、さう云ふ位置へ己を置いた相手が、あの眇だと云ふ事実も、確に己を不快にしてゐる。もしあれがもう少し高等な相手だつたら、己はこの不快を反撥する丈の、反抗心を起してゐたのに相違ない。何にしても、あの眇が相手では、いくら己でも閉口する筈だ。」
馬琴は苦笑しながら、高い空を仰いだ。その空からは、朗らかな鳶の声が、日の光と共に、雨の如く落ちて来る。彼は今まで沈んでゐた気分が次第に軽くなつて来る事を意識した。
それはたまたまなのだろうか。
芥川はしきりに仲間と運座を楽しんだが、点取り俳諧はやらなかっであろう。一口に点取り俳諧と云っても様々な流儀があるようだが、例えば良い句が詠まれると景物などを賜ることもあったようだ。これは一種の勝負事である。馬琴は低い点をつけられて腹を立てたが、私ならそもそも点取り俳諧には参加できない。腹を立てるどころではなくなるのではないかと思うからだ。この「勝負事をやらない」という所も敢えて芥川が馬琴を自分の方に引き寄せたところかもしれない。
そして「さう云ふ位置へ己を置いた相手が、あの眇だと云ふ事実も、確に己を不快にしてゐる。」という偏見は何か芥川の個人的な体験に根差したものではないかと疑う。
山門や源氏の侍どもに、都合の好いい議論を拵えるのは、西光法師などの嵌り役じゃ。おれは眇たる一平家に、心を労するほど老耄はせぬ。
どうも芥川は「眇」の好敵手となることに我慢がならないようだ。眇たるとは「すがめ」の意味ではなく「とるに足りないもの」の意味ではあるが、まさに芥川は「すがめ」を「とるに足りないもの」と見做しているのだ。
つまり二千余年の歴史は眇たる一クレオパトラの鼻の如何に依ったのではない。寧ろ地上に遍満した我我の愚昧に依ったのである。哂うべき、――しかし壮厳な我我の愚昧に依ったのである。
眇の男の云ふことは親切づくなのには違ひない。が、その声や顔色は如何いかにも無愛想を極めてゐる。素直に貰ふのは忌しい。と云つて店を飛び出すのは多少相手に気の毒である。保吉はやむを得ず勘定台の上へ一銭の銅貨を一枚出した。
保吉は眇の男に借りを作るのが気に入らない。対等になるのが嫌なのだ。馬琴の眇に対する差別意識は、保吉とほぼ同じものだ。
「しかし、眇がどんな悪評を立てようとも、それは精々、己を不快にさせる位だ。いくら鳶が鳴いたからと云つて、天日の歩みが止まるものではない。己の八犬伝は必ず完成するだらう。さうしてその時は、日本が古今に比倫のない大伝奇を持つ時だ。」
彼は恢復した自信を労りながら、細い小路を静に家の方へ曲つて行つた。
すべてが終わった地点からの眺めというものは奇妙なものだ。確かに馬琴の「八犬伝」は世間大評判となり、戯作者としての馬琴は大成功したと言ってよいだろう。「八犬伝」の翻案は繰り返し現れ、人々を楽しませ続けてきた。今は少し落ち着いているが、また新しい媒体で「八犬伝」が復活することもあるだろう。そして繰り返しになるが俳人としての馬琴が再評価されることはもう永遠になかろう。
芥川龍之介の俳句も同じだ。散々「すがめ」を揶揄っておいて、寄り目の句を詠んだのに百年間誰にも笑ってもらえなかった。
目を半開きにしても無視される。
津波も無視される。
大食いも無視される。まあ何でも無視だ。よかれと思ってやったことが「ふーん」と無視される。大正六年『戯作三昧』を書きながら、芥川は自分こそは馬琴、漱石どころか、ロマン・ロランをも凌駕する世界的な大作家になれると考えてはいなかっだろうか。
近代の大文豪其名海内に轟ける芥川龍之介(エヘン)氏は早稲田の別邸に引こもり大日仏戦史著作中なり
1906年、明治三十九年の芥川にはその資格が十二分にある。七歳の馬琴にも蕪村くらいにはなれる資格があり、十歳の芥川にも碧梧桐くらいにはなれる資格があったはずだ。しかし二人は詩人にはなれなかった。そしてここにきて急に「神祇、釈教、恋、無常、みないりごみの浮世風呂」と書いた式亭三馬だけではなく、芥川自身がこれを高野百里編の『銭龍腑』という俳諧集にある並びと同じだと意識していたのではないかと思えてくる。どうもこれは詩人になれなかった男が戯作に生きる話なのだ。そして饗庭篁村の見立ての通り、俳諧の修業が戯作に生きたとは言えるのではなかろうか。
いずれにせよ、すべては終わってしまった。時間は戻らない。これで六章が終わる。もう五章には絶対に戻れない。つまり馬琴は家に帰るのだ。そこに一体どんな事件が待ち受けているのか。それはまだ誰も知らない。何故ならまだ読んでいないからだ。
[余談]
饗庭篁村について書いた翌日、ポイントサイトのクイズで
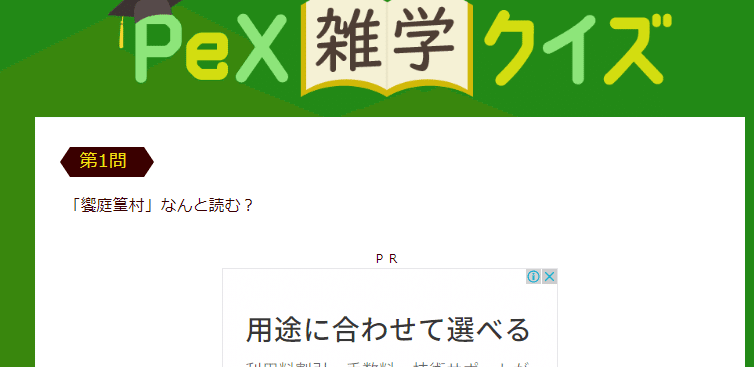
こうやって出てくると驚くよね。·饗庭篁邨と書いたら饗庭篁邨が出てくるのかね?
どうも広告はワードやエクセルまでのぞき込んでいるようだけど、noteの非公開の記事まで読んでいたら怖いな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
