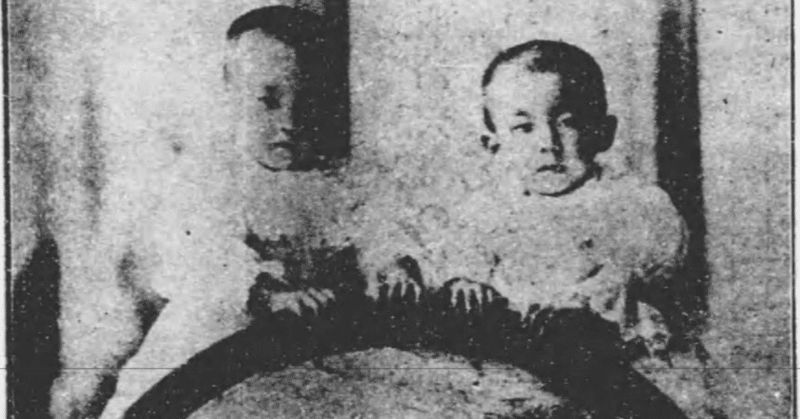
文体の違い 平野啓一郎の『三島由紀夫論』を読む58
※右昭和天皇左秩父宮
それにしても驚くのは、平野啓一郎が『英霊の声』において、川崎君や木村先生の嘘か芝居、この帰神の儀式の真実性を欠片も疑うそぶりを一切見せないことだ。
大丈夫なのかね?
それで本当にいいのかね?
いや、あなた自身に訊いているんだよ。
それで本当にいいの?
三島由紀夫の『英霊の声』において明確に欠けているのは、彼らの声が真実であるという証拠、例えば彼ら以外には到底知りうるはずのない真実の暴露である。
これは何も本当のことでなくとも構わないのだ。実際に現場にいたもの以外では知りえないという些細なこと、例えばまだ帝国ホテルではバイキングが始まっていなかったので朝飯はこんなだったとか、どこそこデパートの屋上にはこれこれのアドバルーンがゆらゆら揺れていたとか。三島由紀夫ほどのストーリーテラーであれば、まずこの帰神の会の儀式が本物である、あるいはあると思わせる証拠を見せつけることは容易ではなかったか。
その小説作法は、『豊饒の海』では基本通りに守られた。少々わざとらしいが、「転生者」にはいかにも因縁があるように仄めかされた。しかし『英霊の声』にはそれがなかった。まるで新聞や週刊誌の記事を読んだとしか思えない情報が垂れ流された。私が帰神の儀式に参加していたら、笑いをこらえるのに必死だったであろう。「月の海上にいるって、どうやって移動したんや、中国人か」と心の中では笑っていただろう。
三島由紀夫は現実と非現実の相克というものを常に意識していた人間で、全部非現実の話なんだけどね、という話を書いていない。ところが『英霊の声』において非現実が現実を犯したように見えるところは最後の川崎君の死そして顔の変容のみであり、それが非現実の世界がもたらした現実世界における力であるかどうかは極めてあいまいなところに置かれている。
なにゆえに川崎君は殺されなければならなかったのか?
この死の曖昧さの意味を平野啓一郎は問わない。
川崎君は何か罰されるように死んでしまう。
解釈の仕様によってはこれは全部川崎君の歪んだ政治思想が吐露された独演会で、木村先生が毒を盛ってもっともらしい落ちをつけただけ、そういう狂信的なカルト集団の酔狂だったと考えられなくもない。
というのも昨日確認した通り、二・二六事件の青年将校たちは非常に現実的で理知的であり、天皇にはげしく片恋した盲信的で武骨な人たち、ただ天皇の馬前で腹を切りたいだけの単純な人たちであったとは考えられないからだ。
三島由紀夫の描き方はある意味正確さを欠いており、蹶起の精神を無視している。敢えて言えば磯部浅一の事件後の怒りそのものはよく吸収しているが、そちらに寄りすぎていて、ほかの将校たちの冷静な態度を全体としては戯画化してしまっている。
一、天皇陛下 陛下の側近は国民を圧する奸漢で一杯でありますゾ、御気付キ遊バサヌデハ日本が大変になりますゾ、今に今に大変なことになりますゾ
ニ、明治陛下も皇大神宮様も何をしておられるのでありますか、天皇陛下をなぜ御助けなさらぬのですか
三、日本の神神はどれもこれも皆ねむっておられるのですか、この日本の大事をよそにしているほどのなまけものなら日本の神様ではない、磯部菱海はソンナ下らぬナマケ神とは縁を切る、そんな下らぬ神ならば日本の天地から追いはらってしまうのだ、よくよく菱海の云うことを胸にきぎんでおくがいい、今にみろ、今にみろッ
—磯部浅一、八月六日
何にヲッー!、殺されてたまるか、死ぬものか、
千万発射つとも死せじ、断じて死せじ、死ぬることは負ける事だ、
成仏することは、譲歩する事だ、死ぬものか、成仏するものか
悪鬼となって所信を貫徹するのだ、
ラセツとなって敵類賊カイを滅盡するのだ、
余は祈りが日々に激しくなりつつある、余の祈りは成仏しない祈りだ、
悪鬼になれる様に祈っているのだ、
優秀無敵なる悪鬼になる可く祈ってゐるのだ、
必ず志をつらぬいて見せる、
余の所信は一分も一厘もまげないぞ、
完全に無敵に貫徹するのだ、
妥協も譲歩もしないぞ
二・二六事件の青年将校たちはどうも現実的にある程度昭和維新が成功すると踏んでいた可能性が高い。また事件後の処分関しても五・一五事件の結果に鑑み楽観視していた可能性が高い。当然彼らの中にも切腹の覚悟をしていた者もいたはずではあろうが、三島が書いたほどに腹を切りたがっていたわけでもないようだ。彼らは恋のためにやみくもに突っ走った馬鹿ではない。
このずれは何なのか?
今、四海必ずしも波穏やかならねど
日の本のやまとの国は
鼓腹撃壌(こふくげきじょう)の世をば現じ
御仁徳の下 平和は世にみちみち
人ら泰平のゆるき微笑みに顔見交わし
利害は錯綜し、敵味方も相結び
外国(とつくに)の金銭は人らを走らせ
もはや戦いを欲せざる者は卑怯をも愛し
邪なる戦(いくさ)のみ陰にはびこり
夫婦朋友も信ずる能わず
いつわりの人間主義をたつきの糧となし
偽善の団欒は世をおおい
力は貶(へん)せられ、肉は蔑(なみ)され
若人らは咽喉元(のどもと)をしめつけられつつ
怠惰と麻薬と闘争に
かつまた望みなき小志の道へ
羊のごとく歩みを揃え
快楽もその実を失い、
信義もその力を喪い
魂は悉く腐蝕せられ
年老いたる者は卑しき自己肯定と保全をば
道徳の名の下に天下にひろげ
真実はおおいかくされ、
真情は病み
道ゆく人の足は希望に躍ることかつてなく
なべてに痴呆の笑いは浸潤し
魂の死は行人の顔に透かし見られ
よろこびも悲しみも須臾(しゅゆ)にして去り
清純は商(あきな)われ、淫蕩は衰え
ただ金(かね)よ金よと思いめぐらせば
人の値打は金よりも卑しくなりゆき
世に背く者は背く者の流派に
生(なま)かしこげの安住の宿りを営み
世に時めく者は自己満足の
いぎたなき鼻孔をふくらませ
ふたたび衰えたる美は天下を風靡し
陋劣なる真実のみ真実と呼ばれ
車は繁殖し、
愚かしき速度は魂を寸断し
大ビルは建てども大義は崩壊し
その窓々は欲球不満の螢光燈に輝き渡り
朝な朝な昇る日はスモッグに曇り
感情は鈍磨し、鋭角は摩滅し
烈しきもの、雄々しき魂は地を払う
血潮はことごとく汚れて平和に澱み
ほとばしる清き血潮は涸れ果てぬ
天翔けるものは翼を折られ
不朽の栄光をば白蟻どもは嘲笑(あざわら)う
かかる日に
などてすめろぎは人間(ひと)となりたまいし
そしてこれが二・二六事件の青年将校たちの現代日本、1966年当時の日本に対する批判だとすると、「月の海からよく見えるね」と言いたくなる。こういっては何だが、月にもテレビがあるのだろうか?
蹶起趣意書の書き手の文体から考えれば、まずこうしたへたくそな詩のようなものは書かれないのではないか、と私は思う。おかしいと思う点は、
・皇祖に対する畏まりがない
・何々に基づいてこれこれがどう間違っているという合理的な指摘になっていない。(自分の独自の価値基準が根拠なく示されている。)
・どうあるべきだ、という建設的な提案がない
本来の二・二六事件の青年将校たちはアマゾン社員が最も嫌う「評論家」ではない。提案者であり実行者である。しかし『英霊の声』の詩はただ嫌味なだけの評論になってしまっている。明らかにペルソナが異なる。こういっては何だが、ぐちぐちと厭味ったらしいだけで美しくはない。
三島由紀夫のことなので蹶起趣意書は必ず読んていたはずである。その三島由紀夫が二・二六事件の青年将校たちが最も言いそうにないことを言わせている。ここには「敢えてそうとした意図」というものがあると考えるべきではなかろうか。
大西は「われわれは戦争に勝つための方策を陛下に奉呈して、終戦の御決定を考えなおしてくださるようにお願いしなければなりません」「われわれが特攻で2000万人の命を犠牲にする覚悟を決めるならば、勝利はわれわれのものとなるはずです」と主張した。
また特攻隊員たちの描き方も少々おかしいが、ここも平野啓一郎はそのおかしさに気がついていないようだ。
三島由紀夫の最期の言葉によれば、おそらく三島は特攻隊が「いける神」でもなければ、歴史の精華を具現する者でもない、ただの陰惨な犠牲者だと見做していた筈だ。
『最後の特攻隊』なんて、学者なんか喜んで見に行くんです。僕は絶対嫌なんです。僕は絶対見たくないんです。絶対嫌なんです。安倍さんも喜んで見に行くんですがね、『最後の特攻隊』なんか見たくない。
恐らく嘘でしょうね。
三島由紀夫にとって神風特別攻撃隊の戦士を英雄視すること自体がおためごかしのインチキに見えていた筈だ。ところが『英霊の声』において三島は彼らを「空母一、巡洋艦一、轟沈の戦果をあげた者」であるとして、一旦英雄にしてしまう。この点に関して平野啓一郎は、
他方で三島は「特攻隊は、あれは命令か自由意思かのすれすれのところで、実際には志願するが、周囲の強制もあるだろうし、なかば命令だけれども」と認めているものの、こうした認識は『英霊の声』には反映されていない。
と明確に指摘しながら、「自らの死を死ぬ」という特攻精神に三島が共感してしまっていることからこの「神風特別攻撃隊の霊が英雄であること」を見許しているように思う。
一方で、
実際には、特攻隊員には「ヒロポン」と名づけられたメタンフェタミンがチョコレートでコーティングされるなどして与えられていたことが知られている。
として、「死の直前に至るまでの覚醒」のフィクション性は指摘しているものの、現在ではこの「ヒロポン説」はほぼ否定されているので何ともちぐはぐだ。
私はやはり「神風特別攻撃隊の霊が英雄であること」に違和感を覚える。
おそらく最も悲惨だったのは神風特別攻撃隊に配属され、自分の意志や判断というものを奪われ、ただ死ぬのだと告げられた兵士が、実際に敵艦に辿り着くこともなくバタバタと撃ち落されていくことを「栄光」だと信じ込まされることではなかったか。
恐らく彼らは神風が吹かないことを知っていた。しかし死なねばならなかった。その死は天皇の人間宣言の前から陰惨なものであった。
ここにはやはり三島らしいひねくれた理屈が隠れている。先に私は「皇軍は亡びたか」として、
もしも「皇軍は亡んでいた」という前提に立つと、開戦から人間宣言まで、天皇の大権というものは蔽われていたという理屈になる。
として、二つの軍隊の違いを指摘していた。もう一度よくよく読み直してみると、二・二六事件の青年将校たちの霊が思わずも言い過ぎたかと思える「皇軍は亡んでいた」という前提は、神風特別攻撃隊の霊にもしっかり引き取られているのだ。
兄神たちはその死によつて、天皇の軍隊の滅亡と軍人精神の死を体現した。われらは死によつて、日本の滅亡と日本の精神の死を体現したのだ。
天皇の軍隊でないなら、天皇が人間宣言しても関係なくない?
ここの理屈は矢張り解らないもので、敢えて言うなら、三島由紀夫が何かややこしいことをしていると言うしかない。
ただ神風特別攻撃隊は自分の意志をはく奪されているので比較すべきペルソナというものがない。もしあるとすればそれははく奪された意志の代わりに注ぎ込まれたスローガン「勝つための貯金」……ではなくて「一億玉砕火の玉だ」のようなものでもあっただろうか。
国民を「一億」とまとめる意味~「日本を取り戻す」とは、「軍国主義日本を取り戻す」そのもの https://t.co/jM666LZPbI:「進め一億火の玉だ」、「一億玉砕、本土決戦」という戦争体制を表す言葉。自己を捨てて国の一部に pic.twitter.com/Jbrc9Y0s80
— 自考志向 (@JIKOUSIKOU) March 29, 2023
その魂が何によって慰められるのかは解らない。しかし天皇の人間宣言に恨み言を云うくらいよくよく月から地球を観察していたとしたら、世界中でカミカゼが畏れられ、それがまさしく日本精神として信じられてきたことを知っている筈である。フィリピンでは神風特攻隊が英雄として尊敬されていたことを知っていた筈である。(後に慰霊碑が出来て慰霊祭まで行われるようになった。)そうしたことは些末なことでやはり天皇の裏切りこそが問題なのだと強弁できなくもないのだが、例えば、おそらくは二・二六事件の青年将校たちよりは素朴な、言ってみれば教養レベルでは一段落ちる筈の神風特攻隊の霊たちが、二・二六事件の青年将校たちの持ち出さなかったものを持ち出している点はいかにも不釣り合いなのだ。
祭服に玉体を包み、夜昼おぼろげに
宮中賢所のなほ奥深く
皇祖皇宗のおんみたまの前にぬかづき、
神のおんために死したる者らの霊を祭りて
ただ斎き、ただ祈りてましまさば、
何ほどか尊かりしならん
などてすめろぎは人間となりたまひし。
などてすめろぎは人間となりたまひし。
などてすめろぎは人間となりたまひし。
冷静に眺めるとやはりこの声はおかしい。宮中祭祀のことなど恐らく神風特攻隊員は知らない筈だ。
平野啓一郎は「9 二・二六事件の将校たちの霊」において、二・二六事件の将校たちの霊の声は不調和で、三島由紀夫自身の声が重ねられ過ぎていると指摘している。そしてその調子っぱずれな響きは作者の意図であり、教養主義に対する批判が込められていると見做す。
そして「15 二つの天皇観」において「文体が違う」という決定的な、本物の作家にしか言えない指摘をする。二・二六事件の将校たちの霊は武骨であり、特攻隊員たちの霊の語りは「ぎこちさがない」としている。さすがは日本一の作家である。
そしてさらに特攻隊員たちの霊が「文明批評」をしていないことを指摘する。素晴らしい。とーこーろーめーが、そこからスコンと足を踏み外してしまう。
だが、それにしても、二・二六事件の将校たちと比して、若い特攻隊員たちの方が、際立って美しい言葉で語り得るということを示さねばならない理由はない。それはやはり、意図的なことではなく、創作上の過失と言うべきであろう。
おめバカこくでねえど。
何が過失だ、こんにゃろめ。
わざとやってんだよ。
もう一回蹶起趣意書読んでみ。
武骨は武骨だけど「文雅に染まらず」でますらおぶりでねか。
それが新体詩みたいな恨み言垂れてるからおがしいっての。
で田舎者の農家の次男三男が、まだ軍人勅諭も覚えきらんうちに前線にやられて死ぬって言うのに、
祭服に玉体を包み、夜昼おぼろげに
宮中賢所のなほ奥深く
皇祖皇宗のおんみたまの前にぬかづき、
神のおんために死したる者らの霊を祭りて
ただ斎き、ただ祈りてましまさば、
そんな台詞が出てくるわけなかろうに。無理だって。「七生報国、天皇陛下万歳」「靖国で会おう」しか言えない、……それが精いっぱいだろうよ。
つまり英霊の声は限りなく如何わしい儀式において、限りなく如何わしく発せられた、カルト宗教発信の言葉なのである。

三島由紀夫が大国主命を天照大神と天皇の間において論じていた記憶が私にはない。『霊学筌蹄』の神霊学は三島由紀夫自身にとっても興味深いものであったことは間違いないが、三島由紀夫が信じ切っていた思想ではなかったはずだ。
大体皆さん大国主命って普段意識してますか?
してないでしょ。
そういう宗教の会の話なのよ、これ。月に住んでいる幽霊の話。しかも全然鎮魂になっていない変な儀式の話。
三島は矢張り『英霊の声』を英霊の魂そのもの、真実の声として描き出すことをしなかったのではないかというのが私の解釈である。まず『霊学筌蹄』を読んでみて再考してもらいたい。
[附記]
大国主命は、
大物主とは別の神だと言われているけれど、いちおう『奔馬』に大物主は出てくるね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
