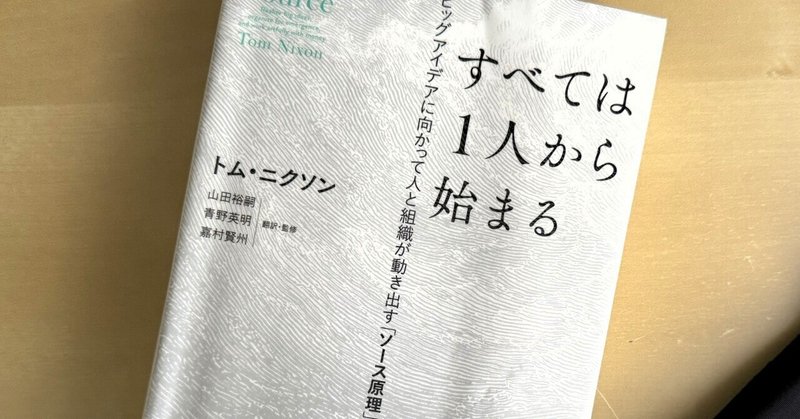
ブックレビュー「すべては一人から始まる ビッグアイディアに向かって人と組織が動き出す「ソース原理」の力」
本書の原題は”Work with Source”で副題は”Realize Big Ideas, Organize for Emergence and Work Artfully with Money”。
著者はTom Nixonという英国在住の起業家・コーチ・アドバイザーだが、元のSourceという考え方は既に一線を退いたPeter Koenigが10年以上の探求を通じて得た洞察をTomが自ら取り入れた経験を踏まえてまとめた本である。
まずSourceとは何か。
Sourceとは「傷つくリスクを負いながら最初の一歩を踏み出した創業者」であり、Sourceたる人は次のような行動を起こす。
まだ存在しない未来を思い描き、それを現実化させる人間のすばらしい力(本書ではこの力を「創造力」と呼ぶ)を発揮する
Sourceは個人的なリスクを取っていることから、イニシアティブ(何かのアイディアを実現するプロセス)に対して事前なオーサーシップ(自分がこのイニシアティブの執筆者・表現者であるという感覚)やつながりが生まれる。
分かりやすい例を考えると、強力なビジョンと力を持つ創業者がそれにあたる。アップルの共同創業者であるSteve JobsやElon Muskがその際たる事例だ。事業家以外にも活動家、コミュニティ・オーガナイザー、アーティストなどもありうる。
しかしこういった天才的なヒーローには独裁的なリーダーシップをとるなど負の側面を伴うことがあるのは周知の事実だ。SteveやElonまで行かなくても創業者が見事なアイディアを現実化する中、組織の規模が大きくなると、トップダウンで運営することが難しくなるし、環境変化に素早く適応することも難しくなる例は枚挙にいとまがない。
このため分散型で自立組織的なアプローチをもって、共通したビジョンや価値観を維持しながら組織の英知を最大限活用しようする動きが活発に見られる。有名なものでは「ティール組織」や「ホラクラシー」などがその一例だ。
一方、こういった分散型自律組織も、トップダウンと対照的に曖昧さを許容するため、アイディアは語るが意思決定できず、実現に向けて動けなくなる例がある。中には我慢できずにトップダウンに逆戻りすることもある。
本書は「ソース原理」によれば、「トップダウン型のクリエイティブなリーダーシップにある最高の部分を取り入れながら、まったく新しい参加型のコラボレーションを実装していくことは可能だ」、「トップダウンとボトムアップの双方の美点を認め、それらを統合して越えていこうとする試みだ」であり、それを今まで実現してきたのだからあなたにもできるはずだ、という。
そしてその実現のための2つのコンセプトとして、「ソースの役割」と「クリエイティブフィールド」を提唱する。
一つ目の「ソースの役割」とはソースは全能の独裁者や英雄的な起業家とは異なり、指示命令する役割を抑え、聞き役に回ることであり、継承可能で、ビジョンのオーサーシップを部分的に他者=「サブソース」と分かち合いことができる、という。
二つ目の「クリエイティブフォース」とは、「ビジョンの実現に必要な協力者やリソースを引き寄せ、各自の貢献を束ねて一貫性を生み出す重力場」と「ビジョンの実現に向けて一緒に行動していける草原や牧草地のような物理空間」の2つを合わせた場をいう。
ここでは組織をモノと見るのではなく、開放された創造プロセスと見る。固定化された「組織」という名詞では無く、個人がどんな風にコラボレーションをおこなうかの仕組みや一貫性を築く「プロセス」に焦点をあて、「組織化する」と動詞的に考える。
そしてその導入においては、<ステップ1>ソースである自分から始める、<ソース2>イニシアチブのソースを特定する、<ステップ3>ソースやサブソースとしての役割へ踏み込む、<ステップ4>フィールドマップをつくる、<ステップ5>サブソースを支援する、<ステップ6>ソース原理を組織作りと規模拡大に活かす、<ステップ7>ソースを継承するか、イニシアチブを閉じる、というステップに分けて把握することを推奨する。
ここまで読み進めると「ソース」を「リーダー(シップを発揮する人)」と置き換えても何ら支障が無いのではないかと思われてきた。要はヒロイックな強力のリーダーに頼るのでは無く、分別のある一人のリーダーとそのビジョンの実現のために日替わりあるいはプロジェクト単位でサブ・リーダーが入れ替わるような組織作りということではないのだろうか。
本書では「ソース原理」という訳語が使われているが、原題が”Work with Source”とあるように本当に原理と呼んでよいものかどうかという疑問もある。実際本書の解説文によると、Peter Koenigは、「ソース原理は「暫定的な自然法則」と語って」おり、「まだ反証が得られていないが将来現れる可能性を考慮」している、との説明も見られる。
また「ティール組織」との積極的な比較が本書には見られ、組織は「魂」を持っているととらえるティール組織には、ソースが去るか、ソースがその洗練された組織化の方法に全面的な責任をもって向き合えなくなると、従来型のパラダイム(例えばトップダウン組織)に逆戻りしてしまう場合がある、と指摘している。このためか、ソース原理ではソースの継承やイニシアチブの解放を準備することで「ティール組織」の欠点を補おうとしている。
本書では最後にサブタイトルにある”Work Artfully with Money”に該当するマネーワークの章がある。これは一言で言うと自分のお金に対するストーリー(マネーライフストーリー)を振り返ることで、自分特有のお金との関係性を理解し、その関係性に対処する、という考え方だ。
元々このマネーワーク講座を開く中で生まれたのがソース原理であり、「誰もが人生のソースである」「ソースがリスクをとって最初の一歩を踏み出したとき、すでにイニシアティブが始まっている(そこにお金の有無は関係ない)」という洞察を理解すると、お金やエゴに惑わされずに純粋に目指す価値を表現できるようになる、という。
全体として「ソース原理」は先にも述べたように「原理」というよりもプロセス手法の集積であり、Peter Koenigが経験から得た洞察の積み重ねと考えた方が良さそうだ。マネーワークの章には「アイデンティティとの向かい方」や「本来の自分を取り戻す」という節もあり、これらはコーチングの中で人々が陥りやすいジレンマから得た洞察と想像する。
また本書では「ティール組織」や「ホラクラシー」等と比較すると、実際に代表的な成功企業の実名は挙げられていない。先行する進化型組織は失敗例もあり、時代と共になかなか永続し難いところがあるので、実名を挙げるよりもプロセス重視とした方が良いという判断かもしれない。
本書の解説文には、進化型組織とソース原理の共通点として、①機械的パラダイム(インプット・アウトプット、マニュアル、パフォーマンスの用語が象徴)から生命体的パラダイム(自己組織化と自己修正のアプローチ)、②パーパスの視点(上司は人からパーパスへ)、③人間愛と人間尊重(パワー・オーバーからパワー・ウイズ)、が挙げられている。
「ソース原理」が時代の移り変わりの中、「原理」として長く生き残っていくかどうかはわからないが、上記共通点については普遍的な概念として共感するところは大きい。時代の変化が激しく、個人が組織よりも重視されていく時代においては、新たな組織・プロセスを模索する流れは今後も続いていくのは間違いないだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
