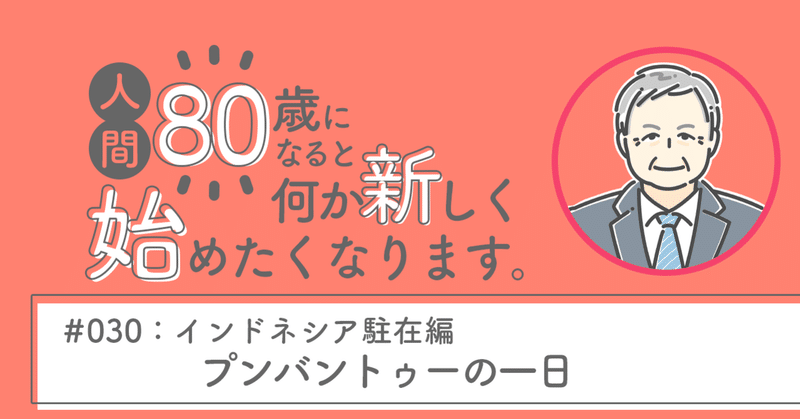
プンバントゥーの一日
プンバントゥー(女中さん)は家族帯同で赴任してきた日本人一家が最初に出会うインドネシア人です。
彼女たちはジャカルタ近郊の農村から出稼ぎに出てきました。
出てきたときは14~15歳ぐらい、まだ何も知りません。
最初は、チュチ(洗濯・掃除係)として、やがて台所で日本人のニョニャ(奥様)の手伝いをしながら日本食の料理法を覚えて、コキ(料理番)に出世します。
何十年もコキをして、若い日本人の奥様より日本料理のレパートリーが多くなれば、引っ張りだこの売れっ子コキとなって高給取りになります。
特に単身赴任者のコキとして雇われると、トゥアン(旦那)が台所に入ってこないのをいいことにして、トゥアンの食材で自分の食事も作るなどやりたい放題になります。
プンバントゥーのハルティーは、義務教育を終えると家計を助けるためにジャカルタに出てきました。
インドネシアの教育制度は、当時6・3・3制の上に3年制の短大または5年制の大学が在りました。
義務教育は最初の小学校6年だけでしたが、就学率は99.5%と東南アジアでは、驚異的な普及率でほとんどの若いインドネシア人は読み書きができました。
実は1万6千の島からなる多島国家で、話されている言語も数百あったインドネシアでは、国民が統一インドネシア語を読み書きできるということが最も大切な国家の目標でした。
初代大統領のスカルノ氏が国是とした「多様性の統一」は正に人口の一番多いジャワ人のジャワ語ではなく、「島々の交易に使われていたマレー語+ジャワ語」の新しい国語を国民全員でマスターすることで国家の一体感を作るというものでした。
今でもバリ島あたりで私が7年間勉強したインドネシア語を話すと、現地の人から、「インドネシア語上手だね!」といわれるのは彼らにとってもインドネシア語は第1外国語に近い言葉だからなのでした。
朝5時、乳母車の八百屋が来る。
ジャカルタの朝は、巡回八百屋さんの鈴の音で明けます。勿論、「アザーン」の荘重な呼びかけも始まります。(第28話参照:イスラム教会の呼びかけ)
女中のハルティーがゴム草履を突っかけて走り出て行きます。
八百屋さんは、大型乳母車に満載した野菜の横から俎板と包丁を取り出して、ハルティーが、
「ミクァ!」(野菜汁そば)
と叫ぶと、フンフンと頷いて、その朝、女中さんが食べる汁蕎麦に入れる野菜を数種類取り出して鮮やかな手つきで刻み、小さなプラスチックの袋に入れて渡します。
日本円にして10円ぐらいです。
プンバントゥーは24時間住み込みで女中部屋の部屋代は勿論無料です。
自分たちの食事は3食自炊ですが、冷蔵庫を持っていないので野菜は必要なだけ、八百屋が切り売りしてくれます。(ご主人の冷蔵庫のものには手をつけてはいけません。)
プンバントゥーは給与のほかに、米、食用油、石鹸などは現物で支給されます。
(田舎の両親に仕送りをするため、自分の食事を切り詰めて病気になったり、ご主人の食材に手をつけたりしないで済むようにしています。)
冷蔵庫を持たない女中さんにとって毎朝やってくる切り売り八百屋は実に合理的です。
まず、いつも新鮮な野菜を食べられる、使い残りの廃棄が出ない。八百屋にとっても、毎朝市場で仕入れて売れ残りゼロになるまで巡回すれば、利益は十分です。
野菜炒めの材料も売ってくれます。
カンクン(空芯菜)、チャベ(唐辛子)、バワンプティ(ニンニク)のセットはおそらく一番安いおかずですが、彼女らの部屋のコンロで炒めているといかにも美味しそうな匂いが立ち込めます。
私の家内もカンクンゴレン(空芯菜炒め)をハルティーから教えてもらって、日本に帰ってきてからも時々やりますが、日本の空芯菜は、一束5円というわけには行きません。
ストレスフリーの日々。
トゥアン(旦那)が出勤して、ニョニャ(奥様)もヒルトンホテルへテニスをしにいくか又は日本人クラブへコントラクトブリッジをしに出かけると、女中さんたちは何もすることがありません。
洗濯物にアイロンをかけ、大理石の床をモップで拭けば掃除も終わりです。のんびり昼寝をします。
給金は実家に仕送りをしても、ベッドと基本的な食事は保証されています。コーランに書かれているように断食明けの回教正月に新しい服を一枚買って1年中着ています。
彼女たちの夢は、旦那の社用車か奥様の乗る家庭車の運転手と結婚することです。
ジャカルタで運転免許証を持っていれば、一種の技術者です。給料は結構いい上に旦那が社用接待でお客さんを夜の街に連れ出したりすれば、夜中の12時ぐらいまでの超過勤務手当がつきます。中には自分の奥さんにお店をやらせているしっかり者の運転手まで居ます。
でも、油断は禁物です。
わが社の生活指導員の黒田氏によると、
「イスラムでは、裕福な人が貧しい人に施しをする事は善行として勧められているというかほとんど義務になっています。」
「乞食にお金を上げると善行を一つ行ったことになりますから、乞食も胸を張って手を出します。」
「つまりお前に善行をするチャンスを作ってやったぜ」
というわけです。
日本人駐在員はプンバントゥーから見れば、とてつもなく裕福な人ですから、旦那のものを分けてもらうことは当然の権利のようなものです。
ある日、A社の駐在員のB氏は、飾り棚の中の置時計が180度回転して、後ろ向きになっていることに気がつきます。首をかしげながら元に戻しました。
しばらくしてもう一度後ろ向きになっていたときには気がつきませんでした。
実はその後、置時計は毎日1cmづつ横に移動し最後に棚からフッと消えていきました。
私はこの話を聞いたときには、思わずその女中さんの知恵に感心しました。
なんという鋭い人間観察力でしょう。
後ろ向きにした時計が元に戻されないということは、誰もその時計で時間を見ていないということです。
つまり家中の人はその時計を使っていないことになります。
静かに時計を横に動かして視界から消えたところで、皆さんが出払った後、その時計はどこかの古物商に売られていきます。
家内には、赴任に当たって、
「盗られて泣くようなものは、日本においてくること」
と云ってありました。
この国でのんびりと暮らすためには、欲しい人にはくれてやってもいい物だけで、生活することに尽きるようです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
