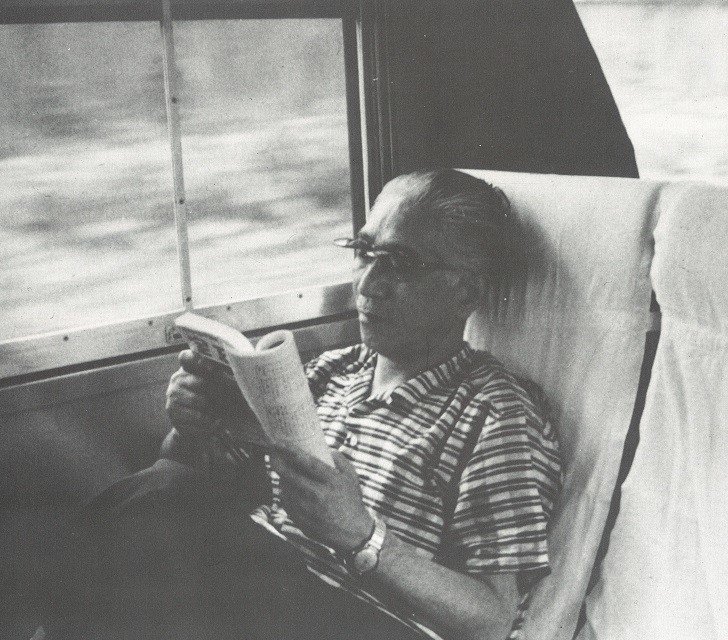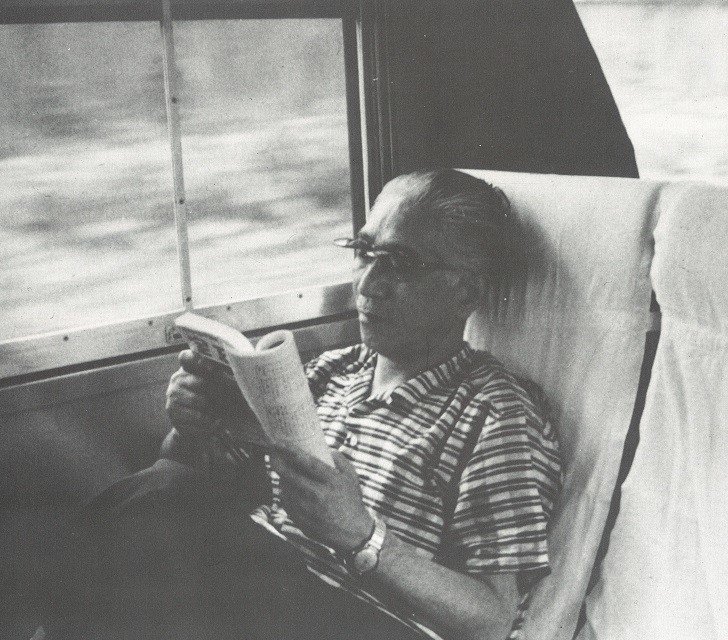無常を心に留めましょう
変化を恐れてはなりません
そこに喜びを見いだし
対応するのが商人の務めです
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。
淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。
世の中にある人とすみかと、またかくのごとし」
日本三大随筆の一つ、鴨長明の『方丈記』の書き出しはあまりに有名です。
長明の生きた鎌倉期は火災や地震、飢饉などの大きな災厄に見舞われた時代でした。
こうした災厄や自身の苦難の体験を糧に、彼は「無常」という境地にたどりつき、「人生とは何か」を主題とした随筆は後世に残る名作となりました。
これは昔話や他人