
サクラバ・ユウ・ショー 第2話

第2話
「アシッドサラダ」といえばサタニカライズでも放送中のクレイアニメの人気作で、毎回物語のおしまいにスタッフのリアルな足がオブジェを踏みつけて台無しにしてしまうのがお決まりの結末となっている。
粘土で作られた家々、並木道、車、幸福な恋人、愉快なモンスターたち。命を吹き込まれたオブジェの織り成す世界や物語を生々しい足がめちゃくちゃにしていく。ひゅー、という効果音。ドシン。破壊神の使者と化した足が世界を廃墟に変える。だれかの小指が舞い上がり学生鞄の中身が飛び出て春キャベツが破裂する。
ひどいやひどいや。どんな視聴者も初めはショックを受けるものだ。ひどいや。だが不思議なことに、いつしかその瞬間を心待ちにしていることに気づく。
「世界を作ったら、まっさらになるまで壊したいんだよね」と監督は言う。「それが楽しいんだ。いつか、僕の本当の足で踏んでみたいものだけど」
水槽の脳が応えている。身体を失ってからも創作意欲があふれ続ける監督なのだ。
「肥大化していく想像力をあえて中断させることで僕の宇宙は調律される。また来週、真っ白な都市の真ん中で逢おうよ。光を信じていようよ。僕はここにいる。きみはどこにいる?」
ひと眠りして、また起きたら、どんな色やかたちを信じていこう。「アシッドサラダ」。8シーズン目も好評放送中!
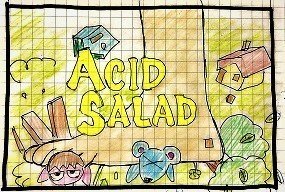
「ふうっ、ふうっ、ひいああああああ」
ここは地下のスポーツジム。碧咲はベンチプレスのトレーニングの真っ最中だ。ベンチに体を横たえて、ゆっくりと息を吐きながら、両腕でバーベルを押し上げる。
「飯を食うんじゃなかったのかよ」
青白い肌の竜人のジノが呆れた顔で見守っている。
碧咲は全身に汗をまとわりつかせている。ひたいに汗が浮き上がっては流れ落ちていく。スポブラも絞れば滴るほどに濡れている。
「こっちの! ほうが! アイデアも! 出そうだからっ……くああああ!」
「なんて移り気ゆかいちゃんなんだ……」
「なんてー!?」
「なんでもない」
ジノは碧咲に背を向けて離れていった。
不思議なジムだった。トレーニングをするために必要な光量がまるで足りていない。というより真っ暗なのだ。そもそもジムかどうかも疑わしい。ミラーボールが回り、人工的な七彩の光を散らしているのだから。おまけに不良のためにあるような音楽が大音声でかかっていて重低音が内臓まで響いてくる。
ジノが帰ってくる。碧咲は休憩中だ。蛍光ピンクの液体を湛えた透明カップを手渡す。
「飲むといい。運動の後にいいらしいぞ」
「何これキモッ。どこで買ってきたの」
「すぐそこの売店だ。ついでに店員の姉ちゃんの乳を揉んでやったぞ」
「やめなさいよ」
カップの底はブルーに光っている。ピンクとブルーは混じり合わず境目が揺れている。ストローが刺さって蓋に固定されている。
「七色に光るキモいバーベルを持ち上げているのだから、発光しているジュースだって飲めるだろ」
「いやだよ!? ぜったい身体に悪いよ!? 運動とか健康とかと対極にある見た目してるし……」
「飲んだらアイデアも出るぞ」
「え、そうかな。じゃあ飲んじゃお」
「単純だな」
ちゅるちゅるちゅる。
「どうだ?」
「これカレーだわ……」
「カレーなワケあるか! 舌凍ってんのか! 貸せ!」
ずずずずずずずっ。
「カレーだった!!」
カレーでした。
キモいドリンクを回し飲みしながら、ジノの視線は碧咲の純粋な笑顔に注がれていた。口角が上がりかけたが、いつもの固い表情に戻る。アシッドサラダ、とつぶやいてみる。奥歯を噛む。
「なにか言った?」
「いや。お互い剣呑な人生だったなと……」
「平和がイッチバーン」
「ああ、元気が有り余ってるよ」
「じゃあ、あれやりましょう、あれ!」
ふたりは並んでランニングマシンで走り始めた。
マシンの眼前に巨大なディスプレイが架かっている。
暗闇のなか、大画面は青空を映している。流星島のベイエリアを、ヤシの木のストリートを、さまざまな色をした軽装の観光客たちを映している。画面はめまぐるしく動きつづけ、砂浜に出たかと思うと、きらめく白波と並走し始めた。
「まるで本当に外で走ってるみたい! ひぃああああああ」
「いい技術だな」
たったったっ。たったったっ。
「ふあっ、ふあっ、ひぃああああああああ」
「黙って走れないのかよ!?」
たったったっ。たったったっ。
「てか、これ酔わない? ひぃ、ひぃあああああ、ああ……うげぇえああああ!?」
「オイオイ」
「だいじょうぶ! こうやって走っていると、私、この島が好きなんだって思える!」
「同じさ」
「この島らしい番組作らなきゃね……!」
碧咲は架空の流星島を快走しながら、思い出と結びつき、今見えている光景が画面に映っているものなのか、記憶の中のものなのか分からなくなってきた。あたたかな風をまとってサーファーの聖地から隠れた穴場まで渚を走り、色んな種類の波と香りを全身に感じながら青春の爽やかさに包まれていく。
次第に碧咲の唇は明るくなり、歌が洩れ出る。それはテレビコマーシャルで流れる、ホテル潮風荘のメロディだった。
潮風荘はいいところ
トゥルットゥルットゥ いいところ
一度入れば出られない
トゥルットゥルットゥ 潮風荘
時間が燃える
部屋が消える
「……父さん、母さん、どこー?」
天国 極楽 潮風荘
トゥルットゥルットゥ 潮風荘
「不気味な宿のCMソングを歌うな! ほかの曲にしろ!」
「はーい!」
メロディを引き連れて街を走る。いつしか碧咲は流星島と一体になっていた。街角にワンピースの不思議な少女の背中が見える。その背中を追っていく。
ああ、そうだ。あの娘の名は……。
碧咲はひとつの名案を思いつく。
「ねえ、この島の不思議って何だと思う」
「ありすぎる」
「サクラバ・ユウちゃん知ってる?」
「当然だ。友達だからな」
「実は私もユウちゃんと友達なんだ」
「そりゃそうだろ。アイツは、なんといっても、流星島みんなのお人形さんでありお友達なのだからな」
流星島みんなのお人形さんであり、お友達。
…………。
流星島。
大洋に浮かぶ大都会。大海原の流れ星。
星のかたちをした都市部から、大自然に覆われた尾を引いている。《流星島の女神》に守られし孤島。
ある災厄の夜を乗り越えて、観光客であふれかえるにぎやかな島の現在を造りあげた。
そこに、不思議な少女がいる。
サクラバ・ユウ。
彼女は《流星島みんなのお人形さんでありお友達》である。
むかしから、いまも、きっとあしたも。
「……そうなのよ。誰に聞いても、あの子と友達だって言うの」
「誇張だと思っていた」
「最近会ってないなー」
「同じだ」
「そこでなんですが、私、思いつきました。サクラバ・ユウを司会者に起用したトークショーを作りたい!」
「……適当言うな!」
だっだっだっだっ。走りながらのツッコミである。
「だめ?」
「こどもだぞ!」
「こどもでいいじゃない」
「低予算なんだぞ!」
「島じゅうをロケと称して冒険しましょう」
「ならばトークショーではない……」
「しゃべらせたいんだよね~。いつかスタジオ使わせてもらおう」
「いや一回きりの番組のはずだろう?」
「絶対人気出るから、続けるつもりで撮ってやるんだ!」
「うわあ……」
ジノがランニングマシンから降りた。碧咲の尻尾の蕾がぴんぴんして揺れているのを眺める。
「で……他の出演者は?」
「私が出れば大丈夫。Dと兼任しながら私がしゃべればいいよね」
「馬鹿まっしぐらじゃないか」
「そうと決まれば、ジノ。貴方がDとカメラを担ってもらうので。やってくれるよね!?」
「待て。気が早いぞ」
「時間がないの。会議なんて通してるひまはないわ。今から撮影しに行こうよ」
「今からとはなんだ今からとは」
碧咲もランニングマシンから降りて満面の笑みを浮かべて言った。
「ユウちゃんを捕まえにいくところから、『サクラバ・ユウ・ショー!』は始まっているのよ!」
「番組名がもう決まっているのか……」
「番組名って大体こうでしょ」
そうなのだろうか。
んでもって。
「で、ユウちゃんって今、どこに住んでるの?」
「知らんのかい!」
二人ともユウがどこに住んでいるのか知らなかった。
「変なジュースを売っていたヤツに聞いてくる!」
「頼んだわ。私もいろんな人に聞いてくる」
「あいよ」
ジノは暗闇のジムを抜けていく。赤や青に照らされて床にのさばっているヨガ集団を縫いながら、彼女もまた黄、緑、青、いろんな色を身体の上に滑らせていく。
強烈な光が飛び込んできて、そこが売店だった。

「おうい、カレーもう一杯くれないかな」
「さっきのお客様ですね。でも、カレーなんてお売りしておりませんよ?」
「ほら、ピンクと青のやつだよ」
「あれは、目薬です」
「目薬なワケあるか、頭ラリってんのか」
「カバ向けの目薬なんです」
「カバに目薬がいるものか。水に潜れば済むのだからな。こんな黴臭いところにいて頭パキり散らかしてるんじゃないぞ、このチキチキボーン」
「正気ですよ、お客様。カバも地上で暮らす時代なんです」
「まあいいや。美味かったし。チップ弾むからもう一杯くれないか。聞きたいことがあるんだ」
店員が例の飲み物を運んできた。じっとジノの顔をうかがっている。
「これ、ピンクと青の二層になっているでしょう? それをこうやって……逆さまにすると……」
「どうなるんだ?」
「……バカにつける薬になります♪」
びしゃっ。
蓋を開けて中身をジノにぶちまけた。
ジノはカウンターから乗り出す。
「なにすんだテメー」
「こちらの台詞です。先刻はよくも乳を揉んでくれましたね」
「ああ……悪かったよ、ごめんごめん」
「ごめんでは済みませんよ。私の左胸の突端は、実家の屋敷を爆破させるボタンになっているのです。来たるべき敵が来て一族の最期を悟ったとき用の自爆ボタンなんです。どうしてくれるのですか」
「それじゃ生活できないだろ!」
「反対側がキャンセルボタンになってますので難を免れました」
「お前はいったい何者なんだ」
店員の尻から緋色の不思議な尾が伸びる。
「高貴な身分も昔の話、わけあって平凡な地下で、平凡な売店員に身をやつしているのです」
「ははーん、さては悪魔だな」
突然、店員の両手が手首から切断される。自由になった両手がジノの角をめがけて飛んでくる。奇術のように浮かんだ両手がジノの角を執拗に揉み始める。
「おいコラ……やめ……」
さわさわと角を揉み始めた。
「なにするんだ、そこに触れるな」
腰から力が抜け、その場にへたり込んでしまう。
「あらあら、ご冗談でしょう。ここまで覿面とは思いませんでした。天空島に棲む竜はツノに刻まれた溝が弱点だそうですね。《空飛ぶ20ポンドピッツァ村》でしたっけ? 変な名前の島……の、ジノ・アウラシップさん?」
「どうして、名前を」
「ウニベルシオさんの首を取ったそうですね」
「敵討ちか?」
「いえいえ違いますわ。昔の級友なだけです。首を取ったということで興味を持ちまして。ちょっかいをかけてみたくなったのですよ。貴方が誰であれ」
浮遊する両手は竜人の全身を揉みつつ、ツノを重点的に狙い始める。
ジノは蠅を追い払うように両手を振りほどく。
くすぐったそうにもがいている。
「忌々しい手め……クソ」
「あらあら、おもしろいですわ~。これが、手力(てぢから)です」
恥ずかしそうというより苦しそうだ。手を振りほどこうとするが力が入らない。助けを呼んではいけないと思う。しかし碧咲の名を呼んでいることに内心驚いてしまう。だが碧咲は来ない。
一瞬、長老の顔が脳裡をよぎった……。
冗談のような名前が付けられた天空島に生まれて、長老と呼ばれる竜だけが幼い彼女のすべてだった。雨が渦を巻いて降りそそぎ、風が縦横無尽にめぐる青々とした草原の臥所に長老はいた。
――肉体が鈍らないように、いつでも暴力を振るえ。むろん、つまらない暴力を除いてだ。
――はい、長老!
――精神が縮こまらないように、いつでも悪口を言え。むろん、面と向かってだ。
――はい、長老!
――我らのツノには個々に異なる溝が刻まれている。触れられただけでも不快な気分になるものだ。どうだ?
――あ、やめてください、長老!
――だが決してツノを隠してはならない。怯えながら過ごすのは我らの生き恥だ。わかったな。
――はい、長老!
――くさくさした惨めな感情で誰かと連衡することと、味噌汁を沸騰させることだけはやってはいけない。我らは孤高だ。ゆめゆめ忘れるなかれ。
――わかりました、覚えておきます!
――味噌汁のくだりは忘れていい。
――え、ええっ?
苦痛だ。ふいに物音が聞こえなくなる。急に自身の不規則な心臓の鼓動を聞く。何かが限界に達しそうだ。でも何が。
「舐めんなこの野郎!」
飛んでいた手をはたき、よろめいた隙をついてラグビーボールのように蹴り上げる。
ひっ、とかすかな悲鳴が聞こえる。あるいは悲鳴ではなかったのかもしれない。
そのとき一人の男が悪魔店員の背後に忍び寄った……!
「アノ……遊んでナイデコッチ手伝ってクレマスカ? ソレト竜ハ虐めちゃダメ……トテモ困ッテル……」
留学生のバイト君だ。丁寧な言葉遣いだが顔に怒りと軽蔑をにじませている。
「そうね、ここらでやめておきますか。ふふふ……でも楽しかったわ……」
ジノは留学生のバイトにユウの居場所を尋ねる。丁寧な答えが返ってくる。それを記憶する。
ところが悪魔の店員はジノを気に入ったのか、やけにニコニコしながら、話に割り込もうとする。
「ねえねえ……私がもっといい情報を教えてあげましょうか? あげましょうか?」
「なんだよ忌々しい」
「ウニベルシオさんの話なんですが」
「それは聞いてない。ユウの情報だけを知りたいのだ」
「そうおっしゃらずに聞いてくださいな。ウニベルシオさんはですね、昔、担任の女教師でアイコラを作っていたんですのよ。とんだマセガキですわね」
「おいやめろ聞きたくない」
「跳び箱50段飛べるんですのよ」
「そりゃよかったな」
「しかし数学の試験でマイナス80点を叩き出したことがあるのですわ」
「器用だなアイツ」
「悪童ゆえ、教師からの罰としてよく手足を切断されていました。しかし首の切断はついぞ見なかったのですが」
「どんな学校だ。悪魔じゃなくてよかった~」
アイツ、しょっちゅうバラバラになるんか……可哀想に……。
ほんでほんで。
悪魔の店員はジェットと名乗った。ジェット・デ・ジェット。女性の名前にしては奇妙だった。ジノたちがデ・ジェット邸に招かれて不思議な一夜を過ごすのは、また別のお話。
そいでもって。
碧咲とジノは機材一式を揃えたのち街へ飛び出していた。眼前に広がるのは本物の色彩だ。光と波と風と汗と愛と勇気と熱気と喧騒とエンジン音と、やるなら今しかないの世界だ。
陽ざしを受けて疑いようもなく今ここにいるふたりが確かな地面を踏んでいる。さて、歩き出すことにしよう。
ふたりとも行動力の鬼にして体力馬鹿にはちがいなかった。だけど碧咲のみひどくお腹が空いていたようで、10秒に1回の頻度で、あああ~~とか、ひぃあ~~とか呻いていたとか。
ごはん、まだだったんですね。
ひぃあ~~~~。

流星島の閑静な山手地区に長い歴史を持つサロン・ド・テが建っていた。
外装は白を基調とし、金文字とパステルグリーンのファサードがエレガントさを醸し出す、それ自体がお菓子の箱のような二階建てのパティスリー。
一階の広々とした空間にはゆったりとした時間が流れ、花と絵画に彩られながら、お客さんたちがお茶とお菓子を楽しんでいる。
ガラスケースには色とりどりのケーキや菓子の数々が並んでいる。
その二階で。
部屋の扉を叩いている黒髪の巨大な女がいた。
「ユウ、返事をしろ、ユウ」
「はいはーい♪」
「下が忙しくなってきた。アニメに夢中なところ悪い。出ていってくれ」
「はーいっ。今行くんだよ?」
大女のほうは音をたてて階段を下りていった。
あとから扉が開き、小さな女の子が出てくる。
それは白いワンピースに身を包み、髪の毛はぐるぐるのくしゃくしゃ、両眼に硝子の義眼をいきいきと輝かせ、意気揚々と階段を下りる最後の一段でつまずいてしまった、流星島みんなのお人形さんでありお友達、サクラバ・ユウだった。
(ツヅク)



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
