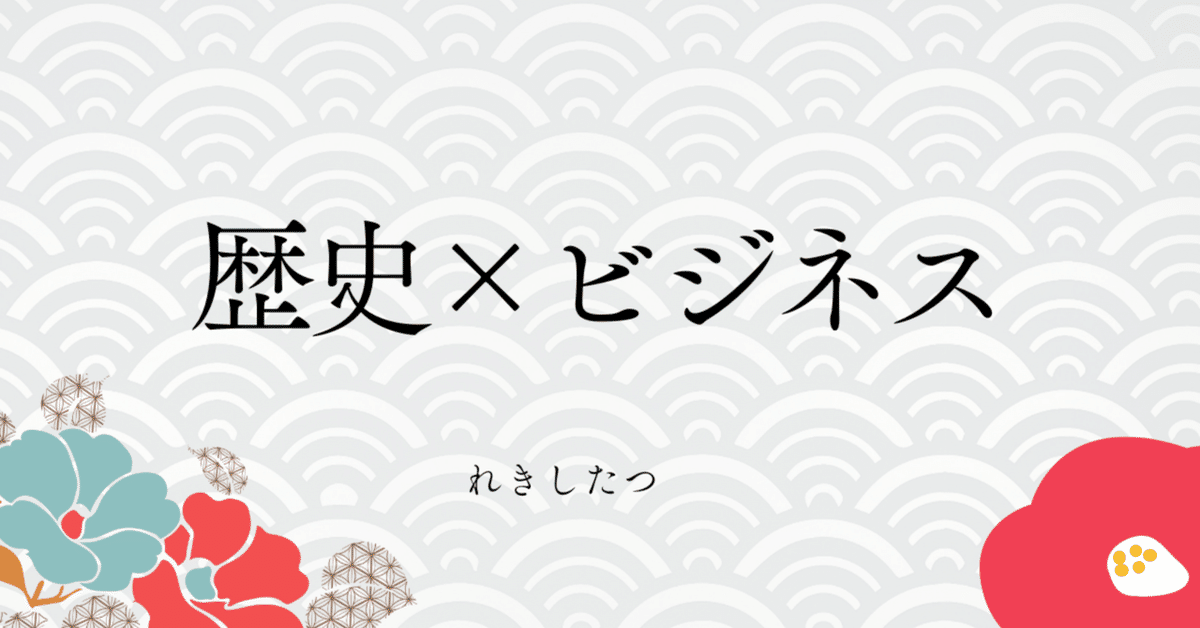
なぜ歴史を学ぶのか
こんにちは。
今回は、どんな出来事を言われても年号を答えられるゲキキモ特技を持つ私が歴史を学ぶ意義について記載しようと思います。
歴史は暗記科目?
そもそもこのテーマで記事を書こうと思った背景として、歴史は学んでも実社会で役に立つことはないと多くの人に思われているのではないかと感じていることがあります。
例えば英語を学べば海外に行った時に役に立つし、数学や物理を学べば技術系の職種では役に立つと思います。一方で、歴史はただの暗記科目で、学んでも活かす場面はなく、テストが終われば忘れてしまうもの、というイメージはないでしょうか。
これは半分正解で、半分間違いだと思っています。
半分正解だと言った理由は、日本の学校教育で行われている歴史の授業は、かなり暗記寄りになっているが、用語や年号を暗記するだけではテスト以外で何の役にも立たないからです。(私が年号を暗記しているのは変な趣味なので無視してください。)
一方で、半分間違いだと言った理由は、歴史を単なる暗記科目としてではなく、人類の物語と捉えると、かなり見方が変わってくるからです。
こちらについては次項で詳しく説明します。
人間は経験から物事を判断する
少し話は変わりますが、皆さんはどのように物事を判断しているでしょうか?多くの方は、「自身の経験」から判断しているのではないかと思っています。
「以前このような行動をしたらこのような結果になった、だから次はこのようにしよう、あるいはこれはしないようにしよう。」「以前似たようなものを見たので、これも似たようなものだろう」
このように、今まで見聞きしたこと、体験したことをベースに、物事を考えたり予測したりすることも多いと思います。
皆さんも、これまでの人生で様々な成功経験や失敗経験をされてきていると思います。そこから判断することである程度未来を予測し、成功確率を上げたり失敗を回避したりしようとしているのではないでしょうか。
歴史は人類全体の経験が集まったもの
自らの経験からの予測は、もちろんある程度有効ではありますが、自身の経験というのは、せいぜい数十年の経験です。
一方、人類全体としては、何億人もの人が、何万年もの経験をしてきています。それが集まり詰まったものが「歴史」と言われるものなのです。
どうでしょう、たった一人の数十年の経験より、何億人もの何万二もの経験の方が、予測に役立ちそうな気がしませんか?
実際、ある程度しっかり歴史を学ぶと、「こういうことがあるとこのようなことが起きがち」といった傾向があることが分かります。その傾向を今の世の中に当てはまると、今後社会がどのようになっていくかを予測できるようになります。
例えば、江戸時代の武士の歴史を学ぶことが、現代の大企業で働く社員のことを予測することもできるのです。(やたら推してますが)
他にも、歴史を見ることで未来を考えられる事例はいくつもあります。
ここ数年、フリーランスやギグワーカーと言われる働き方が注目を集めています。会社員と比べると時間的に自由に働くことができる点が非常に魅力的で、新しい働き方だとマスコミなどでも取り上げられることがあります。
実は、このような流れは35年ほど前にもありました。
1989年、バブルの絶頂期の頃、フリーターが自由で気楽な働き方として注目されていました。「フリーターこそ未来を変える!」と題した雑誌の特集まで組まれています。バブル期はどこも人手不足で、フリーターでも仕事に困ることはありませんでした。
しかし、翌年、バブルが崩壊すると、状況は一変しました。
景気が急速に悪化し、需要過多の状況から供給過多の状況になり、多くの人手も不要になりました。そこで、真っ先にリストラの対象となったのがフリーターでした。多くのフリーターが職を失い、路頭に迷うことになりました。
もちろん、今後そうなると断言できるわけではないですが、歴史は繰り返すと言われるように、似たような方向に進む可能性もあります。
今20代の社会人は、社会人になってから働き方改革などで社会がどんどん自由な働き方になっていくことしか経験していません。そのため、今後もずっとそのように進んでいくと思いがちですが、歴史を見ると、必ずしもそうではなく、むしろ自由寄りの時代の次は制約寄りの時代になることの方が多いです。(揺り戻しなどと言ったりします。)
このように、歴史を学ぶことで、自身の経験を超えた予測をすることができます。
皆さんもぜひ歴史を学んで、実社会に役立てていきましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
