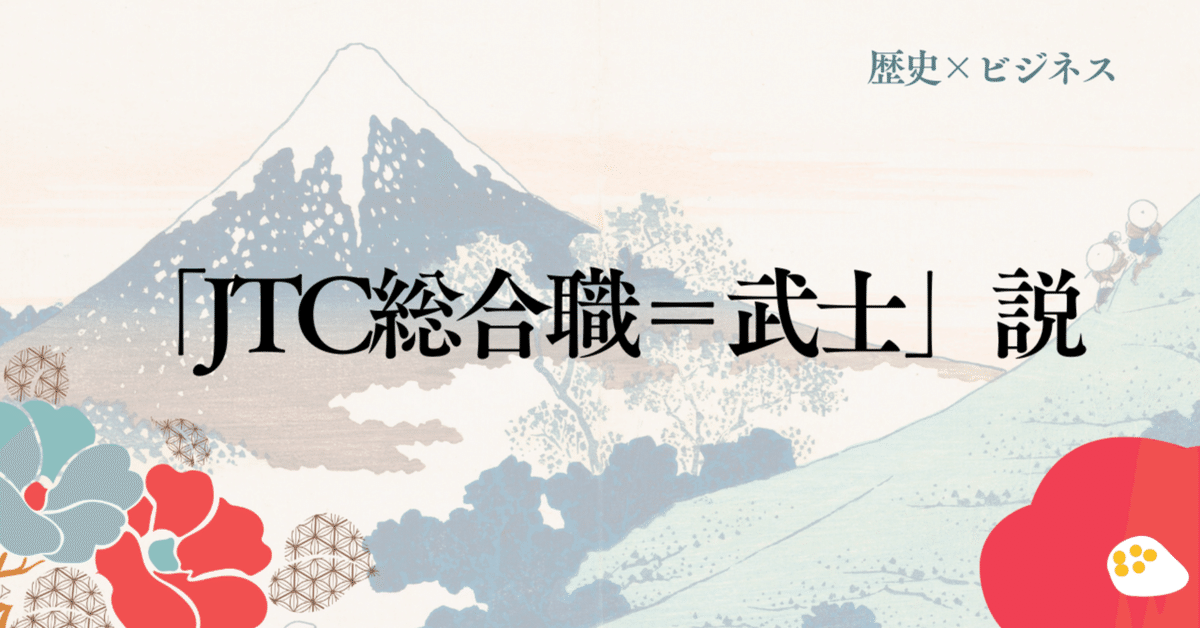
「JTC総合職=武士」説
はじめまして。
私は関西の某大企業に勤める、歴史好きのサラリーマンです。
突然ですが、これまで大企業で働くかたわら、趣味で歴史の勉強をしている中で、謎の「JTC(日本の伝統的企業)総合職=江戸時代の武士」説を思いついたので、ここにまとめようと思います。
JTC総合職の生態
JTC総合職と一口に言っても様々な方がいるのは百も承知ですが、ここでは私の観測範囲で概ね共通すると考えられるJTC総合職の生態について記載します。
JTC総合職を構成する要素は大きく3つあります。(もちろん他にもありますが、ここではこの3つに着目します。)
1つ目は、終身雇用・年功序列です。
これはもう説明するまでもありませんが、多くの日本企業では新卒で入社した企業に定年になるまで勤め、年数を重ねるごとに立場が上がっていきます。(最近は少しずつ変わりつつありますが・・・)
2つ目は、学歴による入社選抜システムです。
大企業に入社するためには、いわゆる学歴フィルターを通過する必要があり、それを乗り越えた人だけが入社しています。
3つ目は、管理サイドと高い報酬です。
総合職で入社した人の多くは、将来的な経営幹部候補として、管理サイド(管理職層や、職位は低くても事業管理や経営企画など部門に所属する層)にいることが多いのではないかと思います。(いわゆる現場で直接的に生産活動に従事することは少ないのではないでしょうか。)
また、その立場から(一般職や中小企業社員と比較すると)高い報酬がもらえることも多いと思います。
武士の生態
次に、江戸時代の武士の特徴についても紹介します。
1つ目は、主君に仕える立場です。
江戸時代の武士は、基本的に主君(将軍、大名など)が決まっており、一生その主君に仕えることになります。
2つ目は、家柄です。
江戸時代は一部例外もありつつ、基本的には家柄によって身分が決まっていました。武士はその中でも最上級の身分で、一部の人だけがその地位につくことができました。
3つ目は、事務作業と家禄です。
武士というと、戦闘をイメージされるかもしれませんが、江戸時代は中期以降はほとんど戦争も怒らない平和な時代だったため、武士の日常の業務は戦いではなく、事務作業にようなものでした。その業務を行うことで、主君から家禄と言われる給料をもらっていたのです。
両者の共通項
ここまでJTC総合職と江戸時代の武士の特徴を挙げてきました。
これらの特徴を抽象化すると、以下の共通項が見えてきます。
①唯一の組織に忠誠を誓う生涯
JTC総合職は会社に、武士は主君に忠誠を誓います。
②選ばれた階層
JTC総合職は学歴で、武士は家柄で選ばれた存在です。
③一定の地位と報酬
JTC総合職は管理ポジションで高い給与をもらい、武士は事務的立場で家禄をもらいます。
このように、JTC総合職と江戸時代の武士には多くの共通項があります。ここからさらに両者の立場をまとめると、以下のように言えるのではないでしょうか。
一定の組織に属し、直接的に自身が生産に携わらずに、管理的な立場で高い報酬を得ている特権的階級
武士の没落
ここまでJTC総合職と江戸時代の武士には共通項があると述べてきました。ここからは、その武士が江戸時代の後どのようになったかという歴史を踏まえ、JTC総合職の今後を考察していきます。
当たり前の話ですが、現代には武士は存在しません。それでは江戸時代に人口の約6%いた武士はどこにいったのでしょうか。
結論から言うと、明治時代に実質的に武士という身分は消滅しました。その経緯を記憶をたよりにざっくり記載します。
ご存じのように、1853年に黒船来航があってから、200年以上続いた江戸時代は急速に終わりを迎えます。そして1868年に明治維新があり、武士は「士族」という身分として存続することになります。
しかし、武士の特権であった名字や帯刀などは平民にも付与されたり廃止されたりし、特権階級としての立場は徐々に失われていきます。そして、ついに1876年には武士の生活を支えていた家禄(給料)も廃止(秩禄処分)されてしまい、士族とは単に戸籍に記載される形式的な身分としての意味しか持たなくなります。これにより、実質的に特権階級としての武士は消滅しました。(なお、太平洋戦争後に形式的にも廃止されます。)
では、なぜそのような事態になったのでしょうか。それはあえて一言でまとめると「地位や報酬が、本質的な価値を上回りすぎたため」だと私は考えています。
江戸時代の前、戦国時代において、武士は戦でその役割を果たし、その結果として高い身分と特権を得ました。しかし、時代が下ると、ただの事務作業や形式的な業務のみに携わっているにもかかわらず、高い報酬を得続けるようになります。本質的には価値を生み出していないのに他の生産者(農民など)が生産した財を食いつぶすだけの存在になったのです。
これは歴史的に長い目で見ると、社会的に矛盾しているため、調整が入ります。(ちなみにフランス革命などもこの類です。)実際、明治政府は国家予算を圧迫する家禄支払(国家予算の約3分の1が何も生産しない武士への給料になっていた)に耐えられず、前述の秩禄処分に踏み切りました。(それに対して士族は黙っていたわけではなく、西南戦争などの反乱を起こしましたが、農民から集められた政府軍に鎮圧されます。)
その後、士族たちは、農業などを始めたり、商売をしたり、公務員になったりと、それぞれの力で生きていくことを求められていくようになります。上手くいった者もいれば、士族の商法と言われるような殿様商売をして失敗する者もいました。つまり、自身の実力で地位や報酬が変わる時代になったのです。
JTC総合職の今後
歴史好きなあまり、武士の話が長くなりましたが、この武士の没落という歴史的事実を参考に、JTC総合職の今後を考察します。
上記で書いたように、武士はその地位や報酬が、本質的な価値を上回っていました。これはJTC総合職でも当てはまる部分があるのではないでしょうか。完成された組織の仕組みによって得られる売上をもとに、高い報酬が支払われています。
しかし、本質的にその人個人が生み出す価値を上回っている報酬を得ていることも少なくないと考えます。(ちなみにこれはいわゆる「職場のエース」のような話とは異なります。なぜなら職場のエースと言われるような人たちも組織があってこそその活躍ができているためです。)
高度成長期は組織規模が拡大していたため、あまり問題視されませんでしたが、今後は人口減少で規模が縮小していく中で、価値を生まない余剰人員に高い地位と報酬を約束し続けることは、企業体力上、難しくなってきます。実際、すでに中高年社員の希望退職などが様々な大企業で行われていますが、これは地位や報酬と実質的価値との乖離が、給与の高い中高年社員ほど大きいためです。
そのため、今後はより個人個人の実力が地位や報酬に影響する時代に変わっていくと考えています。すでにジョブ型などといった言葉も出てきています。単なる一時的な流行りの部分と、長期的な歴史のサイクルの部分を見極める必要はありますが、上記のような状況になりつつあることは間違いないのではないでしょうか。
かなりの長文になってしまいましたが、ふと思いついた「JTC(日本の伝統的企業)総合職=江戸時代の武士」説を自分なりに言語化してみました。ただ、あくまでこれは自身の経験と知識から考察を行ったものであるため、視野が狭かったり、認識がずれていたりするかもしれません。そのような箇所があればぜひコメントいただけると嬉しいです。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
今後も歴史とビジネスを絡めた気付きなどを書いていこうと思います。(初投稿で思ったよりも疲れたので書かないかもしれません。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
