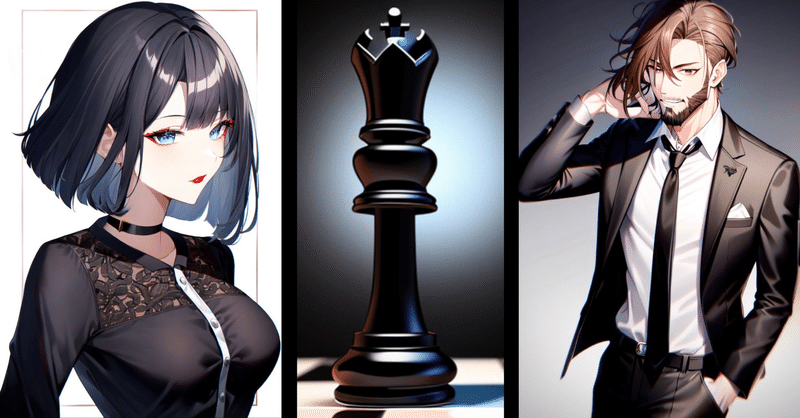
【ハードボイルド】カレン The Ice Black Queen 第三話
→第二話へ
銃撃
検査の結果、やはり肋骨にひびが見つかった。しかし心配した内臓へのダメージはそれほどではなかった。学生の頃にラグビーで鍛えていたこと、そして偶然にも昼食前で、胃がカラだったことが幸した。
安静にしていろと血相を変えたドクターを振り切り、薬だけをもらって病院を出る。時刻は四時を回っていた。余計なアクシデントで時間を食ってしまった。
アポイントはない。遅れたからといって誰からも文句は出ない。だから予定どおり、カレンの住まいへ向かう。マスタングで行くつもりだったが仕方がない。病院前でタクシーを拾った。住所は聞いていなかった。聞かなくても有名人だから調べたらすぐにわかった。
「三番街のカフェの先を右へ」
運転手に指示を与え、シートに背を預けて考える。
先ほどの襲撃は俺への警告だ。だが、誰からの何の警告なんだ。俺が依頼を受けていた案件はとりあえず全部片付いている。綺麗に後腐れがないとは言えないが、暴力による警告を受けるほどの覚えはない。
とすれば、やはりあれはカレンに関係があると見て間違いないだろう。彼女が俺の事務所に現れてすぐのことだからだ。警部補はカレンの話を信じていない。俺も何かあるとは思ったが、警部補から聞いた話を鵜呑みにしたわけじゃない。
しかし今は違う。間接的ではなく、直接カレン本人の口から事情を確かめなくてはならない。
カレンの住まいは、瀟洒な高級アパルトマンが立ち並ぶ一角にあった。少し離れた場所でタクシーを降り、それとなく辺りを観察する。
人通りの中に気になる男たちがいる。黒いジャケットの男と、スケートボードを抱えた少し若い男。それぞれ道を挟んだ反対の位置だ。さりげない風を装っているが、俺の目はごまかせない。
こいつらがさっきの襲撃者なのかは不明だ。そうだとしても、人目がある中では彼らも襲ってこないだろう。それにさっきは不意打ちでやられた。ダメージが残っているとはいえ、正面からの戦いなら負ける気はしない。
目的の場所までゆっくり歩く。何も起こらない。誰も襲ってこない。そのまま歩いて入り口に着いた。短い階段を登ればエントランスだ。そこからさらに建物の中に入るには、頑丈そうなアイアンゲートのロックを中から開錠してもらう必要がある。
洒落たデザインのインターフォンで1007と打ち込み、呼び鈴のボタンを押す。しばらく待ったが特に変化はなかった。昼寝でもしているのかもしれない。あるいはミュージカルビデオに夢中で来客に気づかない可能性だってある。そういえば独身でもカレンが一人で暮らしているとはどこにも書いていなかった。秘密の恋人と一緒に住んでいるのかもしれない。
蓼食う虫も好き好きという諺がある。あれだけ美人だったら、いつも冷たい顔しか見せてくれない女でも構わないという男が、この世界に一人ぐらいいても別におかしくはない。
くだらない空想に浸っていた俺は、インターフォンからの小さな声を聞き逃がすところだった。
「あら探偵さん。アポイントはいただいてないと思ったけれど」
「ええ。今日あなたが私の事務所にいらした時のように、アポイントなしで伺いました」
「ずいぶん意地悪なことをおっしゃるのね」
「それは申し訳ない。正直な性格なものですから」
「どうぞ。入ってすぐ左手にエレベーターがあるわ」
カチっと音がした。優雅なアラベスク格子のゲートがゆっくり開いてゆく。足を踏み入れると後ろでゲートが閉まった。セキュリティは高いようだ。しかしぶっ壊してでも入ろうとする輩に対しては、どんな対策を施そうと無駄だ。
事実、押し入ろうとした屋敷の重厚な門扉を壊すのに戦車で突っ込んだ連中がいるぐらいだから、こんなゲートを突破するなどプロの手にかかれば赤子の手をひねるようなものだろう。
カレンの住まいは意外にも質素だった。と言っても俺の部屋に比べたらその広さはその辺の水たまりと太平洋ぐらい違う。もちろん水たまりは俺の方だ。
もっと豪華な、例えばいかにもなシャンデリアが輝き、床には毛足の長い絨毯が敷かれ、ずらっと並んだ家具は十八世紀のアンティーク、なんて風景を想像していたからかもしれない。
床はフローリングのまま、家具はあまりない。必要最小限しか置かれていないように見えた。凝ったデザインと風格はアンティークなのかもしれないが、豪華というより趣味の良い印象だった。
「このテーブルランプはラリックかな」
「まあ!よくご存知ね。でも残念。アール・デコのものには違いないけどラリックではない。アンティークがご趣味なの?どうぞそこへお掛けになって」
「趣味というほどではありません。だいたい私なんぞには贅沢すぎる」
革のソファー横のサイドテーブルに置かれた優雅な曲線のランプ。その乳白色のガラスは、オパールセントガラスという。現代ではもう作られていない。
「一つ聞いていい?」
「どうぞ」
「どうして服が泥だらけなの」
「おっとすまない。うっかりしていた。部屋を汚してしまったようだ」
自宅に戻る暇がなかったので、俺は彼女の指摘通り泥まみれだった。どおりでタクシーの運転者が変な目で俺を見てたはずだ。
「ここでちょっと待ってて。サイズが合うかわからないけど着替えを持ってくるわ」
カレンが立ち上がり、俺を見つめ、それから奥のドアの向こうに消えた。一人になったチャンスに本当は部屋の中をいろいろ調べたかったが、これ以上こびりついた泥を落とさないように、おとなしくソファーで待つことにする。
それにソファーから動かなくても、いくつか気づいたことがある。部屋に入った時、かすかにタバコに匂いがした。灰皿に吸い殻はない。カレン自身のタバコかもしれないが、ここは来客をもてなす部屋のようだから、俺の前に客がいたと考えた方が自然だろう。
カレンがドアを開けたとき、小さくピアノの音が聞こえてきた。誰かが弾いているというより、ステレオから流れている風だった。奥にあるプライベートスペースで音楽を聴きながらくつろいでいたところを、泥だらけの男が邪魔したようだった。
俺の訪問は歓迎されないものと決めつけていたが、今のところそんな様子はない。事務所に来た時と同様、感情の読めない顔だが、むしろ歓迎されているように思える。自宅に来るなと断った人間が泥だらけの姿でやってきたら、普通の人間なら門前払いにするだろう。
カレンという女に興味が湧いてきた。
戻って来た彼女は、グレーのスーツと白いシャツを抱えていた。それを俺に渡し、サイズが合わないかもしれないがと繰り返した。
スーツもパリッとしたシャツも、クリーニング屋から返ってきたばかりのように清潔な匂いがした。どちらも高級品だ。俺が着ている安物とは雲泥の差である。
丁寧に礼を言う。俺は音楽の話題から始めることにした。
「ジャズがお好きなんですね」
「ジャズ?ああ、聴こえたのね。チェスのことを考えている時以外はいつも聴いているわ」
「さっきの曲は、"Someday my prince will come" ビル・エバンスの名曲だ」
「"いつか王子さまが"なんて、少女趣味が過ぎると思いません?それより、さっきのわたしの質問にまだ答えていただいていないわ」
「時には夢を見るのも大切だと思うが。自分の車に乗ろうとドアを開けたところを二人組の男たちに蹴られたんです」
「まあ大変」
「気がついたら地面に寝ていた。三十分ほど意識を失ったようです。救急車で病院に運ばれ医者に診てもらったら、肋骨にひびが入った程度で、骨折や内臓破裂はありませんでした」
「探偵さんて大変なんですね。とりあえずお着替えになったらいかが。せっかく新しい服をお渡ししたんですから」
シャワーを使っていいとも言われたが、服の下は包帯だらけで面倒だった。それに女一人の家でそこまで好意に甘えるわけにはいかない。
カレンに席を外してもらい、ここで着替えを済ませた。そして拳銃が無くなっていることに今更ながら気づいた。あいつらに蹴り飛ばされた時に奪われたらしい。
着替えたら気分がすっきりした。首回りが緩いのと袖が少し長いのは、元の持ち主は俺よりも大柄ということになる。カレンの元夫のものか。
そのカレンを呼び戻した。中断した話を再開する。
「服をありがとう。きちんとクリーニングしてから返すよ」
「ネクタイはないから我慢して。やっぱり少し大きかったみたいね」
決して笑わない顔に笑みを感じたのは気のせいか。多分、気のせいだろう。
「さて、気絶していた私のために救急車を呼んでくれたのは、誰だったと思いますか?」
「誰って、さあ。通りがかりの人じゃないの?」
「救急車を呼んでくれたのは、十代の少女だった」
「えっ」
「十七歳ぐらいの、黒い髪の少女。おそらく暴漢を撃退したのもその女の子だ。そうでなければ、俺はもっと酷い怪我を負っていたはずです」
話しているあいだ、俺はずうっとカレンの目を見ていた。暴行を受けた時の生々しい様子を語ってもその目は静かなままだった。
しかし、謎の少女のことに触れた途端、その目にわずかな動揺が走ったのを見逃さなかった。
だがそれだけだった。次に口を開いた時には、カレンの声にはついさっきまであった人間らしさが消えていた。わずかな感情の起伏も認められない。恐るべき自制心だ。
そして俺は、なぜかカレンの中に芽生えかけていた俺への好意を失ったことを悟った。
「そろそろ、ここへ来た用件をおっしゃってください」
「警察に赴いたあなたは、誰かに命を狙われていると訴えたそうですね」
「ええ。そうです」
「でも誰に狙われているのかわからないとも」
「そうよ。確かに、応対した若い警察官に訊かれてそう答えたわ」
「私を襲ったやつらに心当たりはありませんか?」
「どうしてわたしが知ってると思うの」
「聞いているのはこちらです」
「失礼な人ね。どうしてわたしが尋問されなくてはいけないのか理解に苦しむわ」
「尋問してはいない。俺に暴行を働いた奴らが、きみを狙っていると考えるのが自然だからだ。きみが俺の事務所に現れ、来なくていいと言われたにも関わらず、俺がきみから直接事情を聞こうと動いた矢先に、暴力のプロがやって来た。そのプロを撃退した謎の少女。警察は信じなくても俺はきみの話を信じる。だから教えて欲しい。嘘はいらない。俺を信じて…」
カレンの瞳が揺らいだ。唇が動き、何か言おうとする。それと同時に、壁の上の方を移動する赤い光に気がついた。
「危ない!」
俺の叫びとほぼ同時に窓ガラスが割れ、赤い光があった位置に穴が開いた。ソファーにいたカレンを庇って床に転がる。さらにもう一発。今度は銃声が聞こえた。
またガラスの割れる音とバシッという着弾音。これで三発目だ。赤い光は狙撃者の銃に取り付けられているレーザーポイントだった。
「カレン、怪我はないか」
「大丈夫です。あなたは?」
「俺か?俺の心配はいらない」
庇った腕の下、カレンの目が光っている。こんな時に人の心配をする余裕があるとは大した女だ。
ジッと床に伏せたまま待った。すると四発目の代わりに、割れたガラスの隙間から車が急発進する音が聞こえてきた。
終わりか?
だが…。
「警察に電話してくれ。窓には近づくな。できるだけ腰を低くして移動するんだ」
「わかった。どこへ行くの?」
玄関へ走る俺の背にカレンの声が飛んできた。
「悪いやつを捕まえに行くのさ」そう言い捨てて、カレン邸を飛び出した。
エレベーターはまだ十階にいた。ボタンを叩き、開いたドアの隙間から中へ倒れ込んだ。痛めた肋骨がさっきからうずいている。
やっと一階に着いた。ドアが開くのももどかしく、両手で押し開ける。転がるように階段を降りて、表通りへ出た時、車道の向こうに並んだアパルトマンのどこかから、パンッとくぐもった銃声がした。
カレンの住居の位置のちょうど正面、少し下の並んだ窓の一つで影が動いた。
やはりそうか。狙撃者はあそこの部屋から撃ったのだ。おそらくライフルだろう。急発進した車は逃げたと思わせるためのブラフだ。通りからはカレンの部屋がある十階は高すぎて射線が通らない。せいぜい天井に穴を開けられるぐらいだ。
赤いレーザーポイントは、カレンの部屋の壁の高い位置にあった。だから水平より少し下、正面の建物の九階もしくは八階のどこかから狙ったのだと俺は予想した。そして撃ったやつはまだその場所にいる。だが、今の銃声は何だ。
けたたましいクラクションに構わず、車の往来を縫うように走り抜ける。傾きかけた太陽に照らされ、オレンジ色に霞んだ通りの反対側へ渡った。
影が動いたアパルトマンは古い建築で、幸いなことにセキュリティゲートなどなかった。エレベーターを無視して、螺旋階段を一段飛ばしで駆け上がる。途中で息が切れた。胸も痛い。吐きそうだ。最後の方はほとんど四つん這いになって登った。
誰も褒めてはくれないが、数時間前に二人組の男たちにサッカーボールのように蹴られ、肋骨にひびが入っている探偵にしては上出来だと思う。
くそったれ。こっちには銃がないのを忘れていた。至近距離からライフルで撃たれたら、俺の身体に大穴が開く。どんな死に様を晒すか考えたくもない。ブラフに引っかかったと油断してくれていることを願おう。
九階に着いた。人影を見たのはこの階の部屋だ。カレンの部屋との位置を計算し、905と表示のあるドアにそっと近寄り、息を殺して部屋の中の様子を伺う。
何も聞こえない。気配も感じない。間抜け面の俺がうっかりドアを開けるのを待ち構えているのかもしれない。
どこかから赤ん坊の鳴き声が聞こえてきた。
ドアノブをそっと握り、ゆっくり回す。そして耳を澄ます。赤ん坊の母親らしき怒鳴り声。そこに父親も加わった。平和だ。もうすぐ俺の腹に大穴が開くというのに、世界は平和に満ちていた。
握ったドアノブをそうっと押してみる。鍵がかかっていなかった。意外だ。もっと用心しないと駄目じゃないか悪党め。
さてどうする。丸腰だが、このままではらちが開かない。その時、遠くからサイレンの音が聞こえてきた。
今だ。中にいるやつが、近づいてくるパトカーのサイレンに気を取られている方に賭けよう。身体ごとぶつけるように一気にドアを押し開け、俺は部屋の中に突入した。
ドアを開けた途端、硝煙の匂いがした。そして俺が刑事だった頃に散々嗅いだ、馴染みのある、生臭いような金属を舐めた時のような匂いがした。血の匂いだ。
誰も撃ってこなかった。撃てるわけがない。そいつは壁を背にして床に座っていた。壁にはべっとりした赤いものが放射状に模様を描いており、がっくりうなだれた頭には、後ろの部分に無残な穴があった。首が急な角度で曲がっているせいで、縁がささくれたようになっている赤い穴は天井を向いている。足を広げた格好で座り、その足の間に血溜まりができていた。壁に咲いた血飛沫の花に比べたら僅かな量だ。
床に手をついて覗き込んでみると、額の真ん中に小さな穴が空いた顔があった。虚な目は何も見ていない。男は完全に死んでいた。
男の傍にはスコープが付いたライフルが落ちていた。狙撃したのはこの男だろう。そして拳銃が一丁。触らないように目を近づける。間違いない。ベレッタM92Fだ。イタリアのメーカーが産んだ最高傑作の拳銃だ。そしてそれは、あの二人組の男たちに奪われたはずの、俺の拳銃だった。
「その人、死んでいるの?」
ギョッとして振り返ると、目の前に銃口があった。さらにその向こうに、俺を見つめる真剣な目。
「カレン!どうしてここへ来たんだ。それにその銃はどうしたんだ」
「あなたが心配だったからよ。相手は銃を持っているのに、わたしの部屋から丸腰で飛び出したりして。それに、わたしのせいで大怪我をした人を放っておけないわ」
「どうして俺が丸腰だとわかる」
「泥だらけの服を着替えたじゃない。あなたは銃など持っていなかった」
「見ていたのか」
「覗いて悪かったわ。でも女の一人住まいに、よく知らない男を入れるんだから、用心するに越したことはないでしょう」
「まあ。それはそうだな。ところで、もう銃を下ろしてもいいと思うが」
「どこかにまだ誰か隠れていたりしない?」
両手で銃を構えたままのカレンが、油断のない目で部屋を見渡した。
「もうとっくに逃げたよ。だから銃を下ろしてくれ」
「それならいいけど」
「ところでハンカチを持っていたら貸してくれないか」
銃を下ろしたカレンが、レースの縁取りのある白いハンカチを取り出し、俺に渡した。そのハンカチで床のベレッタを包んで持ち上げ、銃口を嗅いでみる。
「何してるの」
「撃ったばかりなら硝煙の匂いがするんだよ」
万が一の可能性で、この男を殺したのは俺の銃ではないことを願ったが、無理な願いだった。ベレッタは撃ったばかりだった。
持ち上げたベレッタを、注意しながら元の位置に戻した。立ち上がって窓に寄り、外の様子を窺う。パトカーが四台いる。表通りは通行止めにしたらしい。数人の警官がこちらに向かってくるのが見えた。
「カレン。よく聞いて欲しい。もうすぐここへ警察が来る。だからその拳銃をこっちへ寄越してくれ。きみが持っているとあらぬ疑いをかけられるかもしれない。銃撃を受けて、犯人を追うのに俺がきみから借りたことにしたい」
「よくわからないけれど、その方がいいなら」
カレンは拳銃を俺に渡した。
「俺は逮捕されるだろう。このベレッタは俺の物で、この男を殺したのはこの銃だからな。どうやらまんまと嵌められたようだ」
「…ひどい話ね」
「警察にはきみの警護を頼む。彼らに守られている限り、カレン。きみは安全だ」
氷の女が何か言おうとしていた。しかしそこで時間切れだった。警察が到着し、射殺死体を発見、俺とカレンは両傍を警官で固められ、連行されていった。
♦︎純愛100z%【大人Love†文庫】星野藍月
♦︎ホラーレーベル【西骸†書房】蒼井冴夜
♦︎官能小説【愛欲†書館】貴島璃世
♦︎YouTubeチャンネル

気に入っていただけたらサポートお願いします♪いただいたサポートは創作の活動費にさせていただきます
