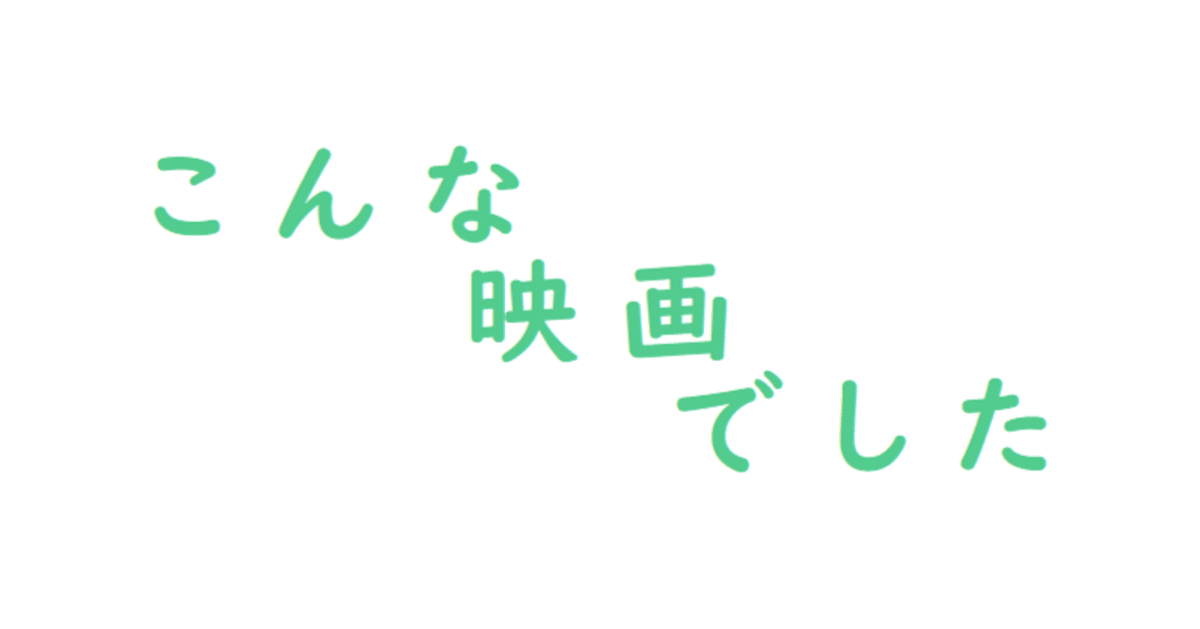
【こんな映画でした】505.[ジュリア]
2020年 2月11日 (火曜) [ジュリア](1977年 JULIA アメリカ 118分)
見終わって、フゥーっとため息が出てくる。フレッド・ジンネマン監督70歳での作品。一生涯、ナチスの蛮行は許せなかったのだろう。しかし、ナチスによる直接的な暴力や殺害シーンなどはほとんどない。それでいて、きちんと私たちにその恐怖と非道を分からせている。
オープニングシーンは静かな湖の畔のボートの上に一人の女性。シルエットなので年齢も誰なのかも分からない。そこに彼女のモノローグ。この映画や人生というものについてのもの。伏線か。
そこからまず海辺の家で、1934年6月のカレンダー(民主党のフランクリン・ルーズベルト大統領の肖像)が映されて、以後フラッシュ・バックが多用されて現在と過去とが行き来する。したがって若い頃のジュリアとリリアンは別の若手の俳優が演じることに。大人の彼女たちは、ヴァネッサ・レッドグレーブとジェーン・フォンダ。
ラストシーンはオープニングシーンと同じ。そこで私たちにもオープニングシーンは、実はあれからもう何年も何年も経ってからのことだと知ることができる。
*
ナチスに限らないが、人権が侵害され、人々が苦しい目に遇わされている時、私たちはどのように行動すべきか。真摯な生き方をする人間なら、悩ましく苦しい選択を迫られることになる。ジュリアは医学部を退学し、反ナチスの運動に関わることに。
まだナチス擡頭以前の二人の再会は、幸福に満ちたものであった。しかしその後は、ナチスの賛同者たちに危害を加えられ大怪我をしたジュリアとの再会であり、さらに次の機会は彼女たちに協力して資金を運ぶという危険な仕事をリリアンは請け負うことに。そのあたりはスリリングである。そしてこのあたりで初めて私などは、リリアンがユダヤ人であることを知らされる。欧米の人間には最初から分かっていることなのかもしれない。
あと辟易させられるのは、やはりタバコの多さ。のべつ幕なしに吸いまくる。レストランでも煙が濛々としていて、色が変わっているのだ。1930年代ということか。
*
以下はオープニングシーンでの、ジュリアの独白。
油絵は年を重ねるとともに透明感を増す。そしてその原形を現し始める。女のドレスを透かして木が見え、子供は退いて犬が現れる。小舟はもはや海にない。これをペンティメント(改訂)と呼ぶ。心変わりをした画家が筆を加えた結果だ。年老いた今、私は思う。過去の私には何があり、今何があるのか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
