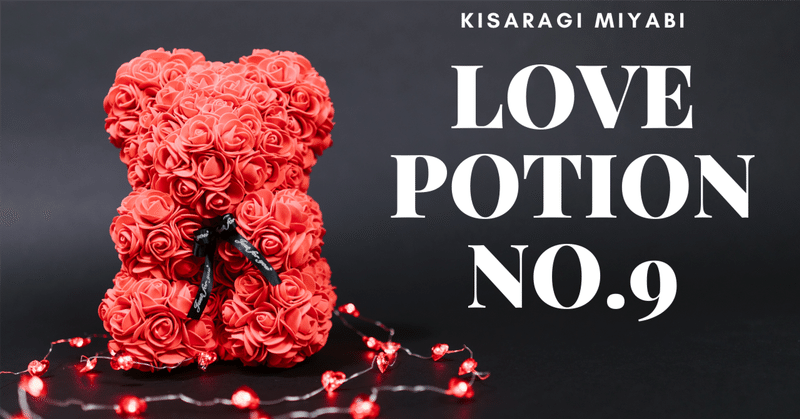
【短編小説】LOVE POTION NO.9(後編)
先を行くお兄さんに気づかれないように、私は美春にこっそりと尋ねる。
「そもそもあの人なんなの?」
「お店の人なんだけど、なんて言えばいいのかな、古道具屋さん?」
……古道具屋さん? 古道具屋さんがいったいなんでチョコレートなんて取り扱っているのだろうか。
先を行くお兄さんはまるでウィンドウショッピングを愉しむかのように飄々と町を歩いて行く。どれだけ歩いただろうか、いつの間にか私達は駅前の裏路地を歩いていた。いつも通学で駅から学校までの道のりを歩いているはずなのに、なんだか全然知らない道だった。
こんな路地なんてあったっけ……?
そんな私の疑問に構うことなくお兄さんは路地の奥の方、奥の方へと進んでいく。
方向感覚が失われていくような気がしたころに、お兄さんはふと立ち止まる。
そこには「古物取り扱い〼」という看板と古ぼけた木製のドア。どうやらそこがお店らしい。
一歩中に踏み入ってすぐに、随分と得体の知れないお店だなと思った。
壁には剥製、あちこちに詩集や画集の古本が山と積まれ、床には何に使うのかも分からないガラクタのようなものが転がっている。正面の木製のカウンターの上には大きな古時計が掲げられている。お兄さんはカウンターの裏へと回ると、こちらを向いて話を始めた。カウンターに居座っている様は確かにこの店の主に見えるから不思議だ。
「さて、それじゃ説明したろかな」
もったいぶった様子で手をこすり合わせ、お兄さんがこちらを見る。妙に楽しそうにこちらを見つめる様子はまるで狐の舌なめずりを思わせる。
「ちょっと待って。その前にまずお兄さんの名前くらい教えてよ」
お兄さんは一瞬きょとんとした顔をしたかと思うと、笑いながら名前を告げる。
「ああ、それもそうやな。自分、拝戸と言う名前やねん。拝むにドアの戸な。これからよろしゅう」
変な名前だな、というのが第一印象だった。そんな私の顰め面に向けて拝戸さんは説明を始める。
「そもそもチョコレート自体が昔は媚薬とされていたんよ。そしてそれは科学的に立証されているんやで」
「ホントですか?」
私は思わず聞き返していた。そもそも学校の先生とかからならまだしも、古道具屋の怪しい店主に言われても説得力がない。
「ホンマやで、信用ないなぁ」
「今日初めて会ったばかりの人を信用しろっていう方が無理だと思いますけど」
「ははっ、確かに。やっぱオモロイなぁ、キミ」
拝戸さんは私を気に入ったみたいだけどこちらは警戒を解くつもりはない。そんなこちらの様子に構わずに拝戸さんは話を続ける。
「そもそもヒトの恋愛感情には脳内ホルモンが関わっとる。『ドーパミン』『ノルアドレナリン』って聞いたことないか?」
「それなら聞いたことくらいはありますけど……」
「さよか。でな、チョコレートに含まれる『フェネチルアミン』っていう化学物質が実はこの脳内ホルモンの放出を促すらしいんやて」
そこまで説明されると、なんとなく本当かなという気になってくる。
拝戸さんは立て板に水、といった勢いで話を続ける。流れるような口ぶりに思わず私も引き込まれてしまう。ちらりと隣の美春を見ると、まるでジャニーズのコンサートにでも来ているかのように、体の前でぎゅ、と両手を組んでお兄さんを見つめていた。
「それならフェネチルアミンの含有量を増やしてやればいいんじゃないかって考えた奴がおったんやな。そいつは実験を繰り返して一番効果のある含有量を割り出した。こういうものは多すぎても効果がないんや。過ぎたるはなお及ばざるがごとし、ってやつや。しかしその量がとっても繊細でな。大量生産は出来なくて、市場にはほとんど出回らん。そんな中、たまたまわいの知り合いが手に入れて、それを一部譲ってもらったんや」
私の様子を見計らってなのか、まるでマジシャンが手品を披露するかのように拝戸さんは自然な動作でスッ、とカウンターの下から小箱を取り出す。
「それがこれ。商品名は『ナンバーナイン』」
宝石箱のように装飾の施されたその箱をそっと開け、こちらにその箱の中身を見せつける。絹の内装に包まれて、つややかに光る板状のチョコレートが納められていた。
私は思わず息を飲む。と同時に疑問が湧き出した。
「これ、板状なんですか? てっきり何かの形をしてるかと思ったんですけど」
「お、ええとこに気がついたね。美春ちゃんからも最初におんなじ事を聞かれたんやけどね。これ、購入者が自分で好みの形に加工すること前提なんよ。実は一度加熱で活性化するように調整されてる」
「なんでわざわざ?」
「渡す相手がもしこのチョコレートの事を知ってて、形が独特やったらバレるかもしれへんやろ?」
あー、なるほど。頷く私の横で、一度説明を聞いているはずなのに、感心したように拝戸さんを見つめる美春。
ふと思う。……もしかして、この拝戸さんのことを美春は好きなのだろうか。
確かに同級生の男子なんかよりはずっと大人っぽくて(そりゃそうだ、実際大人なんだから)心惹かれるのも分かるんだけど、ちょっと年が離れすぎているんじゃないだろうか。
それになんだか怪しいし。
どーかなー、やめたほうがいいんじゃないかなー。余計なお世話かもしれないけど。
そんな葛藤する私のことを知ってか知らずか、拝戸さんは「で、どないする?」と聞いてきた。
「え、何がですか?」
「いやいや、ここまで営業トークさせといていまさら何がはないやろ。このチョコレート、どうする?」
「えーっと……」
営業トークを勝手に始めたのはそっちじゃん、という言葉を飲み込みつつ、私はしばし考える。別に、いま落としたい相手なんていないので、どちらかというとどうやって断ろっかな、という類いの葛藤だった。
「ねえ、沙由理、一緒に買おうよ」
美春がこちらの袖をこっそりと引っ張りながら言ってくる。
そうなのだ。美春は元から買うつもりなのだ。たぶん、一人では買う勇気が出なかったので、こんな回りくどいことをしてまで私を巻き込んでいるのだ。
なによりもまず、そこまでして落としたい相手が美春にいたことがまずショックだった。
なんでも話せる相手だと思っていたのは、どうやら私の方だけだったらしい。でもいくらクラスが別だとはいっても、美春の普段の行動からはとても特定の男子を気にかけているような様子は感じられなかった。私が気がついていなかっただけってことは、私も自分で考えているよりも美春のことが見えていなかったってことなのか。
悶々とした気持ちを抱えている私を知ってか知らずか、拝戸さんが気安い様子で付け加えてくる。
「ほれ、沙由理ちゃん、ホンマは五千円やけど、三千円にしたるよ」
高っか……くはないのか? 値段を聞いて思わず高いと感じてしまったし、確かに私の普段のお小遣いの金額を踏まえればそれなりの価格ではあるけれど、拝戸さんの言う効果がもし本当にあるのであれば、それは決して高くはないはずだ。
それが分かっているのか、拝戸さんはにやにやとこちらを楽しそうに眺めてくる。
私は悪あがきと分かっていながらも、なんとか反論を続ける。
「そもそも古道具屋さんが食べ物売っていいんですか?」
「ダメやね。だから君らにはこの綺麗な箱を売るんや。おまけでチョコレートをつけたるけどな。……ま、ホンマにいらんのならこっちも無理に売りつけるつもりはないで」
私の反論をさらっと躱し、引きの姿勢を見せる拝戸さんを見て、美春は私の方を縋るように見つめてくる。そうだよなぁ、女子中学生ごときが交渉事で大人に勝てる訳がない。
……はぁ。私は溜息をついて、自分の負けを認めたのだった。
***
さて。
私の目の前にはドロドロに溶かされたチョコレートがある。中身はもちろん拝戸さんから購入した『ナンバーナイン』だ。さきほどから甘い匂いを漂わせて、私の鼻を刺激してくる。私はそれを無気力にかき混ぜながら、一体自分が何をしているのかをぼんやりと考えていた。
「ほら、沙由理、手が止まってるよ」
美春の指摘を受けて、私はいつの間にか止まっていたチョコをかき混ぜる手をのろのろと動かし始める。向かい合わせで作業している美春も、私と同じようにチョコレートをかき混ぜているけれど、彼女のボウルに入っているのは普通の市販のチョコレートだ。
美春が準備したハートの型は思ったより大きくて、市販のチョコと混ぜてやらないと分量が足りなかったのだ。
私の行く宛てのないチョコレートは良いとして、美春のチョコは果たして誰の元に届くのだろうか。気になって仕方がない。私はこっそりと向かい合わせで作業している美春の様子を伺う。作業する自分の手元を真剣な表情で見つめ、黙々と作業を続けている美春は贔屓目を差し引いても恋する乙女の表情で可愛かった。
「そろそろいいかな」
美春と私、それぞれが湯煎で溶かしたチョコレート同士を混ぜ合わせる。
わずかに色味の異なる二つのチョコレートは、ぐるぐると渦を描きながら一つになっていく。
ふと、このチョコレートをあの拝戸さんに渡したら、一体どんな顔をするだろうか、なんて考えが頭をよぎった。
いやでも、美春の相手が本当にあの人だとしたら悪いしなぁ。
そう考えながらも拝戸さんのあの人を食ったような顔を思いだすと、とてもじゃないけどあんな怪しげな人物に、私の大事な美春を渡すわけにはいかない、という気持ちがふつふつと浮かんできた。ここは私の身を犠牲にしてでも、あの拝戸から美春を守らなければ。
密かに決意を固めつつある私に向けて、美春がすっ、とヘラについたチョコレートを差し出してきた。
「ねえ沙由理、きちんと混ざってるかちょっと味見してくれないかな」
「ああ、うん」
ひょいぱく、と差し出されたチョコレートを私は口に含む。
『ナンバーナイン』はちょっと苦いと聞いていたけど、普通の甘いチョコと混ざっているからか、まず甘さが来て、その奥に密やかに苦みを感じた。でもそれは不快という感じではなくて、むしろ心地よい味だった。
「うん、いいんじゃない? 美味しいと思うよ」
(……誰にあげるか知らないけどさ)というつぶやきは心の内に押し込んで、私は答える。私の返事に、美春は小さく、よし、と呟いていた。
その頬はいつの間にか真っ赤な林檎のように赤らんでいる。心臓の鼓動が速くなる。
「それなら良かった」
にっこりと微笑んだ美春は、チョコレートをハートの型に流し込みながら、恥ずかしそうに俯いて呟いた。
「これ、沙由理にあげるためのチョコレートだから」
……え?
一瞬理解ができず、ぽかんとする私に向けて、美春が潤んだ瞳を向けてくる。
「えっと、ちょーっと理解が追いついていないんだけど、その、つまり、そういうこと? 私のためって……その、私のことが好き、ってこと?」
顔を更に真っ赤にしてコクコクと頷く美春を見て、正直可愛いな、と思った自分がいたことに自分で驚いた。これはチョコレートのせい? それとも私の本心?
色んな葛藤が渦巻くのだけど、チョコレートのほんのりとした苦みが抜けていくのと一緒にそれは心の奥へと押しやられ、これはこれでなんだかけっこう悪くないかも、なんて思ったりしたのだった。
***
古ぼけた物品が並ぶ店内で、二人の男が話をしている。
「……で、『ナンバーナイン』は売れたのかい?」
「もちろん。上手いこと売れたで。しかも律儀なことにきちんと効果を発揮したって、わざわざお礼を言いに来てくれたわ」
「それは凄いな。しかしフェネチルアミンは加熱すると空気中に揮発してしまうだろう?溶かしてしまえば意味のない商品とばれてしまって、僕の方ではせっかく作った大半が在庫になってしまってるんだよ。いったいどうやったんだい?」
「加熱して揮発してしまうのも、やりようはあるんやで。……例えば一緒にチョコを作る、とかやな」
『ナンバーナイン』開発者の男に向けて、拝戸はにやりと笑いかけたのだった。
<了>
更なる活動のためにサポートをお願いします。 より楽しんでいただける物が書けるようになるため、頂いたサポートは書籍費に充てさせていただきます。
