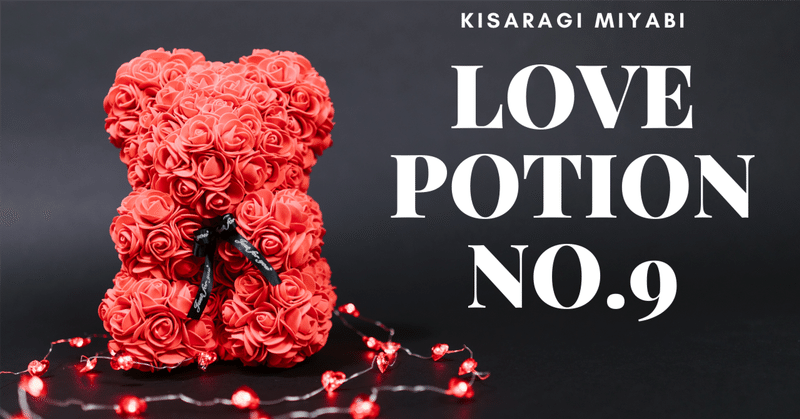
【短編小説】LOVE POTION NO.9(前編)
きっと、バレンタインのせいだ。
二月になると教室の空気がなんだかそわそわしてくる。他愛ないおしゃべりだったり、視線を交わす仕草にもなんとなく緊張感が漂っているみたいに感じる。
でも、私は正直に言うとみんながなんでそんなにバレンタインに必死になっているのかが分からないのだ。同級生の男子がなんだか子供のように思えてしまって、よっぽど仲の良い女友達と話している方が楽しいと思うんだけど、みんなはそうじゃないのだろうか。
そんな感じで浮き足だった教室の雰囲気とは一歩引いた立場に立っていたつもりの私に、メッセージが届いたのはバレンタインの前日のことだった。
***
その日の四時間目の開始間際、机の中に入れておいた教科書を出そうとして中を探ると、見慣れない紙がポトリと落ちた。拾い上げて見てみると、それは小さなメモで私宛のメッセージが書かれていた。定規で線をひいたような文字なので、誰が書いたかはわからない。どうやら移動教室で誰もいなくなったタイミングを見計らって、誰かがこっそりと机の中に入れたみたいだった。
そこには、今日の放課後に旧校舎のはずれに来て欲しいという内容が書かれていた。まるで犯行予告みたいなメッセージだった。
私の通う学校には旧校舎がある。
敷地の端に位置している旧校舎は一部は部活棟として使われていて、教室のある新校舎とは渡り廊下で繋がっている。
私は放課後を待って旧校舎へと向かう渡り廊下を歩いていた。意識しないようにしていたけれど、どうしても自分が緊張しているのが分かる。不自然な歩き方だからか、後ろで結んだ長めの髪が、背中にやたらとぶつかってくる。そのままぎくしゃくと渡り廊下を抜て、旧校舎の裏へと回る。
校舎の陰から少しだけ頭を覗かせて、校舎裏の様子をこっそりと伺う。
人影が見えた。落ち着かない様子でその場をぐるぐると歩き回っている。
「……美春?」
その人影はよく見れば友達の美春のようだった。
ふわりとカールした髪の毛を肩まで伸ばし、おっとりゆったりとした雰囲気を普段は纏っている。背も小さくて穏やかな彼女は、のっぽで忙しない私とはまるで正反対だ。
中学に入ってからはクラスが別々になってしまったけれど、それでも不思議と美春と私は小学校の頃からずっと一番の仲良し同士だった。私は自分のことならなんでも美春に話したし、美春も同じように何でも話してくれた。もしかしたら一緒に住んでいる家族よりも深いところまで共有している相手じゃないかと思っていた。
いったい誰だろう、と緊張していた私はそこで肩の力がするっと抜けて、軽くなった気持ちで校舎裏に辿り着いた。だけど、そこで待っていた美春の様子は、普段のおっとりした雰囲気からは想像できないくらいガチガチに緊張した様子だった。私は思わず声をかける。
「ちょっと、美春、大丈夫? なんかすごく緊張してるように見えるけど」
「……そう見える?」
美春は返事もそぞろにきょろきょろとあたりを見回して、私の他に誰もいないかを探っているようだった。一体何をそんなに緊張しているのだろうか。
「沙由理の方こそ、後をつけられたりとかしてない?」
「してないしてない。なんで誰かが私の後をつけてくるのよ」
私は手を振って美春の不安を振り払う。
「だって、沙由理って美人だし背も高いから、女子の中でも目立つし……」
……そうかなぁ?
自覚はないけど、美春からはそう見えるのだろうか。私からすれば美春の方がよっぽど女の子らしくて可愛いと思っているのだけど、美春はいつも私のことをいつも美人だと褒めてくれる。悪い気はしないけど、いや、むしろとっても嬉しいけれど、なんだか気恥ずかしくもある。
そんな美春はひとしきり辺りを見回した後こちらに近寄ってくると、誰が聞いている訳でもないはずなのに、小声で話しかけてきた。重大な秘密を打ち明けるようにこっそりと。それは確かに魔法のような言葉だった。
「ねえ、『絶対に相手が自分の事を好きになるチョコ』があったら、どうする?」
「……いや、嘘じゃん、そんなの」
私は思わず否定していた。美春には悪いけど、そんな都合の良い話があるわけがない。
「それがあるんやなぁ」
そんな私の言葉に反するようにして、どこからともなく男の人の声がした。私は驚いてあたりを見回す。すると私の真後ろ、死角になっていた木の陰から、一人の男の人がゆらりと現れた。私は思わず後ずさる。
「だ、誰!?」
「うんうん、良いリアクションやね」
私の反応にその人は満足そうに笑みを浮かべる。年齢は二十代前半だろうか? だけど髪の毛は若白髪なのかあえて染めているのか、まだらに銀髪が混じっている。長めの前髪は目元までかかっていて、表情をうっすらと覆い隠している。そこから透けて見える狐目は、ニコニコと愛想良く笑っているようで、どこか胡散臭さを感じさせた。ゆったりとしたコートを羽織り、体の線を覆い隠している。
「ここ、学校の中なんで部外者は勝手に入っちゃいけないんですけど」
飄々とした態度のその人に向けて、私は警戒心を剥き出しにして告げる。
そんな私と男の人の間に割り込んできたのは美春だった。
「違うの、この人は私がよく行くお店の人で、その、さっきのチョコレートの話を教えてくれた人なの」
「そうそう、キミも気になるやろ?」
美春の後ろでにやにやとした笑いを浮かべたまま男の人が言う。怪しすぎる。
「詳しくはウチの店で説明しよか。店まで案内するで」
そう言ってこちらを見もせずにくるりと男の人は後ろを向いてすたすたと歩き出す。私達がついてくるのが当然、と言わんばかりの歩き方だった。よっぽど無視して帰ろうかとも思ったけれど、引っ込み自案の美春がわざわざ私の手を引いて、お兄さんの後について歩き出したので、私もしぶしぶとついていくことにした。
何が楽しいのか、軽く口笛を吹きながら堂々と校内を歩くお兄さんの後をついていきながら、私は美春に問いかける。
「そういえば、なんでわざわざ手紙で呼び出したりなんてしたの。そんなまわりくどいことしなくても、直接メッセージくれれば良かったのに」
「それはそうなんだけど……」
美春は困ったようにお兄さんの方を見て言う。お兄さんは自分に話が振られたことが分かると、こちらを時々振り返りながら話し出した。
「せやな。美春ちゃんは許したってや。自分のお願いで手紙を出してもらったんや」
「何でですか」
「どんな子なのかを見たかったからやな」
「どういうことですか?」
「自分はな、物売りではあるんやけど売る相手を選ぶ。気に入った人間にしか売らんのや。で、美春ちゃんに例のチョコを売るつもりやったんやけど、どうしてもキミと一緒じゃなきゃ嫌言うもんでな。せやからいったいどんな子か確かめさせてもらったんや。悪く思わんといてや」
「人を値踏みするような人は嫌いです」
私の言葉にさも面白げにくっくっく、とその人は笑った。
「うんうん、ええよキミ。その物怖じせんところが気に入った。だから自分の店まで案内しとるんやけどな」
すたすたと先を行くお兄さんについて私達は校外へと出て、街中の方へと向かっていった。
<続く>
更なる活動のためにサポートをお願いします。 より楽しんでいただける物が書けるようになるため、頂いたサポートは書籍費に充てさせていただきます。
