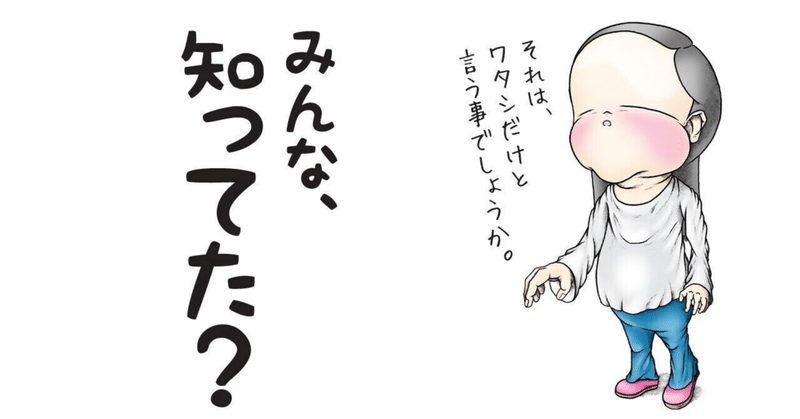
面白いの定義と客寄せパンダ
「面白い」の定義。なんて、今更考えた所で無意味である事はなんとなく分かってる。そんな定義は人それぞれだし、そもそも考えた人なんかいないのがほとんどだ。
でも、僕そういう事を考えなければいけない呪いみたいな物に掛かっているし、そういう事を考えるのが好きなのである。僕の面倒くさい部分だと思ってくれればいい。(要するに黙って聞いてくださいお願いします。という事だ。)
例えば、芸人さんがよく舞台上で笑いを生む手法として「漫才」と「コント」というものが存在する。それぞれの定義は説明しなくても大体わかるだろうし、これを読んでる人に『あのコンビは漫才師だけどやっている事は漫才じゃない。』なんて、陳腐な論理を筋立てる暇人はいないと思っている。
この2つでなぜ面白い物を作れるのかというと、漫才だったら「人間的な面白さ✖️定説には沿っているけれど少し逸れた設定」。コントだったら「キャラクター的な面白さ✖️定説には沿っているけれど少し逸れた設定」で面白さを生むからである。いわば計算式的な物が備わっているのだ。そして、それは文字の中でも計算式的な物が備わっている。それは、追々話すとしてまずは「人間的な面白さ」と「キャラクター的な面白さ」。そして、「定説に沿ってはいるけれど少し逸れた設定」の3つの定義と疑わしさを考えていきたいと思う。
まず、人間的な面白さについて簡単に定義づけていきたいと思う。よく、「漫才は自身の体重が乗ってこないと面白くない」と言われる通り、漫才はプレイヤー自身の面白さが重要視される。良くも悪くも、高学歴で頭がいい人は大声でギャグを用いて動きが滑稽な漫才はできないだろうし、逆に馬鹿な人は伏線を張ったりセンスがあるボケをしたり言葉で笑いを誘うなんてできないと思う。要するに、人間的な面白さとは自分自身の内側から滲み出る物であり、漫才で人々を笑わせようと思うのならまずは自分自身がどういう人間かを知る必要がある。
なるほど…そういうことか。
と思ったそこのあなた。まだまだですね。
先ほども言ったが、人間的な面白さとは自分自身がどういう人間かという事を知る事から始まると言った。でも、ここで一つ考えなければいけない問題が生じる。まずそもそも、自分自身がどういう人間か。なんて、簡単に結論付けられるのだろうか。という問題である。そして、おそらくできないというのが答えである。
考えてみて欲しい。この世の中に東大生が何人いて、全員が東大生漫才をして、はたして全員がM1で優勝できるだろうか。この世の中に既婚している女性が何人いて、全員が旦那の愚痴を漫才にして、はたして全員が寄席を埋められるだろうか。(極論か?)
要するに。人間的な面白さとは自分の中にある何かの掛け算だ。東大出身でも生活するのが苦手ならそれをネタにすればいいし、女性だけど男優りなのならそれを主軸にすればいい。それを一言で表すなんて、きっと広辞苑を作った人でも無理だろう。とにかく。ひたすら掘り起こすしかないのだ。自分の中に眠る武器を。それを磨いていくしかないのだ。
次に、キャラクター的な面白さについて定義付けていきたいと思う。
コントにおいて 何が重要か。と言われたらやっぱり登場人物の面白さだ。そもそも、コントとはフランス語で短い物語と呼ばれるように…なんて説明は今更いいか。要するに、物語に出てくる登場人物の面白い部分をどれだけ引き伸ばせるか。というのが重要になってくる。
ん?でもそれって…。
と思った方。筋がいいですね。きっとこう思ったんじゃないでしょうか。「それって、人によるよね?」と。
例えば、魔女役をやる場合はきっと細身の女性がやるより太っている女性の方がやった方が面白いだろうし、酒浸りの男役はきっと小綺麗な青年より青髭の生えた中年男性がやった方が面白いと思う。
要するに。キャラクター的な面白さとは、キャラクターそのものに自分がどれだけ入り込めるか。というものが重要になってくる。自分の外見。性格。生活習慣から思想までことごとく書き出して、それに似合うキャラを憑依させる。そして、それをコントに似合うサイズに拡大する。
なんとなくここまで読んで察しがついただろうが、漫才にしろコントにしろ中心は自分である。まず、演じるプレイヤーがどんな人物かを掘り起こさなければ面白い物は生まれない。要するに「こういう仕組みのものをやりたい!」というのは成立するけど「こういう人みたいな漫才をやりたい!」というのは成立しない。やったとしても、それじゃ客寄せパンダだ。
それでは最後に。「定説には沿っているけれど少し逸れた設定」について定義付けていこう。
まあ、読んだまんまなのだが、漫才にもコントにも設定というものがあり、客や視聴者はなんとなくの想像を頭の中でする。異性の高校生同士が意識し合えば、この後告白するんだろうなぁ。とか。上司が部下に説教をすれば、きっと部下がこの後に仕事で成功するんだろうなぁ。とか。なんとなくの想像をする。
きっと、これも人それぞれだ。恋愛ものに疎い人は恋愛模様の行く末なんて想像できないだろうし、働いていない人はサラリーマンの気持ちなど想像などできない。
でも、面白そうという設定は万人共通だったりする。
男子高校生が好きな異性を目で追いかけていたらバナナに滑って転んだり、サラリーマンが仕事の悔しさを紛らわすために空き缶を蹴ったらリムジンに当たってそれを弁償としたらデスゲームに参加させられたり。etc。
面白そうという漠然な物はなんとなく存在する。それは、王道から半歩逸れた物だ。
問題はどうそれを現実に掛け合わせるか。要するに、これも掛け算であり、何を掛けるかは人それぞれだ。
というわけで。面白い物というのは掛け算で生まれる。何かと何か。それは小説でもドラマでも音楽でも映画でも一緒なのだろう。
ここまで読んだ方に一つ言いたい。詰まらない議論に付き合ってくれてありがとう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
