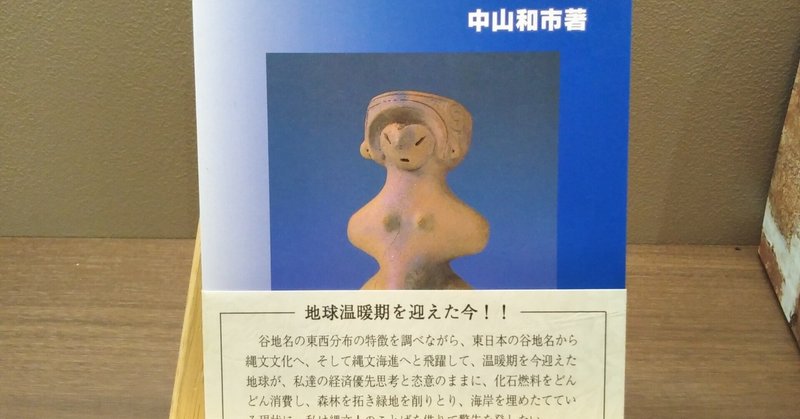
本・縄文海進を経験している私たちの祖先の生活に想いをはせる時、「稲作に適した土地」こそ、最適な避難場所である。
『縄文人の遺産と現代人への警告』。
センセーショナルな題名の本が、筑波書林から2001年に発行された。
著者は、茨城県の大穂町立吉沼小学校校長をされていた中山和市さんだ。
私は、2002年に、著者のお宅まで伺い、著者にインタビューをした。
この本は、貴重な研究の成果であると感得した私は、当時茨城県土浦市にあった筑波書林を訪問し、この本を買い付けた。
帯文にはこう書いてある。
★地球温暖期を迎えた今!!★
谷地名の東西分布の特徴を調べながら、東日本の谷地名から 縄文文化へ、そして縄文海進へと飛躍して、温暖期を今迎えた 地球が、私達の経済優先思考と恣意のままに、化石燃料をどんどん消費し、森林を拓き緑地を削りとり、海岸を埋めたててい る現状に、私は縄文人のことばを借りて警告を発したい。
★人間は何所へ避難すれば?★
森を追われたカラスやハチなどが、今は人間の住む街へ避難してきているが、やがて迫り来るであろう海面上昇の波に、低地を追われる人間はどこへ避難すればよいのか。
私達は子孫のためにも豊かな自然を守り、残すよう努力し なければと切に思う日々である。
(1)
縄文海進を経験している私たちの祖先は、稲作に適した土地に定住してきた。
稲作に適した土地は、低湿地に多く、一般に「谷」と名づけられた。
では、「谷」をなんと読むか?
西日本ではタニと読む地名が多い。
東日本では、ヤ、ヤツ、ヤチと読む地名が多い。
そのほか、西日本ではサコと読ばれたり、
東日本ではサワ、サクと読まれることが多い。
また、「桶狭間」と呼ばれるような「ハサマ(ハザマ)」地名も、「タニ」地名と共に多い。

(2)★アイヌ人・縄文人の「ヤ」「ヤツ」地名。例えば(渋谷)など
★海の民族・海人族(水上生活)の「ハサマ(ハザマ)」地名。例えば(桶狭間)など
★山の民族・南方系弥生人(水田稲作)の「タニ」地名。例えば(鶯谷)など
・日本に稲作と土木技術をもたらした弥生人は、北九州に上陸し、瀬戸内海を東進して河内湾から淀川を遡上し山城国に上陸した。
・同じ大陸や半島から渡来した氏族でも、同じ地域には住まず夫々の地域を占有して定住している。
・「ハサマ(ハザマ)」地名と「タニ」地名という異文化を持った人たちが地域を共有している。
・彼らは元々大陸でも同じか近い地域に住んでいた者たちで、海人族は水上生活を、南方の弥生人達はタニに近い大地上で生活していた。
・航海はなれた海人族が先導し、南方の弥生人達は、より大型のくり舟で後へ従ってきた。
・海人族といっしょに南方から来た弥生人は、同じ地域を共有しても利害が反することはない。
・互いに山の幸と海の幸を交換することによって、両者の生活は豊かになっていく。
・南方系弥生人は、多くのタニを利用してタニ田をつくり、稲作を広げていった結果が、日本一多いタニ地名を生むことになったものであろう。
・ハサマ地名は沖縄や奄美から伝えられたであろう。
・平和な農耕民族である弥生人達は戦乱を避け、海人族の力を借りて 北へ北へと避難し、安住の地を探し求める旅にでたのではないか。これが「数世紀を経ずに弥生文化が東日本へ到達した」理由ではなかっ たかと私は想像する。
・それはまた、海岸近くや河川の流域沿いなどのハサマ地名の分布地とも符合しており、海人族やその土地の縄文人とも交流しながら、湿地を利用した比較的小規模の水田が作られていたものであろう。
・縄文人は自然を壊すことをせず、自然を利用し自然と共生してきた。火山すらも利用してきた。縄文後期以降の寒冷期に入り、生活が次第に苦しくなってくると、せいぜい山麓の原野を焼き払って栗やそばなどを栽培したり、山芋や栗を植えたりして自然利用の工夫をすすめ、あとはひたすら大自然の神を祈りすがる生活であった。
・集落もさびれ、かっての豪華な土器作りの情熱も消えて、代わりに土偶や「御物石器」を天神地神に捧げるようになる。ただ東北の「亀ヶ岡文化」 の繁栄だけは例外である。
・その頃(縄文晩期) 黒潮に乗って日本へ漂着した海人族があった。 彼等は小集団でやってきては「白浜」を見つけて定着し、漁をしながら舟上での生活を続けた。夜は舟同士を結びつけて「もやい舟」として安定させる。
・また近くの「ハサマ」谷に小さな水田を何段にも作り、 「赤米」を栽培した。赤米は主食というよりは神に捧げる目的が主で あったろうし、御神酒も作って海の神に航海の安全を祈った。彼等が長住みついた宇和島や房総・能登には、今も棚田が残っている。
・彼等の採った魚介類は、近くの縄文人達と必要な物資の交換にも使われた。また南方の海で採ってきた珍しい貝などは、貴重な交易品と して使われたであろう。海女達が多分頭に魚などをのせて運んで来る姿は、縄文人達の好奇心をそそったに違いない。沿岸での漁が思わしくなくなると、海人族はまた移動したり、なかには河川をのぼり湖沼 の周辺に住みつく者もあった。こうして「ハサマ」 地名が広まって いったと私は考えている。
(3)
稲作に適した土地をどのように名づけるか?名づけられたか?そこに先祖の由来が隠されている。渡来の由来また自然災害・戦争などで移住した歴史などが、地名に隠されている。
地球温暖期(地球変革期)を迎えた今、人間は何所へ避難すればいいのだろうか?
著者は谷地名を調べたものの、明言はしていない。
しかし、縄文海進を経験している私たちの祖先の生活に想いをはせる時、「稲作に適した土地」こそ、その解答ではないのだろうか。
私は、中山和市さんの谷地名の研究について、そんな風に読み解かせていただいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
