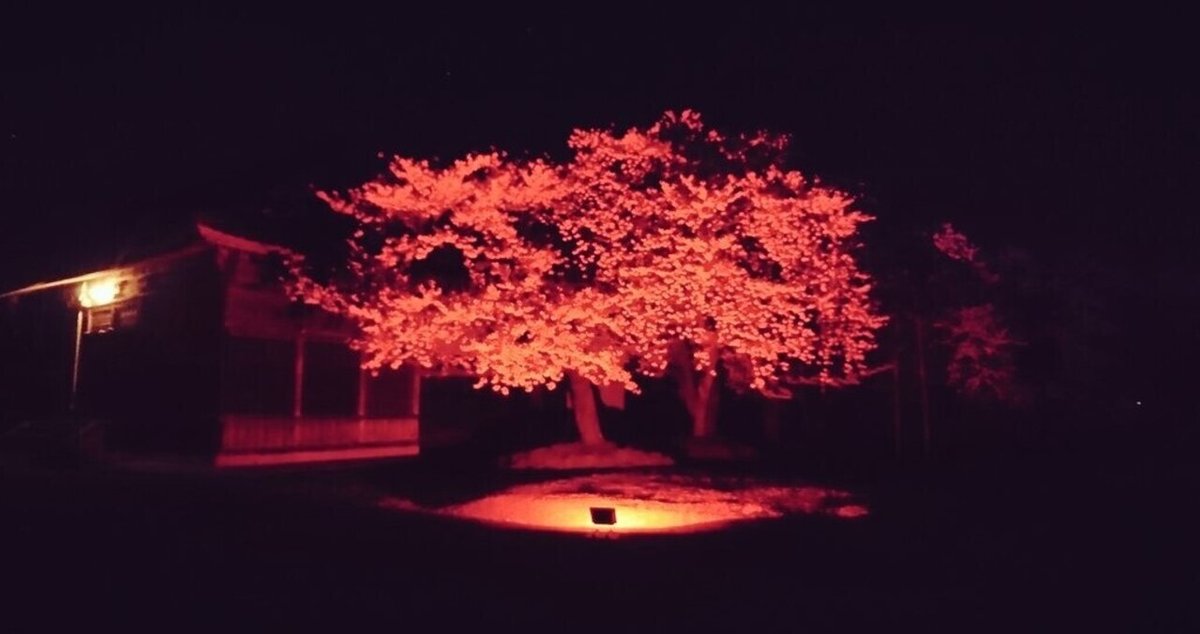
ARuFa「さんさーら!」に見る郷愁の時代性
「【動画あり】一般人だけど20代最後なのでプロにオリ曲を作ってもらった」
https://omocoro.jp/bros/kiji/278460/
この記事から生まれた「さんさーら!」という曲が聴けば聴くほどめちゃくちゃに良く、いろいろと思索を巡らせたので書きます。好き勝手書いています。敬称略。
どういう話をするの?
・キャラクターソングは視聴者が文脈を把握してから聞くことが前提にあるということ
・「さんさーら!」の文脈を共有できる世代のインターネット(狭義)への解釈は、それ以上、それ以下の世代のそれとは異なるのではないかという推測
・今後、音楽はより事前の文脈の把握が必須なものか、あるいはより普遍で概念的なものになるか、どちらかへ先鋭化するのではないかという予想
・「さんさーら!」めっちゃいいよねっていう結論
--------------------------------------------------------------------------
記事を読めばわかる通り、この楽曲はライターのARuFaが「20代を締めくくる曲」をコンセプトとして制作されている。作詞はピノキオピー、作曲は田中秀和。
歌詞は1人の人間の人生をテーマとして制作されており、ARuFaは生身の人間だが、広義のキャラクターソングであると言える。
アニメ作品から派生するキャラクターソングは音楽が関連するアニメに限らず、かなり一般的なものになった。キャラクターソングは多くの場合、キャラクターの性格やストーリー、心情などを反映したものになっており、ターゲットはそれを把握している作品ファンだ。前提にキャラクターへの知識が必要になることによるデメリットとしては、鑑賞し理解できる層が限られ、排他的になることが上げられる。一方でメリットとして、前提知識の部分には詞の中で言及する必要がなくなるため、その分、総合して見た際に通常の楽曲に比べ多くの情報量を提示することができ、共感の解像度を上げることができる。
改めてさんさーら!の詞を見てみる。核に「インターネット」への解釈があるが、詞の中にインターネットという単語は登場しない。この詞だけを読んで、この「地獄」と「天国」がインターネットのことを指していることを察することは普通に考えれば困難だろう。主題がインターネットでありARuFaの20代である、という楽曲外の文脈を持って聞くことで、途端に筋立てと思想が見えてくる。
当たり前のようなことだが、つまり楽曲のターゲットは記事を読み、その文脈を把握した人だということだ。一方で、記事を読みさえすれば万人が受け止められる楽曲なのかと問われれば、インターネットを「最高も最悪も同時に存在する面白い場所」とする文脈を理解し、共感や一種の感傷を持って聞くことができるリスナーの層というのはトータルで見ると果たしてどれだけの幅があるのだろうということも考えてしまう。
この楽曲はARuFaが30歳を迎える記念として制作された。同世代の自分の私見が入るが、2021年現在のアラウンドサーティーは一言で言えば「思春期と“自分も発信できる場所”としてのインターネットが結びつく」という経験をした世代であるように思う。
「ブログ」の流行語大賞入りが2005年。ニコニコ動画のサービス開始が2006年。Twitter日本版が2008年。小学校高学年から中学生、高校生の時代に、それらのツールは広がった。ARuFaは2005年、中学2年生でブログを始めている。
同時に、インターネット(狭義)が一般的でない世界の記憶がある最後の世代でもある。テレビのお笑い番組や音楽番組がクラスの共通言語としての役割をまだ果たしていた時代だ。
現在の子供たちは、物心ついたときからインターネットが身近にある。有線をつないでピーピーガーガー音を立てさせなくてもパソコンはネットにつながる。玩具が当たり前のようにスマートフォンと連動する。ヒーローはブラウン管や液晶の向こう側ではなくYouTubeにいる。ARuFaとダ・ヴィンチ・恐山によるネットラジオ「匿名ラジオ」の「#80これからインターネットを始める子供たちへのアドバイス」では「インターネットのつながっていないパソコンを遊び倒す経験をしたほうがいい」ということがアドバイスとして挙げられている。既にそれは困難になりつつあるかもしれない。
ARuFaの生み出すコンテンツの独自性はその「インターネットのつながっていないパソコン」の質感にあると感じる。アナログな場所があってこそ、インターネットは区別され、未知のおもちゃが詰まっている箱になりうるし、その上でおもちゃ箱を体現したような存在に支持が集まる。箱が消滅し、おもちゃがあらゆるところに置かれ、いつでも触れられるようになったときに、我々がそこに異質な物としての意識を向けることは難しい。
例えばアイドルグループの嵐は、アイドルがテレビでマスに訴える時代とオタク的なコアファン層を濃縮していく時代の狭間に生まれたからこそ、最大級の広く厚いコンテンツに成り得たように思う。同様に、インターネットでの発信が身近でない時代と、普及したために意識的に接することが難しい時代の狭間の世代に「天国でもあり地獄でもある」「針山の上でいかつい鬼とタコパ」するような世界観が見えているのではないだろうか。
おもちゃ箱をひっくり返したようなサウンドに乗せて歌い上げられる詞は、そこが地獄であることも肯定しながら、それでいてあれもしたいしこれもしたいと希望を謳う。狭間の世代の人間へ、「あのころ」への郷愁が突き刺さる。
既にインターネットが生活に溶け込み、手触りが失われてきた時代に、リリックはどこへ向かうのか。1つの推測は、全てのジャンルで「キャラクターソング化」が進むことだ。好みが多様化し、ファンが好きな物だけを聞くシステムが煮詰まるほど、楽曲の前提の共有は容易になるだろう。そのため、楽曲や歌手への前提知識がなければ成立しない楽曲が増えるのではないか。
もう1つの推測は、逆にどんどん普遍性が高くなるということ。時代の移り変わりが速くなればなるほど、決まった価値観や固有名詞について歌うことは難しくなっていく。長く残る楽曲を生み出そうとすると、結果的に歌手や時代の属性によらないものが求められていくのではないか。
時の流れは戻らない。下の世代には新たな音楽とインターネット経験(それをインターネットとして意識的に触れるかは別として)が生まれていく。「老害」として、狭間の時代の記憶は遠くなる。新しいレギュレーションを上塗りしながらネット社会を生きていかなければならない。それをワクワクする行為として捉えていくことができるのか。
我々には「さんさーら!」がある。ゴールテープの下をすり抜けて、いつまでも続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
