
NASAの公式HP記事『90 Years of Our Changing Views of Earth』をみんなで読もう!
先日NASAの公式HPにこのような記事を発見した。「90 Years of Our Changing Views of Earth」(この90年における我々のアースの見方の変遷)。
リリースは2020年。この4年のあいだ全くこの記事の存在に気づかなかったが、歴史的に重要な画像も多くアップされていてとてもおもしろい記事なので、ここで全文の読み合わせをしてみたいと思う。翻訳はDeepLにさせるが、何か不備があれば注釈を入れようとは思う。ではさっそく始めよう。
まず冒頭の導入部分。
地球が球形であることを示す間接的な証拠は長い間存在していたが、20世紀になるまで写真による証拠はなかった。古代ギリシャ人は地球が丸いと信じており、その円周を驚くほど正確に計算していた。一方、観測者たちは、月食の際に月に湾曲した影を落とすことから、地球が球形であると推測していた。航空機の出現により、写真家は地球の曲率を記録できる高度まで到達できるようになった。観測ロケット、そして宇宙船が、地球からますます遠く離れた場所から写真を撮影するようになり、私たちは地球を、最初は完全な円盤として、次には宇宙の空虚さを背景にした、より小さな青いオアシスとして見ることができるようになった。これらの画像を通して、私たちは地球、ひいては私たち自身の宇宙における位置について、より深い理解を得ることができた。
いきなり『地球が球形であることを示す“間接的”な証拠は長い間存在していたが、20世紀になるまで写真による証拠はなかった。』と、20世紀以前の、そして、写真による証拠以外の証拠はぜんぶ“間接的”であるとすら聞こえる。アリストテレスもコペルニクスも衝撃のイントロである。NASAに言わせれば彼らの提出した見解は間接的な証拠でしかなかったのだ。
次に、以下の写真が紹介され、そのキャプションが添えられている。

1931年5月号の『ナショナル・ジオグラフィック』誌に掲載されたキャプションには、「地球の湾曲を横方向から捉えた史上初の写真」とある。アルゼンチンのビラ・メルセデス上空21,000フィートで撮影されたこの写真には、287マイル離れたアンデス山脈が写っていた。地球が平らであった場合の地平線のはるか下にある。
これが1931年である。なかなかに平和だ。いわゆる現在のフラットアース論で言うところの「沈み込み」であるが、これが史上初だという紹介もおもしろい。なぜなら「沈み込み」は別に上空21,000フィートまで上昇しなくても発生するからである。が、科学業界的に公式的な媒体において、その目的のために撮影された写真としては、たしかに史上初なのかもしれない。だがやはりアリストテレスもコペルニクスも衝撃である。山が先端から見え、船は船底から見えなくなるって俺らだいぶ前から言ってただろと。信じてなかったのかよと。ナショジオくそくらえやと。
さて次はそれに関連した、フラットアーサーには毎度おなじみの様式の図で、さきほどのナショジオ記事に添えられていたものであるようだ。

『ナショナル・ジオグラフィック』誌1931年5月号のキャプションには、「(添付の)写真に示された地球の湾曲を説明する図」とある。この図には、地球の湾曲によってアンデス山脈が予想される地平線の下に見えることが説明されている。
ここは特に興味深いものは無い。そしてこのナショジオ1931年5月号の「沈み込み」写真に関してNASAによるさらに詳しい説明が続いている。
『ナショナル・ジオグラフィック』誌の1931年5月号に掲載された記事によると、南米のアンデス山脈の東側で飛行機から撮影された写真が、地球の湾曲の証拠となった。アメリカ陸軍航空隊の将校で航空写真家のアルバート・W・スティーブンス少佐は、1930年12月30日、アルゼンチンのヴィラ・メルセデス上空を高度21,000フィートで飛行中に撮影した。アンデス山脈は287マイル離れており、飛行機の高度よりも高いが、写真の白い水平線で示された感覚的な地平線の下に横たわっていた。写真に添えられた図で説明されているように、地球の湾曲がこの現象を説明している。地球の曲率は写真の横方向にも見えるが、画像は地球の円周の1/360しかないため、その効果は微妙である。
これを「湾曲の証拠である」と言い切っているのが凄い。しかしNASAが言うのであるから間違いない。これが湾曲の証拠である。アリストテレスもコペルニクスも写真技術のある時代に産まれていたらこれほどの大手柄をどこの馬の骨とも知れないアメリカの軍人なんかに奪われることはなかったであろう。なんで21,000マイルも高度が要る?アルバート・W・スティーブンス少佐?誰やと。
さてトピックは変わり、次に2枚の写真とそのキャプションがまず紹介される。
一枚目。

記録的な気球飛行を行ったエクスプローラーII号で撮影されたサウスダコタ州の写真。
二枚目。

オービル・A・アンダーソン少佐(左)とアルバート・W・スティーブンス少佐。
エクスプローラーII気球ゴンドラの前に立つ。
キャプションによれば右側の人物がアリストテレスとコペルニクスを出し抜いたスティーブンス少佐であろう。たしかに一見精悍ではあるが実質的には特に何も考えてなさそうな軽薄な顔つきではある。こういう奴は現代日本の民間人にもゴロゴロいて、大事なときにはあまり役に立たない傾向が強いことでよく知られている。そして続いて詳細な説明が以下である(どうやらこの記事では、まず写真を見せ、次にその簡単なキャプション、そして最後に詳細な説明がくる、という構造になっているようだ)。
アメリカ陸軍航空隊とナショナル・ジオグラフィック協会の共同プログラムで、スティーブンス少佐はオーヴィル・A・アンダーソン少佐とともに、高高度気球から初めて地球の曲率をはっきりと示す写真を撮影した。1935年11月11日、2人はヘリウムを充填したエクスプローラーII気球に乗ってサウスダコタ州ラピッドシティ近くのストラトボウルから離陸し、当時の世界記録である高度72,395フィートまで上昇した。この写真は対流圏と成層圏の境界と地球の実際の曲率を示し、高高度気球からの長距離偵察の可能性を示した。
とのこと。全く平和である。そんなものはわざわざ気球に乗らなくとも、わりとどこでも、たとえば"地球の丸さがわかる"という触れ込みの和歌山県の潮岬とかででも普通に地面に立って見ることが出来る。潮岬についてはよろしければ拙記事をご覧下さい。
では続き。


サブオービタルロケットによって高度65マイルから宇宙から撮影された最初の地球の画像。
ついに来た。これは地上からは見れない。サブオービタルロケットとは、地球を周回する軌道まで到達する高度と速度には満たないものの、弾道を描いて飛行して数分後に地球に帰還するロケット。
そして詳細な説明が続く。
最初の人工衛星スプートニクが打ち上げられる10年以上前の1946年10月24日、ニューメキシコ州のホワイトサンズ・ミサイル発射場の科学者たちは、捕獲したドイツのV-2弾道ミサイルの上にカメラを設置した。ロケットが高度約65マイル(一般に宇宙空間と認識されている境界線の真上)まで飛ぶと、35ミリ動画カメラは1.5秒ごとにフレームをスナップした。数分後、ミサイルは時速340マイル以上で地上に激突して戻ってきたが、フィルムは生き残り、私たちは初めて宇宙から地球を垣間見ることができた。1959年8月14日、衛星エクスプローラー6号が軌道上から地球を初めて撮影したが、画像は細部に欠けていた。1960年4月1日、気象衛星TIROS-1が、23,000枚に及ぶ地球のテレビ画像のうちの最初の1枚を撮影した。
NASAは不親切なのでキャプションではわかりにくいが、先ほどの2枚の写真の2枚目がおそらく1946年にミサイルに設置されたカメラによるものだと思われる。そして説明の最後部にある気象衛星TIROS-1による1960年の写真が1枚目で、1959年のエクスプローラー6号のものはこの記事ではアップされていない。でもググったらそれらしきものがちゃんとあったのでいちおう下にアップしておく。

まったく最高である。
さて次の写真。

ソビエトの通信衛星モルニヤ1-3号が撮影した地球初の全球写真。

ATS-1衛星が静止軌道から撮影した最初の地球画像。

DODGE(国防総省重力実験衛星)による地球全体の初のカラー画像。
さあここまでくるといよいよである。ついに球体大地の全景写真が登場した。球体だ。もう決まりである。これもうガンギマリで球体である。つづく説明を読もう。
1966年5月30日、ソ連のモルニヤ1-3通信衛星が、画質はやや悪かったが、地球を円盤状に写した最初の写真を撮影した。1966年12月11日、先進技術衛星ATS-1が、エクアドル上空22,300マイルの静止軌道から、地球を写した最初の写真を送り返した。1967年8月、国防総省重力実験(DODGE)衛星が、地球全体の初のカラー画像を送信。
うむ、たしかに初のカラー画像だ。素晴らしい。ちなみにガガーリンが「地球は青かった」と言ったのはこの6年前の1961年のことなので、きっと当時の人々は「たしかに地球は青いけど、雲は白く、大陸はなんか汚い」と思ったことだろう。
では次の写真。

上は1966年にルナー・オービター1号が月軌道から撮影した地球の写真、下はルナー・オービター・イメージ・リカバリー・プロジェクト(LOIRP)が2008年にデジタル化したもの。
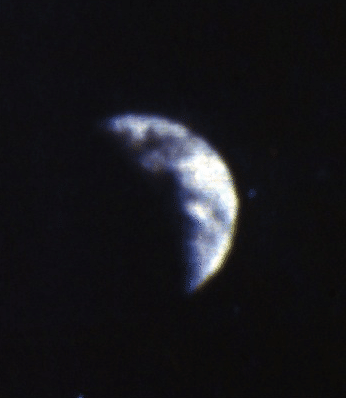
サーベイヤー3号が月の表面から撮影した地球初のカラー画像。
月の表面から撮影した、というのがここはミソであり、なにげに裏テーマでもある。大人は怖いね。
月への初期のロボット宇宙船の主な目的は、その後の有人アポロ・ミッションに備えることであり、軌道上および月表面から月の地形を広範囲にわたって撮影することも含まれていた。1966年8月23日、軌道上から月面の地図を作成するために設計された5機のルナー・オービター宇宙船のうちの1機が、月距離から地球を撮影した最初の写真を撮影した。ルナー・オービター画像復元プロジェクトの一環として2008年に行われたオリジナルのフレームのデジタル復元では、走査線やその他の不完全な部分が取り除かれた。後にアポロ12号の宇宙飛行士が訪れたロボット着陸船サーベイヤー3は、1967年4月30日に月表面から地球を初めて撮影した。
ふむ、ここはあまりおもしろい話が無い。次の写真にいきましょう。

アポロ8号が月周回軌道を初めて周回した際に撮影した有名な「地球の出」の写真。
たしかにこれは有名。

アポロ11号の月面着陸時に撮影された、月面に立つ宇宙飛行士が初めて撮影した地球の写真。
わざわざ着陸船も入れてあるのがたまらないショット。

アポロ17号の宇宙飛行士が月へ向かう途中で撮影したブルーマーブルの画像。
月へ向かうアポロ17号の宇宙飛行士が撮影した画像。
はいきたー!我らがザ・ブルーマーブル!ちなみにこの写真はトリミングやアングル変更や色相の調整は行っているものの合成ナシの1発撮りとのことだそうで、ググるとちゃんとオリジナルのものが出てくる。「AS17-148-22727」という通しナンバーで知られている。これだ。

最高だ。ではつづく説明文を読もう。
1960年代後半から1970年代前半にかけてのアポロ計画からは、人類初の異世界探査を写した、何千枚もの衝撃的で記憶に残る写真がもたらされた。その中には、宇宙飛行士が撮影した地球の写真も含まれており、宇宙の漆黒の闇と広大さを背景に、私たちの惑星がいかに小さく儚く見えるかを物語っている。最も有名なのは、アポロ8号で撮影された地球の日の出の写真だろう。ボロボロになった灰色の月の地形に、滑らかな青い地球の球が宙に浮いているように見えるこの写真は、当時のエコロジー運動にインスピレーションを与えた。人類初の月面着陸ミッションであるアポロ11号では、ニール・A・アームストロングとエドウィン・E・"バズ"・オルドリンが月面に降り立った象徴的な写真が数多く撮影された。アポロ最後の月面着陸ミッションであるアポロ17号の宇宙飛行士は、月へ向かう途中、72,000マイル離れた場所から地球の有名なブルーマーブル画像を撮影した。
こう見ていくとこの時期はNASAの絶頂期なのである。この時期の名作品群はリリースから50年を過ぎた現在でも眩しい光を放ち続け、マスターピースとして人々に影響を与え続けている。素晴らしい。
では次の写真。

マリナー10号が金星と水星に接近する際に撮影した地球と月の画像を合成したもの。
合成?一般的に言ってもだいぶどうでもいい写真である。

木星と土星を探査する旅に出発したボイジャー1号が撮影した、地球-月系の最初の画像。
なるほど、このコーナーは太陽系の惑星への旅がメインテーマなのであろう。どうでもいいとか言ってごめんNASAい。

惑星探査機ガリレオが、重力アシストのために母星との再会を果たした際に撮影した最初の地球の画像。
うむ、やはり丸い。そして青くて白い。どうでもいいけど説明を読もう。
1970年代に入ると、惑星探査機の性能が向上し、長い探査の旅に出る際にカメラを地球に向けるものも出てきた。1973年11月、マリナー10号が金星と水星を探査するミッションに出発して数日後、地球と月を別々に撮影した。1977年9月18日、木星探査機ボイジャー1号は725万マイルの距離で、地球-月系を1枚のフレームに収めた最初の写真を撮影した。打ち上げから2年以上経った1990年12月8日、探査機ガリレオは、木星に接近するために地球の重力を利用して、地球から600マイル以内を通過した。フライバイの間、ガリレオはその洗練された機器とカメラを使って、地球をあたかも未踏の惑星のように調査し、生命体の活動に関連する大気中の微量元素の化学的サインを検出した。
最後の一枚は1990年である。わりと新しい。さてここまでだいぶ長くなってきてNASAの絶頂期も過ぎてしまったが、あともう少しなので頑張りましょう。では次の写真いきますね。ファイト!

ボイジャー1号が地球から37億マイル離れた地点で撮影した、6つの惑星の家族写真。
なんだこれは。これが家族写真(ファミリーポートレイト)だと?NASAの絶頂期はやはり終わったのか。

ボイジャー1号が撮影した地球の画像をNASAがリマスターした「ペイル・ブルー・ドット・リヴィジテッド」。
もはや混迷期または暗黒期である。だがしかしどんなにかつて隆盛を誇ったバンドにも必ずそんな時期は訪れる。そこを越えてさらに作品を残せるかが本当の勝負である。意味がわからないので説明文を読もう。
1990年2月14日、地球からの旅が始まってから12年以上が経過し、電力節約のためにカメラの電源が永久に切られる直前、ボイジャー1号は回転しながらカメラを太陽系に向けた。60枚のモザイク画像には、37億マイル以上離れた地球と呼ばれる青白い点を含む、太陽系の6つの惑星の「家族の肖像」が写っていた。2020年2月、この写真の30周年を記念して、NASAは地球の画像のリマスター版を『Pale Blue Dot Revisited』として発表した。
なるほど、そういういきさつがあったのである。ちなみにリマスターされる前のオリジナルの『Pale Blue Dot』はこちらである。

リマスター要る?
コロナ茶番中だというのに余計な仕事に無駄な経費を使うぐらいなら解散したほうがマシではないのか。
では次の写真。

火星を周回する探査機マーズ・グローバル・サーベイヤーが撮影した地球と月。
はい?
これ前に似たようなのやってなかった?

火星探査機スピリットが火星表面から撮影した地球。
もうダメだ。NASAは終わった。

火星探査機キュリオシティが撮影した地球と月。
本当に終わりだ。こんな作品で観衆に説得力を持ち得ると思ったら大間違いである。もう彼らはあの1972年(ザ・ブルー・マーブルの年だ)のスピリットを失ってしまった。
いちおう説明を読んでおこう。
未来の火星探検家にとって地球はどのように見えるのだろうかと考えたことがあるなら、火星の周回軌道上や地表にある複数の探査機から送られてきた画像を見れば、その見当がつくだろう。探査機マーズ・グローバル・サーベイヤーは、火星を周回する軌道から、8600万マイルの距離から地球-月系の写真を初めて撮影した。地球と月は火星よりも太陽に近いため、地球から見た金星や水星と同じように満ち欠けを見せる。 2003年5月8日に撮影された画像は、地球と月がほぼ4分の1の位相にあることを示している。火星探査機スピリットは2004年3月11日、火星表面から地球を初めて撮影した。2014年1月31日、火星探査機キュリオシティが9,900万マイルの距離から撮影した画像は、地球と月が別々の物体であることを示している(筆者註:"地球と月が別々の物体として見えている。"のほうがおそらく正しい)。
どうでもいい。
さあいよいよ最後の写真だ。この写真を紹介して記事は終わっている。最後に僕のひとこと感想を書いて本note記事も終わるので、あと少し耐えてください。

土星を周回する探査機カッシーニから見た地球-月系。
なんだこれは。
説明。
2013年7月19日、土星を周回する探査機カッシーニは、土星が日食する様子を約75万マイルの距離から撮影した。「地球が微笑んだ日」と名付けられたこのイベントで、地球上の人々はカッシーニが撮影することを事前に知らされ、カメラに向かって微笑むよう促された。写真には、地球と月に加え、金星、火星、そして7つの土星の衛星が写っている。
また家族写真だ。これはもはや完全にネタ切れなのである。「地球上の人々はカッシーニが撮影することを事前に知らされ、カメラに向かって微笑むよう促された。」とあるが、そういう巨大なイベントによって作品の物語に彩りを添えるのがもはや関の山である。さて、この記事の最後のまとめの文章を読もう。読んでこのくだらない景色(view)とおさらばしよう。
過去90年間に撮影された地球の写真が、私たちの母なる惑星、そして宇宙における私たち自身の位置に対する見方をどのように変えてきたか、このレビューを楽しんでいただけたなら幸いである。未来の宇宙探検家たちは、その目的地がどこであろうと、常に振り返り、どんな空であろうと母星を見つけようとするだろう。
くだらない。
さていかがだっただろうか?僕は月面着陸以前の初期のモノクロの写真群を楽しんだ。それらのうちのいくつかは以前に見たことはあったものの、その出自については知らなかったので、こうして公式筋からの情報があると嬉しいし、念のためにこうして手元に残しておくことは後できっと何かの役に立つ。そしてこれはNASAの公式HPのものなので、ソ連もアメリカもなく(だって国家制度は虚構だからさ)球体大地写真の公式ベスト盤(1931−2020)と見ていいのではないか。そのベスト盤が2020年にリリースされたというのは、実に、音楽バンドと同じで、その区切りや転換を予期させるという点では興味深くもあるし、どうでもいいといえばかなりどうでもいい。早く解散しろ。思い返せば僕自身の考え方や価値観も2020年を境に思わぬ転換を否応なく果たした。そこからの眺め(view)は、以前より醜く以前より美しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
