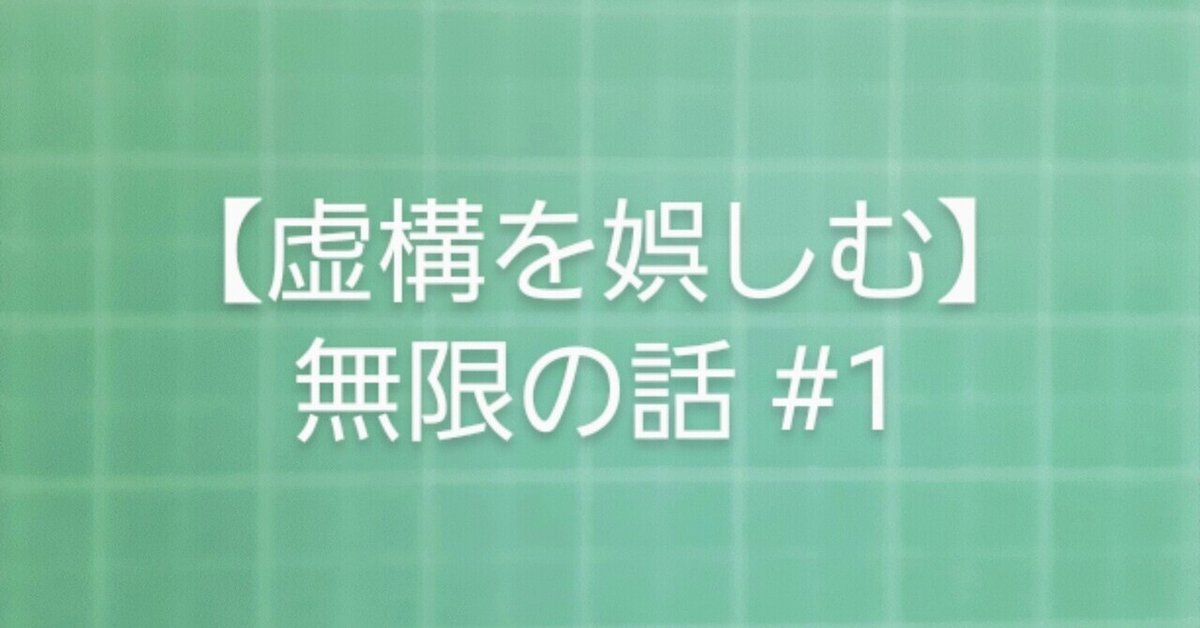
有理数の濃度は錯覚か?
無限集合の濃度についての私説です。
◆
はじめに
有限集合の大きさを表すときは要素の個数を示せば良いのですが、無限集合の大きさを表すときには、濃度という概念を用います。
また、無限集合の基本である「全ての自然数の集合」の濃度を、可算無限といいます。
「全ての奇数の集合」「全ての整数の集合」「全ての平方数の集合」など、多くの無限集合の濃度は、その要素と自然数を1対1対応させられますから、可算無限ということになります。
無限集合の大きさを比較するためには「1対1対応できるかどうか」が判定の基準になるんですね。
今回のテーマ「全ての有理数の集合」の濃度も、やはり可算無限・・・。
どの資料にもそう書いてあります。
しかし、本当に正しいのでしょうか?
◆
「蛇」の証明①
有理数全体と自然数全体を、1対1対応させる有名な証明があります。
「カントールの蛇」とか、「有理数の可付番性に関するカントールの対角線論法」とか呼ばれているものです。
カントールの「対角線論法」は2種類あるので、この記事では混同を避けるために「蛇」の方でいきますね。
◆
まず、有限×有限の平方格子から。
縦5×横5の表で考えましょう。
左上が(1,1)、右上が(5,1)、左下が(1,5)、右下が(5,5)です。
□
「蛇」は格子表左上の(1,1)から始めて(1,1)(2,1)(1,2)(1,3)(2,2)(3,1)(4,1)(3,2)(2,3)(1,4)(1,5)(2,4)(3,3)(4,2)(5,1)(5,2)(4,3)(3,4)(2,5)(3,5)(4,4)(5,3)(5,4)(4,5)(5,5)と、右下まで進んでいきます。
□
全ての点を一筆書き出来ました。
「蛇」は線の上に格子点が乗っている図形ですから、「線の上の格子点」と「面の上の格子点」を1対1対応させたわけですね。
従って、「1×25」と「5×5」の集合の大きさは同じであると言えます。
(個数の比較ではないのがポイント)
◆
「蛇」の証明②
では、同様の操作を無限×無限で行うとどうなるのでしょう。
「蛇」は(1,1)から先ほどと同じようにウネウネと進んで、(1,4)(1,5)(2,4)・・・(5,1)まで来ます。
しかし今回は「無限」なので、5の先に5より大きい数が存在します。
従って(5,1)の次は(5,2)・・・(2,5)でなく(6,1)(5,2)・・・(2,5)(1,6)。
(1,6)の次は(2,6)・・・(6,2)と進むのではなく(1,7)(2,6)・・・(6,2)(7,1)。
□
気付きましたか。
格子表自体は5×5、6×6、7×7、・・・と大きくなっていくのに、「蛇」の方は右上と左下を結ぶ対角線上を行ったり来たりするだけ。
5×5なら(5,1)と(1,5)を結ぶ対角線。
6×6なら(6,1)と(1,6)を結ぶ対角線。
7×7なら(7,1)と(1,7)を結ぶ対角線。
対角線は次々と更新されていくので、「蛇」はそれ以上先へ進めません。
□
有限×有限なら右下まで行けるのに、無限×無限になると、格子表の右下の部分、全体の約半分に当たる三角形の領域へ入れなくなってしまうのです。
「蛇」が入れないということは、その格子点は数えられないという意味。
「時間さえかければ、いつかは数えることができる」のではありません。
「数え始め自体が不可能」なのです。
これでは、どうやっても1対1対応にはなりませんよね。
つまり、
「無限×無限の平方格子点の集合」は「蛇」上の格子点の集合(可算無限)より大きいことが示されたのです。
「大きさの違う無限集合が実在する」という画期的な数学的事実の証明。
まさに快挙そのもの。
◆
有理数の濃度
さらにカントールは「平方格子点」を「有理数」に置き換えることで、問題を「有理数の濃度と自然数の濃度」の比較へと発展させました。
(2,3)なら2/3、(1,4)なら1/4、(3,5)なら3/5・・・という要領。
有理数の網に「蛇」を這わせていくというイメージです。
(無限集合ですから約分による要素の減少は無視して構いません)
□
この素晴らしいアイデアにより、
「平方格子点の濃度は「蛇」の格子点の濃度より大きいのだから、有理数の濃度も可算無限より大きい」との結論に到達。
・・・の、はずだったのですが。
カントールは無限×無限の場合でも「蛇」が平方格子点を数え尽くせる、すなわち「有理数の濃度も可算無限と同じ」と考えてしまいました(!)
・・・なんで?
おそらく、最初に触れた有限×有限の格子表の結果に引きずられた錯覚だと思うのですが。
(ちなみに、無限×有限の格子表は「蛇」で数え尽くせる可算無限です)
・・・「真逆」じゃマズいでしょ。
◆
その後
錯覚かどうかはともかく、カントールは「有理数の濃度は可算無限である」と結論しました。
これが集合論とカントール自身を長く苦しめる元凶となったのです。
当時の数学界には、宗教上の理由から集合論を批難する人はいたのですが、論理的に疑義を呈する人は残念ながらいなかったようで・・・。
というか、カントールを擁護する側の人々も、煽られて感情的になっていたフシがあります。(個人的見解)
まあ、どんな学問も結局は人間の営みですからね。
数学だって同じこと。
・・・しかし、影響が大き過ぎました。
基礎工事で致命的なミスがあったのにそのまま超高層ビルを建ててしまったようなもの。
上層階で不具合が起きるんですね。
◆
濃度差の要因
話を戻します。
あらためて考えてみると、平方格子表では「蛇」が(1,1)にいるときは(2,1)と(1,2)、(5,1)に進んだ時点では(6,1)と(5,2)、(6,1)から(5,2)に進んだ時点では(7,1)と(4,3)・・・のように、未踏査点が常に2個存在しています。
□
「蛇」は、1回の操作では1方向にしか進めませんから、2か所の未踏査点を同時に埋めることは不可能。
それには「蛇」が最低2匹必要です。
・・・1対1対応にはなりませんね。
ちなみに、「蛇」の証明には一筆書きのルートが異なるアレンジバージョンがいくつかあるのですが、未踏査点の個数を見れば本質はどれも同じ。
結局、未踏査点の個数が濃度差の要因だったというわけです。
◆
高次元
直線上の格子点より、平方格子の方が濃度が大きいことは分かりました。
同様に、「縦×横×高さ」の立方格子は未踏査点が3個ですから、平方格子を数え尽くすことのできる2匹の「蛇」であっても、1対1対応はできません。
従って、立方格子の濃度は平方格子の濃度よりも大きくなります。
空間軸が4本の4次元格子なら未踏査点が4個なので、立方格子より大きく。
5次元以上の格子点なら4次元格子より更に大きな濃度になります。
無限集合の濃度に上限はないのです。
(補足:今回は格子点の話ですから、離散数の集合の大小のみになります)
◆
独立した属性
もう少し一般化しましょう。
別に「空間軸」でなくても、独立した属性が複数あれば、無限集合の濃度はそれに準じて大きくなります。
たとえば「無限饅頭」という和菓子の「色」のバリエーションが、可算無限種類あるとして。
この饅頭に「色」を追加しても濃度は可算無限のままですが、「形」などの別の独立した無限属性を追加するなら饅頭の集合の濃度は上がります。
横に無限の「色」、縦に無限の「形」を並べれば、平方格子ですからね。
従って、「色」「形」の2属性の無限から成る饅頭の集合の濃度は平方格子の無限の濃度と同じと分かります。
同様に、「色」「形」「味」の3属性なら立方格子の無限の濃度と同じ・・・
何やら妙な話になってしまいましたがつまりは独立した属性の数が重要だと言いたかったんですよ。
今回のテーマは有理数の濃度。
「有理数の集合」も「分母の整数」と「分子の整数」という独立した2つの属性から成るのですから、平方格子と同じ濃度になるのも必然だったというわけですね。
・・・めでたしめでたし。
(分母・分子ともに0以外。念の為)
◆
表記法
無限集合の濃度の表記法ですが。
平方格子の要素の個数は1, 4, 9, ・・・n²,・・・と増えていきます。
ならば、その先は∞²と書くべきかと。
空間軸は2本、未踏査点も2個ですし。
立方格子の要素の個数は1, 8, 27, ・・・n³,・・・と増えていきます。
ならば、その先は∞³と書くべきかと。
空間軸は3本、未踏査点も3個ですし。
そんなわけで、今後の私の記事では「独立した複数の属性から成る離散数の無限集合の濃度」について、
「直線上の格子点の濃度」を∞¹、
「平方格子上の格子点の濃度」を∞²、「立方格子上の格子点の濃度」を∞³、
・・・のように表記することにします。
◆
おわりに
「独立したn種類の無限属性から成る無限集合の濃度」を、「∞のn乗」と表記したいのだけど「∞^n」くらいしか記号がないんですよ(泣)
要するに、
スカラーなら∞×∞=∞
ベクトルなら∞¹×∞¹=∞²
というような話なんですが・・・。
あ、ちょっと先走りました。
今回はここまで。
◆
「無限の話」考察の概要
①有理数の濃度は錯覚か?
②「無限」の代数的定義と演算規則
③「0.999・・・=1」再考
④図形への応用と「切断」
⑤「連続体仮説」は真(本質部分が)
⑥微積分への応用
⑦雪片曲線の濃度(フラクタル次元)
⑧バナッハ・タルスキのパラドックス
⑨方程式の濃度・解の濃度
⑩5次方程式の「不可解性」
⑪「不完全性定理」の一般化
◆
参考資料
イアン・スチュアート著、川辺治之訳「無限」(岩波書店、2018)
アミール・D・アクゼル著、青木薫訳「「無限」に魅入られた天才数学者たち」(早川書房、2015)
ジョセフ・メイザー著、松浦俊輔訳「数学記号の誕生」(河出書房新社、2014)
Newton2020年12月号「ゼロと微分積分」(ニュートンプレス、2020)
他多数
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
