
現代建築家宣言 Contemporary Architects Manifesto【9】〈境域〉の只中を航海せよ ―暴力、群衆、アイデンティティを超えて
著者・若林拓哉
―現代建築家は、〈境域〉によって逃走する人間に〈闘技〉の場を拓く。
〈現代建築家〉は、〈贈与〉の連帯によって他者と正の連鎖を生むことを希求するものである。そこでは〈歓待〉の精神こそが不可欠となる。一方で、私たちの社会は常に敵対性と隣り合わせにある。この他者との闘争を
前提として、その事実に立ち向かわなければならない。そこで第八回の終わりに現代的な問いのキーワードの一つとして〈境域parages〉を提示して幕を閉じた。まずこの意味内容に立ち入る前に、前回の終盤で少しだけ言及した〈共生主義〉について述べたい。
改めて〈共生主義convivialisme〉とは、哲学者イヴァン・イリイチの提唱した概念に端を発する思想であり、その意味するところは「人と人とのつながりや協力を大切にして、他者への思いやりと、自然への配慮を忘れない暮らし方❖1」である。そしてそれは、個々の異論を認めるが、それが嵩じて殺し合いになることがないよう、危機回避の回路を想定することに重きを置いている❖2。それはなぜか? フランスで二〇一三年に出版された『共生主義宣言』には次のように書かれている。「争いはあらゆる社会につきものだからである。個と個、集団と集団の間に対立が生まれない社会を創ろうというのは幻想である。それどころか、有害でさえある。利害と見解の違いは、たとえば、親と子、長男と末っ子、男と女、最富裕層と最下層、最高の権力者と無力の民、幸運な人と不運な人などの間に、いくらでもあるからだ❖3」。冒頭の〈共生主義〉の意味するものは素晴らしい志であることに間違いないが、それだけでは耳に心地良い理想主義的思想だと受け取られかねない。だが、〈共生主義〉の思想はこの対立構造、闘争性を前提とした議論であることに価値がある。
対立を排除する社会の創造を希求することは幻想であり、むしろ有害でさえある
とするのは、人間の本性から目を背けることになるためである。まずこの前提を共有したうえで、現代における敵対性の諸問題を概観しよう。
現代社会において、ポリティカル・コレクトネスとしては、人種やジェンダー、性的指向、宗教、貧困、移民などの諸問題に対するリベラルな態度が求められる傾向にある。特に建築家という、多様な個人的性質を有する人々を相手にする職能であれば尚更であろう。しかしながら、このリベラルな態度を深堀りしていくと、難しい問題に直面せざるを得ない。というのも、現代社会はかつてなくこのリベラル思想の根幹が揺らいでいるからだ。米国のトランプ大統領の出現はもちろん、英国のEU離脱、コロナ禍における非民主主義国家の国家主導による対応力など、多文化主義や移民問題、個人の権利的自由などの観点において、反リベラル思考に対する支持とその価値が浮上してきているのである。現代社会は、異なる価値観を受け入れる立場から、敵対し排除する立場へと移行しつつあるように受け取られる。リベラリズムの原則は、人権保障の観点から人民の意思決定に介入しようとし、それまでの共同体に所属していなかった移民や外国人に対しても配慮することを要請する。これに対して非リベラルな民主主義は苛立ち、「誰が国民に相応しいか」や「生粋の国民とは」という、新たな争点を呼び込むようになっている❖4。これらにおける争点に至っては、近代社会における「左翼vs右翼」や「保守vs左派」といった分かりやすい二項対立の軸がもはや消失し、その軸は細分化され、階級や階層は「クラスター化」され、そこに属する個人の嗜好や個人的性質に応じて、
場と文脈によって反撥したり結合したり、常にその共同性を変化させていく
ようになっている❖5。ではなぜこのような状況が生まれているのだろうか。
そもそも、いま現代社会において理解されているリベラリズムの歴史は浅い。それは紆余曲折を経て、二〇世紀後半に西洋において立ち現れた「リベラル・デモクラシー」の思想に根ざしている。この「リベラル・デモクラシー」とは、「代議制民主主義を基本に、個人の権利や権力分立を保障したうえで、民意を国政に反映させる仕組み❖6」のことだ。まさに現代日本もこの形で国家が成立している。しかしながら、このリベラリズムとデモクラシーは、一見矛盾しているようにも思われる。なぜなら、リベラリズム=個人の自由であり、デモクラシー=個人間の平等だからだ。通常であれば両立するものではない。だが、考えるべきはその先にある。非常に大まかに流れを説明すれば、近世社会までは、経済的リベラリズムから成り立つブルジョワ階級と彼らの権力が実権を握っていた。つまり資本の格差が著しい状態が続いていたわけだ。それに対抗して生まれたのがファシズムや社会主義といっ
た思想であり、人民主義的民主主義が台頭する。しかしその思想もまた、個人間の平等という題目のもとに抑圧的で強制的な社会を築いてしまう。両者とも戦前〜戦後を経て、負の側面が露呈したため、その折り合いをつける形で、社民的政策❖7を前提として、各国が政治的リベラリズムとデモクラシーを結合させるようになった。重要なのは、リベラリズムには経済的リベラリズムと政治的リベラリズムが存在することである。そして、昨今の新自由主義的動向は、この経済・政治的リベラリズムが一体化する形で出現している。そこでは本来、相互に負の側面を補完し合う形で生まれた「リベラル・デモクラシー」は、すでに自己抑制を失ってしまっている。なぜそうなってしまったのだろうか? おそらく率直に、国家が、国民が、それを望まなくなったからではないか。常に
社会は経済格差・権力闘争・不平等とともにあった。
ゆえに「リベラル・デモクラシー」の安定も長くは続かなかった。否、資本主義の長い歴史から見れば、戦後の「リベラル・デモクラシー」が例外だったと言うしかない。その闘争の思考をさらに掘り下げていかねばならない。
なぜ人間は平和ではなく闘争を、差別を、不平等を望むのか? なぜそれを前提としなければならないのか? 哲学者・今村仁司は次のように語る。
人間は闘争する。闘争は偶然的な現象ではなく、一時的な現象でもない。闘争する人間を生み出す理由が存在する。(…)それは、(…)虚栄心である❖8。
今村は虚栄心こそが、人間を闘争へ、ひいては暴力へと誘い込む原動力であるとしている。では虚栄心はなぜ生まれるのか? 仮に人間が一人で存在しているのであれば、社会もなければ暴力も存在し得ない。翻って、人間が社会的存在であるからこそ、換言すれば
複数の他者と共存するからこそ、暴力が存在する
のである❖9。人間は社会的存在であるとき、自己の優位性を自己内で確信すること、そして他者からの承認を欲望する。この二重の確認によって満足することを本能的に欲している❖10。人間は自然的性質として、それが真実であるか虚偽であるかにかかわりなく、他者に優越することを希求する存在なのである。それは共同体においても同様だ。人間が集まってまとまりをつくるとき、ほかの共同体との差異性の強調とその維持によって、自己同一性を保ち、独立性と自律性を担保する❖11。そしてそこには必ず君主の存在がある。仮に君主が存在しない集団があるとすれば、それはただの「群れ」に過ぎない。秩序の中心として場所をもち、そこに君主を据えることで、政治性が生まれ、ヒエラルキーもまた生じるようになるのだ❖12。この人間の本能的な敵対性・暴力性を前提とするならば、他者に打ち勝つ欲望である虚栄心や傲慢さは普遍的に存在することになる。そしてこれから先、それらが存在しなくなる保証はどこにもない。だからこそ、それを前提に思考しなければならないのである。そして、虚栄心の充足が不十分であるとき、他者への猜疑心もまた生じる。この
虚栄心と猜疑心は、人間の根底にある自然的法則
であろう❖13。それゆえ、よほどの必要に迫られない限り、人間は本能的に協調や安定を望まないはずである。哲学者・東浩紀は言う。
人間は人間が好きではない。人間は社会をつくりたくない。にもかかわらず人間は現実には社会をつくる。言い換えれば、公共性などだれももちたくないのだが、にもかかわらず公共性をもつ。ぼくには、この逆説は、すべての人類学の根底にあるべき、決定的に重要な認識のように思われる ❖14。
人間は自己愛と、そこから生まれる虚栄心、猜疑心によって駆動している。果たしてこれは考え過ぎなのだろうか? 個々人がじっくり自分の胸に手を当ててみないとその実は分からないが、少なくとも全く心当たりのない人間はそうそういないのは確かではないか。本能的には敵対性を求め、理性によって協調を求めているのではないだろうか。
そして、このように他者を蹴落とし、のし上がろうと情動的に生きる人間たちを〈群衆〉と呼ぶ。それは階級、階層を問わず、上位たろうとする欲望をもつ者はすべからく〈群衆〉である。他人の上に立ちたい、他人よりも高い位置に立ちたいという社会的欲望は、平民の間でも、貴族の間でも、平民と貴族の間でも、つまり同等者間と非同等者間を問わずあらゆるレベルに共通であり、そこに闘争が生じる。人間は社会的存在であるかぎり、誰でも〈群衆的〉なのである❖15。この群衆的欲望は、制御しないと「国家」の秩序を脅かす。それは内乱の危険性を孕んでいるからだ。よって、社会的欲望の観点からすれば「国家」の存在は〈群衆〉の関数であるとさえ言える❖16。裏を返せば「国家」とは、共同体の自律性を解体するものだ。なぜならば、これら〈群衆〉によって成立する共同体同士を、同一の規律の中に当てはめ、抑制するためである。その点で、哲学者ピエール・クラストルが未開社会を指して述べた「国家に抗する社会」は示唆的である❖17。人間の情動を抑えるには、それより強い情動で抑え込むしかない。その一つが恐怖である。そしてその恐怖を制度化したものが法律である。「国家」とは、第一に法律に基づいて自己保存する社会なのである❖18。そして、その共同体内でもまた〈群衆的〉な欲望が常に蠢いている。〈群衆〉は、「国家」における君主との関係では階層下に位置づけられることに甘んじるが、同等の人間たちとの間にも〈群衆的〉心理を発動させる。つまり、一般に人間は政治的・経済的リベラリズムによる対等を要求しながら、一方で格差を要求するのである。そして、常に共同体内に最下層の人間群を発生させることを欲望している。人間の社会的欲望とは、差別化欲望である。すると、同等者内から差別される犠牲者が再生産され続けるのである❖19。同等者内の差別化欲望の力学もまた普遍的であるが、例えばいじめられる側やマイノリティ側に全く責任がないかと言えば、そんなことはない。階級・階層的構造や社会的構造によって強制的に差別を強いられている場合を別として、彼らは本質的に敵対者と同等の闘争可能性を有していると言えよう。そこに立ち向かうか、その地位に甘んじるか、そこで明暗が分かれる。
この他者との終わらない差異化・差別化によって、最終的に新自由主義的な自己責任論が展開されるようになる。そして共同体内の紐帯が細分化されることで、自己が寄って立つアイデンティティもまた揺らいでいくことになる。批評家マーク・フィッシャーは、資本主義に代わるオルタナティヴな社会を想像することができない現在の閉塞した社会状況を〈資本主義リアリズム〉と呼んだが、現代社会では鬱病や精神病は自己責任に帰着され、さらにメランコリーを深刻化させる❖20。現代の経済的リベラリズムの再興は、高学歴で高所得の新たなエリートを生む一方、政治的リベラリズムは移民や女性などの権利を増進する。そのなかで、旧中間層は経済的にはもちろん、政治的にも社会的にも相対的な剥奪感に苛まれ、自分たちを「新たなマイノリティ」とみなすようになっている、と社会学者ジャスティン・ゲストは言う❖21。これは欧米白人労働者を対象とした見解であるが、現代日本においても少なからずこの傾向が見受けられるのではないだろうか。現代社会は富裕層5%︱中間層75%︱下層20%に分断されており、富裕層は経済的恩恵を、低賃金・不安定雇用の下層は国家の庇護を受ける一方で、中間層は経済状況、社会的支援ともに最も脆弱で不安定な存在となっているという指摘もある❖22。現実問題として、最も母数の多いこの中間層が「リベラル・デモクラシー」に愛想を尽かしはじめている。昨今の不安定な情勢の中で、この中間層は意識的にも無意識的にも、経済的・文化的状況などに応じて、いつでも社会的マイノリティに転落する恐怖心を抱きかねない状況下にある。にもかかわらず、たとえば移民に労働力を奪われると発言すればレイシストに、グローバルな国際競争を非難すれば怠惰だと咎められる。中間層への抑圧に対する矛先は八方塞がりなのではないだろうか。そうすると、人間はどうなるか? 疎外感を強め、暴力性の度合いを増すのである。文化人類学者アルジュン・アパドゥライは、マジョリティがマイノリティに転じる恐怖に怯え、近接する他の社会的アイデンティティを抹殺して自己のマジョリティの地位にしがみつこうとする意識を〈捕食性アイデンティティ〉と定義した❖23。これはまさしく〈群衆〉心理の裏返しである。また、法学者キャス・サンスティーンは、集団的利益ではなくアイデンティティをシェアしている組織や集団ほど、敵意を煽ったり、他集団と分かり合おうとしたりしない「集団極化」が起こりやすいとしている❖24。人々がポリティカル・コレクトネスやアイデンティティ・ポリティクスを指向すればするほど、加速度的に連帯ではなく分裂を、つながりではなく切断を生み出すことになるのだ❖25。
ポリティカル・コレクトネス派の中心的意見は、個別のアイデンティティ(人種、ジェンダー、性的指向、階級構造など)をただ考慮するだけでは個々人の置かれた場を理解することは不可能であり、それらのうち幾通りかのアイデンティティが集まった「交点」についての分析こそがより重要とし、そこから立ち現れる立体的な像に対する思考を要請する。これを〈交差性intersectionality〉という❖26。この視点は非常に重要であるが、それだけに重きを置くことの危うさもある。それは、個人のアイデンティティを「抑圧」によってどの程度説明できるのか、ということだ。例えば、「黒人への差別が黒人を作る」「ユダヤ人を作り出すのは反ユダヤ主義」と言われることがあるように、アイデンティティは他者からの目線によって培われる❖27。現代社会のリベラル派が重視するのは「抑圧」に基づいたアイデンティティであるが、一方でそれをベースに個人をみること自体が還元主義的思考ではないか。そもそも「抑圧」が個人の成り立ちを下支えするのであれば、その個人の人生すべてが必然的に「抑圧」によって規定されることになってしまう❖28。果たして、これは真にアイデンティティと言えるのだろうか?
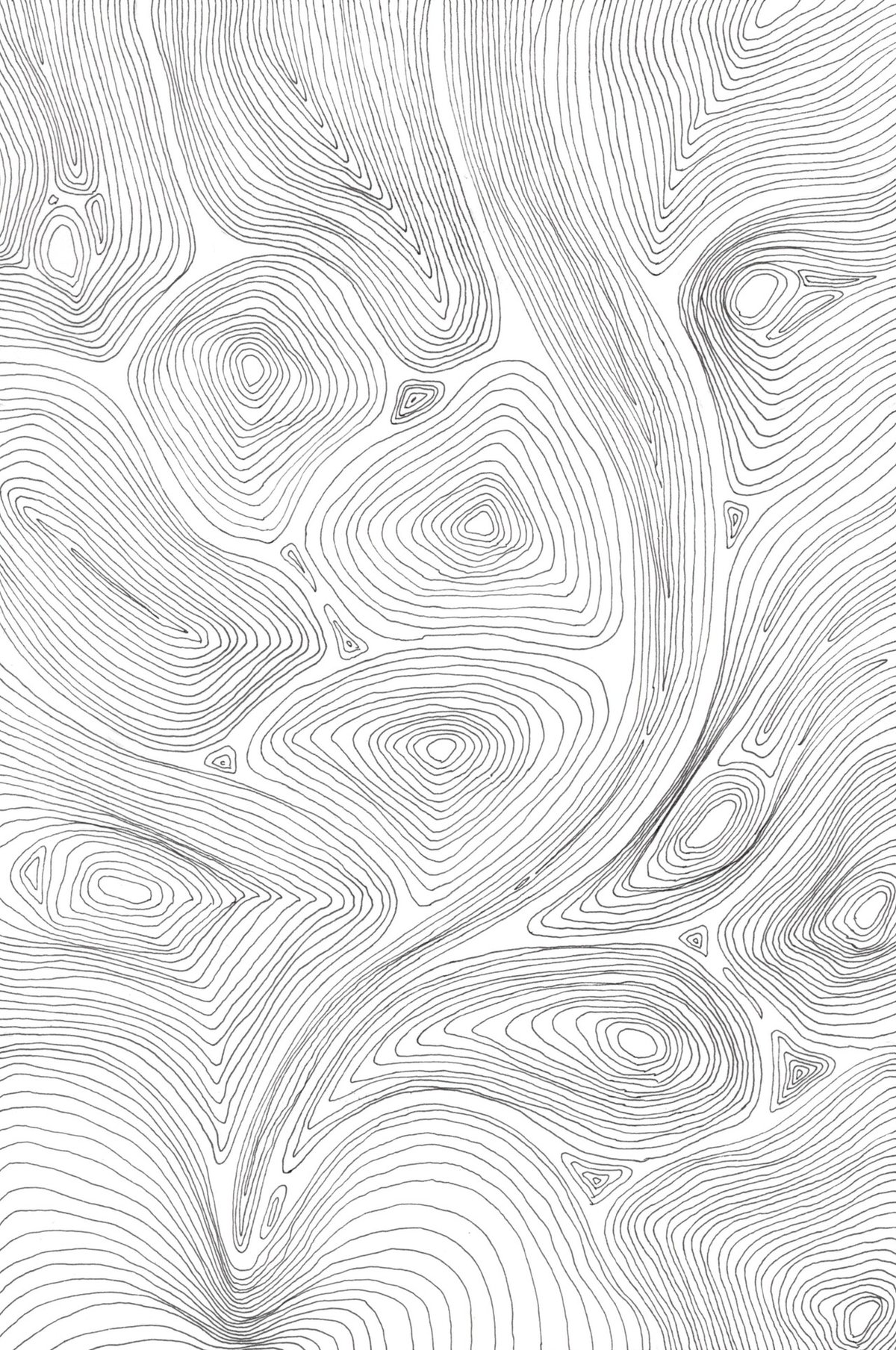
「〈境域〉を漂う」 絵:若林拓哉
ここで冒頭のステートメントを呼び起こそう。〝現代建築家は、〈境域〉によって逃走する人間に〈闘技〉の場を拓く〞。人間は闘争する存在であり、それを下支えする虚栄心・猜疑心が自然的法則であると前述したが、これを野放図にしておいた結果が、昨今の新自由主義的な経済的・政治的リベラリズムの台頭およびアイデンティティ・ポリティクスとその反転である〈捕食性アイデンティティ〉による際限なき暴力性である。だが現代社会の人々の闘争は、ただ本質から目を逸らし続けているだけではないだろうか。
ここから抜け出す道を探さなくてはならない。
そこで提示するのが〈境域〉の概念である。これは哲学者ジャック・デリダが用いたものであるが、辞書的な意味合いとしては「海域」のことを指し、陸についても「一定の広がりを持つ領域」として用いられる❖29。古典的な意味としては「船が航海できる海の領域」を指す漠然とした境界の曖昧な広がりであるとともに、その語源はスペイン語のparar (停止する)を経
由してラテン語のparareから来ている。そこには現前しない不可視の境界があり、それに触れると船は座礁するか、難破して身動きが取れなくなり停止
せざるをえない状況を生み出す、という意味も含意されている❖30。
それらをもとに、〈境域〉を「個/集団の現出しない不可視の境界上あるいはあいだに広がる、一時停止を余儀なくする万物共通の領域」と定義しよう。「リベラル・デモクラシー」の時代と比べ、現代社会は個人/共同体が極めて細分化されているが、それらは不可視の境界線を有し、常に他の境界線を破壊し、飲み込もうとしていると言えよう。それこそが〈群衆的〉心理であり、〈捕食性アイデンティティ〉である。そうではなく、衝突した時点でいちど停止し、状況を俯瞰するための象徴的空間をつくり出さねばならない。情動はそれを超える情動でしか抑え込めないことはすでに述べたが、そのための道を考える必要がある。一つは倫理的行動による要請がある。社会的存在である人間は情動的に動くが、それを外部からの恐怖=法律によって抑制するのではなく、個々人が理性的に行動することを最善とすることだ❖31。だが、すでにそのような倫理的判断が空中分解し、リベラル思考が破綻しつつある現代において、その啓蒙思想がどれほどの効力を持つかは定かではない。そうではなく、闘争性を生かす道を見出すことができないか。
そこで取りあげるのが、政治学者シャンタル・ムフが提唱した〈闘技〉的民主主義である。この〈闘技〉とは、対立する個人/共同体が、その対立に合理的な解決をもたらすことなど不可能と知りつつも、対立者の正当性を承認しあう関係性のことであり、そこでは彼らは敵同士ではなく「対抗者」となる❖32。ムフは次のように語る。
私は(…)「敵対」(敵どうしの関係性)の範疇と「闘技」(対抗者どうしの関係性)の範疇とを区別し、「対立をはらむ同意」―たがいに敵対していても「正当な敵」とみなされる者どうしで共有される象徴的な空間を与える同意―の認識が必要であると示唆した。(…)対抗者がときには激しく闘うが、だからといってその闘いは一連の共有されるルールにしたがうものである。そして彼らの立場は―つまるところは相容れなくても―正当な立脚点をもつものとして受け入れられるのである。「対話的な」立場と「闘技的な」立場の根本的な違いは、後者の目的が、既存の権力諸関係を根底から変容させ、新しいヘゲモニーを樹立することにある❖33。
〈闘技〉的関係は〈境域〉を共有する点で同一であり、対抗的でありながら互いに正当性を受容されるものとして認識される。ここにおいて、「対抗者」の敵対性は排除しえず、むしろ「昇華」されるものでなければならない❖34。そのとき、それまでとは異なるヘゲモニー❖35へと変容する。それはつまり、一方が一方を打ち負かすのではない仕方で、合意の元にヒエラルキーを形成することである。〈捕食性アイデンティティ〉も〈群衆〉も、この〈闘技〉を前提とした〈境域〉内での対抗性ではなく、一方的な暴力性あるいは敵対的な関係性を強いる。他方、倫理的な理性による「対話的」関係性は、そもそも相容れることを前提としており、〈闘技〉を回避して自己の解釈を更新することで、権力的関係性自体は維持することを目的としている。だが、闘争を人間の条件とするのであれば、あらゆる秩序はヘゲモニー的秩序であるという事実に向き合わねばならない。
アイデンティティ・ポリティクスに躍起になったとしても、〈境域〉における〈闘技〉が成立しなければ、それは敵対関係を再生産し、分断を加速させるだけである。現代社会において、この〈境域〉となる空間がほとんど存在せず、〈闘技〉的関係性を構築することもできず、意思ある人々のみにその責任が委ねられているのは何を意味するのだろうか。もし、建築家の職能が空間を創造することであるならば、〈境域〉をこそ創造しなければならない。暴力的な敵対性による分裂と切断を前に、胡坐をかいている暇はないのである。
❖1│ 西川潤、マルク・アンベール著『共生主義宣言 経済成長なき時代をどう生きるか』、コモンズ、2017年、p.50
❖2│ 同上
❖3│ 同上、p.51
❖4│ 吉田徹著『アフター・リベラル 怒りと憎悪の政治』講談社現代新書、2020年、p.48
❖5│ 同上、p.28
❖6│ 同上、p.55
❖7│ 集産主義、財政支出、組合の交渉権、労働権保障など
❖8│ 今村仁司著『抗争する人間(ホモ・ポレミクス)』講談社選書メチエ、2005年、p.60
❖9│ 同上、p.16
❖10│ 同上、p.17
❖11│ 同上、p.9
❖12│ 同上、p.31-32
❖13│ 同上、p.61
❖14│ 東浩紀著『ゲンロン0 観光客の哲学』ゲンロン、2017年、p.64
❖15│ ❖8に同じ、p.73-74
❖16│ 同上、p.74
❖17│ 同上、p.10
❖18│ 同上、p.78
❖19│ 同上、p.88-89
❖20│ 『現代思想2019年6月 特集:加速主義 資本主義の疾走、未来への〈脱出〉』青土社、2019年、p.69
❖21│ ❖4に同じ、p.85
❖22│ 同上、p.83-84
❖23│ 同上、p.8
❖24│ 同上、p.123
❖25│ ❖20に同じ、p.70
❖26│ 同上、p.209
❖27│ ❖4に同じ、p.217
❖28│ ❖20に同じ、p.209
❖29│ ジャック・デリダ著、若森栄樹訳『境域』書肆心水、2010年、p.472
❖30│ 同上
❖31│ ❖8に同じ、p.79
❖32│ シャンタル・ムフ著、酒井隆史監訳、篠原雅武訳『政治的なものについて 闘技的民主主義と多元主義的グローバル秩序の構築』明石書店、2008年、p.38
❖33│ 同上、p.80-81
❖34│ 同上、p.38-39
❖35│ 一般に、合意による支配的な立場や地位、権力を指す

ご感想をTwitter #現代建築家宣言 にお寄せください!
掲載誌は以下より↓↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
