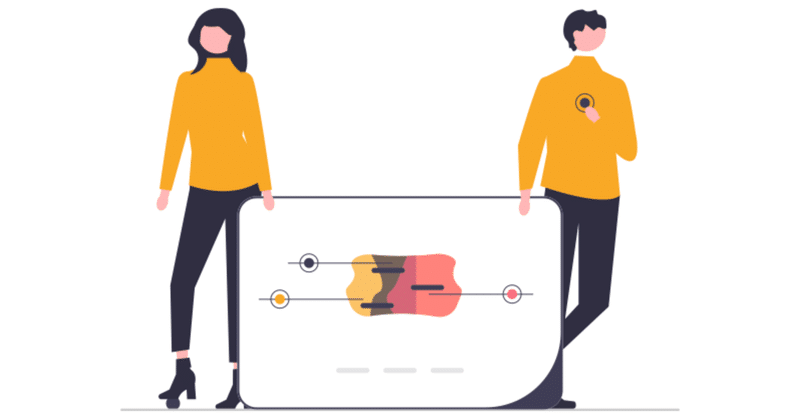
リモートワーク実施企業必見!運用成功の秘訣と適切な従業員評価の方法を徹底解説
企業では必ず従業員の業績評価を行いますが、リモートワーク・ハイブリッドワークが一般化した現在、「直属の部下に直接会ったことがない」という新たな課題に直面する管理職が少なくないようです。
また、パンデミックの影響でチームがリモートワークやハイブリッド勤務に移行する現状において、管理職は、毎日オフィスで隣に座っているわけではない従業員と有意義なフィードバックやキャリアアドバイス、評価をする方法を見つける必要があります。
ここでは、リモートワーク・ハイブリッドワークにおける基礎知識と、管理職がハイブリッド勤務の社員と業績に関する有意義な会話を行うために必要なことをいくつか紹介します。
▼リモートワーク・ハイブリッドワーク下での、マネジメントへの理解を深めたい方はこちら⇩
そもそも、リモートワーク・ハイブリッドワークとは?

新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため、在宅勤務・リモートワークなどの対策を取る企業が増加しています。
政府が発表した「新型コロナウィルス感染症対策の基本方針」のなかでテレワークが推奨されていることもあり、今後はさらにリモートワークが浸透していくことが予想されます。
まずはリモートワーク・ハイブリッドワークそのものについて簡単に解説します。
リモートワークとは?
まずはリモートワークについてです。
リモートワークとは、一般的には「インターネットを介し、企業のオフィス以外で業務を行うこと」を指します。
コロナ禍となってからは、「在宅勤務」も含め、すっかり浸透した言葉ですが、勤務地に縛られないことや、通勤時間の削減など新しい勤務体系として引き続き注目されています。
ハイブリッドワークとは?
次にハイブリッドワークについてです。
ハイブリッドワークとは、先述したリモートワークとオフィスへの出社を組み合わせる勤務体系です。
主に生産性の向上やコミュニケーションの促進、社外とのコラボレーションを活発化させ
という観点から、急速に注目が高まっています。
各社によってどのような勤務体系を採用するか。
その対応は分かれ、出社を義務付けたり、フルリモートワークを推奨したりと、議論が進められています。
リモートワークを成功させる3つのポイント

次に、リモートワークを成功させる3つのポイントです。
ポイント①|時間ではなく、アウトプットベースの考え方をインストールする
ハイマネージャーでは「OKR=アウトプット」と捉え、アウトプットを出せれば時間・場所は自由に決めても構わない、というスタンスでマネジメントをしています。
しかし、日本はまだ「アウトプット」ではなく「時間」をベースに働く…という前提を持っている方が多いように感じます。
例えば自分の親の世代は「リモートワーク・在宅勤務=休み」と捉えている方も少なくありません。
また、世代による「当たり前」の違いだけでなく、個々人の「働き方のスタンス」にも関わってきます。
例えば自分の友人は「リモートワークだと気が引き締まらない」というようなことを言っていました。
朝会で気持ちのスイッチをONにして、夕会でOFFにする…ことがルーティーンになっているようでした。「朝会がないとサボるよね」という感覚みたいでした。
「アウトプットを出す=仕事」という前提がないと、そういう状態になることが多いのかもしれないと感じます。
時間や場所に縛られずとも「アウトプット」を出す…という意識を個人が持たないと、生産性は下がってしまうのかもしれません。
ポイント②|具体的で緻密なスケジューリングをする
リモートワークになれば、いくらチャットツールやビデオチャットが整備されたとはいえ、当然コミュニケーションコストは上がります。一番は「リアルタイム性」が失われることです。
対面だったら、ちょっと移動して相手のデスクに向かって、数十秒で確認を取る…ということができましたが、今はそれができません。
なので、進捗確認のコストをどれだけ下げるかが肝になります。
最終期限から逆算して、「いつフィードバックをするのか」を明確にすることが大切だと感じます。
ポイント③|「場所」だけではなく「時間」の自由も担保する
リモートワークの大きなメリットとして、子育て中の両親や複業の方にも参画してもらえることが挙げられます。
しかしこれは「場所」だけでなく「時間」の自由も担保された状態でなければなりません。
前職のPwCでも、このような背景からスーパーフレックス制(1日に7時間勤務すれば時間帯は問わない)を導入していました。
なので、メンバーにそのような方がいらっしゃる場合、勤務時間をフレックス制にすることは必須です。
リモートワーク下の職場で業績評価を成功させる6つのヒント

最後に、リモートワーク下で難しい、業績評価の際に覚えておきたいポイントを解説します。
ヒント①|明確な評価基準を設定する
白紙の評価フォームは、管理職が即興で作成したり、有意義で建設的なフィードバックをチームメンバーと共有するための時間を取らないという結果になりかねません。
従業員一人ひとりが(勤務地に関係なく)同じように正確で公平な評価を得るためには、管理職がプロセスを進めるための明確な評価基準や質問を確立しておく必要があります。
もしあなたの会社が手動で人事考課を行っているのであれば、従業員のリーダーと質問を手動で共有するか、弊社の年次業績評価会話テンプレートまたは四半期評価テンプレートからいくつか抜き出して使用することができます。
明確な評価基準を設定することで、上司は自分の直属の部下に対して、プロフェッショナルとして成長するためにカスタマイズされた、より徹底的な評価を行うことができるようになります。
ヒント②|目標を用いて成功を評価する
従業員が何をすべきか、なぜそれをするのかを明確にするためには、短期と長期の両方の目標が必要です。
従業員が自宅やオフィス、あるいはその両方で働き続ける間、これらの目標は、彼らのパフォーマンスと成功を測る客観的でわかりやすい指標となります。
対面式のコーチングがない場合、 『従業員の目標』は、ハイブリッド型業績評価の焦点の1つになります。
たとえば、ある従業員が四半期および年間の目標を達成または上回った場合、その従業員は評価期間中に大きな業績を上げたことになります。
もし、ある従業員が定期的に個人のOKRを満たせない場合、その従業員の業績と目標設定について、真剣に話し合う必要があります。
ただし、目標そのものには細心の注意を払ってください。
もし、管理職が意図的に高い目標を設定させ、それが達成できなかったとしても、その従業員の業績が低く評価されるようなことがあってはなりません。
それよりも、各従業員の目標の複雑さを十分に考慮し、その成果を正確に評価するよう、上司に促してください。
そして、目標設定の際には、管理職はチーム内の各個人と緊密に連携し、適切かつ合理的な目標を設定する必要があります。
ヒント③|知っていることに集中する
直接会ったことのない人だからといって、その人のことを知らないとは限りません。
直属の上司に直接会ったことがなくても、その人と一緒に働くことがどんな感じなのかについて、おそらく直感的につかんでいるはずです。
たとえば、会議の準備や納期を守ること、仕事の質などは、たとえバーチャルな関係であっても見抜くことができるはずだからです。
管理職が従業員に行う建設的なフィードバックは、直属の部下がもっとこうすべきだった、こうするべきではなかったという意見によって形作られるのではなく、上司が部下とのやり取りの中で直接観察したことに基づいて行われるべきなのです。
ヒント④|年間を通じてメモを取る
考査期間全体ではなく、過去数カ月間の貢献度や業績に基づいて従業員の全体的なパフォーマンスを評価すると、管理職が偏った見方をすることで近接誤差を起こす可能性があります。
これは、従業員の業績を評価する方法として偏りがあります。
例えば、考査期間の大半を通じて常に最高の業績を上げていた従業員が、新たな健康問題や家族の緊急事態などの理由で過去1ヶ月目標を達成できなかった場合、不公平が生じてしまいます。
従業員のタスク・問題・フィードバックをバラバラのノートに記録したり、最悪頭の中だけに記録していると、評価の時にメモや記録を見直すことは不可能ではないにしても、難しくなります。
逆に、従業員の日々のパフォーマンスデータをデジタルで文書化し、保存する方法があれば、より詳細で正確な情報を引き出すことができ、その結果、より公平に評価することができます。
ヒント⑤|360度フィードバックを活用する
従業員の業績評価について一人だけが最終的な決定権を持つことは、偏った評価につながるだけでなく、その従業員がプロフェッショナルとして、また個人として成長するための貴重なフィードバックを受けられなくなる可能性があります。
偏りをなくし、より公平な評価プロセスを構築する最も簡単な方法の1つは、360度レビュー、つまり自己評価、同僚評価、上司評価で構成されるパフォーマンス評価を実施することです。
これは、直属の部下と密接に仕事をすることがないハイブリッド型勤務の管理職にとって、特に有効な方法です。
従業員の日々の努力をよく知る同僚からのフィードバックや評価を取り入れることができ、その結果、より全体的な評価を下すことができます。
実際、テクノロジーの調査およびコンサルティング会社であるGartner社によると、従業員が同様の業務を行い、相互に関連する目標を持つ仲間から評価を受けると、業績管理プロセスの有用性が3.5%高まり、従業員の業績が14%向上するそうです。
管理職がハイブリッド型勤務のチームに対してよりバランスのとれた公正な評価を行うために、360度レビューを導入することを検討してみてください。
管理職は、業績に関する会話を通してチームの意見を収集し共有することで、従業員の業績についてより完全な全体像を示すことができます。
そうすれば、従業員は毎日一緒に働いている人たちから意見を聞き、より良い同僚やチームメイトになる方法を学ぶことができます。
この方法を取ることで、管理職は従業員の自己評価、チームの意見、上司の評価との間に矛盾があることを認識できるのは明白で、それにより偏りを特定したり、期待に応えられていない部分をピンポイントで指摘したりすることができるようになるのです。
ヒント⑥|従業員を比較しない
最後に、従業員にはそれぞれ個性があることを忘れないでください。
役割・責任・スキル・長所・短所、すべてが異なるので、従業員同士を単純に比較することはできません。
特に、オフィス勤務の従業員は、リモートやハイブリッド勤務の従業員に比べて、日々の業務で顔を合わせ目に留まることが多いので、比較したくなることもあるでしょう。
しかし、この落とし穴には近づかないようにすることが重要です。
従業員自身の過去の業績のみに基づいて評価することで、チーム内で不健全な競争や恨みを募らせることを防ぎ、オフィス、自宅、ハイブリッドのいずれで働いていても、すべての従業員が評価を公正に感じるようにすることができるのです。
ただし、リモート社員を評価する際には、本人がコントロールできる要素のみを含めるようにしてください。
例えば、インターネットの不具合は、従業員が対処できるレベルのものかもしれませんが、その地域のインターネットの質そのものは、従業員がコントロールできるものではないので、評価で不利にならないようにしてください。
同様に、出社が任意であるにもかかわらず、出社できる人が健康状態や家庭の事情で出社できない人よりも高く評価されるということは起きるべきではないでしょう。
オフィスワークの方が何かと良いという事実と異なる不正確な偏見を避けるために、管理職には、チームメンバーと共有するフィードバックについて熟考し、従業員がコントロールできない要素ではなく、実際に改善できる内容にするよう指導してください。
まとめ
いかがだったでしょうか。
企業が従業員にリモートワークを推奨し、多くの企業が予測可能な将来にわたって少なくとも何らかのハイブリッド要素を維持することを計画している中、すべての従業員のために優れた従業員体験(EX)を構築するための投資は重要です。
そして、業績評価はその手始めとして最適な場所と言えます。
公平で公正な人事考課を行うことで、すべての従業員が、経営陣と顔を合わせる時間ではなく、スキルと貢献度に基づいて昇進や昇給を得る機会を平等に得られるようにすることが可能になります。
企業が目標を達成しそれを超えるためには、すべての従業員が成功するための準備を整え、その過程で評価され、感謝されていると感じられるようにする必要があるのです。
だからこそ、公正な人事考課を構築することは、ハイブリッド型勤務の従業員にとってより公平で魅力的な職場を作るための強力な一歩となるのです。
ハイマネージャーの提供する、6つのお役立ち資料はこちら
・・・
ハイマネージャー
OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。







