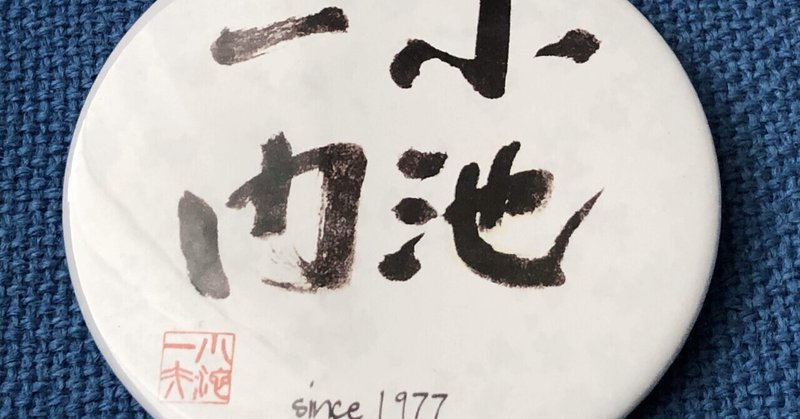
"キャラクターを起てろ!"劇画村塾第4期生 第1章(2)
<スタジオ・シップ本社での入塾式〜本物の小池一夫先生と狩撫麻礼先輩に会う>
株式会社スタジオ・シップ本社の社屋は、東横線の都立大学の駅前から柿の木坂を登った先にあった。
(現在は付近の情景も一変してしまっていて、当時を思い出させてくれるものは道路くらいである……まさに"強者どもの夢の跡"……)
東京へ出て来てから、四年以上が経過していたが、未だ一度も行ったことのない街だった。
(大学が西武池袋線の江古田にある"日芸"だった関係もあって、ずっと南池袋にあるアパートに住んでいたのだ。ちなみに、後年、池袋西口にあった国際空手道連盟極真会館総本部で、極真空手の創始者であり、『空手バカ一代』の主人公のモデルでもある大山倍達総裁にお会いする機会が巡ってくるとは、この当時は想像もしていない)
都立大学駅から歩いて行ったのか、バスを使ったのか、そのあたりの記憶も今や定かではないが、とにかく、なんとか辿り着くことができた。
"スタジオ・シップ"の社名の如く、実際に船を模したようなフォルムの堂々たる洋風の建物で、
(うひゃ~、なんか洒落てるなあ!)
と、感じたことを覚えている。
一階には、夜はバーにでもなりそうな雰囲気の喫茶室まであった。
(後年、この社屋と、さらに隣に設立された"第ニスタジオ"で徹夜したり、寝泊まりすることになろうとは、この時は想像もしていない)
その洒落た社屋のホールで入塾式は行われるという。
おっかなびっくり入ってみると、同期生約六十人が、その場所に集っていた。
さすがに皆緊張の面持ちである。
自分も並べられたパイプ椅子の末席に腰を下ろした。
壁には、ちばてつや先生が描かれた、小池一夫先生とスタッフの皆さんが一つの船に乗って、海を渡っている似顔絵が額装されて掛かっていた。
さらに、ゴルフコンペや野球大会のトロフィーがズラリと並んだ棚もあった。
そして……いよいよ入塾式が始まる旨が告げられた。
司会は、その後、ものすごくお世話になることになる劇画村塾の事務局長のSさんだった。
ややあって、小池一夫御大が姿を見せられた。
雑誌や単行本などの写真で顔は見たことはあったが、もちろん、実際にその姿を拝むのは初めてである。
(うお~! マフィアの親分みたいだ!!)
失礼ながら、第一印象はそれに尽きた。
一メートル八十五センチの身長と、それに比例したような横幅、さらにパンチパーマに、地模様の入った光る素材のスーツ、ピカピカの革靴!
当時、テレビにもよく登場されていた梶原一騎先生の姿を拝見して、同じような印象を抱いていたが、間近に見る小池一夫先生もまた、負けず劣らずの強面のイメージだった。
(劇画原作のドンというのは、なぜに揃ってその筋系のルックスなのだろうか……?!)
そんな不謹慎な思いにとらわれてしまったが、何も知らぬ当時ではやむをえないことと、これは勘弁してもらうしかない。
自分も含めて、入塾者一同が気圧されていると、小池一夫先生に続いて、二人の人物がホールに姿を見せた。
一人はとても知的な雰囲気の可憐な美女、そしてもう一人は、カーリーヘアにサングラスがキマった、ロックミュージシャンにしか見えない男性だった。
「では、最初に、小池一夫塾頭から皆さんに御挨拶があります」
Sさんが告げ、小池一夫先生が我々の前に立たれた。
「小池一夫です。皆さん、ようこそ」
ノーマイクでも、ホール全体に響き渡るような野太い声だった。
話し始めると、まさしく立て板に水の如くで、なおかつ内容も面白い。
(この人、作家というよりも、政治家か噺家かアナウンサーみたいだ。なんて上手に話すんだろう!)
それまでの人生の中で、そこまで話し方の巧みな人に会ったことがなかった。
たちまちにしてその話術に引き込まれ、ハッと我に返った時には小池先生の挨拶は終わっていた。
(小池一夫原作作品のキャラクター達のセリフの秀逸さは、間違いなく原作者本人のこの喋りのセンスに拠っている!)
と、強く思った。
それにしても、尋常ではない大物のオーラだ。
この人から、今後直接教えてもらえるんだと考えると、否応なく胸の高鳴りを覚えた。
「本日は、皆さんの先輩にあたる卒塾生のお二人にも来てもらっています。お二人とも、今やプロとしてバリバリ活躍されています」
Sさんの司会が続く。
(小池一夫劇画村塾の卒塾生! ということは……!)
さらなる期待で血が騒いだ。
「中村真理子さんです」
あの知的で可憐な美女が紹介され、正面に立たれた。
(なんて綺麗な女性だろう……!)
中村真理子先生の御名前と作品は知ってはいたが、当然、御本人のお顔を見るのは、これが初めてだった。
その美貌にポ〜ッと見とれてしまって、ほとんど言葉は耳に入ってこないというていたらく、まったくもって駄目な青二才であった。
(今もほとんど変わりませんが……)
「次に、原作者の狩撫麻礼さんからもメッセージをいただきたいと思います」
Sさんの紹介を聞いて、
(狩撫麻礼! この人が!)
思わず声を上げそうになってしまった。
「どうも。狩撫です」
第一声の声は、ルックスもどことなく似ていたが、俳優の松田優作さんや原田芳雄さんを思わせる声質だった。
低く、ハスキーだが、これまた小池先生と同じでよく通る。
そして、小池先生とはまた違ったベクトルで、話に吸引力があり、なおかつカッコよかった。
狩撫麻礼その人もまた、彼が書く原作作品に登場するキャラクターそのままと言っていいほど、喋る内容も喋り方も、絵になって、ハマっていた。
狩撫先輩が入塾生へのメッセージで述べた内容で、今も鮮明に覚えている言葉がある。
それは、
「小池一夫の”箍(たが)”を外せ」
という、少し挑発的なものだった。
聞いた当時は、今ひとつピンと来なかったが、後年、その意味をはっきりと悟るようになる。
いずれにせよ、大物と美女とロックシンガー、そんな三人を間近に見て、ちょっとミーハー気質のある自分は、すっかりテンションが上がってしまった。
なおかつ、小池一夫と狩撫麻礼という、それまでは一ファンとしてしてしか、その名前と作品に接することができなかった漫画原作者お二人の声を直に聞き、激励されたことで、
(よーし! 俺も頑張って漫画の原作を書くぞ!)
という気になってしまったのだ。
我ながら、まったく単純である。
入塾式が終了して、さっそく第一回目の小池一夫先生の講義が始まった。
興奮冷めやらぬまま、真剣にその話に聞き入った。
「僕が君達に教える最も大切なことは、たった一つしかない」
小池一夫先生が一番最初に言われた。
「”キャラクターを起(た)てろ”、それだけです」
以降、毎回の講義で、もう嫌になるほど、本当に耳にタコができるのではないかと思われるほど、繰り返し繰り返し刷り込まれることになる文言の、これが第一声だった。
「キャラクターを起てることさえできれば、それでもうその作品の八割方、いや、全部ができあがっていると言っても過言ではありません。だから、皆さんも死ぬ気になって、キャラクターを起てる努力をして下さい。その方法を、この塾では伝えていきたいと思います」
キャラクターを起(た)てる、すなわち、漫画の中に登場するキャラクターを読者に強烈に印象づける。二度と忘れないまでに!
確かに、大ヒットした作品には、すべて圧倒的な魅力を持ったキャラクター達が存在している。
小池一夫先生の『子連れ狼』では、公儀介錯人の拝一刀とその息子大五郎の二人がそれだ。
特殊な武器も備えた乳母車ならぬ箱車に乗った大五郎の「ちゃん!」という叫びと共に、日本全国に一大ブームを巻き起こした。
小池先生の講義は、めちゃくちゃ面白い雑談も含めながら、さらに具体的実践的なところへと突き進んで行くのだった。
〈続く〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
