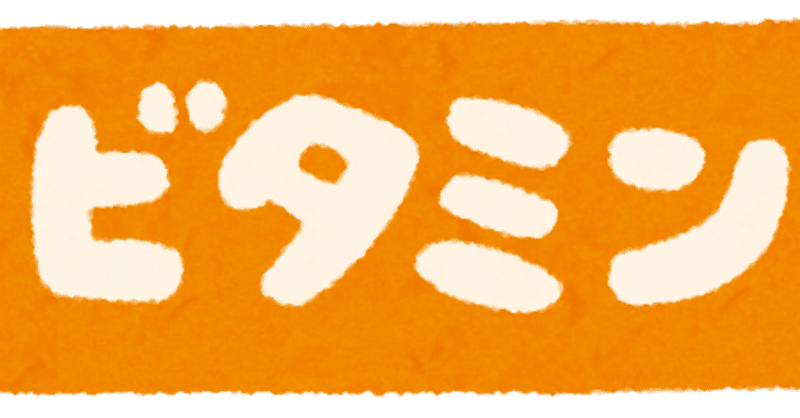
ダイエットの中で出会ったオーソモレキュラーという分子栄養学視点の栄養療法と妻の難病:多発性硬化症に対する治療への可能性について
直近のnoteの通り『金森式ダイエット』という側面から身体について学び始めたが、その勉強を深めていくうちに健康法という観点から様々な学びがあったので記録として残しておきたいと思う。
■学んでいった過程
上にも書いた通り、健康について学び始めたきっかけは自分がダイエットをしたいという動機から始まった。
最初は金森式ダイエットの書籍から始まり、金森さんのTwitterやネットの記事を検索しつつ知識を深めていく中で、体の代謝に着目したり関連した各種サプリの知識を調べたりしながら増やしていった。
その過程の中で確かTwitterからだと思うが、『藤川徳美』先生という方の書籍に出会った。 具体的に出会った本としては以下の通り。
・心と体を強くする! メガビタミン健康法 (藤川徳美先生シリーズ第三弾)
・医師や薬に頼らない! すべての不調は自分で治せる
■藤川先生の本で学んだこと
改めて書評はアウトプットのために書きたいと思っているが、下記に要点をざっと書いておく。(最初に読んだのが『医師や薬に頼らない! すべての不調は自分で治せる』だったので、そちらを中心にした内容となる。)
▼学んだ事
・現代食によって起こった栄養不足という事実
→驚きだったのは、いわゆるバランスの良い食事でも栄養不足なるということ。普通に食事をとっていたら身体に必要な栄養は満たされていない
・糖質の消化には多くのビタミンを使ってしまうので、本来必要な部分に栄養が供給されない。
・栄養不足状態が続くと、それを補うために身体の中だバランスを取ろうとする。結果、代謝異常が生じて不調が起きる。
・代謝異常が積み重なると、統合失調症、糖尿病、膠原病、アトピー性皮膚炎、神経難病、がんなどを発症する。
・一度栄養不足が起きると、戻すのに大量の栄養が必要。普通の栄養量だと回復しない。
・回復には個人差が生じる。栄養不足期間が長ければ長いほど人ほど回復が遅い。
・必要な栄養量は個人差があり、それは体の状態や遺伝などにもよる。例えば水溶性ビタミンは個人差として150倍、脂溶性ビタミンは10倍程度左が現れる事も。
・身体の代謝の仕組み(嫌気性解糖系、好気性代謝)
・症例からの現代の難病とされている病への治療アプローチ
ざっと書くだけでもこれぐらいはある。
この本は分子栄養学という分野から成り立っているものであるので人によっては理論などとっつきにくいかもしれないが、本の書き方がすごく滑らかなので一般書として分子栄養学の入門書として読み易いと思う。個人的には本当におすすめしたい本の一つである。
■妻の難病について
『自分の免疫細胞が過剰反応して自分の神経細胞(脳や脊髄、視神経など)を攻撃し、その結果、神経細胞で変異が起きることで、身体動作への影響、視覚への影響など様々な症状を抱える』
ことを言う。近年では特に若い女性でも増えてきた病気であり、ただ明確な治療法が医学的にないことから難病指定されている病気となっている。
この病は、症状が出る「再発」と症状が治まる「寛解」を繰り返す。最近、妻も再発し症状としては歩行への影響、脱力(握力がなくフライパンなども危ない)、小指が意図するように動かない、また「腰あたりの触られた感覚が膜がある感じ」などと本人は言っていたりする。ちなみにこの病気は周囲から見たら普通の人に見える。
妻が最初に発症(診断まではされなかったものの症状として出ていた)のは、高校3年生の頃だったという。当時は結果的に落ち着いたとのことだったが大学に入学後に再発。その際に正式に『多発性硬化症』と診断されたとのことだった。
その後は再発と寛解を繰り返しながら大学・社会人と過ごし、現在は30代前半になっている。
正直に言って、これまで難病ということで途方に暮れていた感はあったし薬の開発を待っていた。気持ちに寄り添う以外にやれることなど何もないのではないか、と思っていた。
それが意識が少し変わったのでこのnoteで共有させていただきたい。
■多発性硬化症に対する改善症例との出会い
意識が変わったきっかけは、分子栄養学の観点での栄養療法で多発性硬化症の改善症例があることを知ったことだ。これまで『治らない病気』としての認識だったので、それに対しては強烈な衝撃を受けたことを覚えている。
(栄養療法なアプローチを『オーソモレキュラー』という。)
まずは早速その症例の一つをシェアさせていただく。
↓
症例:【症例】多発性硬化症に対するオーソモレキュラー治療、半年でほぼ完治https://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/kotetsutokumi/entry-12567857672.html
→日本人男性の症例。こちらのリンクは先程紹介させていただいた藤川先生の公式ブログとなる。また先程紹介させていただいた書籍にも記載があった。
このブログをきっかけにオーソモレキュラーに関して複数の書籍を買い集め現在勉強を始めた。
なお、こちらの書籍にもカナダ人の症例記録ではあるものの、改善症例があったので、参考リンクとして載せさせていただく。
■オーソモレキュラーと多発性硬化症に対して関連性を感じた背景
オーソモレキュラーの観点では身体に必要な栄養を十分に入れることが前提になっている。反対に言えば、症状が出ている人は身体に必要な栄養を十分に補給できていない、または過去に身体の栄養状態を極端に下げさせるなんらかの出来事があったとも言うことができる。
藤川先生の本ではわかりやすく『質的栄養失調』という言葉で表現されており、これは『糖質過多+タンパク不足+脂肪酸不足+ビタミン不足+ミネラル不足』の食事を続けることによって起きる体の栄養状態を指しており、身体に栄養が足りていない状態を指している。そして、この状態があらゆる病気の原因になりうる。
その上で妻を考えると、、
・糖質中心というか糖質大好きな食生活
→菓子やケーキなどの食べる頻度も非常に多い。
・高校時は週7のソフトボール部。ピッチャーをやっており週末は必ず練習試合で連投。針を打ちながら登板を続けていた。さらに部活のほかにフットサルを夜間に週1〜2程度やっていた。(高校からケーキバイキングなど大好きな女子高生)
という感じなので、オーソモレキュラー的には栄養不足の食生活ど真ん中に当てはまるパターンなのではないかと考えている。
■栄養療法の我が家への導入
オーソモレキュラー的観点からの治療アプローチについては今後別の機会で書きたいと思うが、今我が家で始めたこととしては、
----------------------------------------------------------
・プロテインの導入
・サプリ(鉄、ビタミンC、ビタミンB群、マグネシウム、ビタミンE)の摂取
----------------------------------------------------------
である。
加えて、現状の栄養状態を測るための検査も並行して行っていく。
今後改めてnoteにまとめさせていただく。
■治療の可能性について
今回の内容の学習を通じたり、また妻の背景も鑑みると相関があるのではないかと思っている。そのため治療への可能性を感じており、家族としては希望が持つ事ができた。今後実践とフィードバックを通じて立ち向かっていきたいと思っている。
(妻はさきほど餡まんじゅうを食べていた。先は長いかもしれないが。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
