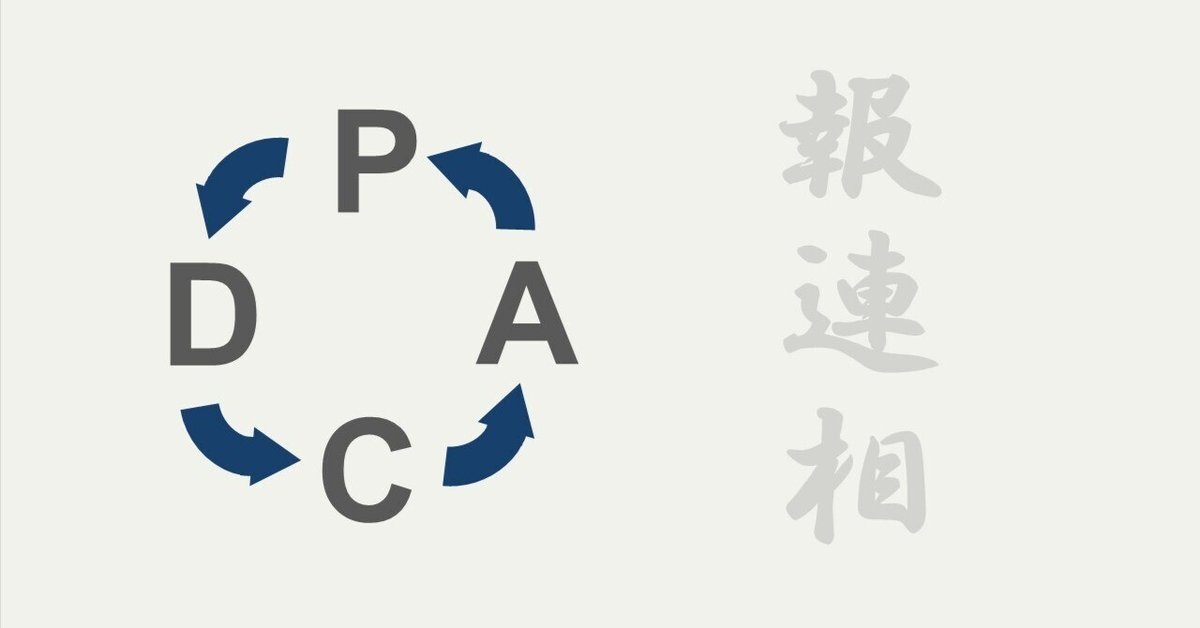
社会人基礎力とは①(PDCAサイクル)
「社会人、特に会社員として働いていくために必要な基礎力とは何か?」と問われると、まずは「PDCAサイクル」と「報連相」だと答える。
みなさんご存じの通り、「PDCAサイクル」とは「Plan(計画)・Do(実行)・Check(検証)・Action(改善)」の頭文字で仕事の質を継続的に高めていく働き方。「報連相」とは「報告・連絡・相談」で組織で効率的に仕事をしていくための手段である。
「PDCAサイクル」が始まるとき
会社に入社したときは、誰しも新入社員である。新入社員研修などで、会社のルールや仕事の仕方、会社の理念や組織構造など、いろいろなことを学ぶ。
基礎を学び、ある程度実務をこなすと、「この業務をどうやって進めようか?」ということが考えられるようになる。そこで「PDCAサイクル」が本格的にスタートする。
サイクルを回し始められないときには
「どうやって進めようか?」と考えている時点で「P(計画)」は始まっている。それに従って実行すれば「D(実行)」となり、そこでの成功や失敗を振り返れば「C(検証)」、次回への改善策を考えれば「A(改善)」と続く。
こうして、「PDCA→PDCA→P…」と続けていけば、おのずと仕事を上手に回せるようになり、生産性を高めていける。
しかし、凡事徹底は難しい。仕事はこちらの都合に関係なく、突然降ってくる。突然トラブルが発生し、大事なお客様からの依頼が飛び込んでくる。目の前には、仕事が山のように溜まっており、大事なプロジェクトの締め切りを前に、深く考えずに手をつけてしう。
誰しも陥ったことがあるシチュエーションであり、落ち着いてPDCAサイクルを回し続けるには時間が足りず、仕事に追いつくため、不本意ながら「D→D→D→・・・」。
そういった時、まずは「P(準備)」をする時間を強制的に確保しよう。会議時間を取るように、考える時間を強制的にスケジュールに割り込ませるのだ。
いうなれば、「PDCAサイクル」を回すための「P(準備)」をして、うまくいかなかったら、どうして「PDCAサイクル」を回せなかったのかを考えて(C:検証)、改善案を考える(A:改善)のである。
良質な「P」は「CA」を促す
「PDCAサイクル」を回していくにあたって、最も大事なのは「P(計画)」である。
「P(計画)」がしっかりとできえちれば、「D(実行)」をする前に頭の中でその仕事が終わっている。明確に業務完了までのプロセスが見えており、万事滞りなく準備が済んでいる状態である。
そこまでできると、まず失敗することが想像できない。うまくいかなかったとしたら、予想を超える何かが発生したからであり、「何があったの?」ということを聞きたくなるだろう。すでにその時点で「C(検証)」始まっている。
それほど興味をもって聞いてしまうと、「じゃあこうしたらよかったね」「それはしょうがない。次回はここまでは準備しよう」など、次回に向けた対策が自然と頭に浮かんでくる。
良質な「P」は「CA」を誘発してくれる。逆に、質の低い「P」をしていると、失敗しても穴だらけで検証する気も起きず、サイクルを回す気にならない。結果として、生産性は高まっていかない。
毎回の蓄積が大きな差になる
「PDCAサイクル」の質は、社会人としての成長に大きくかかわってくる。質の高いサイクルを回し続ければ、おのずと業務遂行能力が上がるが、質の低い「P」しかできないと仕事を上手にこなせないままである。
数年間の蓄積は、個人の職務遂行能力の大きな差となり、ゆくゆくは会社組織としての業務遂行能力につながる。
社会人の基礎力である「PDCAサイクル」の徹底に力を注ぐことは、組織の管理者にとって緊急度は高くはないが、確実に重要度の高い仕事なのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
