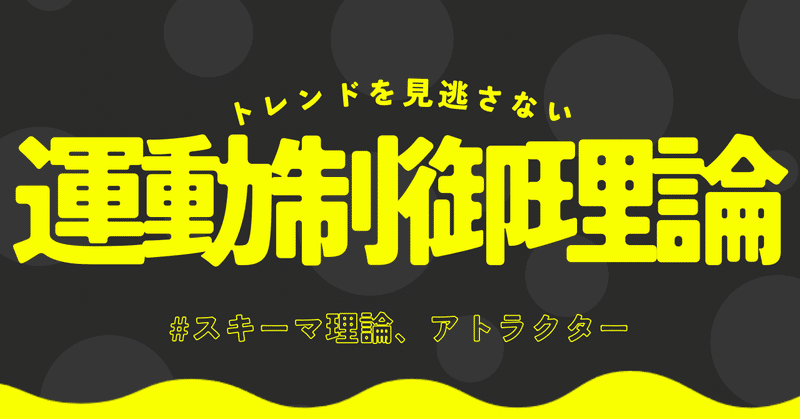
(19676文字)最新トレンドに乗り遅れるな!絶対に知っておくべき運動制御理論と制約主導アプローチ!「運動を生み出しているのは知覚であり、知覚を生み出しているのは?運動です」
踵で押して!より、マットの真ん中に穴開けて!(あらかじめ真ん中に踵をセットしてある)の方がよかった。
— クリニック勤務の柔整AT@コツコツnote書きます (@jusei_at_cscs) July 26, 2023
マットの沈み具合でできてるかできてないかが見てわかる。
一見よいこととは思った、でもその場での変化や改善って長く定着しなかったりとか
この辺整理
アスリハもパフォーマンス向上のためのトレーニングも、時代を経てどんどん進化しています。少し足を止めると、あっという間に置いていかれそうです。
最初にこの理論に出会ったのは2022年(たしか)のS&Cフォーラムでした。筑波大の谷川先生の講義だったと思います。非常にセンセーショナルで革新的でした。その後自分も学び続け、臨床や現場に落とし込めるようになってきました。
色んなセミナーや書籍も増えてきています。どれからはじめたらいいかわからない方、もしくはいきなり本格的なセミナーはちょっと重い方は、ぜひこのnoteで一緒に勉強しましょう。
⭐️読んでわかること&キーワード
・ストレングスは動作の重要なコーディネーションの構築ブロックを改善する
・アスレティックスキルモデル
・ダイナミックシステム
・自由度問題
・スキーマ理論
・エコロジカルアプローチ
・アトラクターとフラクチュエーター
記事の要約
• 運動制御理論: この理論は、運動学習と運動制御の重要性を強調し、運動行動が個体、課題、環境の相互作用によって形成されると提案します。運動行動の決定には、運動プログラム、並行分散処理、ダイナミックアクション、課題指向型、エコロジカル、アフォーダンスなどの理論が関連しています。
• 制約主導アプローチ: このアプローチでは、環境に対して制約を設けることで、人の適応行動としての運動学習を引き出します。筋構築が動作の制御に重要な役割を果たすため、筋の自然な適合性は全体のコンテクスチュアルパターンの基盤となります。
• 運動学習の具体例: 例えば、ラグビーのキックのような状況では、毎回異なる状況があり、同じキック動作は存在し得ないことを説明しています。このような状況で、筋肉だけを鍛えるのではなく、運動制御理論を応用することの重要性を強調しています。
• 多様な運動経験の重要性: 複数の競技経験を持つアスリートが多くの金メダルを獲得した事例を引用し、異なる競技の練習が別の競技でも身体をうまく動かせる力を高めると述べています。 • 理学療法における運動制御: 運動制御には身体の安定性と運動性の二つの論点があり、これらは運動と姿勢の両方の制御を含む概念です。運動制御の向上は運動学習に基づき、発達的な視点が重要です。 この記事は、運動制御理論と制約主導アプローチの基本的な概念を解説し、スポーツや運動学習においてこれらの理論がどのように活用されるかを示しています。
アスリートが試合でパフォーマンスを発揮するために。
noteにまとめながら、去年まで、先月まで、昨日までの俺、やばい!直す!やばい!となりました。
上記の投稿。
なんて声かけるかで、結果が変わるなんていうことは普段からよく経験するところです。前までは、より良い結果がその場で出るように工夫してました。でも、それが長く続かない学習だとしたら?
エコロジカルアプローチを学んで、運動を引き出す、という概念を知りました。環境に対して制約を設けることで、制約を操作することで、人の適応行動としての運動学習を引き出すそうです。そしてトレーニング指導を生業とする自分は、これらを意識することでより高い効果を出せると感じています。
伝統的な運動学習理論では、技術の習得がその状況と実段される課題に特化していることが重視されます。学習転移の文脈では、ある課題や領城のそれまでの練習や経験が、ほかの関連する課題や領城で好ましい実を促進したり(良い転移)、阻害したりします。(悪い転移)
solution setterからproblem setterへ
ほんで、過去ノートとあわせると自分への気づきが半端ない。
— クリニック勤務の柔整AT@コツコツnote書きます (@jusei_at_cscs) July 30, 2023
身体知、知ってますか?めっちゃ大事だなって実感https://t.co/wkbJYv36Oc https://t.co/RQqV6yp3uy
solution setterからproblem setterへ
— クリニック勤務の柔整AT@コツコツnote書きます (@jusei_at_cscs) July 28, 2023
解決方法を教えるのではなく、課題を設定する
学習者が効率的にスキルを習得していける制約を設ける
従来のコーチ像から離れてみる必要がある
ちなみに某SCは指導の際気をつけていることに「指導しすぎること」をあげていた、と人が話していたのを聞いたことがあります。 https://t.co/utPJjsLHMu
— クリニック勤務の柔整AT@コツコツnote書きます (@jusei_at_cscs) July 27, 2023
得てして指導書のエゴになりがち、教えたくなってしまうのが指導車の性か。 https://t.co/XWtvhVnFD3
— クリニック勤務の柔整AT@コツコツnote書きます (@jusei_at_cscs) July 27, 2023
上記の投稿。やっぱり、僕たちは教えすぎてしまう傾向があると思います。
魚を与えるより、釣り方を教える、で、この釣り方の教え方で話は変わってくると。
「解決方法を教えるのではなく、課題を設定する」
「学習者が効率的にスキルを習得していける制約を設ける」
「エキスパートモデル、ターゲットムーブメントからの脱却」
「ターゲットムーブメントは存在しない」
アスリハ、スキルコーチ、トレーナー、これ今の時流に乗らないとですよ。自由度があっていいところと、安定した方がいいところ、どこの安定を深めるべきか、どこの自由度は減らすべきか。まだまだ勉強中ですが。見える世界変わる感じはあります https://t.co/Tycz4NNMSZ
— スポクリ柔@コツコツnote (@jusei_at_cscs) January 7, 2024
多様性、バリエーション、膨大なソリューションの中から一つを選んで実行することについて、みなさんはどう考えますか?全てのソリューションを学習する必要がありますか?いや、学者できますか?
学会でも話があったんですね…繰り返しのない繰り返し…自由度問題… https://t.co/IeeV9A0Oah
— スポクリ柔@コツコツnote (@jusei_at_cscs) January 7, 2024
どういうことか、例えば下の投稿を読んでみてください。
相手のチャージ、どのエリアを取るか、点差、疲労、などなど。
— スポクリ柔@コツコツnote (@jusei_at_cscs) January 6, 2024
RTSを叶えるにはバイメカだけでは語れない部分も視野に入れたい。
もちろんバイメカ、解剖的な視点による介入は前提として必須とは思う。 pic.twitter.com/jKEGwJJwvf
ラグビーをしている様子です。AIで生成しました。
前の方に向かってキックをします。味方からパスがきます。すかさず相手選手がチャージをしてきます。プレッシャーをかかりますし、タイミングを逸すると蹴ることができません。また、コースも変わってしまいます。
このように、キック一つとっても毎回状況が違うことがわかります。味方からのパスの位置、相手の位置、タイミングによって選べるキックは変わるからです。すなわち、同じキック動作は存在し得ないのです。
それなのに、キックがイマイチだからと言ってただ蹴るだけ、もしくはキックに使う筋肉を鍛えるだけでいいのでしょうか?
キックを上手に蹴るために、体を上手に扱おうとすること自体はいいと思います。しかしスポーツのシチュエーションでは悠長なことは言ってられません。時間的な制約がある中で正しいキックを選ばなかればならないのです。
運動制御理論、すごく奥が深いです。従来のコーチ像から離れてみる必要があります。
これらの意味も、読むうちにわかるはず。僕も学び始めて浅いんですけどね。色んな本読んでの内容を咀嚼して書いています。これから学ぶ人の補助になればすごく嬉しいです。
制約主導アプローチは習得できるスキルの質(パフォーマンス)、動作のバリエーション、スキルの維持で伝統的アプローチよりも優れているとされます。それらについて紐解いていきましょう。
多様な運動経験があるとよい?
2016年オリンピック、リオデジャネイロ大会では、複数競技の経験をもつ多くのアスリートが参加して金メダルを獲得したそうです。例えばウサイン・ボルト(短距離走)はサッカーとクリケット、ローラ・トロット(自転車競技)はトランポリン、またシ・チェンマオ(飛び込み)は器械体操をやっていたそうです。様々な種目に参加している、あるいは参加したことがある競技者は様々に有利なようです。各競技の練習が、別の競技でも身体をうまく動かせる力を高める、移行できる要因があると仮定して、その根底にある仕組みは何でしょうか。また、この仕組みをどう捉えたらよいのでしょうか。
noteの内容をざっくりと
新しいアプローチ?であるスポーツに特異的なストレングストレーニングは、効果の転移を促進し、無駄な負荷を回避する重要性が強調されています。部位別アプローチでは限られたエクササイズバリエーションが課題となり、高い負荷が不可避とされますが、コンテクスチュアルトレーニングでは多様性を重視し、質的な過負荷に焦点を置きます。特に、動作の安定した要素への注目が高い強度の動作への転移を可能にするカギとなります。筋構築が動作の制御に重要な役割を果たすため、筋の自然な適合性は全体のコンテクスチュアルパターンの基盤となります。これにより、技術とストレングストレーニングの境界が曖昧になる新しい可能性が広がります。
ロシアの生理学者ベルンシュタインの業績が英語圏に紹介された1967年以降、運動制御の自由度と文脈の問題に挑戦し、個体と環境の相互作用による新たな運動制御理論が提案されました。このシステム論によるアプローチでは、運動行動は一元的な制御ではなく、複数のシステムの相互作用によって形成されるとされます。中枢神経内のシステムだけでなく、筋骨格システムや環境システムも含まれ、個人・課題・環境の相互作用が運動制御を決定します。さらに、運動行動の決定に関連する制御理論として、運動プログラム、並行分散処理、ダイナミックアクション、課題指向型、エコロジカル、アフォーダンスなどが挙げられます。
続いてnoteの中盤ではアダム・シュミットのスキーマ理論についてです。
同理論は、過去の運動プログラムと結果に基づいて回帰直線を引くことで新規運動の精度を高める理論です。スポーツにおいては、選手の心理的・身体的な状況の変動に応じた制御が求められます。ストレングストレーニングにおいては、特異性を最大化することは効率的ではなく、過負荷と変動が効果的とされます。特に全身動作にはアトラクターのフラクチュエーターの概念が有用です。ストレングストレーニングは動作のコーディネーション構築に適していますが、すべての学習パターンに適切ではない場合もあります。外乱を加えることでアトラクターを深化させることも可能です。また、ジャンプスクワットは過負荷を産み出すためには適していないとされ、選手のトレーニングでは自己組織化を促す必要があります。(追記予定の部分)
アトラクター、フラクチュエーターってなんぞや、聞いたことあるけどよくわかない、と言う方。そんな方におすすめのnoteです。
このnoteでは運動制御理論を深掘りし、専門的な視点から学ぶことができます。
それではみていきましょう。
理学療法の資料から引っ張ってきた運動制御について
運動制御には2つの重要な論点が存在します。まず、身体の安定性に関する論点があります。これは、身体が空間の中でどのように安定するかについて考えるものです。そして、もう1つは身体の運動性についての論点です。これは、身体が空間でどのように動くかに焦点を当てます。運動制御とは、運動と姿勢の両方の制御を包含する概念で、非常に専門的な分野ですが、その重要性は大きいですね。
この分野の歴史的背景として、中枢疾患のリハビリテーションなどでは、90年代から機能回復に関して、運動行動が個人、課題、環境の相互作用によって発現するというシステム論が注目されています。日常生活での運動行動や行動は、特定の環境下で課題を遂行する際に身体内部で行われる処理の結果だとされています。この処理過程が運動制御と呼ばれています。身体内部の処理は環境と課題によって多様性を持ちます。運動制御には運動の計画とプログラムの実行、そして感覚フィードバックが含まれており、高度な運動技能の向上は運動学習に基づいています。運動制御の向上過程の理解には発達的な視点が有効とされています。
ここまでの運動制御まとめ
よろしければサポートをお願いします! しっかり投稿に還元していきます!

