
『経済セミナー』2024年6・7月号の見どころ紹介!
このnoteでは、『経済セミナー』2024年6・7月号の見どころをご紹介します!
今号の特集テーマは「これからの労働市場改革を考える」です!
今号のラインナップは以下の通りです:
■ 特集 これからの労働市場改革を考える
今回の特集は「労働市場」に焦点を当てたラインナップをお届けします。
労働市場に関する話題はたくさんありますが、今号では日本型雇用の変化や労働市場改革における法・ルール作りについての議論を中心に取りあげます。
■ 【対談】 「日本型雇用」はどこへ行く?

巻頭を飾るのは大内伸哉先生(神戸大学)と太田聰一先生(慶應義塾大学)による対談「『日本型雇用』はどこへ行く?」です!
労働市場改革は経済学の知見だけではなく、解雇規制などに関する法学分野からの知見が必須です。対談では、労働法学者である大内先生が参加されます。
2023年5月、岸田文雄政権は「三位一体の労働市場改革」を打ち出し、今後の労働市場がどのように変化するのかに注目が寄せられています。年功賃金や長期雇用を前提とした、いわゆる「日本型雇用」はどのように変わっていくのでしょうか?
日本型雇用に対比される概念として、特定の業務(ジョブ)を行う能力をもった人材を採用する「ジョブ型雇用」があります。現行の解雇規制とジョブ型雇用は相容れるものなのかについても、対談で議論しています。また、雇用のあり方の変化に伴い、フリーランス人材の活用についても触れられています。
さらに対談後半では、政府による労働市場改革について批判的に考察を加えつつ、今後どのような政策を行っていくべきかも提案されています。労働市場の変化に応じて、労働者が不利にならないような解雇の仕組み・ルール作りについて建設的な議論が展開されています。
本誌にて、法学者と経済学者による密度の濃い議論をお楽しみください!
■ 労働市場と人的投資のこれから

宮本弘曉先生(一橋大学経済研究所、執筆時点)による記事です! 技術進歩など時代変化に応じた日本の雇用の変化・人的投資について議論しています。
労働市場が変化するにつれて、労働者に対する企業の人的投資の仕方も変わります。
技術進歩の影響は無視できません。近年では、生成AIが登場し日々注目が高まっています。生成AIの登場によって影響を受ける仕事/受けない仕事についても言及されています。
また、これからの労働市場が流動的になっていくとすれば、人的資本に対する投資の主体は企業から個人に代わっていくことも考えられます。リスキリングという言葉も昨今注目されていますね。
■ 「雇用の出口」を問い直す──完全補償ルールの機能と実装への課題
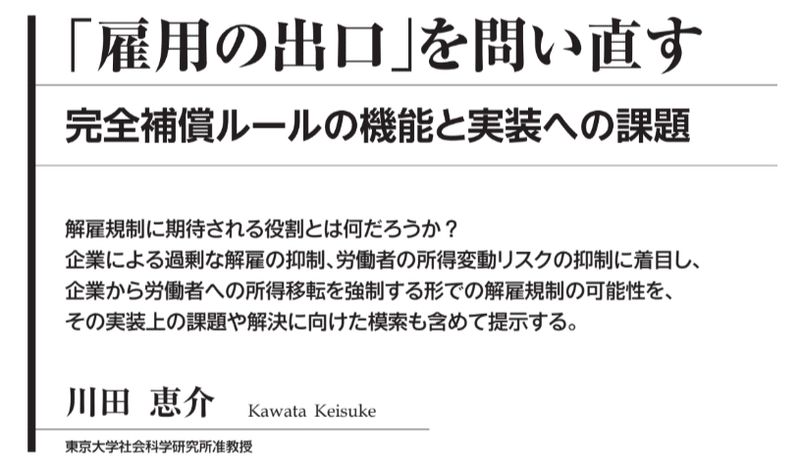
川田恵介先生(東京大学)の記事です!
対談では、これからの労働市場の変化に合わせたルール作りが議論されました。労働市場の流動性を保ちつつ、労働者が大きな所得変動リスクに遭わないよう、うまく仕組みをつくっていく必要があります。
川田先生の記事では、大内・川口(2018)で提案された「完全補償ルール」を紹介しつつ、金銭的補償の仕組みを実装する際の課題を整理・議論しています。
社会経済、特に市場の枠組みを理論的に構築・実装するのは経済学が得意とするところです。川田先生の記事からは、労働者や労働市場のあり方を経済学の観点から考察しつつ、一筋縄ではいかない社会実装の様相をみてとることができます。
■ フリーランスという働き方──現状と課題

平田麻莉様(一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会代表理事)によるご寄稿です!
「雇用」という形にとらわれない働き方として、「フリーランス」と呼ばれる形態があります。
本記事によれば、フリーランスとは「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」と定義されています。
日本における雇用のあり方や労働市場の情勢が変化していく中、フリーランス人材をいかに活用していくかに注目が集まってきています。
一方で、フリーランス人材の活用にあたって、契約におけるトラブルなどの問題に対処していかなくてはなりません。記事内でも触れられていますが、成立したばかりの「フリーランス新法(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)」の影響も今後注目していく必要がありそうですね。
■ 連載
■ 【新連載!】 プラットフォームの経済学 vol.1
プラットフォーム経済学への招待

佐藤進先生(一橋大学)と善如悠介先生(神戸大学)による新連載です!
本連載では、Google、Amazon、Facebookといった巨大デジタル企業に代表される「プラットフォーム」の機能や問題点を経済学的に分析していきます。プラットフォームは非常に身近な存在であり、私たちの生活になくてはならないものになりつつあります。
第1回はイントロダクションとして、「プラットフォームっぽさ」を考えることから始め、プラットフォームが持っていてほしい基本的な性質を考察しています。
第2回は「コールドスタート問題」を取り上げます!
引き続き連載をお楽しみください!
■ マクロ開発経済学 vol.13
無限期間の代表的家計の意味と人口成長

植田健一先生(東京大学)による連載です!
今回は、人口成長を軸に議論を展開しています。
「マルサスの罠」の紹介から始めていき、内生化された人口成長を考慮したモデルを考えます。
今回の内容は、少子化や移民といった人口問題とも関連があります。たとえば、日本における少子化などは人口成長の内生化によって生じると考えられる現象の1つです。人口増加による問題に悩む発展途上国から少子化が進む先進国への移民も、両国に便益を生むと考えられます。
【予告】
植田健一先生・服部孝洋先生による書籍『国際金融論入門(仮)』の刊行を予定しています! こちらもお楽しみに!
■ データで社会をデザインする 機械学習・因果推論・経済学の融合 vol.17
実験デザイン(4)──データ駆動メカニズムデザインへ

成田悠輔先生(イェール大学)・矢田紘平先生(ウィスコンシン大学マディソン校)による連載は第17回を迎えました!
直近の3回では、さまざまな「望ましさ」を最大にする実験デザインを考察してきました。今回は、情報最大化・厚生最大化を融合し、データ駆動的な実験デザインを組むことを考えます。
後半では、メカニズムデザインとの関連にも触れられています。実験デザインと経済学の理論とのつながりが見えてきました。
そして次回(第18回)は最終回の予定となっております。次号もお見逃しなく!
■ 社会保障のこれまでとこれから 福祉国家と実証経済学の視点 vol.2
社会的投資としての教育

安藤道人先生(立教大学)による連載第2回です!前号よりスタートしたばかりの新しい企画となっております。
第1回は「そもそも福祉国家とは何か?」という問いに始まり、福祉国家研究と実証経済学との視点の違いや関係性を整理しました。
第2回のテーマは「教育」です!
教育を社会保障の1つと捉えている人は、あまり多くないのではないでしょうか。しかし、教育に関する権利・義務は日本国憲法に明確に規定されており、教育は市民に当然のように受け入れられている社会サービスなのです。
今回を含め3回にわたり教育に関する議論を展開していきます。次回もお楽しみに!
■ はじめてのマクロ経済学 vol.2
経済成長論の問題意識

盛本圭一先生(明治大学)による、初学者向けマクロ経済学の連載第2回です。前回はGDP、三面等価、物価指数などマクロ経済学の基礎的な概念を取り上げました。
第2回のテーマは「経済成長論」です。
タイトルにもあるように、経済成長をとらえる上で必要となる基礎知識や重要な概念を今回は解説します。
前半では、GDP系列のデータやどのように経済成長の度合いを計算するかなどの基礎知識を紹介しています。
後半では、Harrod-Domar(ハロッド・ドーマー)モデルを用いて実際に経済成長の過程を考えていきます。経済成長の「収束」がキーワードです。
次回はSolow(ソロー)モデルの解説を予定していますのでお楽しみに!
■ どうする独裁者 数理・データ分析で考える権威主義 vol.6
血塗られた安定

浅古泰史・東島雅昌先生による連載。今回のテーマは「提携(coalition)」。
政治的なライバル同士がどのように手を組んで政権を運営していくのかを理論的に考察していきます。
「どのような場合にライバルを手を組むのがよいか?」「誰が最終的に生き残ることができるのか?」といった政治における戦略的な状況を、簡単なモデルと具体的な数値例を用いて理論的に分析します。専門用語で言い換えれば、今回は支配提携(=最終的に誰が生き残るのか)形成についての考察です。
「最も強ければ生き残れる」わけでもなさそうです。気になる方は本誌をご覧ください!
「どうする独裁者」のサポートサイト
■ 海外論文SURVEY vol.129
教育はなぜ犯罪を減らすのか? (Bell, Costa, and Machin 2022)

河原崎耀さんによる解説です!
教育が犯罪を減らすメカニズムをいくつかの仮説を検証する形で考察した論文です。各仮説について実証結果をもとに丁寧に解説をしているので、実証研究の参考にもなります。
原論文(Bell, Costa, and Machin 2022)はこちらからご覧いただけます! ↓
■書評:『教育政策をめぐるエビデンス』勁草書房 中西啓喜/著
評者:北條雅一
気鋭の教育社会学者による書籍を、教育経済学者である北條雅一先生が解説します。本書では少人数学級政策が議論の補助線となっており、経済学分野における少人数学級政策の研究に取り組んできた北條先生による丁寧な解説をご覧ください!
書評欄でご紹介した書籍はこちら↓
■ おわりに
『経済セミナー』2024年6・7月号の見どころをざっと紹介させていただきました!
ぜひお手に取ってご覧いただけたら幸いです!
サポートに限らず、どんなリアクションでも大変ありがたく思います。リクエスト等々もぜひお送りいただけたら幸いです。本誌とあわあせて、今後もコンテンツ充実に努めて参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
