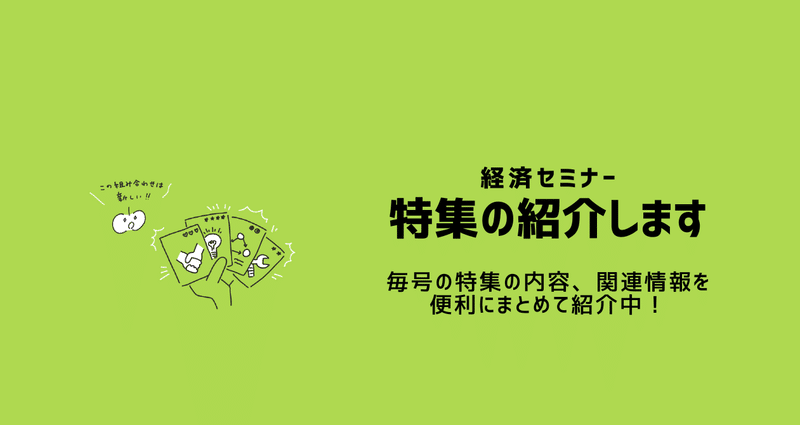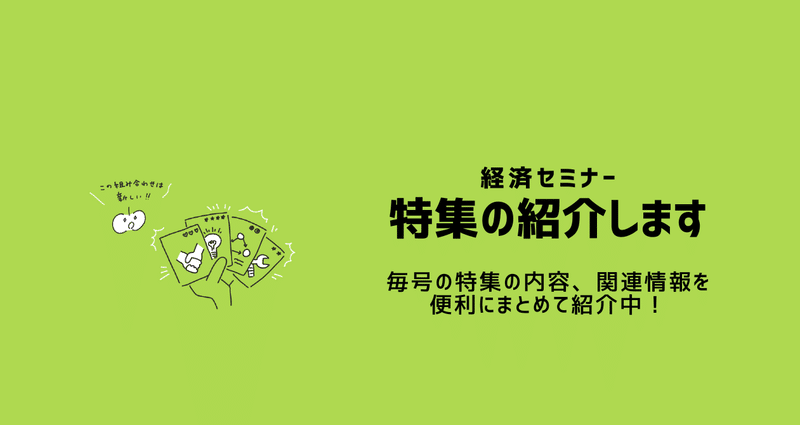「『民主主義 vs. 権威主義』のゆくえ」参考文献+データの紹介!(経セミ2022年10・11月号より)
このnoteでは、『経済セミナー』2022年10・11月号の特集「いま、政治の問題を考える」の巻頭対談、
浅古泰史 × 東島雅昌 「『民主主義 vs. 権威主義』のゆくえ」
で紹介されたトピックの関連情報や、ディスカッションの背景にある研究やデータなどの資料を、リンク付きでご紹介していきます!
対談は、その社会や国がどのように統治されているか、すなわち「政治体制」をテーマの軸に据えて進んでいきます。特に、欧米諸国や日本などで一般的な民主主義と、中国やロシアが代表的な大国