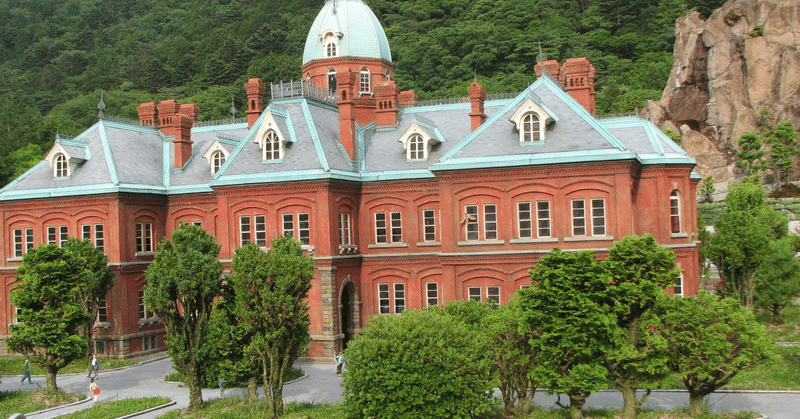
小説「風の仕業」kaze no itazura 3
3
私の現在の生活環境は、奈良の郊外の「借景」のある、割と閑静な場所にあり、子供が通う小学校に近いところに「一戸建て」を設け、歩いていける距離にやや老いた母の実家がある。というより実家の近くに越してきたと云った方が正確だが、マイホームを築いて数年すると、近くに分譲マンションが建ち始め、今度はその近くに郊外型ショッピングセンターやコンビニ、スーパーだのが次々に生まれ、一帯は便利なベッドタウンに「成長」した。しかし私の選択は必ずしも正解ではないことを後で知った。
何故なら、通学はある程度の距離にあってこそ、子供の成長にとって意味があると気付いたからだ。諸々もろもろのことの多くはすべて手遅れである。私なぞ子供の頃は片道二キロの道を歩いて通ったものだ。我が家に井戸水とラジオはあったが、未だ電話のない時代だった。
子供は小学六年になり、さすがにスイミングは卒業したが、遅れ馳せながら塾に通い始めた。私はずっと塾反対派で子供が持ってくる学期末の「あゆみ」すら敢えて見ることはなかった。それは私が子供の成績や学力に興味や関心がなかったからではない。学校の成績を絶対視する考え方が私の気に入らなかっただけである。その点でも妻と意見が異なった。しかし、学校の先生というものは、児童や生徒の成績に関し、自分の裁量でどうにでも数字をつけてしまうものだし、そうできるものだ。そんな物差しで評価を受けた子供が、それで一生を決定づけられるなんてことはあってはならない。
塾の存在理由を認めたくなかったが、ある日近所の塾講師との会談の折り、私と共一な考え方がその講師の中に見出されたため、子供の塾通いを受け入れることになった。
しかし、あれだけ「行きたくない」と主張していたわが息子も、いざ通い始めるや、他の子供二人に混じって積極的に楽しんでやっているのが分った。その後塾の生徒も増え続け多人数となって、たぶん子供もある種の優越感を感じはじめたのだ(しかしこれはかなり経ってからのことだが、その講師は、その教え方とは別にして、多額債務者で、私にお金の無心をしたことがきっかけとなり、塾替えをせざるを得なくなった)。
息子が居間で仰向けに寝転んで、当時流行はやっていた「コロコロ」という漫画本を読んでいた。
「父さん、考え込んでんと、早よ見てやこれ」と分厚い漫画本の上に座って息子が私に催促している姿に焦点が合い、私は我に返った。
息子が持ってきたものは、学校の宿題で出された新聞づくりの材料であった。 私はパソコンに頼らずにそれを仕上げようと息子に言った。そして息子が集めた材料を睨みながら二人で手早く取りかかった。
私たちの小学校時代には、謄写版で新聞を作ったものだが、息子の宿題に結局は三時間あまりを注ぎ込むことになってしまった。それで深夜の仕事は止めにして寝てしまった。
翌朝私は久し振りで早く目覚めてしまった。この辺では珍しい鳥の鳴き声が聞こえたからだ。どうやら近くの林の梢で囀っているらしい。いつものように豆を挽きコーヒーを淹れて、しばらく自然のオーケストラの演奏に耳傾けていた。
その時私と同じ生まれの柱時計が七時を打った。その頃からわが家の情勢は一変する。息子を送り出す準備に追われ始めるからだ。その日も私が台所に立って一心不乱で朝食の用意をしていると、突然息子の声がした。
「父さん、電話」といって、台所の私とカウンターを挟んで向かいのリビングで息子が電話の子機を握って私を呼んだ。
いつしか父親をパパと呼んでいた息子が、父さんと呼ぶようになっていた。幼い子供の声が、やや太くなってき出した頃、私たちの人生も少しずつ変化していたのだ。私は一瞬のうちに現実の世界に放り込まれた。
私は雑誌の編集の樋口女史だろうと思った。もう催促の電話かよ、全く。朝早くに、おれが忙しいってことは彼女も知っているはずなのに……。
私は卵焼きを作っていたところを中断させられ、些か気分を害して電話に出た。
「はい津守です」
私は、もう少しで受話器を落っことすところだった。右手で鏝を持っていたし、子機を左手で受け取って右耳に近づけたから、耳を押しつけていた分相手の声が大きく聞こえた。声の主は全く予期しない人物だった。受話器の向こうの声は、編集部ではない別の女性の声だった。
「朝早くにすみません。私です。お・わ・す・れ、ですか?」と言葉を区切って云い、私の過去の記憶を呼び醒まさせようと促しているみたいだった。
もちろんその声には覚えがあったし、彼女と会食したときの記憶がすぐに脳裏に蘇った。
「でも……」と云って私は言葉を失った。次に出るはずの言葉を探そうとしたとき、彼女が先手を打った。
「実は今自宅にいるんですが、どうしても相談したいことがありまして…。(私は息子の顔やテレビのニュースの画面が見えていたが焦点は合わなかった)あなたの都合のいいときにお電話を頂けませんか」といって、携帯の電話番号を告げたので、私がそこら辺にあったペンに手を伸ばして鏝を持った右手に取り、筆記し終わるや、突然の電話の詫びを云ってそのまま切断してしまった。
私が困惑気に、再びコンロのガスのスイッチを入れてフライパンを暖めようとしてペンを落っことしたのを、息子の大貴が横目で一瞥し、再びテレビに目を移すのが見えた。一瞬私と父が入れ替わって、私が息子になって、息子の朝食を料理する父親の顔を見ているというような錯覚に陥った。きっと息子は何かをつかんだはずだ。私が嘗かつてそうであったように…。
息子はいつものように、カウンターに差し出されたご飯とおかず、味噌汁等をいつものように機械的に取って自分の前に並べ、黙々と食べ、時間が来たらさっさと鞄を持って出発して行った。いつもの「行って来ます」という声が心なしか弱々しく響いたので、玄関の水槽の熱帯魚もまるで勢いを失ったかのように深く沈んでいるように見えた。なぜか私は普段はしないのに子供を玄関先で見送っていた。そして階段を二階に上がりながら息子の去った一階の玄関の小窓の所に、かつて妻が飾ったトールペイントの置物を暫く見下ろしていた。自分の食事を終え、片付けをさっさと済ませると、冷蔵庫の中の物を確かめた。
えーと足りないのはタマネギとレタス、卵とベーコン、それからとつぶやいているうちに、我ながら自分の今の所作について、ある嫌悪感を抱いた。自分は一体今何をしているんだろう……….。そんなことを考え、沈んだ気持ちになっていると、父親の顔が浮かんできた。
父は戦後満州から約二年遅れて引き揚げて来たが、結婚するまで数年間は、傘張りの行商をはじめ、雑多な仕事をして生計を立てていた。
その後、郷里に落ち着いて林業の定職に就いた。田舎では多くの職種があるわけではない。私が物心ついた昭和35年頃は村役場の中で仕事をしていた。
その頃はまだ視力はそんなに衰えていなかったと思う。ラビットというスクーターに乗って通勤していたが、道は舗装とてない当時の砂利道で、たまに私が後ろに乗って走行中、よく砂利の上でタイヤが滑り、転けそうになったことを思い出す。
冷蔵庫やテレビのない時代には不便なりに充実した何かがあったはずだ。今私は果たして過去より充実した日々を送っているんだろうか。水槽の魚に餌をやると、母に電話をしてから車で出かけた。買い物のためではなく、とにかく家の外に出たかったのだ。彼女の電話のことを忘れていたわけではない。愛車のレガシーワゴンに乗って、FMから流れてきたバッハのG線上のアリアに聞き惚れていると、彼女の優美な姿形が徐々に蘇ってきた。
と同時に、なぜ彼女に私の自宅の電話番号が分かったんだろうか、という単純な疑問がそろそろ頭をもたげ始めた。
私はこう考え始めていた。つまり、彼女自身が、編集者の樋口女史の親友か何かで、私をうまく引っかけようと、悪戯をしていたのじゃないかと。それであれば、疑問は一気に解決だ。「なーんだ、そうだったのか」樋口女史のあの独特の表情豊かな、からかった後の笑い顔が浮かんだ。そういえば、彼女から何も云ってこないのも不思議だった。今頃催促の電話があっていいはずだ。私は、スーパーではなく、私がいつもそう呼んでいる「緑の図書館」に向かっていた。
かなり走った後で、いつしか私の右足はブレーキペダルを踏み、車はハザードを出し、道路脇に停車した。ルーム・ミラーに映る景色を見ながら私はつぶやき始めた。
思考を整理するため、私はよくそうやって想念を脳の外に出し、一つの形として具現化する方法を取る。そのとき私の目に映る景色は、植物の光合成のようにある効果をもたらす。私は腕をハンドルにもたせかけ、時々額をハンドル上部にこすりつけながら、回想とも夢想ともつかないようなものにしばらく身を委ねた。何カ所か欠落して意味がつながらないパズルのようなもどかしさを感じていた。
しかし意味はやがて判然としてくるのだろう。私は携帯電話を取り出して、一度樋口女史に確かめておこうと思った。女史のケータイに電話すると、すぐに彼女が出た。今どこにいるかを確かめる前に、今回の原稿の最終稿が終了した旨、次の取材についての打ち合わせについても簡単に用件を言った。
彼女はまず驚いていることが声の調子で分かった。それはまず私からこのような電話をするようなことは普段はないからだ。それで追い打ちをかけるように私は一方的に彼女に謎を掛けてみた。
私がこの間、梅田で唐突にある人と出逢ったこと、今日やはり唐突に電話がかかってきたこと。ややゆっくりと彼女の反応を確かめながら喋った。彼女が会話でどんな仕草、癖を持って話すかを私はある程度知っていた。
一通り聞き終わると、しかし意に反してというか、彼女の反応はまるで肉親が、へえ人生、偶にはそんなこともあるんだ、という感想にも似たような反応でしかなかった。私は実際、がっかりした。
彼女は今、京都の国際会議場に同僚の木村と同行取材に来ている、仕事が終われば大原に足を延ばして三千院を見ておきます、と付け加えた。たぶん最近の放火事件の取材が目的なのだろうと察した。彼女の会話には些かも冗談や冷やかしといった類たぐいの言葉は含まれてはいなかった、私の推測が正しければ。彼女は私の創作したストーリーの上では白だった。先生土産を買って行きますねと元気な声で云ったので私は余計に良心が咎めた。
それよりももっと、私は、「彼女」が私の電話を待っている、という一事が気になり始めていた。ジクソーパズルなら部分をはめないことには意味がつながらない。私は再び携帯電話を取った。しかし今度はすぐには繋がらなかった。プープーと耳の奥で断続的な音がするだけで、話し中か電波状態が悪い時に発する音であった。
電話を助手席に転がしたまま再び進路を南に向け国道169号線に入った。春日野の見慣れた光景、公園の中に鹿と外国人の観光客の姿、散歩する人が鳩と戯れている光景を一瞥して、車を緩やかなカーブの道路に沿い進ませた。
私は何を思い起こすべきだったろうか。仕事のスケジュールと子供の養育、妻との思い出、それとももっと以前の、父が家長たり得た頃のことか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
