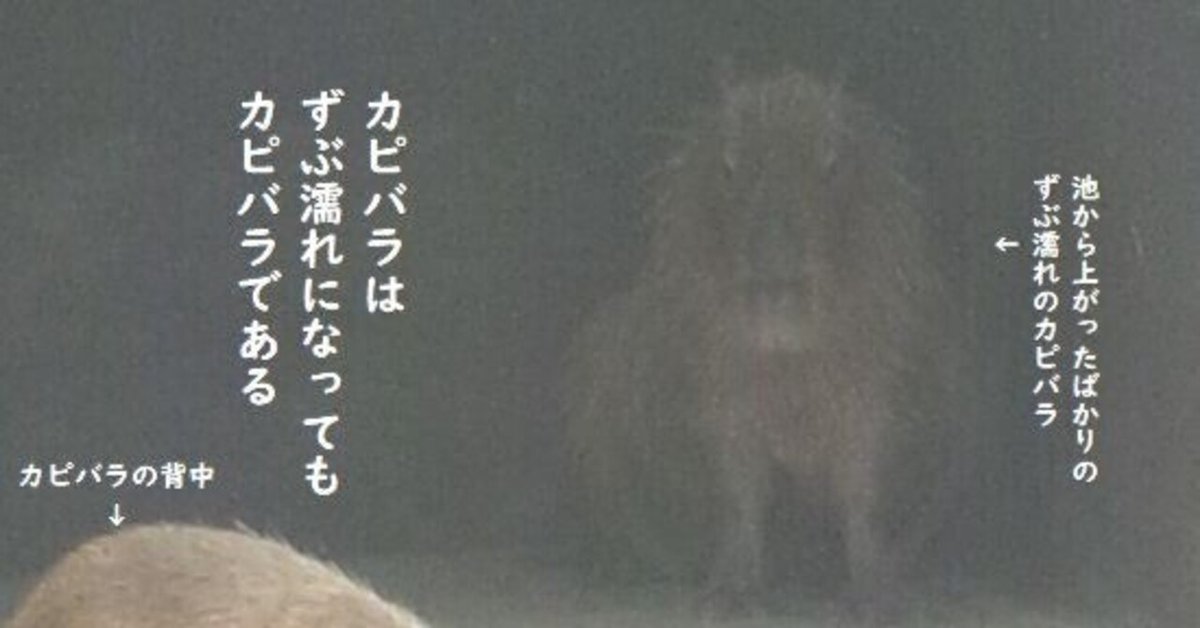
そもそもω(ω)、x(x)という関数は成立しうるのか
野矢茂樹著『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』分析(ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む(野矢茂樹著)|カピ哲!|note)の続きです。これで4章の分析は終わりです。
********************
まず、ラッセルのパラドクスについて野矢氏の説明を見てみよう。
述語ωを関数の形でω(x)と書くことにする。すなわち、ω(x)は「xは自分自身に述語づけられない述語である」という命題関数である。「xは自分自身に述語づけられない」というのは「x(x)ではない」ということにほかならない。それゆえ、こうなる。
「ω(x)」は「x(x)ではない」に等しい。
ここで、ラッセルの指示に従って変項xにwを入れる。すると、こうなる。
「ω(ω)」は「ω(ω)ではない」に等しい。
かくして肯定と否定が等しくなってしまう。これは矛盾となる。
・・・「xは自分自身に述語づけられる」という文章自体がナンセンスになるか、見せかけの自己言及(同じ言葉を違う意味で用いることで自己言及文のように見せかけているだけ)か、単なるトートロジー的説明になってしまうか、どれかであることは前章で説明した。そもそも上記の論議自体が成立しないのである。
もちろん、述語ωを関数の形でω(x)と書くことができるのか、という問題もある。述語ωとは「曖昧(である)」とか「犬(である)」とかいう具体的な言葉(あるいは意味・対象を伴う言葉)である。ω(x)と書き換えたとき、ω(x)=「~は自分自身に述語づけられないような述語である」という論理に変化している。
つまり述語としてのωと関数としてのω(x)とはωの文字が一緒だとしても全く別物なのである。同様にω(x)の x も ω になりえない。xは特定の言葉が入る場所、ωは「~は自分自身に述語づけられないような述語である」という関数なのである。つまり x にωを代入するということ自体、(先に示したような)ニュアンスの恣意的な変更であるのだと言える。
「xは自分自身に述語づけられる」という命題関数をx(x)と表記するのも同じである。xと文字は同じでも、それが表現する意味合いが全く異なるのである。まさに下記のウィトゲンシュタインの指摘のとおりである。
二つの関数に共通なものは文字「F」にすぎない。だが文字はそれ自体では何も表さない。
(この点についてはウィトゲンシュタインの考えと少し異なるかもしれないが)文字そのものが指し示す対象がいかなるものか、そこを正確に把握すれば自己言及文が見せかけのものであることが露呈するのである。
正確に関数として表現するのであれば、
F(x,y)=「x を y に述語づけることができない」
G(x,y)=「x を y に述語づけることができる」
そしてF(x,y)≡¬G(x,y)、さらに F(x,x)≡¬G(x,x)となるだけである。述語づけられないものは述語づけられないし、述語づけられるものは述語づけられるのである。
しかしいくら論理をこねくり回したところで、述語を述語づけるということが実際に出来るのかと言えば、(既に説明してきたとおり)できそうにもないのであるが。
一見自己言及文に見えるものは、実はF’(F)であり、決して自己言及文ではない。
・・・とウィトゲンシュタインが言うように、自己言及文に見えても実際のところ自己言及文ではないのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
