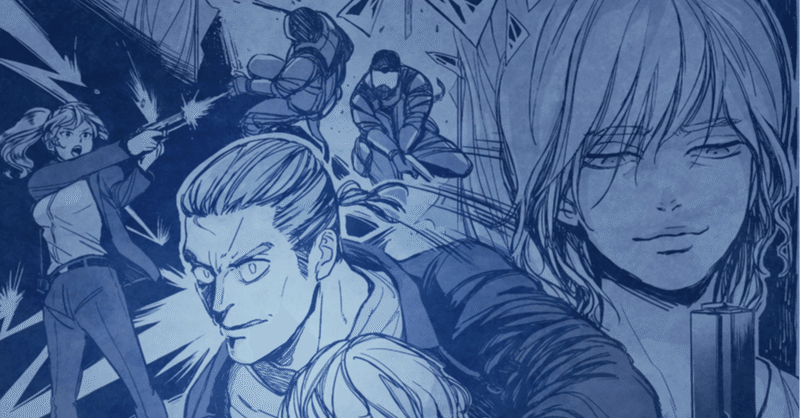
簒奪者の守りびと 第一章 【5,6】
第一章は8シークエンス構成です。4日連続更新。
<4,000文字・読むのにかかる時間:8分>
簒奪者の守りびと
第一章 ジョンブリアン
【5】
ミハイの一族が代々統治してきた王国。名をドニエスティアという。
地理区分では東ヨーロッパに含まれる。この地域の国々の多くがそうであるように、ソビエト連邦に飲み込まれたあと、91年に独立を果たしている。
東のドニエ川、西のプルタ川というふたつの流れに挟まれた地域が国土の大半を占め、北には山脈が連なり、その尾根のひとつが北部国境を成している。南側は黒海に面し、ふたつの河口はデルタ地帯となっている。
もともとヴィクトル・ネデルグの一族は、王都より西寄りのドロキア地域を領地としていた。西の隣国との関係は良好であったから、前線たり得ないネデルグ領は常に平穏であり、中世には王都を凌ぐ発展をみせたことさえあるという。
そのネデルグ領の新たな領主となったのは、クリスチアン・ネデルグ、すなわちヴィクトル一世の長子である。
「2名死んだそうだな」
声を低く抑えたつもりのクリスチアンだったが、タイルとコンクリートに囲まれた屋内プールではその努力も虚しく、反響して増幅された。ここが彼の屋敷でなければ、何人かが驚きの視線を投げかけたに違いない。
「しかも死んだのはドロキア兵だ。傭兵のほうならまだしもよ。それでいて成果なしってのはどういうことだ? なあ」
彼はゴールデンイエローの短髪をタオルで擦りながら、ハンズフリーにした携帯通信端末からの返事を待った。筋肉の低いところに小さな流れができている。
『……でもさ』
クリスチアンは内心で舌打ちした。
『あんまり派手に立ち回るとまずいじゃないか。国民の目に触れないようにするには……』
「気づかれたんなら撤収すりゃいいじゃないか。強行するから返り討ちに遭う」
『そうだけど。でも兄上が殺せって』
「でけぇ声で言うんじゃねぇよ。そういうとこだぞ。アウレリアン」
『ああ……いや、ごめん』
「お前な。相手は十二歳だぞ。お前はいくつだっけ?」
『……二十三』
「立派な大人だろうがよ。いまやお前だって王太子なんだからな。この国の紛争の種を未然に取り除くのは、仕事のうちだと思えよ」
投げ捨てられたタオルが、音もなくタイルの上に広がる。
「オレはこれから王都に向かう。親父には適当にごまかしておけよ。夕食が説教タイムなんてのは勘弁しろよ」
『あ……ああ。待ってるよ』
携帯端末を鷲掴みにし、更衣室に向かって歩き出しながら通話を切断する。どうやら出発前にアルコールが必要になるだろうなと、彼は思った。
◇
ミハイをオリアに託して、ラドゥは外へ出た。警護対象が眠っているわずかな時間を自由に過ごしても罰せられることはないはずだった。それに、この界隈の景色を、多少の感傷を携えて歩いてみようと思ったのだ。学生時代の彼が過ごしたアパートは、ここから目と鼻の先だった。
ひとしきり歩いたあと『青い日傘亭』というカフェテリアに入った。幸い、最も気に入っているテラス席が空いている。トカナとグラスワインを注文すると、ウェイトレスはろくに返事もせずに下がっていった。
通りに面しているが植え込みが高く、外からの視線に晒される心配はない。中庭のようなこの空間を、ラドゥは王立大学の生徒だったころから気にいっている。テラスにはテーブルが三つ。いずれも濃い青色のパラソルが日差しを遮っている。
ウェイトレスではなく、老店主がワインを運んできた。
「おひさしぶりですね。ニクラエさん」
小さな丸眼鏡から、目尻のシワがはみ出ている。
「どうも。懐かしい景色というのは眺めたくなりますね。お元気そうで」
「おかげさまで。この時間はもうイングリッシュマフィンをお出しできなくて。なんだか申し訳ない」
「いや、気にしなくて結構。他の料理でもじゅうぶん美味いから」
「他の料理”でも”ですね」
老店主は笑った。ラドゥは言葉につまった。
「やはりお焼きしましょうか」
「お気づかいありがとう。しかし、やはり朝食として食べにきますよ。もし仕事がやっかいなことにならなければ、明日」
ラドゥがグラスを傾けながら老店主の背中を見送ったとき、携帯に着信があった。画面には「中佐」の文字。ラドゥは反射的に立ち上がる。テラス席に他の客の姿がないのは幸いだった。
「はっ。ニクラエです」
『馬鹿息子たちがまた迷惑をかけたようだ』
バスバリトンの美声。戦場でこれを聞くたびに膝の震えが止まった。
「とんでもございません。陛下の大切な兵士を傷つけてしまいました」
『詫びるには及ばない。おまえは任務を遂行しただけだ。それに、あれらは私の兵ではないよ。ドロキア出身者は平和を謳歌しすぎて鈍っているからな。常に前線に身を置いていたおまえに敵うわけがない。そのあたりを馬鹿息子たちはわかっていないのだ』
「恐縮です。陛下」
ラドゥは深呼吸をした。ため息だと誤解されないように、鼻腔を使ってゆっくりと吐く。
『明朝、トルコの外務大臣が来る。少なくとも明日は馬鹿息子たちも大人しくせざるをえまい。おまえもたまには肩の力を抜くがいい』
「恐れ入ります。しかしながら、元王太子の行動は特殊で、目を離すことができないのです」
『……あやつは賢い。私に復讐しようとしているのだよ』
バスバリトンの主は言葉を切った。ラドゥは呼吸をとめて続きを待つ。
『私を破滅させるための最短距離をよく知っている。……ラドゥ、決して死なせるなよ』
返答を待たずに通話は切れた。携帯の裏側が汗でぬめっている。
ウエイトレスがやってきて、まだ強張ったままのラドゥを一瞥し、何も言わずに料理を置いていった。皿が立てる音の大きさで、チップを渡し忘れていたことに、彼は思い至った。
【6】
「クリスチアン王太子殿下は、ドロキアを発たれたようでございます」
白い軍服に身を包んだ壮年の男が、自らの左胸に手のひらをあてた。これは忠誠を示す仕草であり、この男からそれを受ける資格のある存在は、地球上にただひとりであった。
「そうか」
ヴィクトル一世は執務室の窓辺に立ったまま、振り返らない。
「夕刻にはお着きになられるでしょう」
バラン儀仗長はメガネにかかった前髪をつまんだ。背中まで伸びるモスグレイの後髪は襟足の高さでひとつにまとめているが、前髪はそうはいかない。左右にわけたそれは、じゅうぶんにたくわえた顎髭と同じ位置まで垂れていた。だからといってそれは個人的な趣味ではなかった。儀仗長という立場が、刃物を用いることを許さないのである。したがって散髪もできない。近衛兵の指揮官でありながら、王の身辺を世話する侍従長を兼ねる、特殊な役割であった。
「ご心配ですか?」
「なにがだ?」
「クリスチアン殿下とアウレリアン殿下のなさりようが……でございます」
「……卿にしては」
後ろ手に組んだまま、ヴィクトル一世は向き直る。
「珍しく踏み込んだな」
バラン儀仗長は無言で左胸に手を当てた。
「ミハイが心配か」
「恐れ多きことながら。ミハイ殿下を幼少の頃から存じておりますれば」
「……ミハイを育ててきた卿だけは、やつを殿下と呼ぶことを許そう。しかし、この部屋を一歩出たらそうはいかぬ。気をつけよ」
「歴代の儀仗長は王ただひとりのために仕えてございます。なぜ私だけが例外でありましょう。いまや玉座の主人は、ヴィクトル一世陛下でございます」
「今夜の夕食はダイニングホールでとる。息子たちとな。下がれ」
ヴィクトル一世はふたたび背を向けた。
◇
ラドゥが「青い日傘亭」から戻ったのは、ゾフがリアガラスの応急処置を終えたところだった。幸い割れたのはごく一部だったため、粘着テープと塩化ビニール板で補強し、それを隠すために近所で入手したステッカーを貼った。
「これは?」
「おす。カムフラージュです」
「それはわかるんだが……可愛いな」
途端にゾフの目が輝いた。
「可愛い。そうですか。可愛いですよね。そうなんです、これ。妖精というかモンスターというか、架空の生き物なんです。実は大中小と三種類いまして、これは中と小です。大はサイズ的に無理なんでこの二匹にしました。小さいほうは半透明になったりするんです。けど個人的には中のほうが好きです、色合いとか、仕草とか。あ、これ、袋の中身はどんぐりで……」
ゾフは普段の朴訥さを吹き飛ばすように喋り続ける。ラドゥはそれを片手で制して階段に足をかけた。そのステッカーでは逆に目立つのではないかという疑問はとりあえず胸にしまうことにした。
好きなものを語るとき人は饒舌になるのだ、ということを学習したラドゥは、事務室のドアを開けると同時に、さらなる学びを得ることになった。
ソファに横たわる元王太子が、オリアの膝まくらで寝ていたのだ。
「一度、目を覚まされたんです」
オリアは囁くように話す。
「でも、すいぶんうなされていたので、寝ぼけているというか……」
「王子様が起こす側とは限らないんだな」
少年の目頭には水分が通過した跡が残っている。
「きみを母親だと勘違いしているのかな」
「それはないと思いますが。もしそうだとしても……無理はないかもしれません」
意外な返答に、ラドゥは茶化したくなったが、それは悪趣味だと思いなおしてやめた。
「王妃が亡くなられたのは二年前か。十歳の少年には重すぎる現実だったろうな」
頷くと同時に、オリアはミハイの横顔に視線を落とす。艶のある金色の前髪が、彼女の表情を隠した。
「ところで、リャンカは?」
「服を調達に」
「ああ、そうだったな」
ミハイの上半身は裸のまま、いまだオリアのジャケットを羽織っているだけだった。
「それはともかく、君のおかげで久しぶりにゆっくりと飯が食えたよ」
「いえ。任務ですから」
「君もそろそろ食事を取れ。交代だ」
「え?」
「交代だよ」
「本当ですか?」
なぜオリアが目を丸くしているのか、ラドゥには一瞬わからなかった。
「……いや、膝まくらはしないぞ」
ヘッダー画像は安良さんの作品です!Special Thanks!!
電子書籍の表紙制作費などに充てさせていただきます(・∀・)
