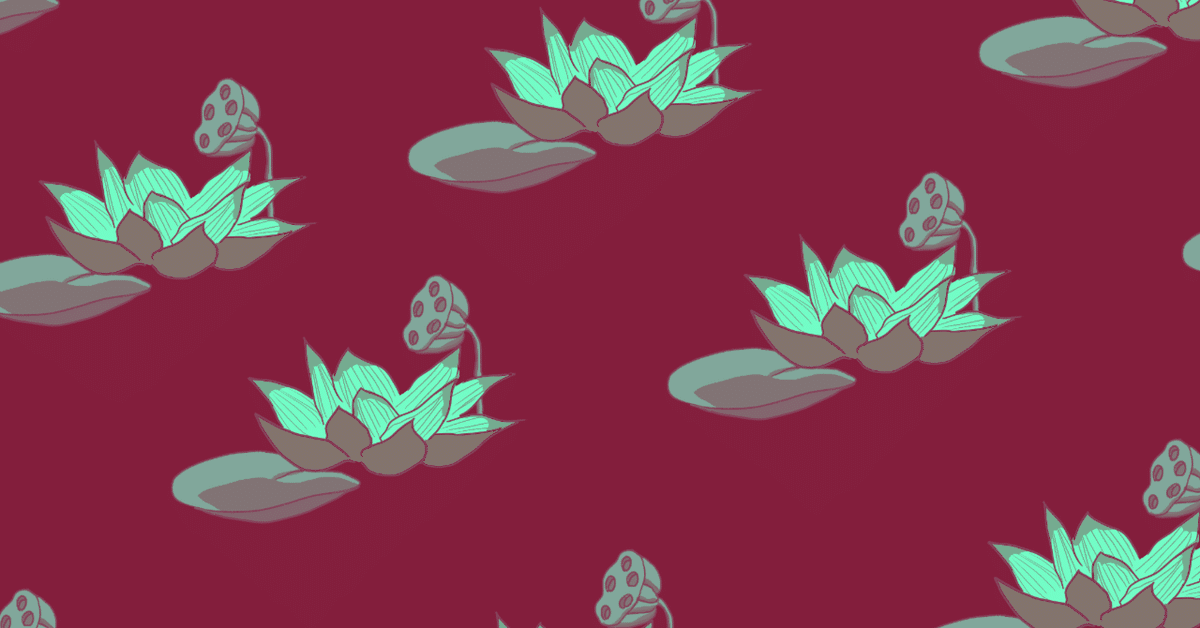
敬意と信仰~現実の歪曲
(9千文字弱あります。ご注意ください)
先日、街で声をかけられた。
誰しも、何度かは経験があるかもしれない。
一枚の新聞を目の前に差し出し、とある新興宗教団体を知っていますかと質問してきたのだ。
その人曰く、
①自分たちの宗教は絶対に正しく
②信じている私たちは成仏し、信じていない人たちは成仏できない
③日本は某国に攻められて滅ぼされるが、信仰心が篤ければそれを防ぐことができる。
だから、
④一人でも多くの人を救いたい
と言う。
また、この信仰を持つことによって、
⑤人間関係の悩みがなくなった
⑥病気が奇跡的に回復した
⑦幸せになった
のだそうだ。
そして、他の宗教についての知識はほぼなく、
⑧これが唯一絶対の真理だから他を知る必要はない
とのことだった。
たぶんその人は、教団の指導に従い、一生懸命自分を変えようとしている。私に声を掛けたのも、その一環だろう。
しかし、敬意が相手と接するうえで自分をこそ変えることにやぶさかでないということとは少し違う。
便宜上、その人をAさんとしよう。
Aさんが話してくれた要素の一つ一つが、組織としては求心力と結束力を強めると同時に敬意からかけ離れていることにお気づきだろうか。
①絶対の正しさ
敬語を使うためには「曖昧さに耐える力」が必要である。
「群盲象をなでる」という諺にあるように、人は把握できるものはほんの一部でしかないのに、それをもとに自身の立ち位置や人間関係を判断しなければならないからだ。
一方でAさんは「この宗教は絶対に正しい」という主張を受け入れることで曖昧さから目を背ける。
念のために補足しておくが、私は信仰を否定するわけではない。
ただ、「自分には真理だとしか思えない」「私はこの信仰を持ち続けたい」ということと、「これは絶対に真理だ!」ということは全く別の事柄である。真理はあるとして、果たして私の信仰はそれに沿っているだろうか、私が真理だと信じているつもりのものが、いつの間にか私の勝手な思い込みになっていないだろうかと謙虚に振り返るなら、それがどのような信仰であろうとも他者へ敬意を払うこともできるし共存が可能である。後者は敬意の阻害要因にしかならない。後者が正しい信仰の在り方なのかどうかは宗教者に委ねるが、異なるものを指して「これは絶対に真理だ!」という人同士では対立することしかできない。対立しないためには断絶しかない。多様な人々がお互いを尊重しながら生きていくうえでは必然的に摩擦を生じさせるだろう。
②絶対に得られる成果
絶対に正しいならば必ずやAさんには成仏という素晴らしいゴールが待っている。そのためには、教団の期待に沿う行動や成果をあげさえすればよいので、ずっとそこに集中できる。死ぬその瞬間までAさんはもう迷う必要がない。私に声を掛けたような勧誘活動を命じられ、もしかしたらノルマやお布施もあるのかもしれない。それでも曖昧さに悩み選択の連続とその責任を求められるプレッシャーから解放され、その代わりに絶対的に正しく報われる努力をすることを選んだ。
本来敬意は相手が変わることを期待せず、自分が変わろうとする。そのときの自分の努力は必ずしも報われるとは限らない。それは相手の自由意思に委ねられているからだ。また人間はすぐに心変わりする。いったんは報われても、すぐに覆されるかもしれない。だから敬意とは見返りがないならやらないというようなものではない。台風が来ようとも干ばつに襲われようとも農夫が畑に種をまくように、ひたすら敬意を払い続けるのだ。
③迫りくる危機の過剰な強調
日本が戦争を仕掛けられるという話は、時期的にもリアリティがあり、そのほかの問題をすべて大したことではない些末な問題だと思わせてくれるだろう。
物がきちんと整頓されていないと気が済まない強迫神経症の治療として、あえてぐちゃぐちゃにすることで、細かな物の乱れが気にならなくなる状態を作ってみせるようなものなので、一定の割合で効果は出よう。しかしそんな荒療治が継続的に行われるなら、薬物依存にも似た状態を作り出すかもしれないし、メンタルの弱い人ならかえって悪化するかもしれないことは容易に想像できる。
たとえば、信者でない妻が子どもの進学先について相談しようと思ったら、子どものために貯金していたお金を夫にすべて布施されてしまっていたとしたら、どうだろう。信者である夫にとっては日本がなくなってしまうかどうかの瀬戸際なのに学校のことなどをのんきに考えるのはナンセンスである。妻や子どものことは些末な問題の中にひっくるめられてしまう。
これは、相手に敬意を払う余裕もない心理状態で苦しんでいた人間が、相手に敬意を払う余裕もない外的な状況をセッティングされたことで自己を責め苛むことから解放されたにすぎない。
本人は苦しみから解放されたかもしれないが、周りはたまったものではない。
どちらにせよ、敬意を相手に払うのに必要な落ち着きと主体性は持ちようがない。
④この苦しみは人類の苦しみである
もしかしたらAさんは、日々、沸き起こる様々な悩みに苦しんできたのかもしれない。しかし、もうそれらは些末なこととして気にならなくなった。
もしかしたらAさんは、それまで自分に自信が持てず、生きる目的や生まれてきた意味を探していたのかもしれない。しかし、この絶対に正しい信仰を持てば、両方とも手に入れることができる。人々が知らない未来を伝え、無知蒙昧な人々を苦悩から救う救世主だ。
私の苦しみは、私が劣っていたからでもなんでもない。この真理を知らなかったからである。ならば、この真理を知らない人たちは同じ苦しみに今この瞬間もがいている。もし真理を知らないのに苦しんでいないならば、それは苦しんでいることが分からないほどに愚かなのだ。(そうでなければ私が苦しんでいたのは私のせいになってしまう)だから、一足先に真理を知った私が、すべての人々を救わなければいけない。
ここに敬意の必要性はない。Aさんが教祖に敬意を払っているように、Aさんは人々から敬意を払われてしかるべき存在であり、信仰を持たない人々に敬意を払う立場にない。本来敬意を払われてしかるべきところを無知蒙昧な人々から冷たくあしらわれることに耐えることこそがAさんにとって必要な謙虚さである。
これは、昨日までとは全く違う自信をAさんに与えてくれたことだろう。
⑤人間関係の断絶
敬語は、人とほどよい距離を取ることで、円滑な人間関係を築くためのツールである。殴ってきそうな人がいたなら、手が届く範囲に近づかなければ喧嘩はできない。逆にもっと知りたいと思える人とは、少しずつ近づいて、お互いが気持ちよい距離を見つける。それは人の判断と都度の調整だから、うまくいかないこともある。双方の思惑が違えば、一方は距離を取りたくても相手が迫ってくることもある。逆もまた然り。
そんな人間関係のトラブルを一切なくそうと思ったらどうすればよいか。
最初から人間関係を作らなければよい。
歯が痛ければ歯を抜き、頭が痛ければ頭をもぎ取ればいいと言っているようなものだが、人間関係の悩みがなくなったAさんは何と言っていたか。
敵を作る
Aさんは、某国が攻めてくると言った。(これを便宜的にB国としよう)
B国を敵と認めさえすれば簡単に味方になれる。そう言っている人がどんな人なのかを知る必要はない。
「B国は敵だ!」
「そうだそうだ!B国は敵だ!」
お互いのことを何も知らなくても、これで仲間だ。
支持率の下がった国家元首が使う手法でもあり、ストレスで破裂しそうな子どもが使う手法でもある。
「B国を擁護するなんてお前はB国のスパイだろう!」「Bちゃんの味方するんならBちゃんと同じ目にあわすぞ!」と言われるぐらいなら一緒に「敵だ」と言ったほうがいい。それ以外の人となりは何も求められないのだから、それまでどれほど批判をしていたとしても関係ない。「B国は敵だ!」と言えば改心した素晴らしい仲間として受け入れてもらえる。言えば言うほど高揚感は大きくなり、撤回するハードルは高くなる。そして人間というものは、言い続けていればだんだんそう思えてくるようにできている。
決められたことだけを話す
通常、職場では仕事の話をする。余計なことを話して人間関係がもつれて仕事に影響が出るのは避けたいので、対立が起きがちな宗教、政治、野球(今ならサッカーもか?)の話は雑談の話題としては避けられる。また結果オーライで結婚の報告はみんなも喜んでくれるが、社内恋愛を大っぴらにできるところは少ない。
そうは言っても、昼休憩を一緒に取ることや歓送迎会や忘年会などで互いを知り親睦を深めようという方向もある。
自分の意見を言ったり反論をする必要もある仕事において、事前に言いたいことを言いやすい人間関係を作っておきたいからだ。
このように、幅はあるにせよ通常は円滑な人間関係のために個人的な付き合いをある程度は推奨し、同時に場を乱さない程度に抑えるというバランスを取っている。バランスを取ることは容易ではなく、それに失敗している職場もあれば困っている個人もいるのが実際のところだろう。
一方でAさんは、初対面の私に教義を延々と話す。
「なぜあなたはそれが正しいと思ったのか」と質問してもその根拠となる教義の話が続く。スラスラと口を突いて出てくる長文は、これまで何度も何度も同じ内容を繰り返し話してきたことを示している。
教団内の人との会話も同じだとしたらどうだろう。
一人が教義について話し、他方は「そうだよね。すごいよね」と相づちを打つ。この教義が絶対に正しいと受け入れている者同士の会話に否定も反論もない。自分のことは教義が正しかったという実例としてのみ伝えれば、周りからは称賛しか返ってこない。自分という存在は教団という母胎に回帰し、教義の羊水に溶けていく。自分の顔や名前は消えていき、一体感だけが残る。人間関係のこじれようがない。
人間が抱える悩みの多くは人間関係の悩みだろう。
それが、消え去る。
仮初めの人間関係
Aさんの話からはずれるが、以前会ったキリスト教系新興宗教のCさんは「私たちは神の国の住人だから日本の選挙には投票しない」と言っていた。
Cさんにとって日常生活は仮の姿だ。ここは本当の世界ではない。
教団内の人間関係はいざこざもなく美しいものかもしれない。そんなAさんも、信仰について知らない人間に囲まれて働いているだろう。信仰を知らない友人たちともたまに会うことがあるかもしれない。しかし、そのときのAさんは仮初めの姿であり、本当の人間関係ではない。Aさんの本質は日本を救う志士であり、謙虚な求道者であり、救世主だ。
職場で上司から嫌なことを言われても、それはもうこの世の汚さの証明でしかなく、信仰心が強まることはあっても考え直すきっかけにはなるまい。
自分の上司や同僚への敬意など、もう一顧だにすることはないだろう。
高ずれば世間とのコミュニケーションが一切取れなくなり、仕事も辞めることになるかもしれない。
断絶の完成
こんな素晴らしい真理を伝えても一向に心揺さぶられない私を見てAさんは業を煮やし、「必ずB国は攻めてくる。それだけは覚えておけ」と捨て台詞を残して立ち去っていった。
私は無知蒙昧な世間の代表として敵視され、Aさんは早く教団内の居心地のよいコミュニケーションに戻りたいと思ったことであろう。
そして教団に帰れば、なおのことこの無知蒙昧な一般市民を救う使命に燃えて勧誘活動に熱が入り、結果として世間とのコミュニケーションの断絶を感じ、教団への依存度が高まるという循環が無限に続く。傍から見れば悪循環だが、信仰心が強まるので組織から見れば好循環だ。もちろん、何人も声を掛ければ、そのうち何人かは信者になろう。どっちに転んでも教団としてはメリットしかない。
⑥現実を教義に合わせる
どっちへ進んだらいいのか分からないのに歩き続けなければならないような不毛な現実から逃れたAさんは、教祖の指示に従って努力をすれば必ず報われる世界にやってきた。迫りくる危機に対応しなければならないので、些末な問題にかかわっている暇もなくなった。今までの苦しみは嘘のように消え去り、約束された希望だけが目の前にある。自分が話すことは常に仲間から肯定され、会社の上司とは違い目上の人は正しいことしか言わない。
こんな素晴らしい世界を成り立たせているのは、この宗教が絶対に正しいからだ。この正しさを疑うことは、この世界を失うことを意味する。だから、教義と矛盾する現実を認めない。教義を支える現実のみを事実として認め、そのように解釈する。
これを、先とは別のキリスト教系新興宗教のDさんは「神中心感謝思考法」といい、教団内で推奨されていることを教えてくれた。これを「神中心」ではなく「教祖中心」や「教義中心」などと置き換えれば、きっと多くの教団に当てはまることだろう。
Aさんは、病気になったものの信仰のおかげで奇跡的に治ったと言った。医者も驚いていたと。
その話が嘘だとは思わないが、原因が信仰であるとは限らない。
私が大学入学直後に体験した話をしよう。
不安だった私に声を掛けてくれた大学生から「うちへ遊びにおいでよ」と誘われて行ったところ、複数名の大人に取り囲まれて、この教団に入れば何でも叶うと勧誘を受けた。そのときにも健康についての話が出ていた。人の悩みのうち、人間関係の問題と並ぶ大きな悩み事だからであろう。
曰く、
・ある人はこの教団を辞めた直後に事故に遭った
・ある信者は事故に遭っても奇跡的に軽傷で済んだ
というようなものだ。
このような話を十も二十も聞かされたが、これ以上書く必要はあるまい。
両方とも「事故に遭った」という事実は変わらないが、ある人は教団を辞めた「から」事故に遭い、ある人は信仰のおかげで事故に遭った「のに」軽傷で済んだのだ。事実は一つでも、解釈次第でいかようにも色付けはできる。
Aさんは「B国が必ず攻めてくる」と言った。本当に攻めてきたならAさんは教祖への信仰をなお一層強く持つことだろう。しかし、攻めてこなかったとしても信仰はいささかも傷つかない。「教祖のおかげ」「皆の信仰のおかげ」で防げたのだと祝えばよい。
さて、このような考え方のどこが敬意に反するのだろうか。
敬意とは、相手を変えようとせず、必要であれば自分を改めることである。この相手とは、人に限らない。現状をありのまま受け入れ、自分をこそ変えるということが本来で、それを人間関係に当てはめたときに「相手を変えようとせず」になるというだけの話だ。
果たしてB国が攻めてこなかったときに「教祖のおかげだ」と思ったとして、自分を守っているわけではないとAさん自身は思うだろう。
しかし、そうではない。
例えば、こんな親がいたらどうだろう。
「うちの子」に問題はないと考える親
「うちの子が手をあげたのは、〇ちゃんが悪口を言ったからですよね。〇ちゃんから先に謝るのが筋じゃありませんか」
「うちの子が勉強できないわけないじゃないですか。それなのにこんな点数を取るなんて、いったい学校は何をしていたんですか」
この親は自分がわがままだなどとは思ってもいまい。うちの子に問題があるはずがないのだから、何か問題があるとすればそれはうちの子以外にあるはずだというところから思考がスタートしているだけだ。本人は、子どもを守る素晴らしい親だと自認しているかもしれない。しかし、周りにいる人はこの親を見てわがままな人だと感じ、対応に苦慮することだろう。少なくとも周囲への敬意に満ちているとは思わないはずだ。なぜなら、本来必要のないこと(先に謝る、業務範囲外の補習など)をするか、その親の言うことを突っぱねるか、どちらにしても不本意な選択をしなければならなくなるからだ。
では次に、こんな会社員がいたらどうだろうか。
自社商品は完璧だと考える社員
「うちの商品は完璧なのに買わないなんて、この客の目は節穴だな」
「うちの商品よりも、ライバル社の商品が売れるなんてあり得ない。きっとライバル社が実績を水増ししているだけだ」
こんな社員がいたら、それが熱血であればあるほど、社内は困ってしまうだろう。
もし会社丸ごとこんな考え方をして客に対して怒りをあらわにし、ライバル社を公然と批判するような会社が実際にあったとしたら、ニュースになるであろう程の迷惑な話だ。
通常は、こんな会社はあり得ない。なぜならば、どの会社も社会の中で成り立ち、社会に共にいる人たちを顧客や取引先としているからだ。
一方で自分が信じている宗教が絶対に正しくなければならないAさんは、教義上間違っている現実社会に対して、このように考えることを遠慮する必要はない。おそらくは教義上も無知蒙昧の輩として定義づけられ何かしらの名前を与えられていることだろう。凡夫、異端、悪魔、地獄へ落ちることが定められた人たち、などなど。
⑦幸せとは、何か
Aさんが、自身の今の状態を幸せだと思っていることは間違いない。
それでは、Aさんが感じている幸せとはなんだろうか。
いろいろと説明の仕方はあるだろうが、一つ言えることは目的と手段の勘違いだ。
例えばお金は幸せになるための一つのツールではあるかもしれないが、幸せそのものではない。もし、幸せそのものなら金持ちほど幸福度が高く、貧乏人が幸せにはなり得ないということになってしまうが、決してそんなことはない。それなのに、お金を手に入れることが目的になってしまう人がいる。100万円儲かったなら200万円欲しくなる。お金が手に入ると嬉しくて、お金を持っていると自信が持てる。昔は買えなかったものが余るほど買えて、人からチヤホヤされる。昔は人に頭を下げてばかりだったのに、今はみんなが自分に頭を下げる。
だから、1000万円欲しくなり、1億円欲しくなり、お金のことばかり考えるようになる。そのために大事な人が去って行っても、チヤホヤしてくれる人を集めて自分は幸せだと自分に証明し続ける。しかし、この人は自分に満足しているわけではない。だからいつまでたってもお金集めは止められないし、かえってエスカレートしていく。
このような人はほかにもいるだろう。例えば資格を取るのが趣味で、たくさん資格を持っているという人もいるだろう。一方、資格を持てばきっと有利な仕事に就けるはずだと思って多くの資格を取りはするものの、就職面接にも行かずに家にこもって勉強している人がいるとしたらどうだろう。
前者は、資格を取ること自体が目的だから、資格を取れば満足である。
一方、後者は、目的は良い仕事に就くことなのに資格取得に没頭している。これは結局のところ、仕事に就く恐怖を先延ばしにしているだけだ。
Aさんも、最初の目的は現実社会で幸せになることだったはずだ。しかし、それが成仏という死んでみなければ分からないようなものにすげ替えられてしまった。
そして、日本をB国から救ったとしても、きっとすぐに不幸を避けるための次の課題が設定されるだろう。その課題に立ち向かうことが契約書の対価であるから、一生懸命立ち向かうほどにその契約への期待は大きくなる。
つまり、Aさんは教祖の署名が書かれた「あなたを幸せにします」という契約書をたくさん集めており、それを幸せそのものだと思っている。契約書に書かれたその実行日は死後。
それまでは、その契約書を眺めて悦に入る。
うまくいけば、死ぬその時まで。
⑧無関心
Aさんは他の宗教についての知識もなく、関心もない。
「これが間違った宗教であり、絶対に正しい宗教が他にあると分かれば宗旨替えしますか?」と聞けば、もしかしたら「する」と答えるかもしれない。
しかし、実際にはそんなことはない。それは曖昧さが戻ってくることを意味するのだから。
教義をより学ばなければならないし、教義に沿って自身を高め人々を救うために余っている時間は全て使われている。
Aさんは、時間をすべて教団に捧げることにより曖昧さに気付くことなく、絶対の世界に安住することができる。他の宗教に限らず、絶対性を脅かすものに目を向けてはならない。
いやいや、何に目を向けようともこの宗教の絶対性が微塵も揺らぐものではないのは分かっているけれども、分かっているからこそ、そんなものに割く時間はない。時は迫っているのだから。
聖なる天蓋に守られて
何も枠組みがなく、すべてが曖昧であれば人は生きていけない。
貨幣価値にしても、本来ただの紙や金属に過ぎないものを全員が同じ価値を信じることで経済が回る。
しかし、現在の社会の枠組みでは曖昧過ぎて砂漠の真ん中に放り出されたように感じる人もいる。(自分の家にいるよりも刑務所にいるほうが幸せだという人だっている)
悪いことをしてはいけないと教わったのに、悪いことをしている奴らがいい思いをしているのはなぜだ。
周りは幸せそうなのに、なぜ私はこんなにも不幸なんだ。
人間は誰も平等なはずなのに、なぜ社会はこんなに不平等なんだ。
誰も答えてくれない問いに明確な答えを与えられたとき、それに人は縋りつく。それはシェルターの役割をも果たし、時に誰もが必要とするかもしれない。
社会の枠組みと社会から避難するシェルターとしての信仰の枠組みとの間に明確な境界線はない。それでも、そこに本来の敬意があるかどうかが、目安にはならないだろうか。
そして、それは同時に、曖昧さに傷つき苦しんでいるときに、曖昧さを受け入れる敬意を求めない環境が人にとって必要なのだということを示しているのではないだろうか。
それでは、また。
世界や自分自身をどのような言葉で認識するかで生き方が変わるなら、敬意を込めた敬語をお互いに使えば働きやすい職場ぐらい簡単にできるんじゃないか。そんな夢を追いかけています。
