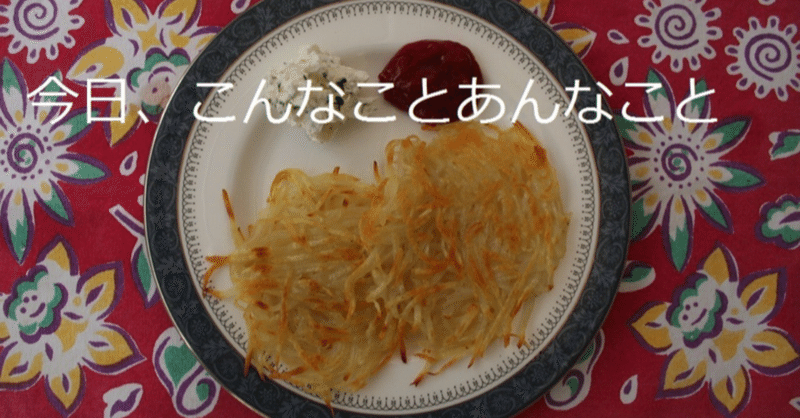
心を動かし機能を維持すること
「暇と退屈の倫理学」(國分巧一郎著)文庫本も出ているのね。
はるか昔人類はもともと狩猟で食べ物を得ていて、誰もが遊牧民であった。それが農耕により定着して変化が少ない日常となったことは、本来人間の本能とは異なること…という箇所がとても印象でした。
そうか、暇や退屈というのは、人間にとって耐えられないものなんだ。感覚的にとてもよく理解できる。停滞している変化のない日常って苦しい。平穏で安定…だけでは満足できないことが、人間には組み込まれている。
確か昔、新聞で、不活発症候群という言葉をみたことがある、ネットで調べてみると「生活不活発病」「廃用症候群」って言うのが正しいよう。災害や大病で寝たきりの後の現象などを主に指すらしいけど。私が昔新聞で見た不活発症候群は、ひきこもりとの関連で書かれていた。じっと家にこもっているとだんだん体も心もなまってくる。特に、精神面での影響が深刻だと。
体は…たとえば、寝たきりになると筋力が15%落ちるらしい…リハビリでかなり順調に機能回復する。簡易マッサージのお手伝いをすることがあって、人の身体の回復力ってすごい、と目を見張った。
精神面の回復も、体と同じと思う。ほんの少し無理して(頑張って)やってみることが、きっと大事。欝々するときも身支度を整えて出かけるだけで、精神が前向きになるきっかけになる。すっきり晴れ晴れとはいかないまでも、かなり精神の回復を促してくれる。
生きている限り、体も心も、機能を使い続けていかないとその機能が後退し、さびついてしまう。なんか、人間の一生って泳ぎ続けるまぐろみたい…。
精神面では、人と話すことが、すごく大きな役割を担っている。
買い物や飲食店で初対面の店員と話すだけでもかなり違う。こちらの意志を伝える、相手の言葉を受け取る、機嫌良いか不機嫌か相手の反応で推察する…。
ましてや交渉や雑談や身の上話や…、会話によって作動する心の機能は大きい。様々な感情…思いやりや怒りや驚きやetc…スイッチが入る。心が動くとき、それは嬉しい楽しいことばかりでないけれど、何にも感じないよりは、生きる力を発動するにはきっといい。
心の停滞という黄信号を感じたら、暇と退屈を感じない状況に置くようにして、小さくても心を動かすという試みが大切なのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
