
天皇の紋章
9月9日は重陽の節句。
陰陽思想では奇数は陽、偶数は陰であり、陽の数で最大の9が重なる日として中国の重陽節が日本に伝わり、平安時代より宮中行事の1つとなっている。またあくまで旧暦9月9日であり、正確には今年は10月4日となる。
重陽の節句の由来としては、後漢時代(西暦25年~220年)の頃、桓景という人物が故郷を離れて道士である費長房のところで武芸の修行をしていた。桓景は9月9日に費長房に帰郷せよと言われ、その通りに帰郷し、家族を連れてカワハジカミという薬草を入れた袋を腕に巻き、高みに登って菊花酒を飲んだという。
その後、桓景が家に帰ると飼っていた家畜が全て命を落としていた。師である費長房にそれを話すと、師は「主人の代わりに難を受けたのだ」と言われた。それが広まり、重陽の節句になると、高みに登り、カワハジカミを入れた袋を腕に巻き、菊花酒を飲むという厄祓いの習慣が生まれたという。
日本でも菊花酒を飲む風習が残っている。
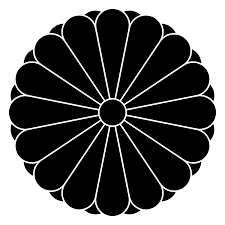
前置きが長くなったが、天皇の紋は何故「十六枚菊八重」、いわゆる菊の御紋となったか?
定説では後鳥羽上皇が好んで使い始めたと言われているが、果たして本当なのだろうか?
天皇の最古の紋章は「日月紋(じつげつもん)」といわれている。
天照大神は日の神であり、天皇は日の御子として日を重んじたことから皇室の紋章として用いられた。錦の御旗が日紋であることは知られているところである。

では菊の御紋は何故、天皇の紋章となったのか?
そもそも菊花紋の形象のルーツは古代メソポタミアの蓮華紋(ロータス文様)にあるといわれているが、それはまた別の機会に述べることとする。
いくつかの古い文献に天皇家の菊花紋の成り立ちについて述べているものがある。
江戸中期の国学者であり、律令研究家でもある荷田在満(かだのありまろ)の著書『羽倉考』では、菊花が古来より神仙の草花とされたことから、皇位を譲位し、仙洞(上皇の住まい)に移られた上皇にふさわしい紋章であることから、元来菊花紋は仙洞の標としたものを、後世にこれを混同して在位中の天皇にも菊花紋を用いてしまったという説を唱えている。これを定説に当てはめれば、後鳥羽上皇が天皇譲位したときに、仙洞御所の御印として相応しい菊花紋を用いたことを、後にこの解釈を混同し、以降に天皇の紋章として用いてしまったということになる。

また荷田とやや同時期の有職故実研究の壺井義知の著書である『文飾雑談』では、後鳥羽上皇が刀剣に菊花紋を刻印し、御袍やそのほかの御物にも用いていたことから、起源は不明であるが、後鳥羽上皇が菊花紋を最初に用いたことは認めざるを得ないと記している。
一方で、この2つの説に真っ向からの反した説を唱えていたのが、明治時代の文学博士 小中村清矩である。彼の著書である『陽春廬雑考(やすむろざっこう)』では、菊花紋は古来より朝廷に用いられており、白河院が法勝寺を建立したときにすでに軒瓦に用いられていたという。また後鳥羽上皇が鍛えた刀に刻印した菊花紋は、承久の乱以前に存在したと主張している。さらに、それ以前に平安末期の公卿である松殿其房(藤原其房)が装束に菊花紋を使っていたといわれ、天皇の紋章を臣下が使うわけがないので、後鳥羽上皇以前に菊花紋は普通に朝廷で使われていた紋章であると書かれている。
私見としては、この小中村説で法勝寺の軒瓦に菊花紋が使われていたというのは疑問であり、法勝寺は白河院が建立したのち、地震や落雷、応仁の乱などで複数回焼失しており、その都度再興はするものの、天正年間あたりで廃寺となっている。それらの背景を考えると、明治期に出土した瓦が白河院建立時のものとは断定できない。
また仮にそれが白河院建立時のものであったとしても、当時の寺院の軒瓦の文様から考察すると、複弁蓮華文の可能性が高く、それを菊花文と見間違えて判断された可能性が高いのではないかと感じる。

いずれにしても、諸説あり、起源が断定できない菊花紋であるが、天皇を示す神々しい紋章として輝く菊花紋は、
我が国が誇るべき象徴の1つであることに変わりはない。
参考資料
『羽倉考』荷田在満 著(江戸時代中期)
『文飾雑談』壺井義知 著(江戸時代中期)
『陽春廬雑考』小中村清矩 著(明治31年)
写真データ
東京国立博物館名品ギャラリーより「菊花紋蒔絵香合」(室町時代)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
