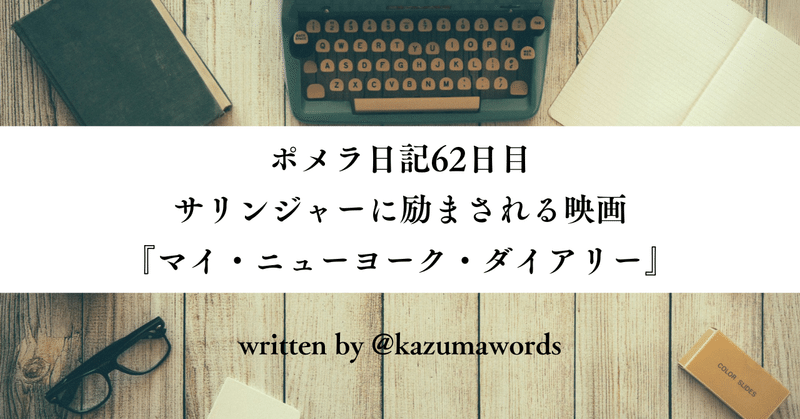
ポメラ日記62日目 サリンジャーに励まされる映画『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』
・サリンジャーが出てくる映画の話
「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」という映画を知っているだろうか?
僕はつい先日、この映画を観た。なぜかというと、J・D・サリンジャーが物語に登場するからだ。
実在するサリンジャーをモデルにした映画というのは、意外と多かったりする。
たとえば、サリンジャーの生誕百周年を記念して作られた『ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー』は、ドキュメンタリー映画として記憶に新しい。
(僕は公開時に劇場に見に行った。映画館の座席に座っていた若者は僕だけだった)
「ライ麦畑の反逆児」はサリンジャー生誕百周年のときに梅田の劇場でひとりで観たんだけど、周りは僕よりも一回りも二回りも年配の方たちで、僕と同年代のやつはそのシアター内にはひとりもいなくてそのことにかなり驚いた記憶がある。
— kazumawords. (@kazumawords) April 21, 2022
古いものだと『小説家を見つけたら』という映画がある。ガス・ヴァン・サントの映画が好きなので、学生の頃に観たのだけれど、明らかにサリンジャーをモデルにしたと思しき作家(フォレスター)が出てくる。
そのうち、文学ブログ「もの書き暮らし」に「サリンジャーが出てくる映画」をまとめようと思っているんだけれど、今日は「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」について語ってみよう。
・『マイ・ニューヨーク・ダイアリー』のあらすじ
実は邦訳された原作本が2015年に出ていて、そのタイトルは「サリンジャーと過ごした日々」(柏書房)という。

原題は『My Salinger Year』で、その名の通り、J・D・サリンジャーを巡るお話だ。
なぜ「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」というタイトルが付いているのかというと、大学院を出たばかりの主人公「ジョアンナ・ラコフ」が、ニューヨークの老舗出版社で働きながら、作家(詩人)になる夢を捨てきれずにもがく「ビルドゥングス・ロマン(成長物語)」であるからだと思う。
成長したジョアンナが、ニューヨークで過ごした日々を振り返る。彼女はかつて、J・D・サリンジャーのエージェントだったのだ。
実在する著者であり、この物語の原作者でもあるジョアンナ・ラコフは、冒頭の時点では、大学院卒の女の子で、詩人になることを目指していた。
大学で「他人の詩を分析するのはもうたくさん」と考えたジョアンナは、「昼は都会のニューヨークで働いて、夜はカフェや安アパートで執筆する」という、大半の文学部生が一度は考えそうなことを実行に移すため、出版社(アメリカなので出版エージェント)へ就職活動をはじめる。
育ちのいい、箱入り娘のお嬢さん、といった雰囲気のジョアンナが、右も左も分からないまま入り込んだのは、ニューヨークでも屈指の老舗エージェントだった。
※ちなみに作中で名前は出てこないが、この出版エージェントは実在し、1929年に設立された「ハロルド・オーバー・アソシエイツ」がモデルになっている。
「タイプライターは打てるか?」と聞かれ、とりあえず「打てます」と答えたばかりに、彼女は採用され、面接を終えてオフィスの廊下に出ると、そこには作家の肖像画がずらりと並んでいた。
J・D・サリンジャー、F・スコット・フィッツジェラルド、アガサ・クリスティ、ウィリアム・フォークナー……、と聞けばもう十分だろう。ジョアンナはとんでもない大物作家たちの原稿を手がけるエージェント会社に就職してしまったのだ。
・作家志望と文学部生の夢を次々に打ち砕く出版エージェントの現実

「出版エージェントに作家志望はいらない」と、バリバリのキャリアウーマンであるボスの「マーガレット」に何のひねりもなく否定され、タイプライターと文章の打ち方から学ばされるジョアンナ。
その次は、サリンジャー宛に届く大量のファンレターに「定型文」を返し、延々とシュレッダーに掛け続けるという、なかなか気が滅入る作業(僕だったら一日中読み耽っていそう)を任される。
しかも、ジョン・レノンを撃ったマーク・チャップマンが事件現場で「ライ麦」を持っていたという有名な一件があるので、一応、ファンレターにはすべて目を通せ、あぶないやつがいたら判別しろ、というかなりセンシティブな要求付きである。
文学部生が抱きそうな夢や希望とか、サリンジャーファンによる独特の熱意みたいなものは、出版エージェントで働くことで片っ端から潰されていくわけだけど、健気にもジョアンナは、サリンジャーファンの文面がどうしても見過ごせなくなり、彼らに報いるための行動に出る。
そんなときにオフィスから一本の電話が掛かってくる。どうせ、どこかのサリンジャーファンが電話を掛けてきたのだろうと高をくくってジョアンナは電話を取る。その相手は、「ジェリー」こと、J・D・サリンジャーそのひとであった……というストーリー。
・「君は詩人なんだろ? だったら電話番で一日を終えるな。毎日書くんだ」

登場人物に感情移入するような見方は、創作するひとはあんまりやっちゃいけない読み方らしいけれど、このときばかりはジョアンナに肩入れしたくなる。
ジョアンナは言ってみればエージェントに専属のライターであり、秘書であり、ニューヨークのような都会ならどこにでもいる文学部卒の女の子だった。
彼女がほんとうに書きたいのは詩だと分かっているけれど、実際に任されているのは電話番と会社の雑用だった。
そんなジョアンナに、サリンジャーが電話越しに語りかける。「君は詩人なんだろ? だったら電話番で一日を終えるな。毎日書くんだ」と。
映画なので、サリンジャーの台詞に多少の「色」は付いているかもしれないが、それでもこの言葉を聞いたときにはやっぱりぐっときてしまった。
書くことを諦めそうになったときは、お気に入りの作家の言葉が一番効くと思う。
サリンジャーが好きなひとは、「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」をお試しあれ。
2024/01/23 23:43
kazuma
余談:文学ブログ「もの書き暮らし」では、最近ハマっているゲーム『リバース:1999』と作中の冒頭で登場する「フィッツジェラルド」の小説の話をしています。『グレート・ギャツビー』の一節を引用してくるゲームなんて、なかなかないよね。
もの書きのkazumaです。書いた文章を読んでくださり、ありがとうございます。記事を読んで「よかった」「役に立った」「応援したい」と感じたら、珈琲一杯分でいいので、サポートいただけると嬉しいです。執筆を続けるモチベーションになります。いつか作品や記事の形でお返しいたします。
