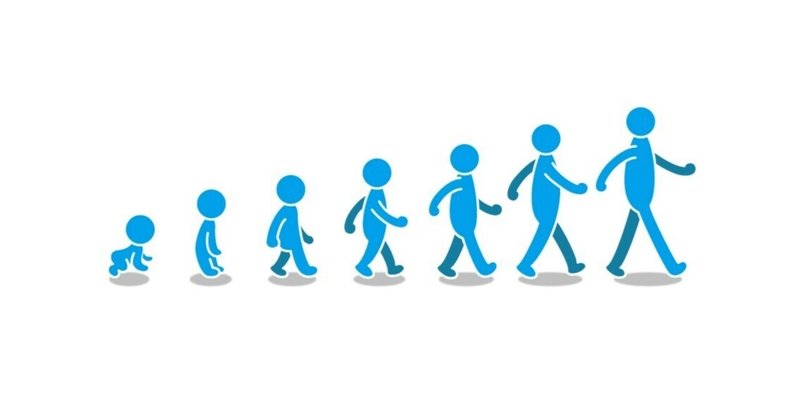
多様性×集団脳でホモ・サピエンスは勝ち残った
数週間前、NHKスペシャルでヒューマン・エイジというとても面白い番組を見ました。かつて地球上には、我々ホモ・サピエンスとネアンデルタールという2種類の人類が存在していた。しかし、ネアンデルタールは、今から約4万年前に絶滅した。一方、ホモ・サピエンスは現在地球上で大反映するまでに至った。何がこの大きな差を生んだのか?
体格・身体能力では、ネアンデルタールの方が、ホモ・サピエンスより強靭だった。脳の大きさには差がなく、この2種類の人類の知能には大きな差はなかった。言葉を使う能力、火を使う能力でも差は見られなかった。
差が見られたのは、それぞれが暮らす集団の大きさだった。ネアンデルタールは、家族単位の小さな集団で生存していた。一方、ホモ・サピエンスは、一緒に生活する集団をどんどん大きなものにしていった。
多様性×集団脳でホモ・サピエンスは勝ち残った
弓矢などに使われた石器を比較すると、ネアンデルタールとホモ・サピエンスに大きな違いが見られた。ネアンデルタールは、何万年にも渡って同じような石器を使い続けた。家族単位で生活していたネアンデルタールは、先祖が使用していた石器を、次世代に引き継ぐのがやっとだった。一方、ホモ・サピエンスの石器は、時代とともに急速に進化していった。大きな集団の中で生活してホモ・サピエンスの中には、これまで引き継がれてきた考えや、これまでの常識にとらわれない新しい多様なアイディアを持つものもいた。使えないアイディアもたくさんあっただろうが、中には画期的なアイディアもあり、何世代にも渡ってそれらを取り込み蓄積することで、巨大な技術革新となり、ネアンデルタールとは比較にならない速度で進化していった。
つまり、個々で見ると、優れた点は全く無かったのに、大きな集団を作り、多様性を大切にすることで、新たなアイディア・知識を蓄積し、集団脳、すなわち社会全体で賢くなっていくことで、体格・身体能力では全く敵わなかったネアンデルタールに生存競争で勝ったということです。
多様性×集団脳を重視する組織・社会・国しか生き残れない
このホモ・サピエンスとネアンデルタールの生存競争の話は、現在の人間社会にも、とてもよく当てはまるなと思いました。多様性を大いに認め尊重し、集団脳としてそれを知識・経験・アイディアとして蓄積し成長できる組織・会社・社会・国は、これからもどんどん元気に成長できるでしょう。
一方、多様性を認めきれず、現状維持に甘んじてしまえば、ネアンデルタールのような末路となるでしょう。管理する側から見ると、多様性がなく、わざわざ変化し続けるよりも、現状維持できた方が、短期的には楽で効率的なので、大きな落とし穴となりがちです。
特に孤立した島国である日本の出身で、その文化の中で育ち、性格的にも変化のない日常を繰り返すことを苦と思わない自分は、「多様性×集団脳」を相当な意識を持ってを実践していかねばと思った次第でした。
ジェンダーギャップ・ジェネレーションギャップ・カルチャーギャップ
ジェンダーギャップ、ジェネレーションギャップ、カルチャーギャップが十分に解消されていない組織・会社・社会・国は、この重要な多様性でとても大きな損をしていることになるでしょう。例えば、ジェンダーギャップ。ヒトの論理的・感情的思考と性スペクトラムはとても密接に関係しているので、男性社会が未だはびこっている会社・組織は、多様性の面で、とんでもなく大きな損をしていることになります。短期的に見れば男性社会は、価値観が均一で話がまとまりやすく効率的に仕事が進みやすいかもしれません。しかし、多様性を欠いて小さくまとまっているだけでは世界からは置いていかれてしまうでしょう。
多様性×集団脳で成長し続けるためには
偉そうなことを書いていますが、自分が短絡的に自分と異なる多様性を排除し、楽な方へ逃げる傾向のある人間だと自覚しているので、自分への戒めとして書いています。どうしたら、自分の多様性だけを押し通すだけでなく、他人の多様性を尊重し、多様性×集団脳を最大化して成長し続けられるかを考えてみました。
過去への執着・未来(変化)への不安を持つ自分を認める
変化しないことが最大のリスクと自覚する
自分のちっぽけさを自覚する
過去への執着・未来(変化)への不安を持つ自分を認める
人間誰しもこれまでの経験に培って生きてきているし、自分がこれまでに経験したことのない自体に遭遇すればびっくりするでしょうから、素直に、過去への執着・未来(変化)への不安を持つ自分を認めてやることがはじめの一歩だと思いました。自分の常識から外れた多様性に遭遇した時に、生じるネガティブな感情反応というか拒否反応は、とても自然なものだと認識できます。最初に拒否反応が生まれるのは当然のことであると認識できれば、その後、抵抗なく受け入れやすくなります。
変化しないことが最大のリスクと自覚する
新たな多様性を受け入れて、成長し続けると考えるととてもエネルギーのいる生き方のように感じますが、多様性を重視せず、変化しなかったネアンデルタールの末路を思い出せば、変化しないことが最大のリスクと自覚することはすぐできます。
自分のちっぽけさを自覚する
小さく考えていると、「いつも新たな多様性に遭遇するためにそれを取り入れて、集団脳として成長し続けるべし」と、とても骨の折れる、エネルギーをいる生き方のように感じます。でも、全人類で考えてみたら、大自然の中にいる自分の存在を考えてみたら、自分がいかにちっぽけな存在で、自分の中で何がどうなろうと、地球にとってはびくともしないとるに足らないことだと思えて、気が楽になります。上手くいく時もあればいかない時もある。ただ、自分のやれる範囲で挑戦していこうと気楽に考えられるようになります。
と自分を戒めながら、多様性×集団脳で少しずつでも成長していきたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
