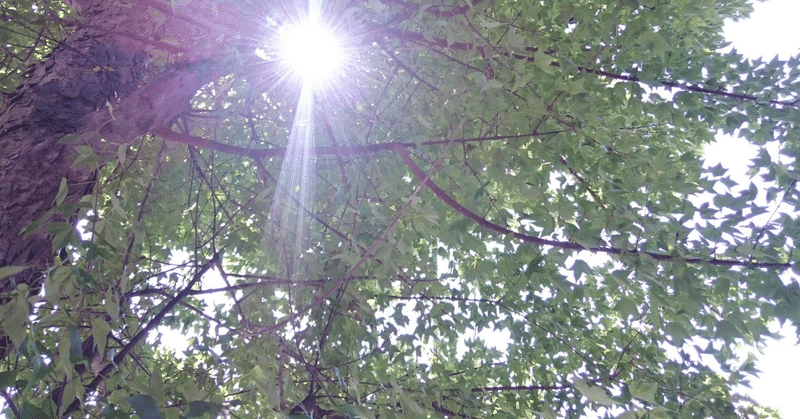
価値の森:生態系的システムの多様性のメカニズム
はじめに
生態系的システムが繁栄するためには、多様性が重要な要素となっています。この多様性を支えているメカニズムとして、「価値の森」という考え方を提案したいと考えています。
価値に着目して考える
生態系的システムにおける多様性は、進化によってもたらされます。
進化は、環境にマッチした個体が生き残る、という自然淘汰あるいは適者生存によって時間とともに進行していきます。
このことを、価値という考え方に着目して掘り下げて考えてみます。
変異がおきて何らかの機能や性質を獲得したとします。その時、その機能や性質が、種が生き残るのに役に立つ場合と、役に立たない場合があります。当然、生き残りに役に立つ機能や性質を獲得できれば、生存能力が向上し、生き残りやすくなります。これが進化です。
この時、獲得した機能や性質は、「種の生存」に対して「役に立った」わけですから、価値という言葉で言い直すと、「種の生存」に対して「価値」があったということになります。
良く言われる話ですが、進化によってどんどん機能や性質を獲得していって、とても強い生物種が誕生したとすると、周囲の他の生物種が生存するために必要なエネルギーや資源を奪いつくしてしまい絶滅に追い込んでしまい、その結果、その強い生物種の生存もできなくなる、ということが考えられます。
このため、単に機能や性質が進化していくことが「種の生存」にとって良いこととは限らないということになります。うまく、他の種とのバランスを取って協調することができる必要があります。
もう一度、今度は別の視点で価値に着目して考えてみます。
進化によって新しい種Aが登場した時、その種Aが別の種Bの生存にとって役に立つ場合と、役に立たない場合があります。つまり、価値という言葉で表現すると、進化した新しい種Aは、その「種Aの生存」に対して「価値」のある「機能や性質」を獲得すると同時に、「種Bの生存」に対して「価値」のある種である、ということができます。模式的に書くと下記のような関係になります。
「種Aが獲得した機能や性質」
↓↓ 価値を提供
「種Aの生存」
↓↓ 価値を提供
「種Bの生存」
このようなことが起きると、自分が進化しなくても、種Aの進化のおかげで、生存能力が向上わけですから、種Bはラッキーですね。
上記とは逆のパターンもあり得ます。種Cが登場した時、既に存在していた「種Dの生存」が「種Cの生存」に対して「価値」がある場合です。模式的には以下になります。
「種Cが獲得した機能や性質」
↓↓ 価値を提供
「種Cの生存」
↑↑ 価値を提供
「種Dの生存」
そして、もっと幸運が重なると、「種Eの生存」が「種Fの生存」に役に立つ場合も出てくるでしょう。このケースも模式的に書いてみます。
「種Eが獲得した機能や性質」
↓↓ 価値を提供
「種Eの生存」
↓↓ ↑↑ 価値を提供
「種Fの生存」
価値のループが出てきました。Win-Winの関係です。
こうしてみてきたように、進化によって、その進化した種の生存だけに価値がある進化もありますが、他の種の生存との間にも、価値提供関係が生じる進化があるということです。
価値の森
種と種の間の生存に対する価値提供関係に着目すると、生態系のネットワークは、弱肉強食の側面ではなく、共存共栄の関係になっていることが分かりやすくなります。
先ほどは2つの種の間の関係だけを描きましたが、1つの進化で3つの種の間や4つの種の間に新しい価値提供関係が生じることもあります。またこの進化が繰り返されることで、種と種の間の価値提供関係は、複雑なネットワーク構造を形成していきます。
こうして形成された多数の種が織りなす複雑で緊密な価値提供関係のネットワークは、多様な生物種が共生する森のような空間を作り出します。もちろん、生物種のネットワークは特定の空間内に閉じたものではありませんが、様々な生き物が複雑な共生関係を構築しているイメージをしやすいため、この価値提供ネットワークを「価値の森」と呼ぶことにしたいと思います。
もちろん、新しい種が別の種の絶滅を招いたり、既存の価値提供関係を崩してしまったりということはあります。ちょうど、新興企業が古い企業のビジネスを破壊するようなものです。
しかし、こうした個々の進化を経験しながら、「価値の森」はその構造を変化させていきます。そして、「価値の森」全体としてより多くのエネルギーや資源を、周囲の環境から獲得する能力を得ていくものと考えられます。また、そのネットワークの複雑さと多様性が、周囲の環境の変化対する強靭さを「価値の森」にもたらします。
価値の森のもう一つの側面
実は、ここからが価値の森の話の本番です。
先ほどは、種と種の生存における価値提供関係に着目しましたが、今度は機能や性質について考えます。
新しく獲得した機能や性質が、別の種の機能や性質にとって役に立つ、というケースが考えられます。模式的に書くと、以下のような関係です。
「種Gの生存」
↑↑ 価値を提供
「種Gの機能や性質」
↓↓ 価値を提供
「種Hの機能や性質」
↓↓ 価値を提供
「種Hの生存」
もちろん、運が良ければ、機能や性質同士にも価値のループができることもあるでしょう。
「種Iの生存」
↑↑ 価値を提供
「種Iの機能や性質」
↓↓ ↑↑ 価値を提供
「種Jの機能や性質」
↓↓ 価値を提供
「種Jの生存」
さらには、2つの機能や性質同士だけでなく、より多くの機能や性質が関係する場合もあるでしょう。こうして、機能や性質の単位でも、価値の森のネットワークが広がりを持ちます。
次に、進化や変化の過程で、ある機能や性質が、もうその種の生存にとって価値がなくなるケースがあります。人間でいえば盲腸や、サルのころにはあった尻尾をイメージしてもらえばよいでしょうか。そうした機能は、種の生存にとっては無駄ですので、変異の過程で退化していくと考えられます。
ただし、不要になったからと言ってすぐに退化するわけではないので、しばらくはその機能は残り続けます。そして、何らかの事情で再び必要になることもあり、残しておいたことが幸いするケースもあると思われます。
さて、少し理屈の上での話になりますが、機能や性質同士がループ構造を有している状況で、各機能がそれぞれの種の生存に特に関係がなくなるケースを想像してみましょう。先ほどの模式図を変化させると以下のようになります。
「種Iの生存」
(価値の提供関係が消失)
「種Iの機能や性質」
↓↓ ↑↑ 価値を提供
「種Jの機能や性質」
(価値の提供関係が消失)
「種Jの生存」
機能や性質の価値のループが残りました。
この記事の最初の方で見た、種と種の生存同士の価値の提供関係のループ構造は、Win-Win関係でお互いの生存を支えあうものでした。
しかし、この機能や性質同士のループはどうでしょうか? 種の生存から分離してループ構造を有しているのは面白いですし、なんだかこのループがなくなってしまうのはもったいない気もします。
しかし、種の生存に対する価値提供関係がなくなってしまった機能や性質は、やがて退化していく運命にあります。どちらかの機能や性質が消えた時点で、このループ構造も消えてしまいます。少し残念ですね。
しかし、話はここで終わりません。
価値を維持する能力
生物種が、種と種の生存に役立つ関係を、価値というキーワードで見てみましたが、生物種が自らこの価値提供関係を認識して、選択的に価値がある関係を維持しようとしているわけではありません。
このため、先ほどは生存に役に立たなくなった機能や性質はやがて退化に伴って消えるという話をしましたが、生存に役に立つ機能や、種の生存同士のループ関係がなぜ消えないのかと考えると、その機能や関係が崩れるような変異をしても、単にその変異をした個体が消えるだけです。元の種は残り続けます。つまり、自然淘汰によって残っているにすぎません。
しかし、価値の提供関係を認識して、選択的に価値の関係を維持する能力を持った存在がいます。人間です。
人間は、自然淘汰に頼らずに、生存に役に立つ機能や性質を獲得する能力を持っています。これは、価値という言葉で考えると、何が自分の生存に取って価値があるを認識し、価値があるものを選択し、維持する能力を持っている、と言えます。この能力を駆使して、自分の生存に取って価値のある機能や性質を、増やしていき、生存能力を飛躍的に向上させていくことができたわけです。
生存に取って価値のある機能や性質の代表格が、道具です。人間自身の肉体や遺伝子に獲得される機能ではないですが、道具という身体の拡張とも呼べるものを機能させて、人間は生存能力を高めています。食料を取るための道具、寒さから身を守る道具、他の人間と情報を効率的に伝達しあって社会を形成して生産性や外部環境からの防御力を高めるための道具、などです。
道具的価値、という考え方がありますが、人間の生存にとって、こうした道具はとても価値があるものです。こうした「道具」が「生存」に取って「価値」があると認識する能力が、「人間の生存」に対して「価値」があるものとして獲得されたのでしょう。
こうした道具は、直接人間の役に立つものだけでなく、他の道具を生み出したり、維持したりするのに役立つ間接的なものもあります。このような道具には、物質的なものだけでなく、知識的なものや習慣的なもの、精神的なものもあります。
そして、これらの道具同士の価値提供関係は、人間が様々な発見や発明をしていく中で、「価値の森」を形成していきます。
その中には、ループ構造を含んだものも出てきますし、時代と共に、人間の生存にはもう不要になった、というものもあります。
この価値の森がシンプルであれば、そうした生存に不要になった道具はすぐに切り捨てればよいのかもしれません。
しかし、ループ構造を含む複雑なネットワークを形成する価値の森においては下記の理由で、生存に不要になった価値を、簡単には捨てられません。
人間は本能的に価値関係を重視する性質が強い
複雑な価値の森の構造を認識することは難しい
人によって上記の程度に差があり、コミュニティ内で意見が分かれる
さらに、以下のことも行われていきます。
実際には生存に価値を提供しているわけではないものを、バイアスにより生存に役に立った、これからも役に立つだろうと認識しまう場合がある
生存に価値があるが、間接的な連鎖があって理解が難しいものは、上の世代から下の世代に、言葉や習慣や儀式などによって「価値があるから大事にせよ」という形で伝承されていく。
このような経緯を辿って、生存にとって価値がなくなってしまったものであっても、維持されていきます。
そして、さらには、生存とは分離してしまったものたちが、複雑な価値の連鎖や循環構造を持つと、やがてそれ自体が本質的な価値を持つと認識されます。道具的価値ではなく目的価値となるのです。
こうして、価値の森の中には、多様な目的価値が生まれてきます。また、その目的価値に対する道具的価値を持つものも生まれ、そこにも価値のネットワークが形成され、それがまた切り離されて、一部が目的価値になる、そういった形で多様性を増していきます。
こうして形成された複雑な目的価値と道具的価値の森の中で、我々は生きているわけです。
そして、この価値を認識・選択・維持する能力は、人間知性の一つの大きな役割だと考えられます。
おわりに
このように見ていくと、「存在する」ということに対して価値があるかどうか、ということを出発点にして、価値の関係がつながっていき、循環構造やネットワーク構造を形成して、多様で複雑な価値の森を形成していくという姿が見えてきます。
そして、価値を判断することができる人間の社会の中では、必ずしも自分たちが「存在する」ために必要なものだけでなく、そこから分離された様々な「目的価値」を維持していることも見えてきました。
最後に少しだけ触れましたが、これらの価値を認識することが、知性の役割だという視点を提示しました。価値と知性とが、人間以外のシステムではどのように解釈できるのかを掘り下げることで、知性についての理解がふかまるかもしれません。
サポートも大変ありがたいですし、コメントや引用、ツイッターでのリポストをいただくことでも、大変励みになります。よろしくおねがいします!
