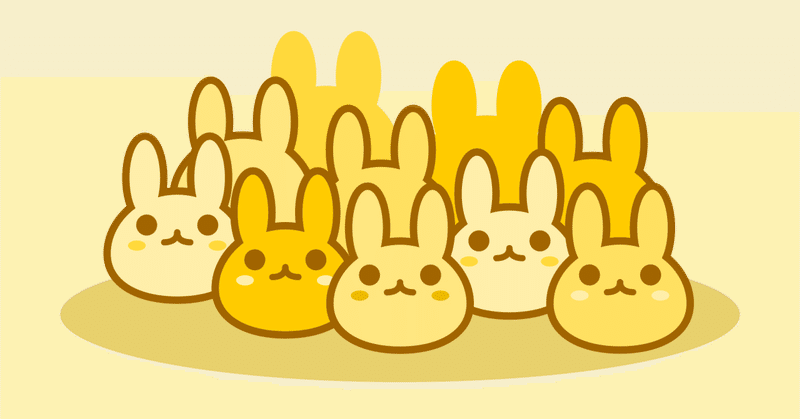
あらためて、いつも何を言いたいのかを書いておく
9月ですね。月初めでキリが良いので、毎度の話をします。僕がいつも言っていることは「人間の本能の行動様式と、現代環境のズレ」です。世の中の問題のほとんどが、それに起因していると思っています。
そのズレには、いろいろなものがあって。最近、市民権を得てきているなと思うズレは、食事です。人間は本来、このようなものを食べるべきだった、とかいう食事法が流行っていますね。糖質制限なんかは、その一派です。
ただ、これも微妙なのは、人間も1000年ぐらいのスケールでは、根本的には変わらなくても、多少は変わるんです。なので、糖質(つまり農業)に対応した身体に進化も、しているということは、ある。
つい最近、日本人の腸内細菌叢は米に対応しているという研究を目にしました。ま、そりゃそうだろうと思います。腸内細菌叢は人間のDNAとは関係ありませんから、進化というレベルでは無く、比較的、変わりやすいものだと思います。海藻から栄養を吸収できるのは、日本人に特有とも言いますし。トンガ人はタロイモからタンパク質を摂取できるから、イモだけ食べても、めちゃめちゃムキムキマッチョになります。
これはヤギとかウシも同じなんですが、草を食べてムキムキになっているでしょう。でも、草というのはタンパク質が少ないです。セルロースとかの食物繊維です。で、肉(ヤギ肉)はタンパク質です。
どうやってセルロースをタンパク質に変換しているかというと、それをやっているのが、細菌なんです。草食動物は、胃や腸に色々な細菌を棲まわせている。その細菌が、セルロースを分解して、増える。で、その細菌を吸収するわけです。細菌はタンパク質ですから。
つまり、草食動物は、腸内に「細菌養殖場」を持っており、草を餌に細菌を増やします。その細菌を食べているんです。結局、肉を食っているんです。セルロースをタンパク質に変換するというのは、細菌の仕事であり、ヤギがやっているわけじゃ無いんです。
ま、それも、現代の文化ではヤギと細菌を別存在として扱いますが、一緒と言ってもいいです。お互いに、無ければ生きられないのだから。という意味で言えば、ヤギは草を食べる、と言ってもいいんだけど。ヤギは、草を食べる細菌を食べる、という表現もできるということです。
竹を食べるパンダも同じです。あいつ、熊の仲間ですから。本当は、木の実とか小動物を食べるんですよ。でも竹だけでやっていけるのは、腸内細菌が竹を分解して、その腸内細菌を食べている(腸で吸収している)からです。日本人が米を食べるのも、トンガ人がタロイモを食べるのも似たようなもので、腸内細菌の活動により、米やタロイモを分解して吸収するわけです。
話が脇道に壮大に逸れましたが、何を言いたかったかというと、その程度の微細な適応は1000年程度で出来るんですが、そもそも人間が何を食べるべきか、とかいうのは数万年というスケールのDNAの設定で決まっています。
でも現代社会は、10年単位ぐらいで変化する。コンビニにパンや炭酸飲料が溢れている環境なんて、人間は想定していない。人間が想定している環境(数万年前のもの)では、糖質は貴重ですから、すぐに摂取した方が良い。そこらへんに糖質があるコンビニという環境を、我々のDNAは想定していないわけです。
なので、食べたいように食べ、飲みたいように飲んでいると、不健康になる。本能的な行動では、現代の環境(コンビニ)に対応できないのです。ま、食べ物の話は比較的、分かりやすいのですが。そういうズレが発生している。
別のズレとしては、これは僕が一番主張しているものですが、個人と集団というズレです。人間のDNAは「集団」で生きるように設定されている。大体、100人ぐらいの集団を想定しています。なのに現代社会は「個人」で生きるように出来ている。そのズレが、精神的にさまざまな苦痛を引き起こしている。
現代的な働き方なんていうのも、そうです。朝8時から夕方17時まで規則正しく働くこと。こんなのも本能は想定していないことです。想定では、雨の日は動かず、晴れの日は動くとか。ま、この辺も個人差があって、みんながそうなわけでは、ありませんが。
というのは、先ほど言ったように、人間は「集団」を設定されていますから、集団の全員が一斉に休んだりしたら、集団は困るわけです。活動が全停止しますから。一部は活発だった方が良い。ということで、台風の時にテンション上がるやつとか、夜型の人間とかも、少数存在するんです。
また、時間スケールの問題というのも、あります。我々の本能は、長いスパンの因果関係を感じにくい。100年後のことなんてもちろん、1年後のことだって、感じにくいのです。1年後のことを考えるという生き方は「農業」と共に発生したと思います。
農業は、せいぜい1〜2万年ぐらいの歴史です。一部、このぐらいのスパンの本能に書き換えられている人は、出てきていると思うんですけど(家庭菜園がマジで大好きな人とか)。普通は、1分後とか、1時間後とか、それぐらいの「未来」に対してしか、感情は動かない。
だから「ゲーム」は面白いんです。1年かかるゲームとか、無いでしょう。行動することと、その行動への報酬は、1分とか1時間とかの時間差です。それを面白く感じる。人間が本能的に因果関係を感じられるタイムスケールは、せいぜい、そのぐらいです。
狩猟採取のタイムスケールは、そんなものです。木の実がある、それを拾えば食べられる、その行動(拾う)と報酬(食べる)のズレは、せいぜい数秒とか1分とかです。獲物を獲るために追いかけるにしろ、せいぜい10分とか1時間のタイムスケールです。狩猟採取の時間は、そんなものです。
ですから農業的な1年後のことや、ましてや100年後のことなんて、考えられるわけが無い。考えるというか、本能として「楽しめる」わけが無い。
でも現代社会では、環境問題でも放射性物質の処理でもインフラ投資でも、100年ぐらいのタイムスケールは、当たり前に考えないといけない。そんなことは、本能的に出来やしないという問題があります。
いわゆる「理性」というのは、僕は、本能の反応ではなく、環境内でどう行動するべきかを論理的に考える思考だと思っています。という意味で「理性」という言葉を使えば、100年後のことは、本能ではなく、理性でしか考えられない。そして、理性の結論は、本能的な結論と矛盾することもある。
100年後のことを考えて環境規制しようとしたら、それによって潰れる会社も出てくる。そこで苦しむ人もいる。そういう人の苦しみを、我々は本能的に共感して感じる。その人たちの苦しみを感じると規制できない。ま、そんな矛盾は数多、出てきます。
本能と、理性。これを言い換えると「楽なこと」と「正しいこと」です。
本能に従えば楽だというのは、言い換えると、本能が想定する行動をとれば、脳や身体は快楽物質という報酬系を分泌してくれるからです。だから楽になる、幸せになる。我々のDNAが「これをやったら良いよ」という行動をとれば、単純に、楽になり、幸せになります。
一方で「正しいこと」というのは、あえて定義をすれば、人類が繁栄することだと思います。そのぐらいしか、人類の共通目標は無いと思いますので。その目標に至るための論理的思考が、理性です。
ま、その目標設定というのは、理由があるものでは無いので、えいや、っと決めるしか無いんですが。理性ができるのは、目標設定ではなく、理由なき目標設定の後の行動です。目標と現状をつなぐことです。で、人類の繁栄という目標を設定したとして、その目標に照らし合わせた時に、どういう行動を取ったら有利になるかというのが「正しいこと」です。
現代社会は、そもそも、この「楽なこと」もきちんと目指せていないし、「正しいこと」に対する共通理解も無いのですが。そこの理解が進んだとしても、必ず、この「楽なこと」と「正しいこと」のギャップは存在します。ズレているんです。
だって、我々の本能(楽なこと)は、100人ぐらいの集団での原始生活を想定しているんですから、一致させようと思ったら、原始社会に戻るしか無いんです。で、それをやらないというのであれば(やらない方が良いと思うし)、必ずギャップが存在する。
「楽なこと」と「正しいこと(人類の繁栄)」の間の、どこに「社会制度」を持ってくるのか、という問題が究極の問題です。
で、これは絶対的な正解は、ありません。環境は、技術の発展で常に変化している。インターネットがある社会と、無い社会では、環境が違います。また、大きなタイムスケールで言えば、DNAも書き変わってくるでしょう。1万年ぐらい経てば、そこそこは農業に適応した人間も誕生していると思いますから。「正しいこと」はもちろん、「楽なこと」も微妙にずれている。当然、その間の社会制度も、微妙にズレてくる。
人間がやるべきことは、それぞれの時代で、どのような社会制度を構築すれば、最も「楽なこと」と「正しいこと」を両立できるか、それを試行錯誤しながら試していくことです。
環境は変化し続けます。隕石だって、いつ降ってくるか分からないし。環境は外部のことなんで、なかなかコントロールできません。ま、技術発展により、できるだけ「環境が変化しないように」することは、やるべきことだと思います。その方が、社会制度を変化させなくて済むので、楽なんです。人間の技術は、環境の安定のために使うべきです。
ま、そんなことを毎度、色々なことにスポットライトを当てて書いている、ってのが、僕がやっていることです。9月の月初めということで、そんな所信表明を改めてしてみました。またあした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
