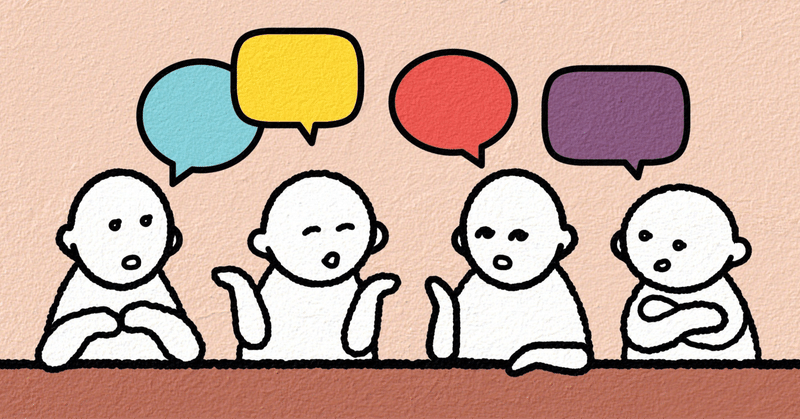
久しぶりなAIRゼミを終えて
今日は大学でのゼミのお話を。
うちのゼミでは学年別ゼミとは別に、2年生から4年生まで全員参加してもらい、Area Innovation Reviewの記事を読んでオンラインで意見交換するっていうAIRゼミを週1回のペースで実施している。
https://www.areaia.jp/article/service/61
例年は新メンバーが揃う4月からスタートしているんだけど、今年度は諸事情により5月スタートで、その初回が今朝だった。
ここ数年は、毎週アップされる新ネタ3本ほどをテーマとして、学生の希望でチーム分けをして、ブレイクアウトルームで意見交換してもらい、その内容を代表者がOneNoteにまとめ、最後に全体に共有し、それに対して僕がフィードバックするというスタイルで実施していた。
けど、今年度は、個人的な今年のテーマである、少しやり方を変えてみるってことをふまえ、全員に選んだネタに対するディスカッションを経て考えたことを簡単な文章にまとめてもらい、それを最後に全員に向けて共有し、それに対して僕が簡潔なフィードバックをするというスタイルにしてみた。
なぜそうしたかというと、発表するメンバーが固定化されていたこともあるけど、それ以上に個々人の文章力向上のためのトレーニングになればいいなと思ったから。
今回からこの形式にしてみて自分自身の変化という意味で、気づいたことが1つあった。
時間の都合上20分間で20名近くが1人ずつ書いた内容について簡単に話し、それに対して僕から簡単なフィードバックをする感じになったんだけど、限られた時間のなかでやるから、とにかく瞬発力が問われる。ただ、ここ数ヶ月、このnote投稿を続けていることによる効果が発揮されたのか、それぞれに対して比較的サラッとコメントできるようになっていた。
このサラッとというニュアンスには、これまでよりも瞬時にポイントの見極めができるようになっていたこと、とっさに引き出せる他の事例や事象等の引き出しが増えたこと、以前より手短にコメントできるようになっていたこと、などが含まれている。まだまだ改善の余地はあるものの。
これには我ながら驚いたし、これこそが継続による効果だなって実感して嬉しくなった。
だから、とにかく今年は年間300本の目標を達成すべく、地道に日々の継続を重ねたいって、改めて思った。
こういう効果もあるんで、学生のみなさんにも是非オススメしたいところ。
やると決めて、あとは何も考えずに、ただひたすら続けるだけでOKだし。
ということで、今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
