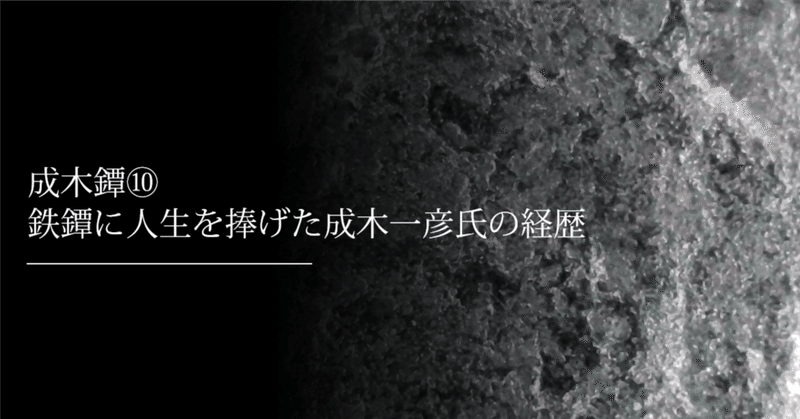
成木鐔⑩ 鉄鐔に人生を捧げた成木一彦氏の経歴
現代鐔工であり鉄鐔製作に生涯をささげた成木一彦(作家名:成木一成)さんの経歴について調べてみました。
現存数についても経歴と照らし合わせながら考察しようと思ったものの、書いていると3時間過ぎてしまって今日まとめるのが辛くなってしまったので明日にまわすことにします。
という事で今日は成木さんの経歴のみまとめました。
尚、経歴については「自家製鋼による鐔つくり(著:成木一彦)」と「企画展鍔の美 鐔工・成木一成の挑戦(岐阜県博物館)」を参考に、時系列毎に中身を補いながらまとめています。
恐らくどの資料よりも成木氏の経歴についてまとめた自信があります。

・成木一成氏の経歴
1931年(昭和6年)9月10日岐阜県中津川氏にて成木清一の長男として誕生
1945~1950年(昭和20~25年)小山富士夫・荒川豊蔵に師事して古陶磁の研究に従事
1960年(昭和35年)病の為下半身の自由を奪われ古陶磁の研究を断念。父から見せられた1枚の鉄鐔に強烈な印象を受け、鐔の研究と試作を開始。
1963年(昭和38年)中津川市実戸にて本格的に鉄鐔の製作を開始
1966~1969年(昭和41~44年)高橋勇氏より加賀象嵌技法を習得
1975年(昭和50年)頃 砂鉄を吹いて鐔の地鉄を作ろうと考え始める。それ以前は洋鉄使ってみたり、江戸時代の古鉄を集め刀匠に依頼して板状に伸ばした鉄を使用し鐔製作を行っていた。
1977年(昭和52年)第1回個展「美濃の四季を追う」を銀座松屋で開催。
美濃古陶磁にある素朴で力強い絵付けを鐔に表現。岐阜県知事より卓越技能者として表彰。
1978年(昭和53年) 自家製鋼による鐔作りを開始。紺綬褒章受章。第二回共同展「鉄蛭巻太刀拵の再現」を銀座松屋で開催
1981年(昭和56年)中津川市より鉄鐔製作技法による無形文化財保持者に指定される
1982年(昭和57年) 炭焼きからたたら作業を一貫して行うようになる。昭和57年11月~昭和58年1月まで、連日けら押し作業と記録作成を行う。採集した砂鉄、鉄鉱石は国内各地から50数か所に及ぶ
1983年(昭和58年)各地砂鉄を原料に自家製鋼により第2回個展「自家製鋼による鐔つくり」を開催。国内各地の砂鉄、鉄鉱石による鉄の比較。「自家製鋼による鉄鐔つくり」も発刊。
1986年(昭和61年)黄綬褒章を受章
1987年(昭和63年)第3回個展「柳生三十六歌仙鐔」を桑名市博物館にて開催。柳生鐔の本歌は31枚製作されたところで柳生連也が他界。その20年後に書かれた絵図には残り5点の鐔の図が不明とされているそうで、成木氏が名称にちなむ極意から考えてその5枚も製作し36枚展示。
1998年(平成10年)「日本刀のかなめ「鐔」成木一成・石田哲夫二人展」を星と森の詩美術館にて開催。
1999年(平成11年)日刀保の新作名刀展で初めて特賞(会長賞)受賞。以後毎年11回連続で同賞受賞と「企画展鍔の美 鐔工・成木一成の挑戦に記載。
2000年(平成12年)新作名刀展で特賞(会長賞)受賞
2001年(平成13年)新作名刀展で特賞(会長賞)受賞。「紫錆色の鉄肌を追い求めて 成木一成の世界」展を星と森の詩美術館にて開催。
2002年(平成14年)新作名刀展で特賞(会長賞)受賞。「成木一成の世界鉄鐔の美を追い求めて」を岐阜県博物館にて開催。
2003年(平成15年)新作名刀展で特賞(会長賞)受賞
2004年(平成16年)新作名刀展で特賞(会長賞)受賞
2005年(平成17年)新作名刀展で特賞(会長賞)受賞
2006年(平成18年)新作名刀展で特賞(会長賞)受賞
2007年(平成19年)新作名刀展で特賞(会長賞)受賞
2008年(平成20年)新作名刀展で特賞(会長賞)受賞
2009年(平成21年)新作名刀展で特賞(会長賞)受賞。無鑑査認定
2010年(平成22年)以降も毎年コンクールへ出品。無鑑査なので賞は無し。
2011年(平成23年)岐阜県伝統文化継承功績者顕彰状を授与される
2013年(平成25年)「鐔の美 鐔工・成木一成の挑戦」展を岐阜県博物館にて開催
2022年 施設にて他界
明日、成木鐔の現存数について考察してみようと思います。
今回も読んで下さりありがとうございました!
面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。
記事更新の励みになります。
それでは皆様良き刀ライフを!
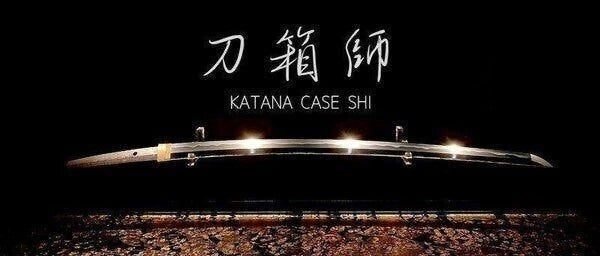
↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
