
目貫の前所有者を探る
昨日目貫の桐箱にある落款が何と書いてあるか分からない…とツイートしたところ皆様のお陰で僅か1時間あまりで読み方が分かりました。
本当にありがとうございました。
Twitter界隈の皆さん優秀すぎますっ!!

皆様のハイパーパワーのお陰で1時間ちょっとで解読されました。
— 刀箱師 | 中村圭佑 | 展示ケース作家 | 刀とくらす。 (@katana_case_shi) October 27, 2022
居瑞慈
士雲光
と書いてあるようで「慈光瑞雲居士」と読めるようです!
本当にありがとうございました🙇♂️ https://t.co/zT1fVRw5LK
という事で今回はこの「慈光瑞雲居士」が一体どのような方なのか、調べてみました。
①戒名とは?
まず「居士」とある事から「戒名」である可能性が高いと思われます。
戒名は仏門を叩いて仏道に生きることを決めた者に対し師匠が弟子に授ける名前の事で、ここでいう師匠は菩提寺の住職であり、弟子は戒名を授けられる人を指します。
つまり住職を通じて仏様の門下に入るという意味があります。
なぜ戒名を授かるかと言えば、故人が仏様の門下に入る事で、迷わずに極楽浄土に行けると考えられている為のようです。
戒名の歴史は長く、古くは中国仏教で日本には仏教と共に伝わったといいます。つまり西暦552年頃です。
もともとは故人に付けるものではなく、修行を積んで仏様の弟子になった証として生きているうちに授かるものでしたが、現在では死後に戒名を授かる事が増えました。
ただ現代でも瀬戸内寂聴さんのように僧侶の職に就き、生きているうちに戒名を授かる方もいるので、必ずしも故人に付けるものとも限りません。
②戒名の見方
「〇〇院■■△△居士」とあった場合、それぞれ以下を表すようです。
○○院:院号
■■:道号
△△:戒名
今回は「慈光 瑞雲 居士」となっています。
院号は無いので、道号が「慈光」、戒名が「瑞雲」であると思われます。
因みに「居士」は階級を表すようで、江戸時代には上級武士などが対象になっていて庶民に使用されることは稀だったと言われています。
階級が高い順に「大居士」→「居士」→「禅定門」→「清信士」→「信士」。
因みに有名所で言えば、千利休は利休居士。
しかし現代ではこれらの階級もお金で買えるようになっており、本来戒名は寺院への貢献度で決まるはずが、そうならない現状があるようです。
つまり居士が付いているからと言って階級が高い人だったとは言えません。

③「慈光」という道号について
次に「慈光」と書かれた道号について。
道号とは悟りを開いた者に与えられる称号のようなものらしいです。
現代では故人の人柄や性格を連想させる部分として解釈されるようで、故人の特徴と戒名のバランスを取りながら付けることが一般的のようです。
因みに「死」や「病」など縁起が悪い物や、反対に「笑」や「祝」など縁起が良い文字は避けるのが普通のようです。
難しそうですね…。
と言う事で、「慈光」が人柄や性格を表すとすれば、慈しみをもった温かい光のような人、といった感じでしょうか。
④「瑞雲」という戒名について
瑞雲は仏教などでめでたい兆候として現れる紫や五色の珍しい雲の事を指します。昔から縁起物として画題にも選ばれてきました。
いかりや長介さんなんかは「瑞雲院法道日長居士」のように、院号部分に瑞雲が入っていたりします。
とまぁ残念ながら瑞雲だけで個人を特定できるものではなさそうです。
因みに話は逸れますが私の所蔵している半太刀拵も漆に金粉で瑞雲が描かれています。
なんだか繋がりが見えて縁を感じます。

⑤終わりに
と言う事で今回の話をまとめると、目貫の箱に押された落款「慈光瑞雲居士」から、この目貫の前所有者は、慈しみの心をもった温かい光のような人、と第三者から思われていた人ではないかと思われます。
個人の特定までしたかったですが、現状ではこれ以上に何も手掛かりがないので分かりません。
今後同じ落款の付いた刀装具をお持ちの方との出会いなどあれば、もしかしたら進展するかもしれません。
こういった刀や刀装具の購入をきっかけに調べものをして、想像もしていなかった部分の知識が付いたりなどもするので面白いですね^^


今回も読んで下さりありがとうございました!
面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^
記事更新の励みになります。
それでは皆様良き御刀ライフを~!
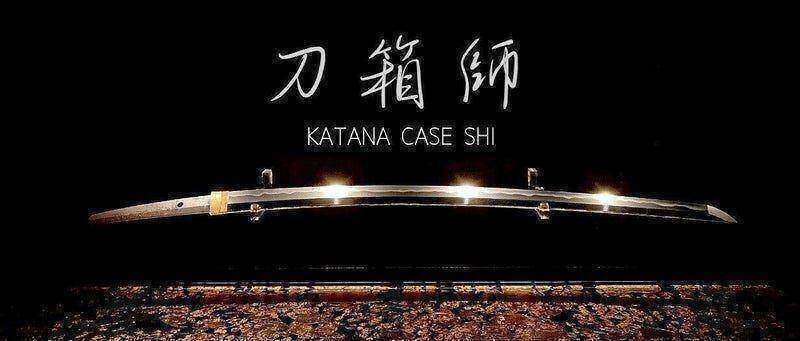
↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
