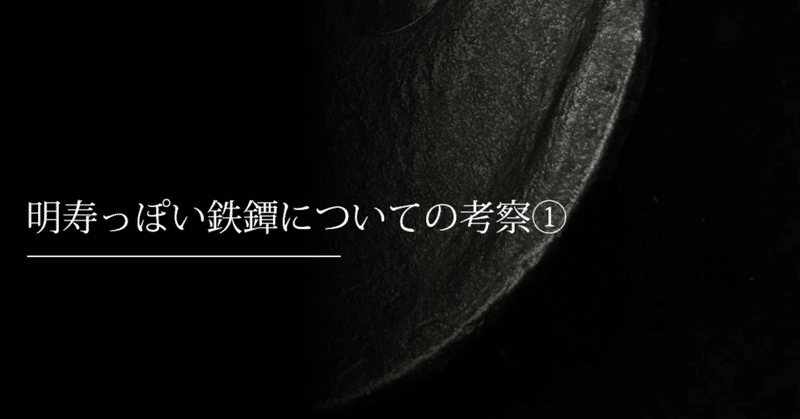
明寿っぽい鉄鐔についての考察①
先日オクにて面白そうな鐔があり落札した。
打ち返し耳が埋忠明寿かその近くの者の作と似ているような気がして頭から離れなくなってしまった。

鉄質については写真では分かりづらい所もありこれはある意味博打。
結論から言えば鉄質は手入れも行き届いており焼きなました鉄は艶もありとても良い物だった。
それがこちらの鐔。
「無銘埋忠」で保存鑑定書が付いています。





・埋忠明寿作との比較
明寿の鐔の耳はなだらかな高低差を生み出しており、それが織部焼などに現れる歪みのようであり何とも言えぬ味わいがある。
捻り耳をした明寿の鐔は真鍮地を用いた作が多いが鉄地も存在する。



因みに真鍮地の作だと以下のようなものがある。


明寿の捻り耳はなだらかになり、光忠になると段差が生まれると言うが、あくまで全体的な傾向であって明寿にも部分的には急な箇所が見られるように個人的には思う。
どちらかと言えば段差の縦横と高さ方向に緩急をつけてより楽しめる変化を生み出しているのが明寿のようにも感じる。
まさに茶器に見られる歪んだ変化ではないだろうか。
特に以下の鐔はそれを体現しており素晴らしい。

上記鐔と今回落札した鐔を比較すると高低差の変化にかなり劣りが見られるので、明寿作にしては躍動感が至らない気がしてくる。

以下は耳の拡大図である。


部分的にめり込ませるほど深く彫る事で変化を付けようとしている事が見て取れる。

・二字埋忠との比較
ここから先は
906字
/
6画像

このマガジンを購入すると過去記事も全て見れるようになります(単体購入記事以外)。初月無料なのでお気軽にご登録ください。
またまずは月に2~4回程を目標にここでしか読めないディープな内容も書いていく予定です。
このマガジンについて機能を探りながら出来そうな事をどんどんやっていくつもりです。読者限定の交流会(鑑賞会)などもやります。
刀箱師の日本刀note(初月無料!過去記事も読み放題)
¥600 / 月
初月無料
日本刀の奥深さや面白さ、購入するに当たって持っておいた方が良い知識などについて日々発信しています。 今まで820日以上毎日刀についての記事…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
