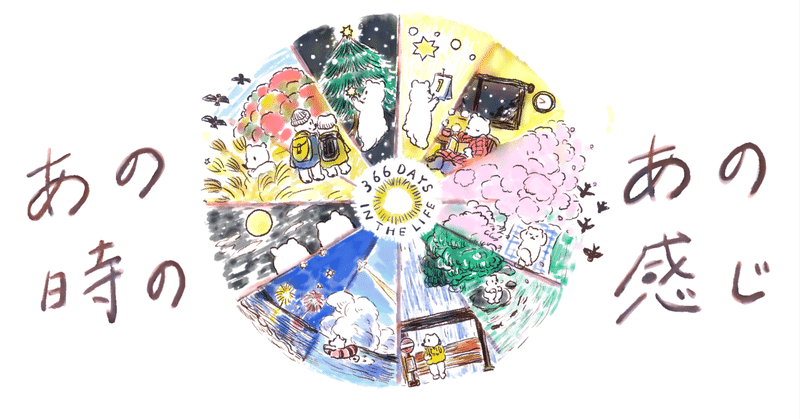
冬の日、部屋の中で火をともすときの、あの感じ|安達茉莉子
2月はまるで冬の底のように思う。少しずつ日が長くなっているはずだけれどその実感はなく、12月頃から寒い寒いといって身体を縮めて暮らしていた疲れが一気にくる。一年のうちで一番寒いこの時期は、冬の底に横たわるように暮らすことが多い。何もする気が起きず、朝も起きる気にならない。ようやく外に出たとしても、待っているのは冷たい風。時には雪すら混じる強風に吹かれながら、コートの襟に埋もれるように首を縮こめ、駅のホームで電車を待つ。こんなに寒いのに外に出なければならないなんて、何かの罰だろうか? なんとか最低限、海底を這う静かな深海魚のように息をしているだけで、精一杯。このままずっとこの底で横たわっていたい。
何ひとつ自分から事を動かそうという気にならない。時間は流れ、ただお腹だけが空く。冬の底でも、朝起きてみると窓の外は淡く光っている。曇り空を透かしてちゃんと光は届けられているようで、この弱々しい明度の低い冬の朝の光は嫌いではない。だけど息を吐くと白くなるような寒々しい食卓でご飯を食べたくはない。あるときから、食卓に燭台を置き、食事の間はキャンドルを灯すようになった。寂しさから始めたことだったけれど、食卓に火があるのは、思ったよりも良いものだった。小さくても、本物の火。みるとほっとする。ようやく人心地がして、凍らせてあったパンを焼いて、昨日の残りの野菜スープも温めて、白い息よりも皿から立ち上る湯気が多く部屋に溶けていく。
趣味で集めていた燭台が役に立ち始めた。食卓に置くのは、長野県は松本の民藝のお店で買った、インド製の黒い鉄の燭台。仕事机に置くのは、岩手は盛岡の書店BOOKNERDで展示をしていた、タカノミヤ / takanooomiyaさんの陶器の燭台。鈍く眠い冬の朝も、その燭台に置いた火を見ていると、気合いなんて少しもなくても、ただ自然と机に向かえるようになった。
ふっと息をかけて火を消したときに上がる白い煙を、窓のそとに逃すとき、外から入る風は冷たくても意外と心地良かったりする。そのままベランダに出て、遠くを眺めていると、大気はもやがかかったように霞んでいる。鈍く光る白い空。2月は何もしたくない。だけどそんな中でも光るものを集めていると、冬の底にあってもあまり侘しい思いをしないようになる。
何も自分からは行動を起こす気になれないと思っていたら、友人の美術家である山形敦子さんが滞在制作を行っている、北軽井沢にあるキャンプ場「北軽井沢スウィートグラス」に、遊びにこない? と誘われた。受動性はまだ生きていたので、誘われるがままに、のたのたと防寒服をスーツケースに詰め込み、予定していたよりも何本も遅れて新幹線に乗った。2月なのでしょうがない。
浅間山を臨むキャンプ場には、滞在2日目に雪が降った。気温はマイナス10度近いなか、サラサラした粉雪がとけることなく降り積もっていく。キャンプ場というよりも、森の中に招かれたような感覚になる。カラマツの樹や木製のコテージが、雪に包まれて真っ白になってゆく。雪が音を吸収し、静かなコテージの中で薪ストーブの火を眺めていた。火を眺めている間は、雑念も燃やされるのか、何も考えない。ただ無心に火を見て、薪の木目を眺め、重さを感じ、頃合いを見て薪ストーブに放り込む。太い薪に火がしっかりと入った頃、レバーを下げてストーブ内の空気量を調整する。薪ストーブの中で踊るように形を変える炎をみていると、自分の小さな部屋の中にある小さなキャンドルを思い出した。
生の火は小さいけれど、手をかざせばしっかりと熱いし、燃えれば煤も煙もでる。生きたもの、という感じがする。私は少しでも、生きたものに触れていたい。どんなところにいても。
薪ストーブの上に乗せっぱなしのヤカンには、ちょうどいい温度の白湯ができている。立ち上がり、琺瑯のマグカップに入れてゆっくり啜る。夕暮れが近づき、だんだん外が青く染まっていく。とろりと降り積もった白い雪が青い闇の中に浮かび上がり、それに包まれるようにいくつもテントが立っていた。雪に埋もれそうなテントの中にも灯りがともっている。前日の夜、星を見にキャンプ場の森の中を散歩したとき、氷点下のテントからは灯りと静かな笑い声が柔らかく漏れ出していた。この人たちにとって、キャンプをしにきたら雪が降ったのは、むしろご褒美だったのかもしれない。寒さも、雪を被る浅間山の姿も、テントの中の灯りも、全部。他では感じられない瞬間にある幸福を知っている人たちがこんなにいる。
そういえば、このキャンプ場を運営する有限会社きたもっく代表である福嶋誠さんと明美さんご夫妻が、着いた初日に私たちをバギーに乗せて雪の残る山道を案内してくれた。その日は晴れ渡っていて、遠く浅間山が霞んで見えた。バギーを降りて散策する。葉が落ちた冬の山の中には光が差し込み、夏とはまったく違って明るい。明美さんが私の方を振り返って、
「山の中で暮らしているとね、冬の方が樹に生命力を感じるの」と言った。
「なんといっても、こんなに寒いのに、樹はしっかり立ってるんだもの」
私は目の前の樹を眺める。何にも自分からやる気にならないと嘆いていたこの頃の私は、少し傲慢だったかもしれない。与えられるものをちゃんと感じて、自分の身に巡らせる時間は、得難いもので。何より、大自然の中にいると、自分で何もかもできるなんて思わなくなる。自然があって、自分がある。私たちは大きな世界の中で生きている。
そんなことを思い出しながら、薪ストーブの火を眺める。私の小さな部屋のキャンドルをともす瞬間を思う。北軽井沢の地で採られた非加熱の蜂蜜をちびちびと舐めながら、敦子さんが淹れてくれたコーヒーを飲む。なんでも目分量な私と、しっかり水の量を測る敦子さん。すっきりと水のように飲めるブラックコーヒーと、花の香りを口に含むような蜂蜜の甘さはよく合う。この蜂蜜の向こうには、具体的な名前をもつ土地と花、関わる人達の姿がある。歩いたこともないその場所を想う。知らないことばかりだ。冬にキャンプをする人が多いことも、蜂蜜とコーヒーが合うことも。山や森のことも。それが不思議と、希望に思える。

連載『あの時のあの感じ』について
今、私たちは、生きています。けれど、今を生きている私たちには、自由な「時間」が十分になかったり、過ぎていく時間の中にある大切な「一瞬」を感じる余裕がなかったりすることがあります。生きているのに生きた心地がしない——。どうしたら私たちは、「生きている感じ」を取り戻せるのでしょうか。本連載ではこの問いに対し、あまりにもささやかなで、くだらないとさえ思えるかもしれない、けれども「生きている感じ」を確かに得られた瞬間をただ積み重ねることを通じて、迫っていきたいと思います。#thefeelingwhen #TFW
著者:安達茉莉子(あだち・まりこ)
作家、文筆家。大分県日田市出身。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関での勤務、限界集落での生活、留学など様々な組織や場所での経験を経て、言葉と絵による作品発表・エッセイ執筆を行う。著書に『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』(三輪舎)、『臆病者の自転車生活』(亜紀書房)、『世界に放りこまれた』(twililight)ほか。
