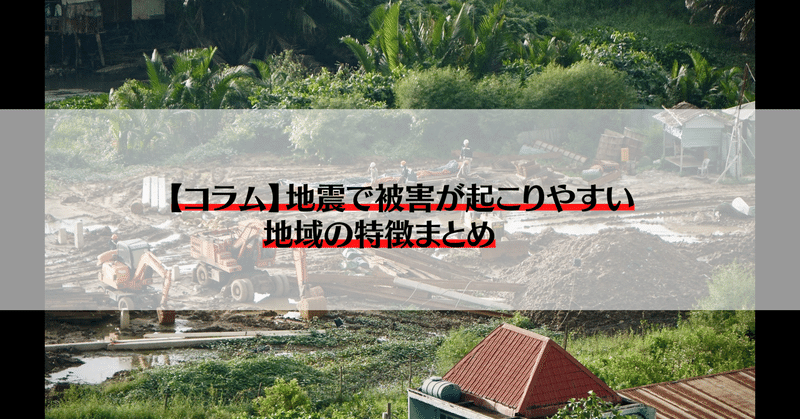
【コラム】地震で被害が起こりやすい地域の特徴まとめ
「この辺りは地盤が固いから」
「ここは地盤が緩いから地震の被害がやばい」
日頃の雑談や地域の人との話の中で、こんな話題が出てくることはありませんか。
同じような規模・深さの地震でも、地域によって被害の状況は大きく変わります。ここでは、地震で被害が起こりやすい地域の特徴をまとめてみました。
地震被害が起こりやすい地域の特徴1:埋立地
一般的に、海・河川などだったエリアを埋め立てた土地は、地震の被害が起こりやすいと言えます。
その他「液状化現象」と言って、大きな地震が起きた時に文字通り「道路が液状化」し、地盤の沈下や家屋の倒壊などを引き起こすケースもあります。
地震被害が起こりやすい地域の特徴2:海の近く
海の近くは津波被害が想定されますので、地震被害が起こりやすい地域の一つと言えるでしょう。
例えば太平洋沿岸沿いの各地域は、太平洋海溝で大きな地震があると津波の被害を受けるリスクがあります。
地震被害が起こりやすい地域の特徴3:活断層の真上
日本に無数に走る活断層。
【活断層とは】
過去に地震が発生した・またはその形跡がある断層のことを言います。活火山と同じ意味合いです。
過去に地震が発生した形跡・実績がある場合は、今後も地震が起こる可能性が残されているという理論です。この理論を基にして、重要な施設の建設は活断層の上では行わないなど様々な使われ方をします。
断層が破断すると大きな直下型地震につながりますが、この断層帯の真上に位置する家屋や地域も大きな被害を受ける可能性があります。
高齢の方などが「この辺は断層が走っているから何があるか分からない」などとおっしゃることがありますが、それはあながち間違いではないのです。
【大原則】日本はどこでも地震被害が起こりうる
まず大原則としてお伝えしておくべきことがあります。
日本は、どこでも地震の被害が起こり得るということです。
確かに地震が起こりづらい地域・起こりやすい地域は物理的にタイプ分けができます。しかし、絶対に地震が起こらないといえる地域は存在しません。
例えば、地震が発生しづらいことで知られる北海道の道北地方。旭川市などは、かつて震度3以上の地震を観測することがほぼありませんでした。
一部で「旭川以北は震度3以上の地震がない安全地帯」という安全神話のようなものもありましたが、2018年の胆振東部地震でその記録は破られました。
空白域では地震が来ない?
「空白域」という言葉があります。
【空白域とは】
断層帯が確認されていない地域のこと。
つまりその地域では直下型地震を引き起こすもとが存在しないという認識が一般的です。しかし、これは今のところ、確実な理論ではありません。
なぜなら昨今、特に平成後期に入ってからですが「未知の断層帯」による地震の被害が多発しているからです。
歴史学的な調査を含めて過去に地震が発生したことが確認できていないエリアでも、実は活断層があり、大きく破断して直下型地震を引き起こすというケースが近年増加傾向にあります。
そのため、断層の空白域では地震が来ないというのはもはや過去の安全神話といえそうです。
例)2019年 熊本地震
2019年の1月、新年早々に熊本県で震度6弱の地震を記録しました。この地震は主に和水町という地域を襲いましたが、和水町は本来地震の活断層の「エリア外」という認識が主流でした。近隣には、布田川断層や日奈久断層など過去に大きく揺れたことのある断層帯が走っていますが、その活動領域の外のエリアで震度6弱という大きな地震を引き起こしました。
このように、空白域で地震が来ないのは過去の考え方と言えるでしょう。
これは海底も同様のことが言えます。海の底でも未知の断層があるケースもあり、今までに地震の発生履歴が確認されていない海域で大きな地震を引き起こすことがあります。
まとめ
このように、地震が起こりやすい地域は過去の統計上いくつか明らかになっています。
被害が起こりやすい地域としては特に、活断層の真上や海の近く、さらに埋立地などが考えられます。
しかし、近年になって空白域と呼ばれる「活断層が走っていないと思われていた」地域でも震度6弱の地震を起こすことがあるなど、全国的にどの地域でも決して油断できない状態になりつつあります。
「この辺りは地震による家屋の被害が無いだろう」として保険をないがしろにする方もいらっしゃいますが、反対に空白域や過去に地震被害でなかった地域ほど今後は警戒して保険などを手厚くしておくという考え方も良いでしょう。
参考:こんなこともいけるの?という作業の例
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
